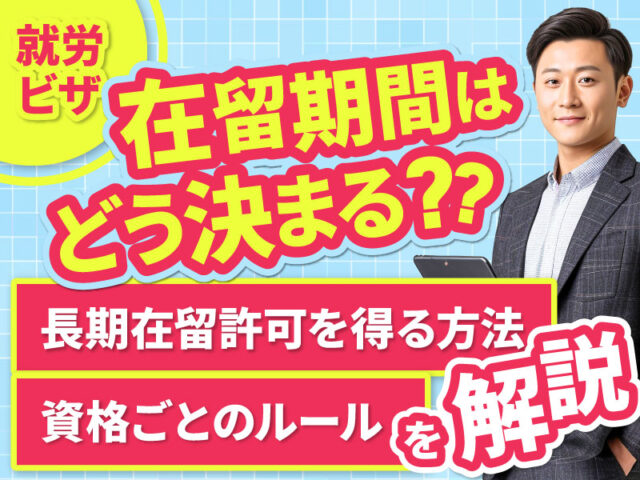外国人材の受け入れが進む中で、就労ビザの「在留期間」は企業にとって重要な管理項目のひとつです。
どのくらいの期間働けるのか、契約満了後も引き続き雇用できるのかは、採用戦略や業務体制の構築に大きく影響します。
この記事では、就労ビザの在留期間の基本的な考え方をはじめ、主な就労ビザごとの期間の違い、長期間の許可を受けるための工夫、在留資格ごとの期間決定のルールなどについてわかりやすく解説します。
INDEX
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
就労ビザの在留期間の基本概要
外国人を雇用する企業にとって、就労ビザと在留期間の仕組みを正しく理解することは非常に重要です。
まずは、就労ビザとは何か、そして在留期間が制度上どのように位置づけられているのかをそれぞれ解説します。
就労ビザとは
就労ビザとは、日本で報酬を受ける活動を目的とした在留資格の総称であり、外国人が企業などに雇用されて働くためには、該当する在留資格を取得している必要があります。
なお、「ビザ」という名称がついていますが、本来のビザを意味する査証とは異なり、これは在留資格を指す用語として一般的に用いられているものです。
法務省が定める就労可能な在留資格には、以下の19種類があります。
| 就労ビザ(就労系の在留資格)の一覧 |
| 「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能」「技能実習」 |
なお、「技能実習」は、主に発展途上国への技能移転を目的とする制度ですが、実際には企業での就労を伴うため、実務上は就労ビザの一種として扱われています。
在留期間とは
在留期間とは、外国人が日本に在留する際に、一度に許可される滞在可能な期間を指し、在留資格ごとのルールに基づいて個別に定められます。
在留期間は、入国時の「上陸許可」、在留資格の「変更許可」や「更新許可」など、在留資格に関する各種許可の際に法務大臣によって決定されます。
なお、海外から外国人を招へいする際に行う「在留資格認定証明書交付申請」は、入国前の事前認定手続であり、この段階では在留期間は決定されず、実際に日本に入国して上陸許可が下りた時点で在留期間が付与されます。
主な就労ビザの在留期間
就労ビザの在留期間は在留資格ごとに異なり、それぞれの活動内容や受け入れ機関の状況などを踏まえて個別に決定されます。
在留期間には、一般的に「3か月」「6か月」「1年」「3年」「5年」などの区分があり、同じ在留資格であっても、申請内容や過去の実績により異なる期間が許可される場合があります。
特に企業の人事担当者にとっては、対象となる就労ビザの標準的な在留期間を把握しておくことが、雇用契約の期間設定や入管申請の補助をする際に重要です。
「技術・人文知識・国際業務」の在留期間
「技術・人文知識・国際業務」は、企業での技術職・事務職・翻訳通訳などの業務に従事する外国人に付与される代表的な就労ビザの一つであり、多くの企業で活用されています。
この在留資格に付与される在留期間は、「3か月」「1年」「3年」「5年」と定められており、申請内容や受け入れ機関の活動状況に応じて個別に判断されます。
在留期間の決定は、たとえ同じ職種・同じ雇用先であっても、過去の在留実績や申請書類の整合性などにより、1年の許可となる場合もあれば、3年または5年の長期の在留が許可されることもあります。
「特定技能」の在留期間
「特定技能」は、一定の専門性や技能を有する外国人が日本で就労するための在留資格であり、分野ごとに設けられた受け入れ基準を満たすことで認められます。
この在留資格には「特定技能1号」と「特定技能2号」の区分があり、在留期間の取り扱いもそれぞれ異なります。
特定技能1号は、通算5年の在留期間を上限とする在留資格であり、一度に付与される在留期間は「1年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間」です。
一方、特定技能2号は通算の在留期間に上限の定めがなく、一度に付与される在留期間は、「6か月」「1年」「3年」のいずれかになります。
特定技能1号から2号への移行を希望する場合は、1号の在留期間の上限5年が経過するまでに2号への移行要件を満たした上で在留資格の変更をする必要があります。
「技能実習」の在留期間
「技能実習」は、開発途上国等への技能移転を目的として、日本の企業で一定期間働きながら技能を習得するための在留資格であり、段階に応じて在留期間が定められ、最長で通算5年の滞在が可能とされています。
技能実習は「第1号」から「第3号」までに区分されており、それぞれの在留期間は、第1号が「1年を超えない範囲」、第2号および第3号が「2年を超えない範囲」で、いずれも法務大臣が個々に指定する期間が付与されます。
各段階への移行時には要件適合性の審査が行われるため、在留資格変更許可申請を行う必要があります。
「高度専門職」の在留期間
「高度専門職」は、高度な専門性や技術を有する外国人材を優遇的に受け入れるための在留資格であり、ポイント制に基づいて在留が許可されます。
高度専門職には「1号」と「2号」があり、「1号」の在留期間は5年と定められていますが、所定の条件を満たすことで「高度専門職2号」へ変更することができ、「2号」に移行すると在留期間に上限がなく無期限の在留が可能となります。
在留期間の決まり方
外国人に付与される在留期間は、単に在留資格の種類によって機械的に決まるものではなく、入国審査官が審査の際に使用する内部規則「入国・在留審査要領」に基づいて、個々の申請内容を審査した上で決定されます。
この審査では、活動内容の適正性や受け入れ機関の体制、本人の過去の在留状況などが総合的に判断され、その結果によっては同じ在留資格であっても1年の許可にとどまる場合や、3年、5年といった長期の在留期間が認められる場合があり、一律の期間が与えられるわけではありません。
希望する在留期間を取得できる可能性を高めるためには、在留期間決定のルールを理解した上で、申請の準備をすることが重要です。
所属機関のカテゴリー
所属機関のカテゴリーとは、外国人の就労ビザに関する審査において、受け入れ先となる企業や団体の規模や信頼性を基に分類された区分のことを指します。
このカテゴリーは、在留期間決定の判断や提出書類の省略要件などに影響を与えるため、企業が外国人を雇用する際の重要な審査項目の一つです。
具体的には、「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「研究」「教育」「経営・管理」「技能」などの在留資格において、所属機関のカテゴリーが審査対象となります。
カテゴリーは通常、上場企業などを上位とする「カテゴリー1」から、設立間もない中小企業などを含む「カテゴリー4」までの4段階に分かれており、上位のカテゴリーに属する所属機関ほど長期の在留期間が認められやすい傾向があります。
公的な義務の履行
在留期間の決定においては、外国人本人の「入管法に基づく届出義務」や義務教育期間の子供がいる場合は「子供に教育を受けさせる義務」などの公的な義務を適切に履行しているかどうかが重要です。
住所変更や就労先の変更などに関する届出を怠ったり、期限を守らなかったりする場合には、在留状況に問題があるとみなされ、許可される在留期間が短くなる可能性があります。
公的な義務の適切な履行は、審査の際に、長期の在留期間を付与しても問題が生じないと判断してもらうために不可欠な要素となります。
過去の在留実績や職務上の地位
在留期間の決定にあたっては、外国人本人の過去の在留実績も重要な判断材料とされます。
たとえば、納税や社会保険料の支払いが遅延している場合や、法令違反などの問題がある場合は、たとえ業務の内容に問題がなかったとしても、在留期間の決定に影響が出る可能性があります。
また、本人の職務上の地位についても、管理職や専門的立場にある場合には、企業内での役割や責任の重さが、安定的な在留につながると評価され、比較的長期の在留期間が認められる可能性があります。
所属機関の活動実績
在留期間の判断においては、外国人本人の情報だけでなく、所属機関である企業や団体の活動実績も重要な審査対象となります。
特に、企業の経営が安定しているか、継続的な事業活動が行われているかといった経営状況は、外国人を受け入れる体制として信頼できるかどうかを判断する材料とされます。
また、過去に外国人を受け入れた実績や、労働法や入管法上の義務違反などがないことも審査においては重要なポイントとなります。
就労予定期間
在留期間の決定にあたっては、契約期間や雇用予定期間が短い場合には、他の要件を満たしていたとしても短い在留期間しか認められない可能性があります。
たとえば、入管に提出する申請書や雇用契約書に記載された雇用期間(就労予定期間)が6か月未満の場合には、在留期間も6か月となる可能性が高くなり、1年や3年といった長期の在留許可は得られないことが一般的です。
外国人従業員の長期在留を希望する場合は、企業側としては長期的な雇用を前提とする契約内容と、それに見合った活動計画を明示することが、より長い在留期間の取得において有利に働く可能性があります。
長期の在留期間を取得するには
在留期間は在留資格の種類によってあらかじめ定められた範囲内で決定されますが、その中でもできる限り長期の在留期間を得るためには、申請内容や企業の体制、本人の在留実績などを整えることが重要です。
3年または5年といった長期の在留期間が認められた場合は、本人の生活の安定や企業側の雇用計画の見通しに寄与するだけでなく、将来的に永住許可を申請する際の「直近の在留期間が3年または5年であること」という基準の一つも満たすことになります。
次項では、長期の在留期間を取得するために意識すべき申請上の注意点や、所属機関の体制整備などについて紹介します。
申請内容に矛盾が生じないようにする
在留期間の審査は、原則として申請者が提出する書類の内容に基づいて書面審査によって行われるため、提出書類に矛盾がある場合には、審査官に不信感を与える原因となり、在留活動の継続性や適正性に疑問があると判断され、長期の在留期間が認められにくくなる可能性があります。
たとえば、雇用契約書と申請書の就労予定期間や報酬額が一致していない、公表している事業内容と申請書に記載の業務内容にずれがある、といった書類上の不整合は、虚偽や誤認を疑われる要因となります。
そのため、申請書類を作成する際には、すべての文書において記載内容の一貫性と正確性を確保し、提出前に十分な確認を行うことが重要です。
所属機関のカテゴリーを格上げする
所属機関のカテゴリーは、在留期間の審査における重要な判断材料の一つであり、特定の就労ビザにおいては、所属機関の区分が高いほど長期の在留期間が認められやすくなります。
たとえば「技術・人文知識・国際業務」の場合、所属機関のカテゴリーは1から4までに分かれており、上場企業や公的機関などはカテゴリー1、一定基準以上の源泉徴収税額を納める企業はカテゴリー2、源泉徴収額が基準に満たない企業はカテゴリー3、新規設立企業などはカテゴリー4という形で分類されます。
所属機関のカテゴリーは、一定の条件を満たすことで上げることができますが、たとえば経済産業省が認定する「健康経営優良法人」の取得することで、カテゴリー1に格上げされる制度もあります。
また、所属機関が外国人従業員の在留資格申請を取り次ぐオンライン手続きの利用承認を受けることで、カテゴリー3の企業であってもカテゴリー2として取り扱われるようになり、提出書類の簡略化や長期の在留期間取得が期待できます。
カテゴリーの格上げは、在留期間だけでなく、企業としての信頼性向上にもつながるため、外国人雇用を継続的に行う企業にとっては戦略的に取り組むべき項目の一つです。
活動内容を詳細に説明する
在留資格の申請書には「活動の内容」を記載する欄がありますが、用紙上のスペースは限られており、2行の簡潔な記載しかできない形式となっています。
そのため、実際の業務内容や就労の背景を十分に伝えるためには、添付資料によって補足説明を行うことが非常に有効です。
たとえば、申請書の活動内容欄に「別紙活動内容詳細参照」と記載し、別紙で職務内容や勤務体制、業務の流れなどを具体的に説明することで、審査官に正確な理解を促すことができます。
基本的な提出資料だけでは伝わりにくい情報、たとえば曜日ごとのスケジュールの違いや季節・時期による年間の業務内容の変化などを詳細に説明した上で、全ての業務内容が申請する就労ビザの活動内容に該当していることを伝えることができれば、審査官の視点からも長期在留を許可しても問題ないと判断しやすくなります。
理由書などで情報を補足する
在留資格の審査においては、申請書や定型的な添付資料だけでは、申請者がなぜ長期の在留期間を必要としているのかといった事情が審査官に十分に伝わらない場合があります。
そのため、必要に応じて「理由書」などの自由記載形式の書面を提出し、人材採用の背景事情や意図を丁寧に補足することが効果的です。
たとえば、外国人従業員に将来的に責任あるポジションを任せる予定であり、短期の在留期間では業務の継続性や企業運営に支障が出るといった事情を具体的に説明することで、長期在留の必要性に説得力を持たせることができます。
参考:特定技能ビザから別の就労ビザへ変更するには?違いや条件と合わせて解説
まとめ
就労ビザの在留期間は在留資格ごとに異なるほか、申請内容や所属機関の状況、外国人本人の実績などを踏まえて個別に判断されるため、長期の在留期間を得るには、提出書類の整合性や理由書の活用、所属機関のカテゴリーの格上げなど、さまざまな工夫が必要となります。
外国人を雇用する企業にとって、在留期間の正しい理解と制度のポイントを踏まえた適切な対応は、人材の定着と安定的な経営に直結するため、申請準備の段階から長期の在留期間を取得できるよう意識して対策することが重要です。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。