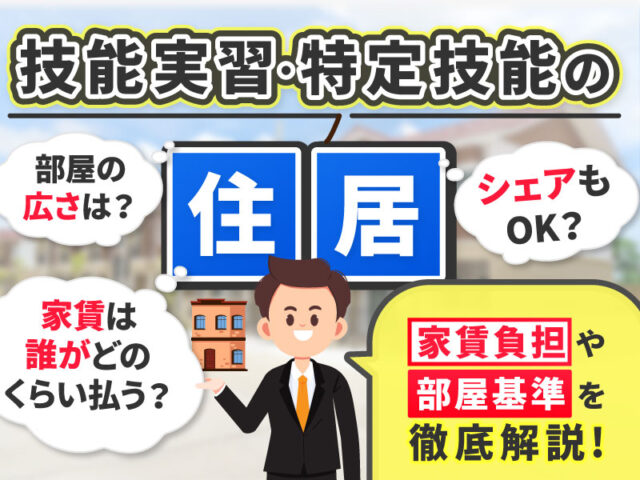「技能実習生を受け入れる際住居確保においてどんな条件があるの?」
「技能実習生の住居費用は?家賃控除の上限はあるの?」
このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
技能実習制度では、住居の確保は受け入れ企業側の義務です。
住居の準備には設備基準や安全基準など満たすべき条件があり、家賃控除にも上限額が設定されています。
定められている条件をクリアしなければ、トラブルの原因になるほか、技能実習生の受け入れ自体も認められない可能性もあります。
本記事では、技能実習生の住居に関する設備基準や条件、家賃控除の上限額について詳しく解説していきます。住居選びのポイントや実際の選び方についても紹介しているので参考にしてみてください。
外国人採用前に
知っておくべき
チェックリスト

この資料でわかること
- 外国人採用前のチェックシート
- 採用前の具体的なチェックポイント
- 人材紹介会社を利用するメリット
- 優良な人材紹介会社の選び方
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
【基礎知識】技能実習生の住居確保は企業の義務

技能実習制度において、受け入れ企業による技能実習生の住居確保は法律上の義務です。
技能実習生が安心して技能習得に専念できる環境を提供するため、受け入れ企業は住居環境の整備をしなくてはいけません。
義務化された主な理由は以下の通りです。
義務化された主な理由
- 難しい日本語の契約書が読めない・書けない
- 契約に必要な書類を用意できない
- 大家さんが外国人に部屋を貸さない
- 日本での保証人がいない
- 収入がない・少ないため保証会社の審査に通らない
このような技能実習生ならではのハードルがあり、自力での住居確保は困難です。
住居に関する具体的な基準については、技能実習制度運用要領において詳細な規定が設けられています。また、企業が技能実習生に寄宿舎や社員寮を提供する場合は、労働基準法の寄宿舎規程に基づく設備基準や安全基準を満たすことが必要です。
これらの法的根拠により、企業は単に住居を用意するだけでなく、適切な居住環境の維持管理も含めて責任を負うことになります。
【関連記事】
技能実習生を受け入れるための条件や体制整備の基準について解説
技能実習生の受け入れ準備とは?生活環境や労働環境など条件別に紹介
技能実習生の受け入れは、企業が独自で採用活動を進められますが、大半の企業が監理団体に依頼します。住居確保のサポートもしてもらえるため、自社での対応が難しいと思ったら監理団体に支援業務を委託しましょう。
「外国人採用の窓口」では、あなたのエリアに近い監理団体を一括検索できるサービスを提供しています。無料相談も受け付けているので、技能実習に関する小さなお悩みもお気軽にご相談ください。
技能実習生の住居に関する条件

技能実習生の住居基準は「適切な宿泊施設」を確保することが前提です。
適切な宿泊施設とは、以下のような危険を避けた安全な住居のことです。
安全な住居の基準
- 火災の危険がある
- 有害な作業場の近く
- 騒音や振動が多い
- 土砂崩壊などに巻き込まれるおそれがある
- 過度な湿気や浸水のおそれがある
- 汚染のおそれがある
出典:技能実習制度 運用要領|厚生労働省
そのうえで、以下の3つが主な住居の基準となります。
- 部屋の広さ・割り振りの基準
- 部屋の設備基準
- 住居の設備基準
それぞれ見ていきましょう。
部屋の広さ・割り振りの基準
技能実習生の部屋の広さは、日本人の住居水準を考慮して以下のように定められています。
部屋の広さ
- 1人につき4.5㎡以上(約3帖)
- 活動時間が異なる人の寝室は別
部屋の広さは寝室として使えるスペースのみを指し、床の間や押し入れは含みません。
また、部屋を複数の実習生でシェアする場合には、就業時間・睡眠時間が違う実習生を同じ寝室に割り当てることはできません。
シフトのローテーションを組んでいる場合には、同室の技能実習生は日勤のみ、夜勤のみといった同じ組み合わせの勤務時間にすることが求められます。
部屋の設備基準
技能実習生が居住する部屋は、以下の設備が備わっている必要があります。
部屋の設備
- 施錠可能で持ち出せない個人別の収納スペース
- 部屋の面積7分の1以上の採光できる窓
- 必要な冷房、暖房設備
技能実習生が部屋をシェアするときには、身の回り品を収納できるだけの容量がある鍵付きのロッカーなどを用意する必要があります。
持ち出せない対策として、チェーンロックや南京錠、防犯ワイヤーなどで収納ボックスを建物に取り付ける方法でも問題はありません。
暖房設備は備え付けでなくても、ストーブを用意すれば条件を満たします。
住居の設備基準
住居全体の設備基準としては、快適な生活に必要な設備が整っていることが求められます。
例えば、以下のような設備が完備されていなければなりません。
住居の設備
- トイレ
- 洗面所
- 浴場(脱衣所含む)
- 洗濯場
- 衛生的で照明や換気の設備が整った食堂や炊事場(ある場合)
- 適切な消火設備
また、2階以上に寝室がある建物の場合には、安全な場所に避難できる階段の設置が必要です。
原則は1ヵ所ですが、収容人数が15人以上の場合は2ヵ所以上の異なる場所への階段の設置が必須となります。※すべり台や避難はしご、避難用タラップなどが用意できていれば、階段は1ヵ所でOK
技能実習生の受け入れで住居以外に準備すべきもの

技能実習生の住居確保と合わせて、以下のような日常生活に必要な設備や用品も受け入れ企業が準備する必要があります。
| 設備 | 例 |
| 家具 | 机、椅子、ベッド |
| 家電 | 冷蔵庫、洗濯機、エアコン |
| 通信環境 | インターネット環境、Wi-Fi |
| 生活用品 | 布団、タオル、食器類、調理器具 |
入居後すぐに生活を始められる基本的な用品を準備しましょう。特に、技能実習生の文化的背景を考慮した調理器具の選定が大切です。
また、消火器や救急箱といった安全対策用品、清掃用具などの衛生管理に必要な用品も整備が求められます。これらは労働基準法の寄宿舎規程でも設置が義務付けられており、適切な配置と定期的な点検が必要です。
技能実習生が支払う?住居関連の費用負担における条件

技能実習生の住居に関わる費用負担については、以下の項目それぞれで異なるルールが定められています。
- 初期費用|受け入れ企業が負担
- 家賃|相場は2〜3万円
- 水道光熱費|技能実習生が実費を負担
各費用の負担条件について見ていきましょう。
初期費用|受け入れ企業が負担
住居契約時に発生する初期費用は、受け入れ企業による負担が一般的です。
敷金、礼金、仲介手数料、火災保険料などの契約諸費用は、技能実習生の負担軽減と円滑な受け入れのため、企業側で準備する必要があります。
これらの初期費用は技能実習生の給与からの控除対象外とされており、企業の受け入れ準備費用として計上することになります。
自社所有の物件や社員寮を提供する場合は、敷金や礼金といった契約費用は発生しないため、企業の負担を軽減できるでしょう。
家賃|相場は2〜3万円
技能実習生の家賃相場は、地域にもよりますが月額2〜3万円程度が一般的です。
家賃相場は、技能実習生の給与水準を考慮して設定された額で、生活費を圧迫しない範囲での負担となるよう配慮されています。
家賃は、技能実習生本人との合意の上で給与から控除・徴収することができます。周辺の賃貸料相場より高く設置したり、不当な金額を徴収したりといった、会社側が利益を上げるような請求はできません。
【関連記事】
技能実習生の給与の相場は?報酬の決め方や法律上のルールについて解説
『技能実習生』の受け入れ費用、監理団体の料金相場を解説【費用項目一覧表あり】
家賃控除額の計算方法
技能実習生からの家賃控除は、実際にかかった住居費用を基に計算します。
企業が賃貸物件を借り上げて提供する場合、実際の家賃額を居住者数で割った金額が一人当たりの控除額となります。
複数の外国人社員が1部屋をシェアすることが一般的ですが、その場合は、家賃や水道光熱費の実費を入居人数で割った金額以内を控除・徴収できます。
家賃の計算方法
■家賃(管理費・共益費含む)が総額9万円の家を3名で使用する場合
9万円÷3名=上限3万円/1名あたり
技能実習生本人の家賃負担の相場は「1名あたり2〜3万円程度」となっているため、この金額を上限の基準として控除・徴収することが望ましいでしょう。
なお、途中帰国などがあり入居後に人数が減ってしまった場合、最初に設定した1名あたりの控除・徴収金額を上げることはできません。
外国人採用の窓口では「外国人雇用にかかる費用徹底分析」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人雇用にかかる費用を
事前に知りたい方へ

この資料でわかること
- 外国人雇用にかかる費用一覧
- 海外在住の外国人採用にかかる費用
- 日本在留の外国人採用にかかる費用
- 外国人雇用のコストを抑える方法
水道光熱費|技能実習生が実費を負担
水道光熱費については、原則として技能実習生が実費を負担することになります。
計算方法は、水道、電気、ガス会社からの請求額を基に、居住者の人数で割った金額を技能実習生に請求するのが一般的です。
技能実習生の水道光熱費の負担相場は「1名あたり5千円〜1万円程度」です。例えば、月の電気代が1万2千円で4名が居住している場合、一人当たりの負担額は3千円となります。
水道光熱費の控除においても、過度な負担とならないよう配慮が必要であり、使用量に応じた公平な分担となるように配慮しましょう。
技能実習生に用意可能な住居のタイプ

技能実習生の住居として企業が用意できる住居タイプは、主に以下の2つです。
- 賃貸物件
- 会社の寮・社宅
それぞれの住居タイプの特徴を解説していきます。
賃貸物件
賃貸物件は、企業が技能実習生の人数に相当する広さのアパートやマンションを借り上げて提供する住居です。
この方式では、企業が契約者となって一般的な賃貸住宅を借り、技能実習生に住居として提供します。
賃貸物件を選択するメリットとしては、受け入れ人数に応じて柔軟に物件規模を選べる点や、立地条件を比較検討できる点が挙げられます。
また、技能実習期間終了後は賃貸契約を終了できるため、長期的な設備投資が不要である点も企業にとって利便性が高いと言えるでしょう。
会社の寮・社宅
会社側が保有している社宅・社員寮に住んでもらうというケースもあります。
日本人社員も住んでいる既存の社員寮に技能実習生を入居させる形態では、自然な国際交流が生まれやすく、日本語学習や文化理解の促進につながります。
人数が4名以上になる場合や、毎年同じ時期に技能実習生を受け入れる企業では、一軒家を借り上げて専用の住居として活用する場合もあります。
会社の寮・社宅の家賃負担は、建設/改装にかかった費用や物件の耐用年数などを考慮して算出した金額を、入居者人数で頭割りした額を控除・徴収することが可能です。
寮・社宅の家賃計算方法
■自己所有物件の場合の計算例
物件総額÷耐用年数÷12ヶ月÷居住人数=1名あたりの徴収上限金額(月額)
※物件総額には土地代を含まず、リフォーム代や家電購入費等は含む。
ただし、賃貸・借り上げ物件と同様に、会社側が利益を上げるような不当な請求はできません。
技能実習生の住居を選ぶ際のポイント

技能実習生の住居を選ぶ際のポイントは、主に以下の4つがあります。
住居を選ぶ際のポイント
- 職場へのアクセスが良いか
- エアコンや給湯設備などがあるか
- プライベート空間を確保できるか
- 安全対策が充実しているか
職場に電車やバスといった公共交通機関で通勤しやすく、生活必需品の購入や医療機関の利用に便利な立地であれば土地勘がない外国人でも安心して生活できます。
また、インフラ設備と適切な居住スペース、オートロックや防犯カメラなどで、技能実習生にとって安全な環境を整えましょう。
技能実習生の雇用をご検討中なら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「技能実習生の住居条件や費用負担について、専門家に相談したい…」
「信頼できる監理団体を見つけたいが、どこを選べば良いかわからない…」
「技能実習生の受け入れ手続きや住居準備について、サポートを受けたい…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した監理団体や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
条件検索機能により、貴社の業界・業種に精通した技能実習生の受け入れ支援に強いパートナー企業とのマッチングをお手伝いいたします。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けているので、技能実習生の受け入れに関するお悩みがある方もお気軽にお問い合わせください。
技能実習生の住居に関するよくある質問

最後に、技能実習生の住居に関するよくある質問と回答を紹介します。
技能実習生の住居に関する法律はなんですか?
技能実習生の住居に関する法的根拠は、主に2つの法律によって定められています。
まず「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」では、実習実施者が技能実習生の適切な住居環境を整備する義務について規定されています。
また、労働基準法も技能実習生の住居に関する法的根拠となっており、特に企業が寄宿舎や社員寮を提供する場合には、労働基準法の寄宿舎規程に基づく設備基準や安全基準を満たすことが求められます。
また、技能実習制度運用要領では、居住スペースの広さや設備基準、安全対策などの具体的な住居条件が定められています。
技能実習生が支払う家賃の上限は決まっていますか?
技能実習生の家賃について、具体的な金額の上限が法令で決まっているわけではありません。
ただし家賃の徴収に関しては、法令で「実費を超えて徴収することは禁止」されているため、企業が利益を得る目的での過度な請求はできないルールとなっています。
実際の家賃負担額は約2〜3万円で、賃貸物件の家賃を入居する技能実習生の人数で割った額が一人あたりの家賃負担として設定されるのが一般的です。
家賃控除額は、技能実習生の給与水準や生活費を考慮したうえで、過度な負担とならない範囲として設定されています。
技能実習生は一人暮らししても良いですか?
技能実習生の一人暮らしは、法的には可能です。
ただし、宿舎の内容については事前に「技能実習計画認定書」に記載して申請しなければならないため、受け入れ企業は住居タイプや部屋割りなどの居住計画を、事前に決めておかなくてはいけません。
実際の運用においては、企業側の意向や監理団体の指示によって共同生活になる場合が多く見られます。
共同生活が選択される理由としては、以下の理由が挙げられます。
共同生活が選択される理由
- 住居費用の抑制
- 技能実習生同士のサポート体制構築
- 企業側の管理負担の軽減
技能実習生の生活環境については本人の希望だけでなく、企業の受け入れ体制や地域の住宅事情なども考慮した、住居形態の選択が望ましいです。
技能実習生の寮で起こりやすいトラブルは何ですか?
技能実習生の寮生活では、日本の生活習慣や文化の違いに起因するトラブルが発生しやすい傾向にあります。
最も多いトラブルはゴミ出しに関する問題です。母国と日本では分別ルールや収集日時が大きく異なるため、適切な分別ができずに近隣住民から苦情が寄せられる場合があります。
また、騒音に関するトラブルも頻繁に発生します。技能実習生同士の会話や深夜帯の電話が、近隣住民の迷惑となる事例も少なくありません。
これらのトラブルを防ぐには、入居前の生活ルール説明と継続的な指導が必要です。
【関連記事】
外国人労働者のトラブル事例15選|対策や未然に防ぐ方法も解説
特定技能外国人・技能実習生が日本での生活で困ること│必要なサポートとは?
技能実習生が住む部屋の広さの基準は1人あたり何畳ですか?
技能実習生の住居における部屋の広さについて、法令で明確な畳数の基準は定められていません。労働基準法の寄宿舎規程では、一人当たりの居室面積を2.5平方メートル以上とすることが規定されています。
これを畳数に換算すると、約1.5畳程度が最低基準となります。
しかし、実際の運用では技能実習生の生活環境向上のため、一人当たり3畳程度のスペースの確保が一般的です。
特に複数人での共同生活となる場合では、プライバシーを確保できる個人スペースの設置が推奨されており、快適な居住環境の提供が求められます。
宿泊施設(寮・アパート)はいつまでに準備が必要ですか?
技能実習生の宿泊施設は、技能実習計画認定申請時までに準備が必要です。
技能実習計画認定申請書には、住居の所在地や設備内容、居住予定人数などの詳細情報を記載しなければなりません。
申請から認定までには、通常2〜3ヵ月程度の期間がかかるため、技能実習生の受け入れ予定日から逆算して、余裕を持った準備スケジュールを組むことが必要です。
また、住居の確保だけでなく、家具や家電製品の設置、生活用品の準備なども含めて完了させておく必要があります。
技能実習生が入国後すぐに生活をスタートできる状態にしておくことで、円滑な受け入れ体制を整えられます。
技能実習生の受け入れ前には条件に合う住居を準備しよう

技能実習生の住居確保は企業の法的義務であり、適切な住環境の提供が受け入れ成功の鍵となります。
住居には労働基準法の寄宿舎規程に基づく設備基準を満たす必要があり、一人当たり2.5平方メートル以上の居室面積確保が条件です。また、家具・家電や生活用品、安全設備の準備も企業の責任範囲に含まれます。
費用負担については、初期費用は企業が負担し、月額2〜3万円程度の家賃と、水道光熱費を技能実習生が実費負担するのが一般的なルールです。住居タイプは賃貸物件または会社の寮・社宅から選択できます。
立地や設備、安全性を考慮した住居を選び、技能実習計画認定申請までに準備を完了させることが必要です。
適切な住居環境を整備することで、技能実習生が安心して技能習得に専念でき、企業の人材育成目標達成にもつながります。住居準備に関して不安がある場合は、専門機関のサポートを活用して計画的に進めるとスムーズです。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。