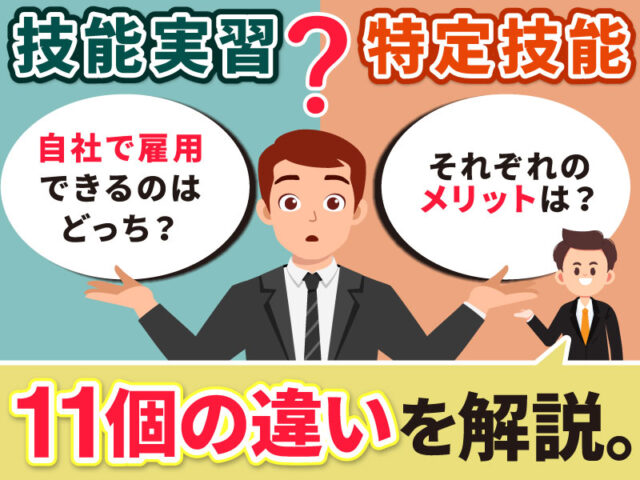「技能実習と特定技能はどんな違いがある?」
「技能実習と特定技能ではどちらが自社に適しているの?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
技能実習は途上国への技術移転による国際協力が目的の制度である一方、特定技能は人手不足解消を目的とした就労制度です。
2つはいずれも外国人を雇用できる制度ですが、目的や対象者、雇用期間などが違います。
制度の違いを把握しないまま採用すると、自社のニーズに合わない人材を雇用してしまう可能性があるので、記事を参考に理解を深めましょう。
本記事では、技能実習と特定技能の違い11項目を比較表を交えて解説します。制度の特徴や、それぞれの制度で外国人を受け入れる際のメリット・デメリットも紹介しているので参考にしてみてください。
特定技能外国人の
採用を検討したい方へ
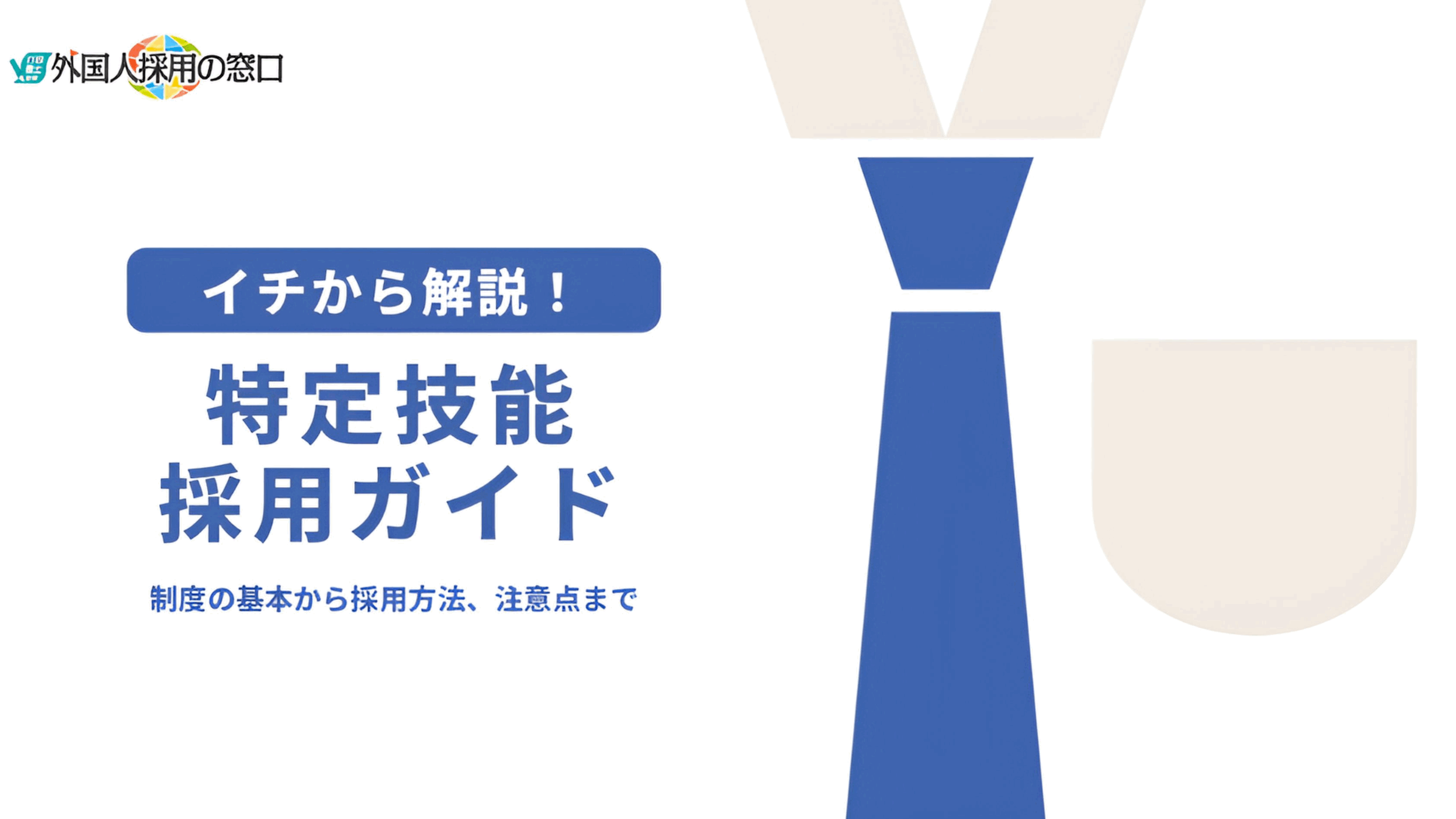
この資料でわかること
- 特定技能制度で従事できる分野
- 在留資格「特定技能1号」の取得条件
- 特定技能1号外国人を雇用する流れ
- 登録支援機関の役割と仕事内容
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
【比較表】技能実習・特定技能「11」の違いの違い11個

技能実習・特定技能は、どちらも外国人が日本で就労活動するための在留資格の一種です。
「外国人が日本企業で働く」という点ではどちらも同じですが、以下の11項目において違いがあります。
- 制度の目的
- 働ける職種・業務
- 在留期間
- 技能水準
- 試験の有無
- 受け入れ可能人数
- 受け入れ・採用方法
- 家族の帯同
- 転職の可否
- 関わる団体・企業
- 給与水準
それぞれの違いや雇用ルールを確認したうえで、自社に合った外国人採用を進めていきましょう。
違い1:制度の目的
技能実習と特定技能では、大前提として制度の目的に大きな違いがあります。
技能実習は、開発途上地域等の出身者に日本の高い技術力を現場実習(OJT)を通じて習得してもらい、その技術や知識を母国の経済発展のために活用してもらう国際協力を目的とした制度です。
一方、特定技能は、国内で人材を確保することが難しい産業分野において、一定の専門性・技能を持っている外国人を受け入れることで、深刻化する人手不足を補うことを目的とした制度です。
| 制度 | 目的 |
| 技能実習 | 技術・知識移転を通じた開発途上地域等への国際協力 |
| 特定技能 | 人材を確保することが困難な産業分野における、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることによる人手不足の解消 |
なお、技能実習制度については2024年の法改正により、2027年に廃止されることが決定しています。新たに「育成就労制度」が創設され、従来の国際協力から、より実質的な労働力確保と人材育成を目的とした制度に変わる予定です。
育成就労制度については以下の記事で詳しく解説しているので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
育成就労制度とは|いつから始まる?技能実習との違いや転籍の条件を徹底解説
違い2:働ける職種・業務
技能実習は、91職種168作業で受け入れできます。
特定技能は、2024年に新たに追加された4つの産業分野を含む16分野(特定技能2号では11分野)での受け入れが可能です。
この通り、技能実習と特定技能では受け入れできる職種が異なっており、どちらかで受け入れができたとしても、もう一方でも必ず受け入れができるとは限りません。
| 制度 | 職種 |
| 技能実習 | 91職種168作業 |
| 特定技能 | 16分野(2号は11分野) |
参考:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(91職種168作業)|厚生労働省
特定技能1号の各分野の仕事内容|出入国在留管理庁
特定技能2号の各分野の仕事内容|出入国在留管理庁
【関連記事】
2025年最新版!技能実習生を受け入れできる分野・職種・作業一覧
特定技能の職種一覧と各産業分野・業務区分の概要、仕事内容について徹底解説 | 外国人採用の窓口
違い3:在留期間
技能実習は、1号が1年間、2号が2年間、3号が2年間(合計で最長5年間)と定められています。
特定技能は、1号が通算5年以内、2号は期間上限がありません。そのため、特定技能2号になれば、移、日本で長期雇用が可能です。
| 制度 | 在留期間 |
| 技能実習 | 技能実習1号:1年以内
技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(合計で最長5年間) ※3号以降は各種要件あり |
| 特定技能 | 特定技能1号:通算5年
特定技能2号:上限なし |
違い4:技能水準
技能実習は、原則として、本国で同種の業務に従事していた経験が必要ですが、あくまでも技能・知識を習得してもらう目的となっているため入国前に高度な専門スキルは求められません。
特定技能は、1号・2号それぞれ、職種に応じた一定以上の経験・知識が求められます。
| 制度 | 技能水準 |
| 技能実習 | 特になし |
| 特定技能 | 職種に応じた一定以上の経験・知識が必要 |
違い5:試験の有無
技能実習の場合、特に事前の試験はありません(介護職のみ、日本語能力試験N4レベルの日本語能力が必須)。
特定技能では、「日本語能力を測る試験」および、特定産業分野ごとに「技能評価試験」への合格が必須です。
技能実習から特定技能への移行の場合、技能実習2号または3号を良好に修了している場合はこの試験が免除されますが、技能実習と特定技能の産業分野が違う場合は試験を受ける必要があります。
| 制度 | 日本語能力 |
| 技能実習 | 特になし |
| 特定技能 | 日本語能力を測る試験(国際交流基金日本語基礎テスト、日本語能力試験、介護日本語評価試験※介護分野のみ)および技能評価試験への合格が必須 |
違い6:受け入れ可能人数
技能実習と特定技能では、受け入れ可能な人数が異なります。技能実習は、適切に指導が行き届くように人数制限が設けられています。
常勤職員数(雇用保険加入者数)に応じた人数が規定されており、仮に常勤職員数が30人の場合、初年度に受け入れられる人数は3人です。
特定技能は、介護・建設分野を除いて、雇用人数に上限はありません。
建設の場合は、自社の常勤人数を超えない範囲、介護の場合は事業所ごとに常勤介護職員の総数を超えない範囲、という規定があります。
| 制度 | 人数制限 |
| 技能実習 | 人数制限あり(常勤職員が30名以下の企業は3名など) |
| 特定技能 | 原則、人数制限なし(介護・建設分野除く) |
【関連記事】
技能実習生の受け入れ人数に上限はある?企業の規模別の制限や算定方法を解説 | 外国人採用の窓口
違い7:受け入れ・採用方法
技能実習生は、外国政府認定送り出し機関と提携した「監理団体」から紹介してもらう必要があります(企業単独型を除く)。
特定技能では、日本人の採用と同じく、受入れ企業が求人サイトなどを活用して募集したり、人材紹介会社から紹介を受けたりといった自由な採用活動が可能です。
| 制度 | 採用方法 |
| 技能実習 | 監理団体からの紹介が必要 |
| 特定技能 | 受入れ企業が自由な方法で採用 |
【関連記事】
技能実習生を受け入れるための条件や体制整備の基準について解説
特定技能に関しては、介護・建設業を例に以下の記事で詳しく解説していますので参考にしてみてください。
【関連記事】
特定技能!介護職の受け入れ方法|メリット・デメリット、技能実習との違いも解説 | 外国人採用の窓口
建設業界の外国人材不足を解決!特定技能受け入れガイド|メリット・デメリット、事例
外国人採用の窓口では「特定技能外国人採用ガイド」がわかる資料を無料配布しております。採用活動で大事なポイントがわかる内容です。
30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
特定技能外国人の
採用を検討したい方へ
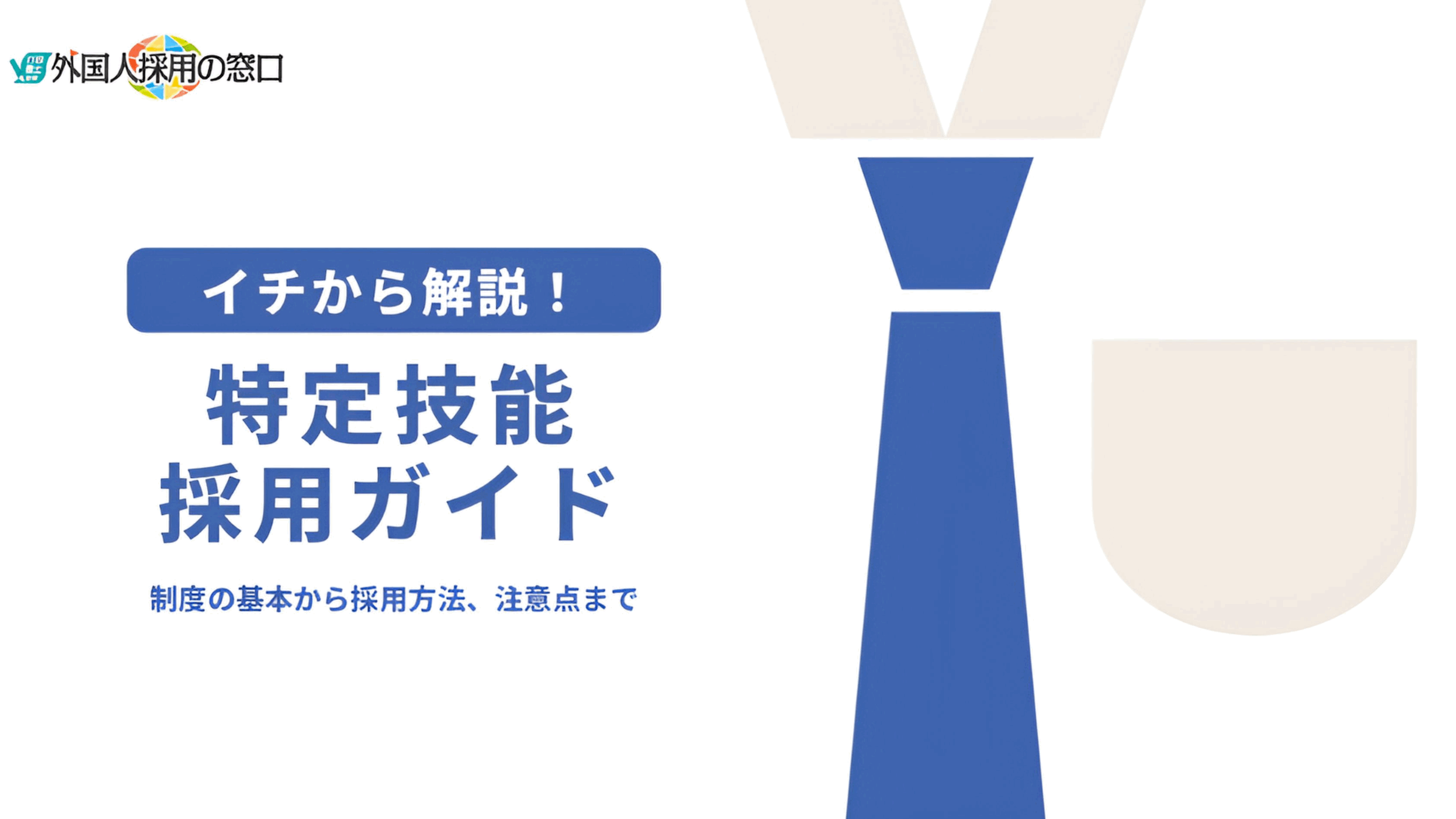
この資料でわかること
- 特定技能制度で従事できる分野
- 在留資格「特定技能1号」の取得条件
- 特定技能1号外国人を雇用する流れ
- 登録支援機関の役割と仕事内容
違い8:家族の帯同
技能実習は、家族帯同ができません。
特定技能は、2号のみ、母国にいる配偶者ならびに子どもに限り日本に呼び寄せることができます。
| 制度 | 家族帯同の可否 |
| 技能実習 | 家族帯同は不可 |
| 特定技能 | 「特定技能2号」のみ家族帯同が可能(条件あり) |
違い9:転職の可否
技能実習は、技能を習得するのが目的のため転職は原則できません。
技能実習2号から3号に移行するタイミングで一時帰国し、転職を希望した場合や、受入れ企業の倒産、感染症による特例が適用された場合など、転職が認められる例外もあります。
特定技能は、「同一分野」または「転職先分野の技能評価試験合格+日本語能力試験N4レベル以上」を満たせば転職が可能です。
| 制度 | 転職の可否 |
| 技能実習 | 原則、転職は不可 |
| 特定技能 | 同一分野内であれば転職が可能 |
【関連記事】
特定技能外国人は『転職』できる!企業が知っておくべきルール・手続き・注意点【事例付き】
違い10:関わる団体・企業
技能実習生の雇用には、受入れ企業の指導や監査を行う「監理団体」「外国人技能実習機構(OTIT)」「送り出し機関」など、受入れ企業と実習生の間に入る関係者が多くなります。
特定技能の場合は、企業と特定技能外国人との間で雇用契約を結ぶため、基本的には2者間で完結します。ただし、一部の国では外国側の法令により外国政府に認定された送り出し機関の利用が必須となる場合があります。
採用時には人材紹介会社や求人広告会社などが関わる場合があります。また、外国人サポート体制が整っていない企業であれば、特定技能外国人の生活面における義務的支援をおこなうために「登録支援機関」を活用するケースが一般的です。
| 制度 | 団体・企業 |
| 技能実習 | 監理団体、外国人技能実習機構(OTIT)、送り出し機関など |
| 特定技能 | 特定技能外国人本人
※人材紹介会社、登録支援機関などの採用・生活サポートも依頼可能 |
【関連記事】
5分でわかる|監理団体とは?サポート内容や選び方のポイントを解説
登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説
「外国人採用の窓口」では、希望するエリアの外国人向けの人材紹介会社や監理団体、登録支援機関を検索でき、貴社のニーズを満たした最適なパートナーを見つけることができます。
無料相談も受け付けておりますので、技能実習・特定技能に関してお困りごとがあれば、お気軽にお問い合わせください。
違い11:給与水準
技能実習生・特定技能外国人いずれの場合も、労働基準法により「日本人と同等以上の報酬(最低賃金以上)」の支払いが義務付けられています。
しかし、実際の給与水準には差が見られます。厚生労働省「賃金構造基本統計調査(令和6年)」によると、月額賃金の平均は以下の通りです。
| 制度 | 給与 |
| 技能実習 | 187,700円 |
| 特定技能 | 211,200円 |
出典:在留資格区分別にみた賃金|厚生労働省
特定技能は、一定のスキルを持つ即戦力人材を対象としています。そのため、技術を学ぶ段階の技能実習よりも給与水準が高く設定される傾向です。
【関連記事】
技能実習生の給与の相場は?報酬の決め方や法律上のルールについて解説
特定技能外国人の給与相場は?報酬の決め方や分野別の平均賃金について詳しく解説
技能実習を受け入れるメリット・デメリット

技能実習生を受け入れるにはメリットとデメリットがあります。
- 技能実習生を受け入れるメリット
- 技能実習生を受け入れるデメリット
それぞれ詳しく見ていきましょう。
技能実習生を受け入れるメリット
技能実習制度のメリットは、幅広い候補者層から人材を選考できる点です。
前述の通り、特定技能制度では候補者層が限定的になりがちですが、技能実習制度では、基本的なコミュニケーション能力と意欲があれば、多くの人材から選考することができます。
これにより、企業側としては、自社の要望に合った外国人材を見つけやすくなります。
製造業や建設業、農業などの基礎的な技能職種を中心とした90職種が対象となっているため、幅広い分野で人材確保が可能です。
技能実習生を受け入れるデメリット
技能実習制度のデメリットとして挙げられるのが、基礎からの教育が必要であり技能習得に時間を要する点です。
技能試験に合格することなく受入れ可能な一方で、即戦力として活用することは難しく、一定の教育期間が必要です。
技能実習制度では、1号から3号までの段階的な期間設定があり、最長で5年間の実習期間が設けられています。
この期間を通じて、外国人材は段階的に技能を習得していくことになりますが、企業側としては、その間の教育コストや生産性の低下などを考慮する必要があります。
特定技能外国人を受け入れるメリット・デメリット

特定技能制度の活用においてもメリットとデメリットがあります。
- 特定技能外国人を受け入れるメリット
- 特定技能外国人を受け入れるデメリット
それぞれを詳しく解説します。
特定技能外国人を受け入れるメリット
特定技能制度の大きなメリットは、即戦力として外国人材を活用できる点です。
特定技能の対象者は、分野別の技能試験に合格し一定の日本語能力を有する人材です。
これにより、すでに一定の技能・日本語能力を持った人材を確保でき、入国後すぐに会社の戦力として活躍してもらえます。
特定技能の1号では、在留期間が通算5年までと定められていますが、2号では更新回数の制限がありません。
つまり、2号での受入れであれば長期的な雇用が可能となるのです。
長期的な視点に立った人材活用を実現できる点は、特定技能制度の大きな魅力と言えます。
外国人採用の窓口では「特定技能外国人の受入れ診断チェック」の資料を無料配布しております。フローチャートを使って自社で特定技能外国人の受け入れ可能かどうかを簡単に診断できる内容です。
30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
特定技能外国人を
受け入れるかお悩みの方に
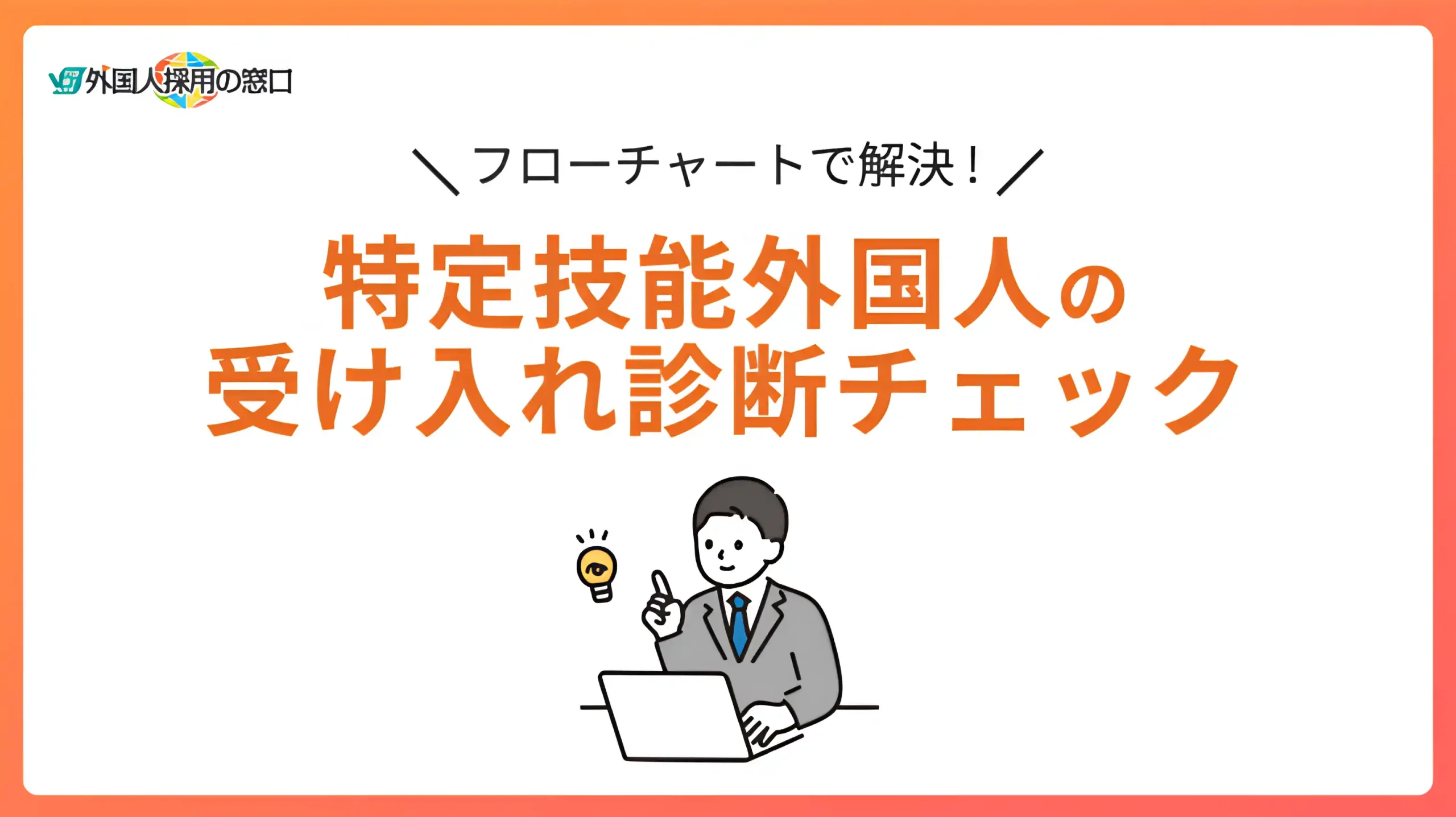
この資料でわかること
- 外国人雇用の簡易診断チャート
- 在留資格「特定技能」の特徴
- 特定技能の対象分野
- 特定技能外国人受け入れの基本条件
特定技能外国人を受け入れるデメリット
一方で、特定技能制度の活用には、人材確保の難しさというデメリットもあります。
分野別の技能試験に合格し、日本語能力試験N4以上の語学力を有するという高い要件をクリアした人材のみが対象です。
また、スキルを持つ人材は競合他社からも多くの引き合いがあるため、自社に魅力を感じてもらうためのお給料も技能実習生と比較して高額となります。
このハードルの高さゆえに、特定技能の候補者層は限定的となるため、求める人材像に合致する外国人材を見つけ出すのは思いのほか簡単ではありません。
技能実習から特定技能へ移行も可能

技能実習を修了した外国人材が、さらなるキャリアアップを目指し、特定技能への移行も可能です。
技能実習生が特定技能へ移行する際には、一定の要件を満たす必要があります。要件を満たせば、通常は必須の技能試験と日本語試験が免除されます。
主な要件は以下の2点です。
特定技能への移行要件
- 技能実習2号を良好に修了している
- 技能実習での作業と、特定技能1号の業務に関連性がある
この2点を満たすことで、試験を受けることなく特定技能への移行手続きが可能です。
また、日本語能力についても、技能実習2号を良好に修了していれば、特定技能1号の日本語能力試験N4の合格条件が免除されます。
特定技能1号では、技能実習で従事していた職種と同じ分野で就労することが可能です。そのため、実習で身につけた技能をさらに発展させ、即戦力として活躍することが期待されています。
企業にとっても、すでに自社で働いている技能実習生を特定技能へ移行させることで、継続的な雇用と安定した労働力の確保が実現できます。
【関連記事】
徹底解説|技能実習1号、2号、3号の違いや移行手続きの疑問を解決!
技能実習から特定技能1号への在留資格の更新は公的手続きに該当し、外国人雇用の手続きに強い行政書士事務所に業務を委託すると確実かつスムーズに申請が進められます。
「外国人採用の窓口」では行政書士事務所の一括検索サービスを提供しています。ご希望のエリアや業種などを条件検索して、あなたのニーズにマッチした事務所を探せます。
無料相談も受け付けておりますので、外国人雇用に関する小さなお困りごともお気軽にお問い合わせください。
外国人採用をご検討中なら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「技能実習と特定技能について詳しい人に相談したい…」
「信頼できる監理団体や登録支援機関の探し方がわからない…」
「外国人採用の専門知識を持つ信頼できるパートナーを見つけたい…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した監理団体や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
貴社の採用したい在留資格や国籍の外国人に合わせて、最適なパートナー企業とのマッチングをお手伝いをいたします。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けているので、技能実習・特定技能に関するお悩みがある方もお気軽にお問い合わせください。
技能実習・特定技能に関するよくある質問

最後に、技能実習・特定技能に関するよくある質問と回答を紹介します。
技能実習制度は廃止されるんですか?
現行の「技能実習制度」は廃止され、新たに「育成就労制度」が創設される予定です。
2024年の法改正により、技能実習制度は2027年4月に新制度へ移行し、2030年までに完全に廃止されることが決定しています。
この変更の背景には、技能実習制度が抱えていた人権問題や労働環境の課題がありました。
新しい「育成就労制度」では、制度の目的を「人材育成と労働力の確保」の両立へと転換する予定です。これにより、外国人労働者の権利保護を強化し、より透明性の高い制度運営が期待されています。
技能実習生と特定技能外国人ならどちらを雇用するのが良いですか?
どちらの制度を選択するかは、企業の目的と状況によって決まります。
即戦力が必要で人手不足が深刻な企業には、特定技能外国人の雇用が適しています。一定の技能と日本語能力を持つ人材を採用できるため、教育期間を短縮し、すぐに業務に従事してもらえます。
一方で、時間をかけて人材を育成したい企業や、採用コストを抑えたい場合は技能実習生の受け入れが向いています。幅広い候補者から選考でき、長期的な視点で技能を身につけてもらうことが可能です。
自社の求める人材像を明確にし、制度を選ぶと良いでしょう。
技能実習と特定技能の違いを踏まえたうえで外国人の雇用を検討しよう

技能実習と特定技能は、どちらも外国人労働者の受け入れ制度ですが、目的や対象者、雇用条件など11の項目で大きな違いがあります。
技能実習は国際協力を目的とし、基礎から技能を身につけてもらう制度である一方、特定技能は人手不足解消を目的とし、即戦力となる人材を受け入れる制度です。企業の状況や求める人材像に応じて、最適な制度を選択することが成功の鍵となります。
これらの制度の違いを理解し、自社のニーズに合った外国人採用を進めることで、労働力不足の解消と企業の成長を実現できるでしょう。
特に、在留資格の要件や支援体制の整備、監理団体や登録支援機関との連携が不可欠です。
外国人雇用に関する専門知識や手続きを自社で対応するのが困難な場合は、監理団体や登録支援機関、人材紹介会社などの専門機関への相談を検討し、計画的に外国人雇用を進めましょう。
専門家のサポートを受けることで、外国人労働者が安心して働ける環境づくりにつながります。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。