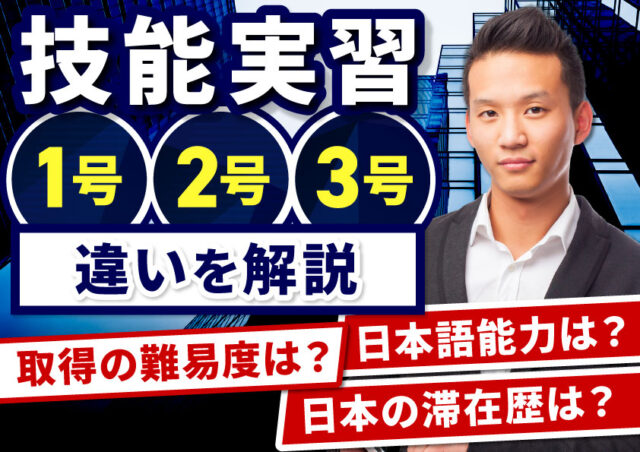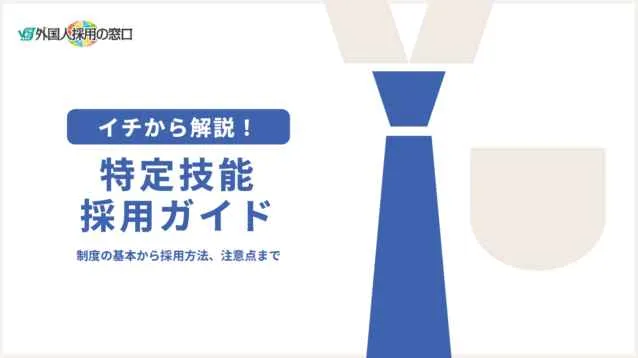「技能実習1号、2号、3号の違いが分からない」
「2号から3号へ移行するときの手続きを知りたい」
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
技能実習制度では、1号・2号・3号で受け入れ要件や在留期間、移行条件が異なります。違いを理解しておくと、受け入れの計画が立てやすくなり、在留資格を移行する際にも外国人に対して適切なサポートができるようになります。
本記事では、技能実習1号・2号・3号の特徴をもとに、受け入れ要件や在留期間、従事可能な職種の違いを解説します。1号から2号、2号から3号、技能実習から特定技能に在留資格を移行する方法も紹介しているので、参考にしてみてください。
弊社「外国人採用の窓口」では、技能実習生の雇用に関する相談を無料で受け付けております。お悩み・聞きたいことがある方は、以下の問い合わせフォームまたは電話にてお気軽にお問い合わせください。
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
技能実習1号・2号・3号の違い【比較表あり】
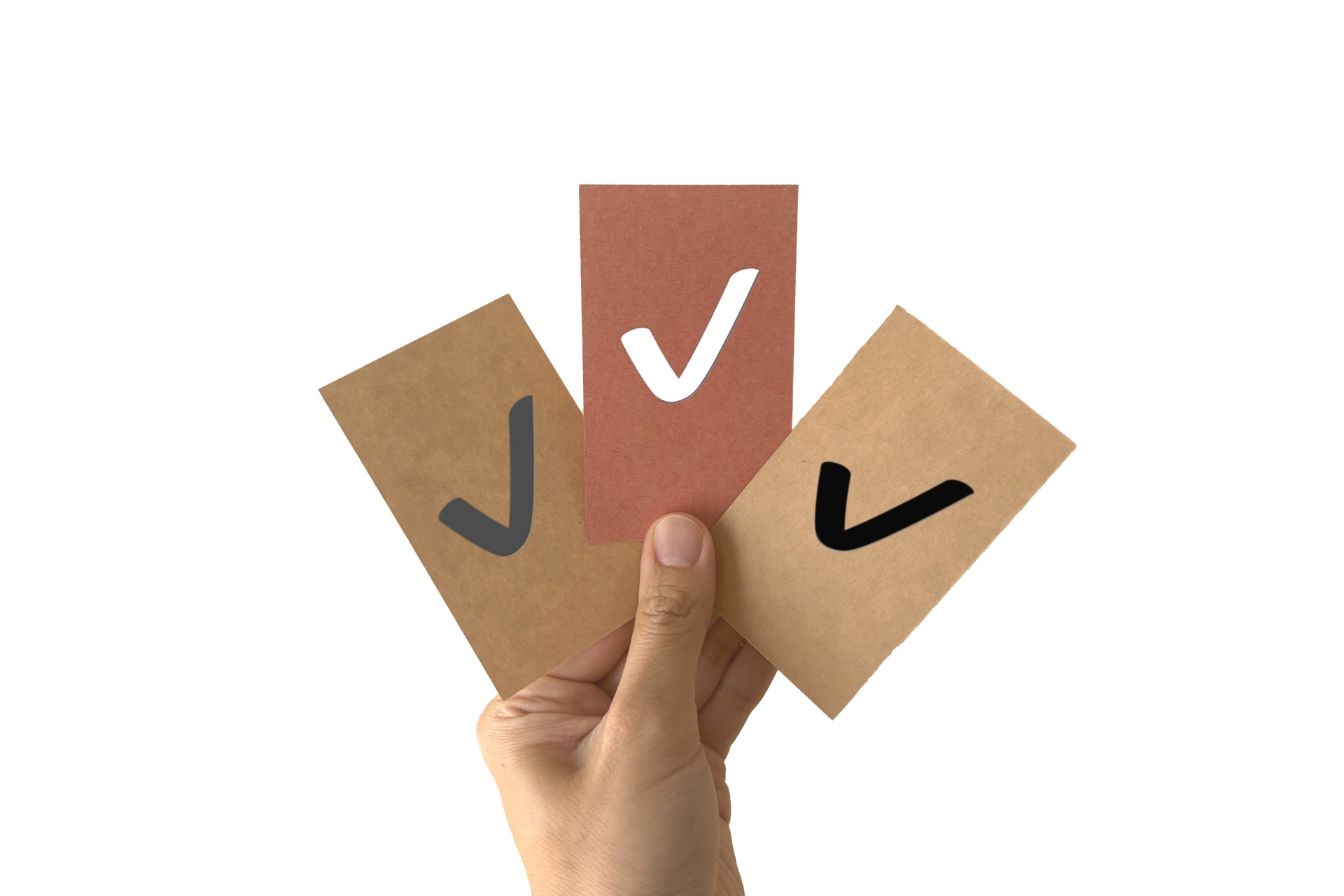
技能実習制度とは、日本が開発途上国の外国人を技能実習生として受け入れ、実際の仕事を通じて学んだ技術や知識を、母国の産業発展に役立ててもらうことを目的とした制度です。
在留資格は実習期間や技能レベルに応じて「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」に分かれています。在留資格の違いを以下の表にまとめました。
| 在留期間 | 対象職種 | |
| 技能実習1号 | 1年間 | 制限なし ※技能実習2号に移行するには移行対象職種と同一の職種である必要がある |
| 技能実習2号 | 2年間 | 91職種168作業 |
| 技能実習3号 | 2年間 | 技能実習2号移行対象職種と同一(技能実習3号が整備されていない職種を除く。) |
参考:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧│厚生労働省
参考:外国人技能実習制度について(令和7年4月1日改定版)│厚生労働省
ここからは各在留資格の特徴を詳しく解説します。
技能実習1号の特徴
技能実習1号とは、技能実習生が日本の基礎的な技術・知識を学ぶための在留資格です。
在留資格は1年で技能実習1号での実習の職種は、特に指定されていません。しかし、技能実習2号へ進む予定の技能実習生は、技能実習1号の段階で後述する「移行対象職種・作業」と同一の職種で実習をおこなう必要があります。
また、技能実習制度は開発途上地域等への技能移転や経済発展を目的としているため、同一作業で反復のみの単純労働に従事できません。
技能実習生は、入国して原則2ヵ月、受け入れをおこなう企業もしくは、監理団体が実施する入国後講習を受講します。入国後講習では、日本語や日本の生活習慣、文化や社会の基礎知識などを学びます。
入国後講習を終えたのちに、技能実習生と雇用関係を結び、実習が開始されます。
参考:外国人技能実習制度とは│JITCO公益財団法人 国際人材協力機構
技能実習2号の特徴
技能実習2号とは、技能実習1号の実習を経て基本的な技術・知識を修得した外国人が、より高度な技術・知識を習得するための在留資格です。
在留期間は2年で、技能実習2号で技術習得する職種・作業は、主務省令で定められた以下の「移行対象職種・作業 91職種168作業」に限られます。

参考:技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(91職種168作業)|厚生労働省
技能実習生を受け入れできる職種・作業については以下の記事で詳しく解説しています。理解を深めたい方はあわせてご覧ください。
【関連記事】
2025年最新版!技能実習生を受け入れできる分野・職種・作業一覧
技能実習1号から2号への移行には、基礎級の技能検定または技能実習評価試験の合格が条件です。移行方法はこのあと詳しく解説するので、このまま読み進めてみてください。
参考:外国人技能実習制度とは│JITCO公益財団法人 国際人材協力機構
技能実習3号の特徴
技能実習3号とは、技能実習2号を良好に修了し、さらに高度で熟練した技術・知識を習得する在留資格です。
在留期間は2年で、職種・作業は、技能実習2号で学んだ職種であることが条件です。
ただし、クリーニングや農産物漬物製造業など、技能実習3号では実習対象外の職種があるので事前に確認が必要です。
技能実習3号での実習を終えたあとは、学んだ技術や知識を母国で活用するために原則帰国します。
参考:外国人技能実習制度とは│JITCO公益財団法人 国際人材協力機構
技能実習におけるイ・ロの違いは?

技能実習(イ)・(ロ)は、在留資格の受け入れ方法の違いを表しています。
(イ)は、日本企業が自社の海外子会社から直接実習生を受け入れる「企業単独型」です。(ロ)は、監理団体等を通じて実習生を受け入れる「団体監理型」です。
令和6年に公開された外国人技能実習機構の統計によると、技能実習制度を利用する企業の約98%が団体監理型(ロ)を選択しており、監理団体のサポートする流れが一般的です。
参考:外国人技能実習制度とは│JITCO公益財団法人 国際人材協力機構
技能実習1号から2号に移行する方法
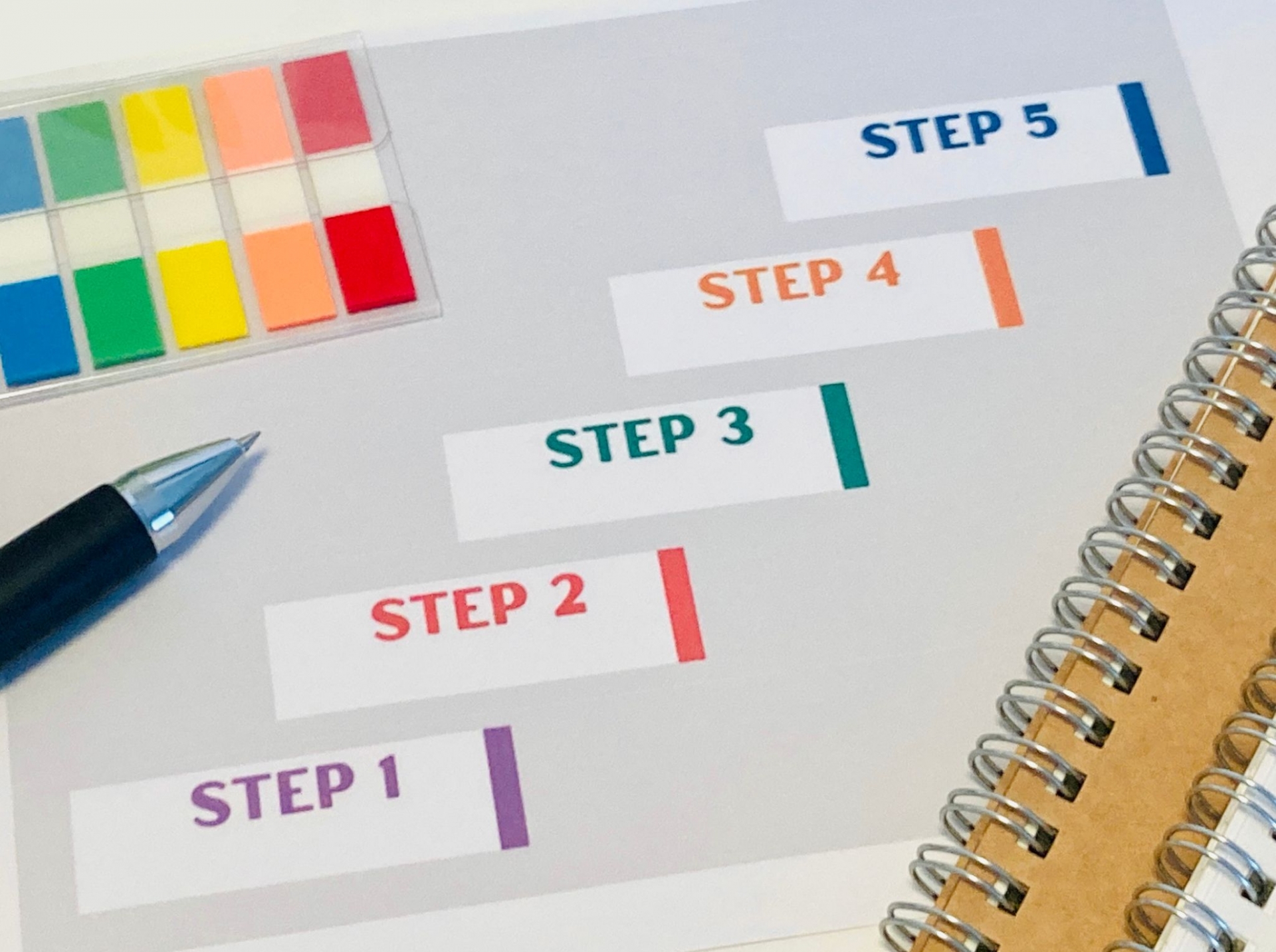
技能実習2号へ移行するためには、以下2つの条件を満たす必要があります。
技能実習2号へ移行する条件
1)技能検定「基礎級」の学科試験と実技試験に合格する
2)技能実習2号でおこなう作業が、移行対象職種・作業である
技能実習2号でおこなう作業が、移行対象職種・作業である技能実習生は、1号の技能実習開始から8~9ヵ月目に技能検定「基礎級」を受験し、学科試験と実技試験の両方に合格する必要があります。
試験を受ける時期
技能検定「基礎級」の申し込みは、第1号実習修了の6ヵ月前までにおこなうことが推奨されています。不合格だった場合の再受験は1回までとされており、再受験を考慮すると早めの受験が望ましいです。
試験合格や対象職種の条件を満たし、外国人技能実習機構での2号技能実習計画の認定、出入国在留管理庁での在留資格変更許可が下りると技能実習2号へ移行できます。
参考:技能実習生等向け技能検定の概要│厚生労働省
技能実習2号から3号に移行する方法

技能実習3号へ移行するためには以下3つの条件を満たす必要があります。
技能実習3号へ移行する条件
1)技能検定「随意3級」の実技試験に合格する
2)第3号技能実習開始前、または開始後1年以内に1ヵ月以上一時帰国する
3)実習実施者・監理団体ともに「優良」の基準を満たしている
技能実習生は、2号の技能実習開始から1年6ヵ月~1年10ヵ月目に技能検定「随意3級」を受験し、実技試験に合格する必要があります。
技能検定「随意3級」の申し込みは、2号実習修了の12ヵ月前までにおこなうことが推奨されています。技能実習2号同様に再受験の機会は1回のみで、再受験の可能性も視野に入れて余裕を持って受験の計画を立てるのが良いです。
一時帰国のルール
第3号技能実習開始前、または開始後1年以内に1ヵ月以上の一時帰国が義務付けられています。帰国時に、技能実習生の欠員が出るため、受け入れ企業は事前に人員体制を整えておきましょう。
技能実習3号への移行する際は、受け入れ企業と監理団体が、「優良」な実習実施者(受け入れ企業)・監理団体の基準を満たす必要があります。
優良な実習実施者・監理団体となるためには、技能の修得などの実績や法令違反・行方不明者の発生状況、技能実習生に対する支援体制などの各項目を点数化し、150満点中90点以上を獲得しなければなりません。
参考:「優良」な実習実施者・監理団体について JITCO公益財団法人 国際人材協力機構
技能実習と特定技能の違い

技能実習と特定技能は、制度の目的が異なります。
技能実習制度の目的
技能実習制度は、日本で働きながら技術や知識を学び、帰国後に母国の発展に活かすことで、国際協力を推進する制度です。
特定技能制度の目的
特定技能制度は、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材の受け入れを目的とした制度です。
特定技能制度では、在留資格「特定技能1号」と「特定技能2号」があります。
「特定技能1号」は特定の産業分野で、ある程度の知識や経験が必要な仕事に就労できる在留資格です。「特定技能2号」は、特定の産業分野で、特定技能1号よりも高い熟練技能が必要な仕事に就労できる在留資格です。
技能実習と特定技能の違いは、以下の記事で詳しく解説しています。比較表を交えてわかりやすく説明しているので、参考にしてみてください。
【関連記事】
技能実習と特定技能の違いとは?11のポイントを比較表で徹底解説
技能実習3号と特定技能1号の違い
技能実習3号と特定技能1号の違いとは、制度の目的や立場です。
技能実習3号は、外国人技能実習制度において、最大2年間、指定された職種・作業を母国の発展のために学びます。
特定技能1号は、特定技能制度において、通算5年間、指定された分野で労働者の一員として働きます。
要求される技術水準は、技能実習3号より特定技能1号の方が高いです。
具体的には、該当分野での知識または経験を必要とする技能を習得や日本語能力試験(N4以上)の合格など、現場で即戦力として活躍できるレベルが求められます。
参考:特定技能 ガイドブック│法務省
外国人採用の窓口では「特定技能外国人採用ガイド」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下の画像をクリックの上、どうぞお受け取りください。
技能実習から特定技能に移行する方法

技能実習生が、技能実習2号を良好に修了かつ、技能実習2号の職種と特定技能1号の分野が関連していれば特定技能1号に移行できます。
新しく特定技能1号の在留資格を取得する場合、各分野の技能評価試験と日本語能力試験の合格が必須です。
しかし、技能実習からの移行ルートで規定の条件を満たした方は、技能評価試験と日本語能力試験が免除されます。※一部の分野では試験あり特定技能1号外国人を受け入れる場合、企業は「1号特定技能外国人支援計画」の作成と、義務的支援を実施する必要があります。
自社対応もできますが、専門知識や人的リソースが不足している場合、登録支援機関に業務を委託できます。
「登録支援機関」は企業からの委託を受けて、特定技能1号外国人の支援業務を代行する専門機関です。豊富な経験と専門知識により、適切な支援を提供してくれるため、企業の負担軽減と外国人材の定着率向上が期待できます。
「外国人採用の窓口」では、あなたの企業にマッチする登録支援機関を一括検索できるサービスを提供しています。無料相談も受け付けておりますので、登録支援機関に関する悩みがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
技能実習生をスムーズに受け入れるポイント

技能実習生をスムーズに受け入れるにはいくつかポイントがあります。
主なポイントは以下の3つです。
- 制度の理解を深める
- 信頼できる監理団体を探す
- 行政手続きは専門家に委託する
できることを実践して、トラブルなく技能実習生を受け入れましょう。
制度の理解を深める
制度の理解を深めると、法律や規則を守って、安全に実習生を雇用できます。
また、外国人雇用に関する法令は定期的に改正されるため、制度に対してアンテナを張っておくと、ルール改正時にすぐに対応できます。
直近の法改正は、2024年に発令された「育成就労制度」です。現在の「技能実習制度」は今後廃止予定となっており、2027年までに育成就労制度に完全移行予定です。
育成就労制度については以下の記事で詳しく解説しています。新制度の準備に備えたい方は参考にしてみてください。
【関連記事】
育成就労制度とは|いつから始まる?技能実習との違いや転籍の条件を徹底解説
参考:育成就労制度の概要│厚生労働省
信頼できる監理団体を探す
監理団体の中には、高額な手数料を請求したり、虚偽の入国後講習記録を提出したりする悪質な団体もいます。
信頼できる監理団体に依頼することで、制度や法令に沿った適正な手続き・管理が行われ、違反やトラブルを未然に防げます。
弊社「外国人採用の窓口」では、ご希望にあう監理団体を検索できるサービスを提供しています。信頼できる監理団体のみとしかお取引していないため、安心してご利用いただけます。
行政手続きは専門家に委託する
海外在住の外国人を技能実習生として受け入れるには、在留資格認定証明書交付申請が必要です。
申請は行政手続きに該当し、必要書類の不備や記載ミスがあると不許可になる確率が高まります。
申請手続きを実施できるのは、原則外国人本人です。企業側は、助言などの間接的なサポートはできますが、十分な知識と経験がないと十分な知識と経験がないと適切なサポートが困難です。
自社でのサポートが難しいと判断したら、公的手続きの専門家である行政書士に依頼する選択肢もあります。専門の資格を有しているため、外国人に代わって申請手続きを代理できます。
自社業務に専念したい場合は、専門家の力もうまく借りましょう。
【関連記事】
在留資格認定証明書の申請方法と入国までの流れや手続きの注意点について解説
技能実習生の雇用をご検討中なら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「技能実習生の受け入れに関して誰かに相談したい!」
「信頼できる監理団体を見つけたい…」
「在留資格の変更手続きは専門家に委託したい…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した登録支援機関や行政書士事務所、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
条件検索できるため、あなたの業界・業種に精通した特定技能の就労支援に強いパートナー企業とのマッチングをお手伝いします。
【完全無料】当サイトで利用できるサービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けているので、技能実習生の受け入れに関するお悩みがある方もお気軽にお問い合わせください。
技能実習1号・2号・3号の違いを知ってスムーズに受け入れよう

技能実習1号・2号・3号の違いは、習得する技能レベルと在留期間です。
1号から2号、2号から3号に移行する場合は、学科試験・実技試験の合格や対象職種の要件を満たす必要があります。
本記事で解説した在留資格の違いや移行方法を参考に、技能実習生の受け入れを進めてみてください。
技能実習生の受け入れは監理団体を通じておこなうのが一般的です。
当サービスでは、ご希望のエリアや雇用したい国籍などの条件で検索し、企業のニーズにあう監理団体を検索できます。無料で利用できるので、信頼できるパートナーをお探しの方は、お気軽にご活用ください。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。