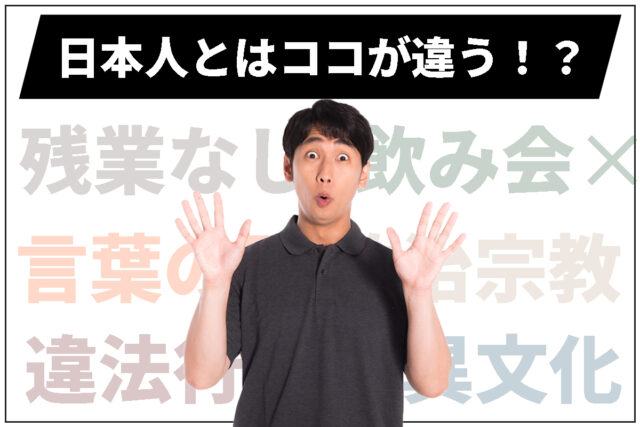「外国人を雇用した時どんなトラブルが起こるのだろう?」
「トラブルを事前に防ぐ方法があるなら知りたい」
このような悩みをお持ちの方もいるでしょう。
外国人雇用は人手不足の解消につながる一方で、言語や文化、価値観の違いによるトラブルが起こりやすいのも事実です。
しかし、代表的なトラブル事例やその対処法をあらかじめ把握しておけば、いざというときに落ち着いて対応でき、トラブルの発生自体も防ぎやすくなります。
この記事では、外国人雇用でよくあるトラブルの事例を15個紹介しています。トラブルへの対処法や未然に防ぐ方法についても解説していますので参考にしてみてください。
外国人採用の基本で
お悩みの方に
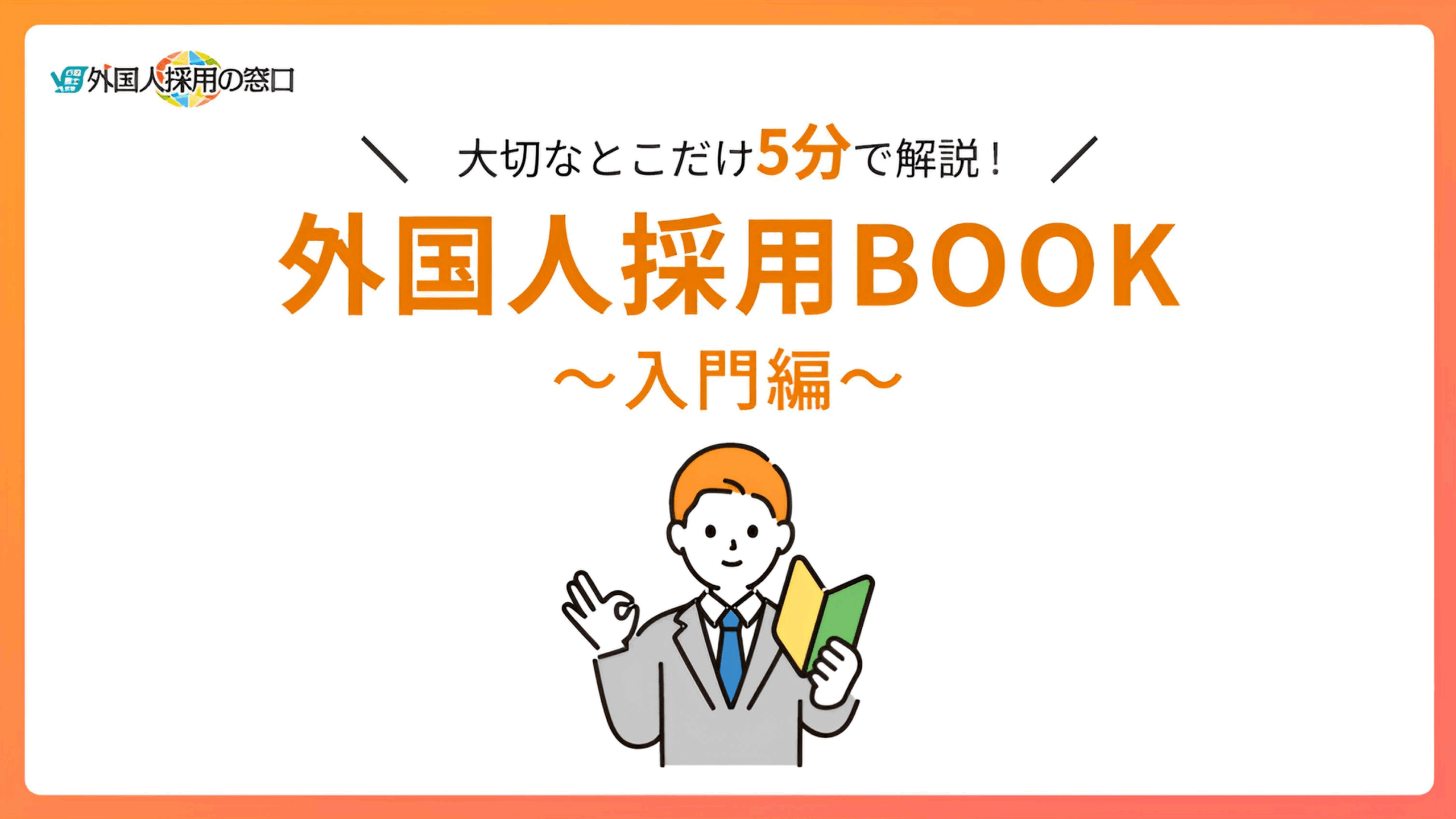
この資料でわかること
- 外国人労働者の現状
- 雇用できる在留資格の確認方法
- 外国人雇用における注意点
- 外国人を受け入れる流れ
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
外国人雇用でのトラブル① 違法に関する事例

外国人雇用において違法行為への意識差からトラブルに発展するケースがあります。代表的なトラブル事例は以下の4つです。
- 著作権を侵害する
- 会社の備品を無断で持ち帰る
- 在留カードを偽装している
- 在留資格の期限が過ぎている
詳細を順番に見ていきましょう。
著作権を侵害する
外国人のコンプライアンスの意識の差から違法行為につながってしまうことがあります。
以下は、著作権侵害に関するトラブル事例です。
英会話教室に非常勤講師として勤務し、教材作りに関わっていた外国人が、無断で他の教材に引用していたことが判明。その後の会社による調査結果において、他の教材にも無断で引用していたため、解雇処分を言い渡されました。
参考:外国人労働者の雇用をめぐる 相談事例 東京都の労働相談から
会社に著作権がある資料やデータを無断で持ち出したり、第三者に渡したりする行為は、法律で禁止されています。外国人労働者にも十分に説明し、確実に理解してもらいましょう。
会社の備品を無断で持ち帰る
会社の備品を無断で持ち帰ったり、私用に使ったりしてしまう場合があります。会社の備品を勝手に持ち出すと窃盗罪や横領罪に問われる可能性があります。
外国人労働者のなかには感覚的な違いから「会社にあるものを持ち帰っても問題ない」と考えてしまうケースも珍しくありません。
このような誤解を防ぐためにも、入社時のオリエンテーションで、どのような物品が持ち帰り禁止なのか具体例を示して説明しましょう。
在留カードを偽装している
外国人が日本で働くためには在留資格が必要です。しかし、不法滞在者や就労資格のない外国人が合法的に日本で就労・生活しているように見せかけるために在留カードを偽造するケースがあります。
適切な在留資格がない外国人を雇用すると、事業主も不法就労助長罪に問われ懲役3年、または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
在留カードの真偽確認には、出入国在留管理庁が公式に提供している「在留カード等読取アプリケーション」を活用すれば簡単に判別が可能です。
在留資格について詳しく知りたい方は、以下の関連記事を参考にしてみてください。
【関連記事】
採用してもいい在留資格って? | 全29種一覧&職業例あり
在留資格の期限が過ぎている
外国人の中には、更新手続きを忘れて在留資格の有効期限が切れている場合もあります。
その状態をオーバーステイ(不法残留)と言い、外国人は最悪の場合、強制送還されます。
オーバーステイに該当すると、外国人だけでなく、企業側も処罰の対象です。不法就労助長罪に問われ、懲役3年、または300万円以下の罰金が科される可能性があります。
そのため、外国人を雇用する際には、雇用前に在留資格の提示を求め、有効期限が切れていないかを必ずチェックしましょう。
また、企業側が外国人の在留資格の有効期限を把握して、満了日が近づいたら更新手続きを促せばトラブル回避につながります。
在留資格の更新は公的手続きに該当し、外国人雇用の手続きに強い行政書士事務所に業務を委託すると確実かつスムーズに申請が進められます。
「外国人採用の窓口」では行政書士事務所の一括検索サービスを無料で提供しています。ご希望のエリアや業種などを条件検索して探せますので、お気軽にご活用ください。
外国人雇用でのトラブル② 契約時・雇用時に関する事例

外国人労働者を雇用するにあたって契約時や雇用時に起こりやすいトラブルは以下の2つです。
- 労働条件を理解しないまま契約する
- 解雇時に企業を訴える
事例と一緒に詳しく見ていきましょう。
労働条件を理解しないまま契約する
外国人労働者の中には、雇用契約書の内容がよくわからないまま確認せず契約を結んでしまう方もいます。雇用条件の理解が不十分であると、入社後のトラブルにつながる恐れがあります。
外国人に雇用条件を説明するときに気をつけたい点は以下の5つです。
外国人に説明するときに気を付ける点
- 雇用条件は口頭だけでなく書面を準備する
- 可能であれば母国語での雇用条件書を準備する
- 就業規則についても説明する
- 担当する業務について詳細に説明する
- 不明な点がないか十分な質疑応答をおこなう
これらの点を丁寧に実施すれば、双方にとって安心できる雇用関係を築けます。
【関連記事】
無料DL!外国人を雇用する際の雇用契約書サンプル&解説|作成ポイント、法律、トラブル事例も
解雇時に企業を訴える
外国人に解雇を告げる際にも、トラブルが起こる可能性があります。
例えば、勤務態度の悪さや試用期間中の能力不足を理由に解雇した場合に、解雇理由に納得できずに相談窓口に駆け込むケースも多く見られます。
参考:外国人労働者の雇用をめぐる相談事例
外国人が解雇理由に納得できない場合、不当解雇として訴えられるリスクもゼロではありません。
このようなトラブルを防ぐためには、あらかじめ雇用条件に退職時の手続き方法や解雇事由を明確に記載することを推奨します。
外国人雇用でのトラブル③ 仕事観に関する事例

外国人雇用における仕事観の違いからくるトラブルは良く見られます。
代表的なトラブル事例は以下の5つです。
- 遅刻や納期遅れが発生する
- 報連相(報告・連絡・相談)をしない
- 残業せずに定時で帰ろうとする
- 飲み会への参加を断る
- 失踪してしまう
順番に解説します。
遅刻や納期遅れが発生する
国籍や文化的背景によっては、時間にルーズな外国人もいます。
以下は時間のルーズさが引き起こす仕事上のトラブル例です。
外国人トラブル例
- 出勤時間や会議に遅刻する
- 提出物の納期に遅れる
- 顧客との約束が守れない
時間を重視する傾向にある日本人にとっては許容しがたい行動のため、チームワークの乱れや顧客との関係性悪化に発展しかねません。
外国人に日本の風習や文化を知ってもらう機会を作り、日本における時間厳守のルールへの理解を深めてもらいましょう。
報連相(報告・連絡・相談)をしない
外国人は日本人特有の報連相(報告・連絡・相談)を理解していない場合があります。
個人主義の文化圏出身者にとって、作業途中での報告は必要ないと考えることも1つの要因です。
報連相を重視する文化を持つ日本では、以下のような問題につながりかねません。
外国人トラブル例
- 勝手に判断して業務を進めて品質低下や納期遅れが生じる
- 問題が発生しても報告せず大きなトラブルに発展する
- 情報共有が不足して重複作業や連携ミスによる業務効率の低下を招く
外国人労働者に報連相の重要性を丁寧に説明し、日本の職場文化におけるコミュニケーションの取り方を身につけてもらいましょう。
残業せずに定時で帰ろうとする
雇用した外国人の母国では定時に仕事を終えるのが一般常識というケースもあります。
日本企業のように残業が当たり前という国は決して多くありません。まずは日本での働き方や考え方を理解してもらうために、丁寧に説明をする必要があります。
中には残業をすると残業代が支払われることを知らない外国人もいます。
「残業=ただ働き」と考えている外国人もいるので、残業をした場合には残業代を支払うことを伝えると安心してもらえるでしょう。
飲み会への参加を断る
日本ならではの文化に、仕事終わりの飲み会(飲みニケーション)があります。
日本では当たり前の文化ですが、雇用した外国人は、家族との時間やプライベートを最も大切に考えているかもしれません。仕事後の飲み会を強要する、または断りにくい雰囲気にするのは控えましょう。
コミュニケーションの場が不足している場合には、ランチやお茶に誘ったり、個別にミーティングをおこなったりして、就業時間中にコミュニケーションをとる工夫をしてみてください。
失踪してしまう
令和5年度の技能実習生の失踪者数は、9,753人にのぼり過去最高の数となっています。
外国人が失踪してしまう主な理由は、労働の条件や環境の問題です。外国人に対して安い賃金で過酷な労働を強いた結果、劣悪な環境に耐えきれずに外国人労働者が逃亡してしまうケースがあります。
外国人労働者にも、日本人と同じように労働基準法や最低賃金法が適用され、日本人と同じ待遇・賃金で雇用しなければなりません。
企業側が外国人への差別がない働きやすい環境を整えれば、外国人労働者の失踪を防ぐだけでなく、長期雇用につながります。
外国人雇用でのトラブル④ 文化・言語の違いによるトラブル

外国人雇用において文化・言語の違いによるトラブルも良く起こります。
主なトラブルは以下の4つです。
- 宗教や礼拝や断食が仕事に影響する
- 宗教や政治などタブーな話でいざこざが生じる
- コミュニケーションが十分に取れない
- 顧客や取引先を怒らせる
事例とともに見ていきましょう。
宗教の礼拝や断食が仕事に影響する
外国人が信仰している宗教によっては、礼拝や断食があるものもあります。就労時間と宗教的行為が重なれば、仕事に影響が出てしまう場合があります。
例えばイスラム教では、一日に5回、決まった時間にメッカの方向に向かって礼拝します。
礼拝のルールに関しては事前に外国人と話し合い、お互いが納得する取り決めを作ることが望ましいです。しかし、ルールに不満を覚えたり、ルールを破って礼拝をした場合に、トラブルに発展する恐れがあります。
イスラム教ではラマダンと呼ばれる断食の期間もあります。断食の期間には、日中の食事だけでなく水を飲むことも禁じられています。
そのため、断食の期間中は、体力が低下して、生産性が下がったり、集中力が落ちたりと業務に支障をきたすケースも少なくありません。
宗教や政治などタブーな話でいざこざが生じる
従業員が衝突するきっかけに宗教や外交の話題を職場に持ち込むことが挙げられます。宗教や外交について話をすること自体は問題ありません。しかし、以下のようなケースではトラブルに発展する恐れがあります。
トラブルに発展するケース
- 個人を国の代表かのように責め立てる
- 人格を否定するようなことを伝える
- 宗教や外交の考え方を一方的に否定する
これらのトラブルを未然に防ぐために、既存の従業員に対しても多様性の理解促進やハラスメント予防の研修等を検討しましょう。
コミュニケーションが十分にとれない
外国人の中には、日本語がうまく話せない人もいます。
コミュニケーションが十分にとれないと、意思がうまく伝わらず、すれ違いや誤解が起きてトラブルにつながるケースは少なくありません。相手の日本語レベルに合った話し方を心がければ、意思疎通が通じやすくなります。
また、中には、日本語を十分に喋れない外国人に対して、からかって悪意のある言葉を投げたりする従業員もいます。このようなトラブルを避けるためにも、外国人労働者を受け入れる前に、従業員に対して多様性やハラスメントに関する研修を実施しましょう。
【関連記事】
日本語が話せない外国人労働者との接し方とは?トラブルも解説!
外国人採用の窓口では、外国人雇用における基本情報が知りたい方に向けて「外国人社員とのコミュニケーションのコツ」がわかる資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人社員との
やりとりでお困りの方に

この資料でわかること
- 外国人雇用における言語課題
- 伝わりにくいコミュニケーション例
- 伝わりやすいコミュニケーション例
- 外国人社員にあった指導方法
顧客や取引先を怒らせる
日本語でのコミュニケーションが不十分であるために、顧客や取引先を怒らせてしまう場合もあります。
例えば、取引先とうまくやり取りできずに、発注ミスや納期のずれが生じたり、顧客からの要望をくみ取れずにクレームに発展してしまったりするケースです。
日本語がまだ上手でない外国人には、日本人の従業員とペアを組んで業務にあたるなど適宜フォローできる体制にすると不要なトラブルを軽減できます。
外国人労働者とのトラブルが起きた時の対処法

外国人労働者と万が一トラブルが起きてしまった時の対処法は以下の2つです。
- 本人と直接話し合う場を設ける
- 外国人労働者とのトラブルに関する相談窓口を利用する
冷静かつ建設的な対応で、双方にとって納得のいく解決を目指しましょう。
本人と直接話し合う場を設ける
問題が起きたときは、まず外国人従業員としっかり話す時間をつくりましょう。相手の不満を聞くだけで気持ちが落ち着いて、そのままトラブルが解消されるケースもあります。
以下は、話し合いの際に意識してほしいポイントです。
話し合いで意識するポイント
- 意見が職場のルールと相違する場合は会社の方針を明確に伝える
- 資料の開示を求められても専門家に相談してから対応する
どのような状況でも感情的にならず、冷静な対話を心がけてください。
また、話し合いの内容はきちんと記録に残しておきましょう。対応した証拠を残しておけば、後日のトラブル防止に役立ちます。
外国人労働者とのトラブルに関する相談窓口を利用する
外国人労働者とトラブルになり話し合いでは解決が難しい場合には、相談窓口を利用する方法もあります。
外国人雇用に関するトラブルの相談窓口は以下の4つです。
| 相談できること | 相談窓口 |
| 在留資格関連 | 外国人在留総合インフォメーションセンター |
| 就労関連 | 外国人労働者相談コーナー・ハローワーク |
| 職場のハラスメント関連 | 各都道府県労働局内の雇用環境・均等部(室) |
もし、外国人とのトラブル解決のために労働審判を考えている場合には、弁護士会に相談してみる方法もあります。
この他にも、技能実習なら監理団体に、特定技能外国人であれば、登録支援機関への相談が可能です。これらの機関からサポートを受けている場合には、トラブルについて相談してみると良いでしょう。
【関連記事】
監理団体とは?サポート内容や選び方のポイントを解説
登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説
「外国人採用の窓口」では、希望するエリアの監理機関や登録支援機関を検索でき、貴社のニーズを満たした最適なパートナーを見つけることができます。無料で利用できるので、お気軽にお試しください。
外国人労働者とのトラブルを未然に防ぐためのポイント

外国人労働者との不要なトラブルを避けるためには、外国人労働者が働きやすいように受け入れ体制を整え、価値観や文化の違いを理解する姿勢を持つ必要があります。
外国人を雇用するときには以下のポイントをおさえて準備を進めましょう。
- 外国人労働者の受け入れ態勢を整える
- 雇用契約書の内容を明確にする
- 日本の仕事観・文化を伝える
1つずつ解説します。
外国人労働者の受け入れ体制を整える
外国人労働者が働きやすいように、受け入れ体制を整えることが大切です。外国人が不満や不安を抱えると早期離職につながるほか、逃亡や失踪に発展するリスクもあります。
以下は受け入れ体制を整える具体例です。
受け入れ態勢を整える具体例
- 文化・価値観の理解を深める研修を実施する
- 社内で日本語教室を開催する
- 外国人労働者向けの苦情・相談窓口を設置する
- 住居の確保や銀行口座開設など生活面のサポートを提供する
- 在留資格の更新などの法的手続きをサポートする
これらのサポートを自社だけでおこなうのが難しい場合には、外部への委託も可能です。
例えば、特定技能1号外国人を雇用する場合には、登録支援機関に委託できます。登録支援機関では、特定技能1号の外国人を雇用するときに必要な支援計画や義務的支援を行ってくれます。
数ある登録支援機関の中でどの機関に依頼すれば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。
無料で登録支援機関の一覧を検索でき、雇用したい地域や国籍、業界、職種、在留資格などから、貴社にぴったりの機関をご紹介します。
雇用契約書の内容を明確に伝える
外国人労働者と雇用契約を結ぶ際には、業務内容や雇用条件について誤解が生まれないように正しく伝える必要があります。
きちんと伝わっていないと、雇用後に「聞いていた条件と違う」「この仕事は自分の業務ではない」などの誤解や不満が生じてトラブルに発展する可能性が高くなります。
労働条件を正しく伝えるためには、雇用契約書の内容を通訳を介して伝える、母国語で書面を準備するなどの配慮が必要です。
分からない点や疑問点も解消できるように確認し、明確にわかりやすく伝えるようにしましょう。
外国人採用の窓口では、外国人雇用における基本情報が知りたい方に向けて「外国人採用BOOK~入門編~」がわかる資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人採用の基本で
お悩みの方に
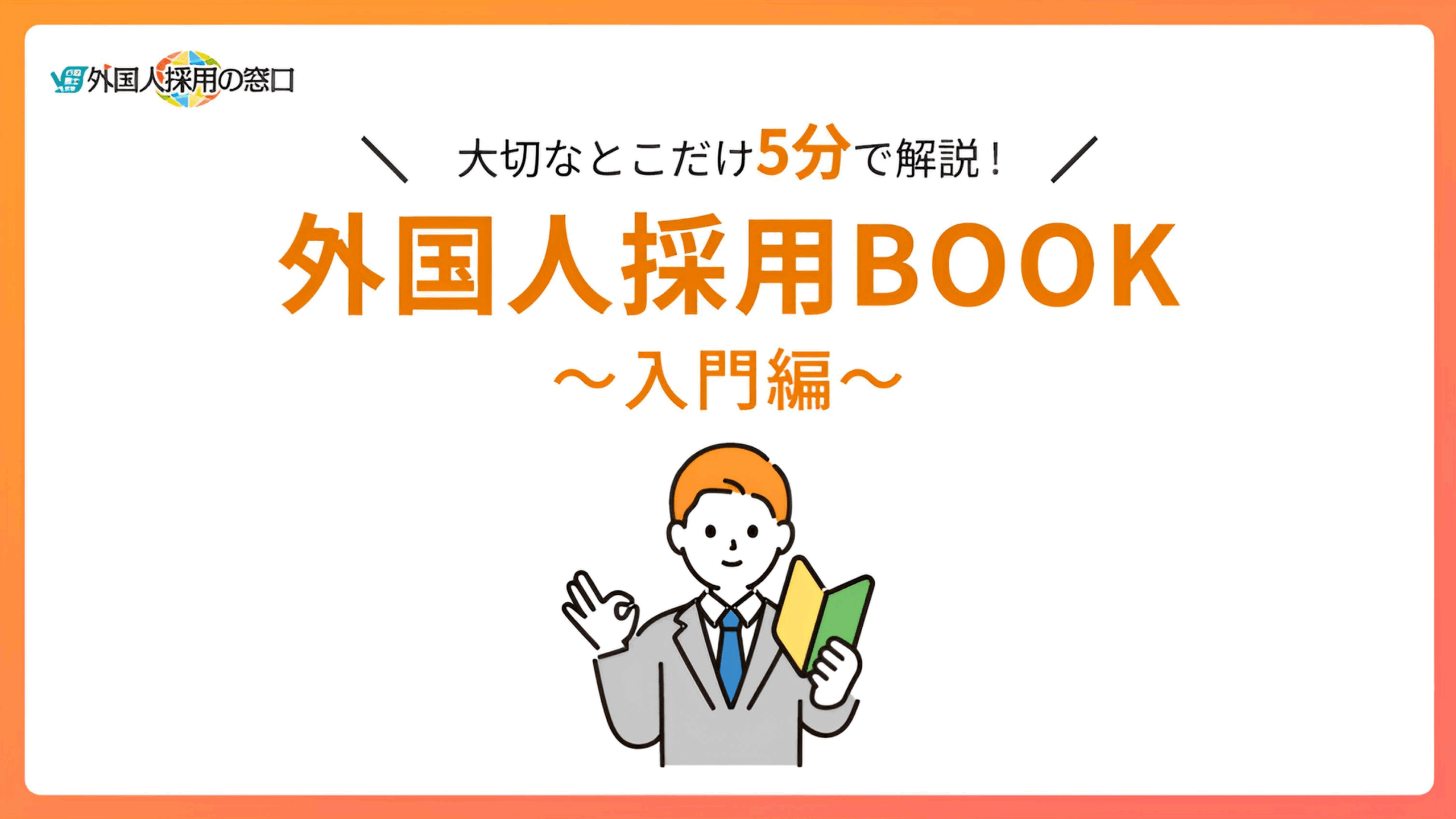
この資料でわかること
- 外国人労働者の現状
- 雇用できる在留資格の確認方法
- 外国人雇用における注意点
- 外国人を受け入れる流れ
日本の仕事観・文化を伝える
外国人労働者とのトラブルの多くは、文化や価値観の違いによるものです。
日本の企業で働くには、日本の仕事観や文化を理解してもらう必要があります。雇用前のオリエンテーションや定期的な研修を通じて理解を深められるようにしましょう。
また、日本の従業員に対しても、働いている外国人の文化や仕事観を理解する姿勢を持つ事も大切です。
お互いに文化や価値観の違いを受け入れて協力できる体制を整えるようにするとトラブルを未然に防げます。
外国人労働者の受け入れに不安がある方は「外国人採用の窓口」にご相談ください

「外国人雇用で不要なトラブルを防ぐためにプロのアドバイスがほしい…」
「初めての受け入れで不安なので手続きを外部機関にお願いしたい…」
「登録支援機関や監理団体など、どの会社を選んだらいいのかわからない…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した監理団体や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
外国人雇用におけるプロの仲介会社は、企業と外国人労働者の間で起こりやすいトラブルについて熟知しており、相談すれば適切なアドバイスをもらえるケースも多いです。
自社だけの対応が難しいと感じたら、当サービスの条件検索にて、あなたの業種・雇用したい在留資格・国籍に対応した仲介会社を探してみてください。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
完全無料でこれらサービスをご利用いただけます。外国人雇用を前向きにご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
外国人労働者のトラブル事例を知って対策を考えよう

外国人を雇用すると、言語や文化、価値観の違いからさまざまなトラブルが生じやすいです。トラブルが万が一起きてしまった場合には、本人と直接話し合い、それでも解決が難しい場合には、外国人雇用に関する相談窓口の利用を検討してみてください。
外国人労働者とのトラブルを避けるためには、外国人労働者の受け入れ体制を整え、文化や価値観の違いを理解する姿勢をもつことが大切なポイントです。雇用条件についても丁寧に確認し齟齬がないようにしましょう。
もし、自社だけでおこなうのが難しい場合には、行政書士や登録支援機関、監理機関などの外部の支援機関を利用するとスムーズに進めることができます。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。