「外国人労働者を雇用したいけど、言語や文化の違いから問題が生じないか心配」
「外国人労働者の雇用で直面する課題を解決して、働きやすい職場環境を作りたい」
このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
日本国内では深刻な人手不足を背景に、外国人労働者の需要が高まっています。
しかし、実際に雇用を進めるとなると、在留資格や賃金・労働環境といった複雑な問題・課題に直面するケースも少なくありません。
本記事では、外国人労働者の雇用における具体的な問題点と効果的な解決策について解説していきます。業界別の取り組み事例や問題解決によって得られるメリットについても紹介しているので参考にしてみてください。
外国人採用の基本で
お悩みの方に
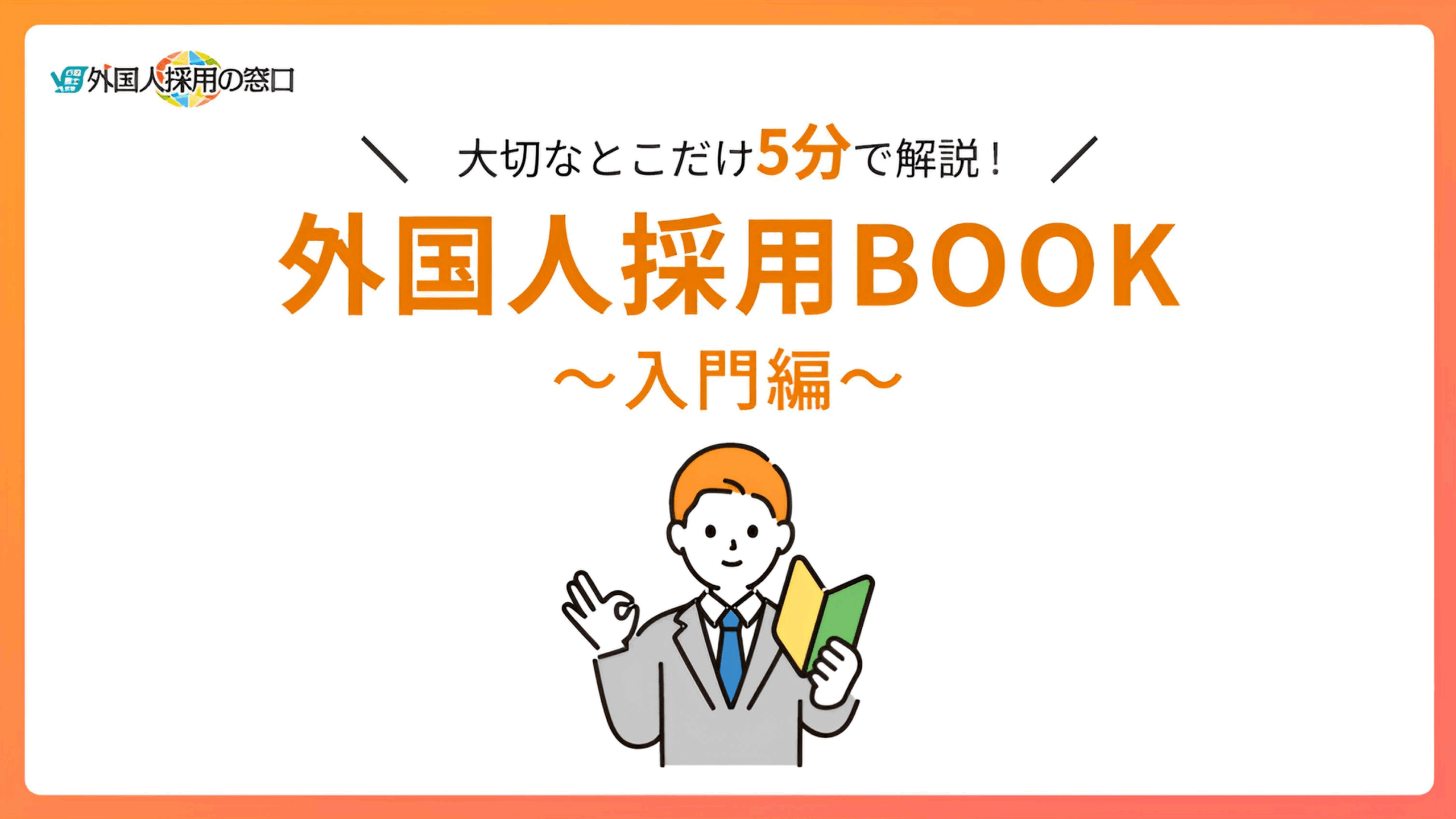
この資料でわかること
- 外国人労働者の現状
- 雇用できる在留資格の確認方法
- 外国人雇用における注意点
- 外国人を受け入れる流れ
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
外国人労働者に関する問題の現状

日本で働く外国人労働者数は年々増加傾向にありますが、雇用する企業側ではさまざまな課題に直面しているのが現状です。
厚生労働省の「令和5年外国人雇用実態調査の概況」によると、日本で働く外国人労働者数は約159万人に達しています。多くの企業が外国人材を重要な労働力として活用している中で、以下のような問題も挙げられています。
| 外国人労働者の雇用に関する課題 | 割合 |
| 日本語能力等のためにコミュニケーションが取りにくい | 44.8% |
| 在留資格申請等の事務負担が面倒・煩雑 | 25.4% |
| 在留資格によっては在留期間の上限がある | 22.2% |
| 文化、価値観、生活習慣等の違いによるトラブルがある | 19.6% |
出典:厚生労働省「外国人雇用実態調査の結果」
特に日本語能力によるコミュニケーション問題は約半数の企業が直面しており、外国人労働者の雇用における深刻な問題となっています。
外国人労働者の雇用における6つの問題点

日本国内で外国人労働者を雇用する際には、いくつかの重要な課題が存在します。
- 在留資格によっては就労制限がある
- コミュニケーションに問題がある
- 差別で過酷な労働環境にさらされる
- 低賃金・賃金未払い問題がある
- 地域社会との関係に溝がある
- 法的ルールや手続きが複雑である
これから説明する課題を理解し、適切に対処することが求められています。
在留資格によっては就労制限がある
外国人労働者の雇用において、最も大きな課題の一つが就労制限です。
日本の在留資格制度は非常に複雑で、資格ごとに就労できる業種や条件が異なります。
このため、企業は外国人労働者を雇用する際に、適切な在留資格を確認しなければならず手続きが煩雑になる場合があります。
また、就労制限があると、企業側が求めるスキルや経験を持つ人材を確保するのが難しくなるケースも少なくありません。
これにより、企業は必要な人材を見つけられず、結果的に人手不足が解消されないという悪循環に陥る可能性があるのです。
在留資格ごとの就労制限の内容や職業例については、以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
【関連記事】
採用してもいい在留資格って? | 全29種一覧&職業例あり
コミュニケーションに問題がある
外国人労働者を雇用する際にしばしば直面する課題の一つが、コミュニケーションの問題です。
言語の壁は、業務の円滑な進行を妨げる要因となり、誤解やトラブルを引き起こす場合があります。
また、文化や習慣の違いからくるすれ違いも、職場の雰囲気を悪化させる要因です。
さらに、外国人労働者が社会的に孤立するケースも多く、これが精神的なストレスを引き起こす可能性もあります。
こうしたコミュニケーション課題への対処は、外国人労働者の定着や職場の生産性向上において非常に重要です。
外国人労働者を雇用検討している方に向けて「外国人社員とのコミュニケーションのコツ」のお役立ち資料を無料で用意しています。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人社員との
やりとりでお困りの方に

この資料でわかること
- 外国人雇用における言語課題
- 伝わりにくいコミュニケーション例
- 伝わりやすいコミュニケーション例
- 外国人社員にあった指導方法
差別で過酷な労働環境にさらされる
外国人労働者が直面する課題の一つに、差別で過酷な労働環境にさらされる点が挙げられます。
外国人労働者は、過酷な労働条件や長時間労働にさらされるケースもあり、これが健康や生活の質に悪影響を及ぼすリスクにつながりますが。
特に、労働時間の管理が不十分であったり、適切な休暇が与えられなかったりする場合、心身の疲労が蓄積し、結果として労働意欲の低下や離職につながることも少なくありません。
また、労働環境の悪さは、外国人労働者が日本での生活に適応する上でも大きな障壁です。
言語や文化の違いから、労働条件についての不満を表明するのが難しい場合も多く、これがさらなるストレスを生む要因となります。
低賃金・賃金未払い問題がある
外国人労働者の雇用において、低賃金や賃金未払いの問題は深刻な課題の一つです。
多くの外国人労働者は、生活費をまかなうために日本に来ているため、適正な賃金が支払われない場合、経済的な困難に直面します。
特に、技能実習生制度においては、実習生が受け取る賃金が低く設定されているケースが多く、労働条件が厳しい状況が指摘されています。
さらに、賃金未払いの問題も頻繁に発生しており、労働者が働いた分の報酬を受け取れないケースが後を絶ちません。
このような状況は、外国人労働者の生活を脅かすだけでなく、企業の信頼性にも悪影響を及ぼします。
地域社会との関係に溝がある
外国人労働者の雇用が進む中で、地域社会との関係性が希薄になることが懸念されています。
外国人労働者が地域に馴染めず、孤立した状態で生活するケースが増えているのです。このような状況は、地域住民との交流が不足して、相互理解や信頼関係の構築が難しくなります。
また、地域社会における外国人労働者への偏見や誤解が広がって、さらなる溝が生まれる場合もあります。
これにより、外国人労働者が地域に対して抱く不安感や疎外感が強まり、結果として地域全体の活力が低下する恐れもあるのです。
地域社会と外国人労働者が共に成長し、支え合う関係を築く取り組みが重要です。
法的ルールや手続きが複雑である
外国人労働者を雇用する際、法的なルールや手続きが非常に複雑であることが大きな問題です。
日本には多様な在留資格が存在し、それぞれに異なる条件や手続きが求められます。
このため、企業側は適切な在留資格を選定し、必要な書類を整える業務に多くの時間と労力を費やさなければなりません。
また、法改正や制度変更が頻繁に行われるため、最新の情報を常に把握する作業にも苦労するでしょう。
このような煩雑さが、外国人労働者の雇用をためらわせる要因となっています。
在留資格の申請・更新手続きについては、公的手続きに精通した行政書士への委託が効果的です。
「外国人採用の窓口」では、希望するエリアの行政書士事務所を検索でき、貴社のニーズを満たした最適なパートナーを見つけられます。無料で利用できるので、お気軽にお試しください。
外国人労働者の問題に対する6つの解決策

外国人労働者の雇用における問題を解決するためには、以下のような多角的なアプローチが必要です。
- 外国人の在留資格や法律の理解を深める
- 日本人社員との交流の機会を増やす
- 給料や福利厚生を日本人社員と同等にする
- 日本語教育の機会を提供する
- 多言語で情報提供する
- 明確なキャリアパスを提示する
それぞれの解決策について具体的に解説していきます。
外国人の在留資格や法律の理解を深める
外国人労働者を雇用する際には、在留資格や労働条件に関する法律を正確に理解することが不可欠です。
日本には多様な在留資格が存在し、それぞれに異なる就労条件が設定されています。
企業はこれらのルールを把握し、適切な手続きで、法的トラブルを避けられます。また、外国人労働者も自分の権利や義務の理解が重要です。
これにより、労働環境の透明性が高まり、双方の信頼関係の構築につながります。
ルールの理解を深めるためには、専門家のアドバイスや、研修の実施が効果的です。
外国人雇用における法的な留意点については、こちらの記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
最新|外国人採用で失敗しないための注意点!在留資格別条件、採用プロセス、法律、文化の壁、トラブル事例
日本人社員との交流の機会を増やす
外国人労働者が日本の職場にスムーズになじむには、日本人社員との交流がとても大切です。
交流が増えると、文化や考え方の違いを理解し合え、信頼も深まります。以下は企業側と外国人労働者の関わりが増える効果的な取り組みの例です。
取り組みの例
- チームでのレクリエーションや社内イベントを定期的に開く
- 英語が話せる先輩社員をメンター(相談役)としてつける
- 英語での相談窓口を設ける
交流のきっかけを増やせば、外国人も安心して働けるようになり、職場全体の雰囲気もよくなります。結果として、仕事の効率も高まるでしょう。
給料や福利厚生を日本人社員と同等にする
外国人労働者には、日本人社員と同じ給料や福利厚生を用意しましょう。待遇が平等なら、仕事へのやる気が高まり、長く働いてもらいやすくなります。
そもそも国籍や社会的身分などを理由とした賃金、労働時間をはじめとする労働条件の待遇差は「労働基準法第三条」で禁止されています。
待遇への配慮は、人材を守るだけでなく、企業の成長につながる「未来への投資」として考えてみてください。
待遇面以外の注意点については、以下の記事で紹介していますので参考にしてみてください。
【関連記事】
外国人雇用の注意点を徹底解説!受け入れるメリットも一緒に紹介
日本語教育の機会を提供する
外国人が日本で安心して働くには、日本語の習得が欠かせません。言葉が通じにくいと、職場でのやりとりに時間がかかり、誤解も起きやすくなります。そのため、企業が外国人労働者の日本語学習をサポートしましょう。
以下は企業で取り組めるサポート例です。
サポート例
- 社内で日本語教室をひらく
- オンライン学習の仕組みを導入する
- 学習のようすを定期的にチェックし、必要に応じて個別指導をする
こうした工夫があれば、外国人は早く職場に慣れ、自信を持って仕事に取り組めます。
業務マニュアルや掲示物などの文書を作成する際は、難しい表現を避け、理解しやすい「やさしい日本語」を使用すると、外国人労働者のスムーズな日本語習得に役立ちます。
外国人労働者との日本語コミュニケーションに不安がある方に向けて「やさしい日本語コミュニケーション 」のお役立ち資料を用意しています。「やさしい日本語の基準が知りたい」という方は、無料でダウンロードできますので参考にしてみてください。
外国人社員との
日本語コミュニケーションに
お悩みの方に

この資料でわかること
- 日本語が難しい理由
- 外国人と会話するときの注意点
- やさしい日本語の概念
- やさしい日本語のポイント
多言語で情報提供する
外国人労働者が職場で安心して働ける環境づくりには、多言語での情報提供も効果的です。
業務に関するマニュアルや社内通知、研修資料などを複数の言語で表記すると、外国人労働者の理解力の向上が期待できます。
多言語で情報提供する方法
スマートフォンのアプリをはじめとする、ICTを積極的に活用した多言語対応の導入で、リアルタイムでの情報共有が可能です。
また、翻訳アプリや音声認識機能を活用すれば、即座に必要な情報を母国語で見られるため、業務効率の向上にもつながります。
さらに、ピクトグラム(情報や指示を、単純化した絵や図形のみで伝える視覚的記号)や図を使った視覚的な表示も非常に有効です。
言語に依存しない図解やイラストを活用することで、文字による説明が困難な場面でも、直感的に理解できる情報提供が可能になります。
これらの取り組みにより、外国人労働者にとって必要な情報を適切に受け取れる環境を構築できます。
明確なキャリアパスを提示する
外国人労働者が日本で長く働き続けるには、将来の働き方の道筋をはっきり示すことが大切です。
キャリアパスが不明確な場合、外国人労働者は先が見えずに不安を抱え、モチベーションが下がってしまうリスクがあるからです。
以下はキャリアパスを明確にするための対応策です。
キャリアパスを明確にする対応策
- 定期的な人事評価や研修を実施する
- 昇進やスキルアップの流れを説明する
- キャリアについて相談できる場を用意する
今後の成長のイメージが見えると、外国人労働者に安心感が生まれ、長く働きたい気持ちにつながります。
外国人労働者にとって、働きやすい職場のポイントは以下の記事で解説していますので、参考にしてみてください。
【関連記事】
外国人が多い職場の特徴とは?働きやすい職場にするポイントも解説! | 外国人採用の窓口
【業界別】外国人労働者の問題に対する取り組み事例

外国人労働者の雇用における問題解決のため、各業界では以下のような、さまざまな取り組みが実施されています。
- 製造業での事例
- サービス業での事例
- 介護分野での事例
企業の事例を通じて、効果的な解決策を確認していきましょう。
製造業での事例
機械器具製造業の「株式会社水登社」では、社員の約4分の1が外国人労働者という環境で、包括的な支援体制を構築しています。
外国人社員向けには日本語やビジネスマナーの研修を実施し、翻訳した社内通達をSNSで配信し情報共有を徹底しています。
また、生活支援員による相談窓口を設置しているため、職場だけでなく生活面のサポートができるのも特徴です。
さらに、日本人社員向けに「やさしい日本語」の研修を実施して、方言や擬音語など外国人に伝わりにくい日本語を使わないよう意識づけを図っています。
この取り組みにより、一つの企業に長く勤める日本の働き方の良さを先輩外国人社員が後輩に伝えるようになり、外国人社員の定着にもつながっています。
参考:経済産業省近畿経済産業局「外国人材の受入れ・活躍事例をご紹介します」
サービス業での事例
大阪王将を展開する「株式会社ヒロフードサービス」は、社員35名のうち20名が外国人労働者という高い割合で外国人材を活用している企業です。
ヒロフードサービスでは、同じ出身国の外国人労働者を技術・人文知識・国際業務の在留資格でマネージャーとして雇用し、後輩外国人のサポート役に配置しました。
雇用した外国人に対して作成するキャリアプランによって、将来の展望が明確になり長期的な雇用関係を構築しています。
日本人社員も「やさしい日本語」研修会などに参加し、双方から寄り添う姿勢を示すことで、円滑なコミュニケーション環境を実現しています。
参考:経済産業省近畿経済産業局「外国人材の受入れ・活躍事例をご紹介します」
外食業界における外国人労働者の雇用状況については、以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
【関連記事】
外食業界における外国人雇用に関する実態調査|採用状況、採用方法、採用の課題について
介護分野での事例
栃木県内で8つの福祉施設を運営する社会福祉法人では、500人の職員のうち11%にあたる53人が外国人労働者です。
外国人に対して言語の壁を取り除く工夫として、ピクトグラムの掲示やマニュアルの内容がやさしい日本語で紹介されました。
特に細かな作業には写真を添えて、視覚的に理解しやすい環境を整備しています。
また、外国人を一堂に集めた研修会を定期的に開催し、業務への理解を深めるとともに、外国人労働者同士のネットワーク構築も支援しています。
参考:NHK「増える外国人労働者の労災 あなたの職場は大丈夫?【Q&Aも】」
これから外国人労働者を雇用検討する方に向けて「グローバル採用で成功・失敗する企業の特徴」のお役立ち資料を用意しています。「他の企業はどうやって成功したの?」「リスクと解消策を事前に知っておきたい」という方は、無料でダウンロードできますので参考にしてみてください。
戦略的な外国人採用で
他社と差別化したい方へ

この資料でわかること
- 中小企業と外国人採用の相性
- 外国人採用で差をつける方法
- 外国人が持つ在留資格の特徴
- 特定技能外国人の採用戦略
外国人労働者の問題解決で得られる4つのメリット

外国人労働者に関する課題に真剣に取り組むことで、企業は以下のようなメリットを享受できます。
- 人手不足を解消できる
- 外国人労働者の定着率が上がる
- 企業のブランドイメージアップに繋がる
- 海外展開の強みとなる
これから説明するメリットを理解し、自社の課題を解決していきましょう。
人手不足を解消できる
日本国内では、少子高齢化が進む中で人手不足が深刻な問題となっています。特に、製造業や介護業界などでは、労働力の確保が急務です。
外国人労働者を雇用すれば、これらの業界における人手不足を効果的に解消できます。
多様なスキルや経験がある人も多く、外国人労働者は企業の生産性向上に貢献してくれる存在です。また、彼らの存在は新たな視点やアイデアをもたらし、職場の活性化にもつながります。
したがって、外国人労働者の雇用は、単なる労働力不足の解消にとどまらず、企業全体の成長促進に期待が持てます。
なお、外国人労働者の採用がうまくできるか不安な場合は、人材紹介会社の利用がおすすめです。
適正な人材とのマッチング以外にも、在留資格や各種届出のサポートを受けられ、外国人労働者の定着率向上にもつながります。
数ある人材紹介会社の中でどの人材紹介会社を選べば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。
無料で外国人紹介会社の一覧を検索でき、雇用・受入れしたい地域や国籍、業界、職種、在留資格などから、貴社にぴったりの会社・団体をご紹介します。
参考:
外国人労働者の定着率が上がる
外国人労働者に関する課題に真剣に取り組めば、定着率向上につながります。
定着率が高まれば、安定した人材を確保でき、業務の効率化や生産性のアップも期待できます。
職場への定着に向けた対策と成果についての全国的な調査結果は、以下の記事で紹介していますので、参考にしてみてください。
【関連記事】
外国人労働者採用後の労働環境の変化|採用する際の課題や採用後の成果について
企業のブランドイメージアップに繋がる
外国人労働者を積極的に雇用する企業は、多様性を尊重する姿勢が評価されブランドイメージの向上につながります。
ブランドイメージが高まれば、顧客や取引先からの信頼を得やすくなるため売上アップにも直結するでしょう。
また、ダイバーシティを推進すると、社会的責任を果たしていると見なされさらなる評価アップが期待できます。海外展開の強みとなる
海外展開の強みとなる
外国人労働者を雇用することは、企業にとって海外展開の強みとなります。
多様なバックグラウンドを持つ外国人労働者は、異文化理解や国際的な視点を企業にもたらし、グローバルな市場での競争力を高める要素となります。
特に、外国人労働者が持つ言語能力や地域特有の知識は、海外進出を目指す企業にとって貴重な資源です。異なる視点やアイデアが交われば、新たなビジネスチャンスが生まれる可能性も高まります。
外国人労働者の問題を減らして雇用したいなら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「外国人労働者を雇用したいが、言語の壁や文化の違いによる問題が心配…」
「外国人労働者の雇用に関する課題を解決できる専門家を見つけたいが、どこを選べばよいか迷っている…」
「在留資格の手続きやサポート体制について専門家に相談したい…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した監理団体や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。貴社の採用したい在留資格や国籍の外国人に合わせて、最適なパートナー企業とのマッチングをお手伝いいたします。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
これらサービスは、完全無料です。外国人雇用を前向きにご検討中の方は、お気軽にご利用ください。
外国人労働者問題の解決策に関するよくある質問
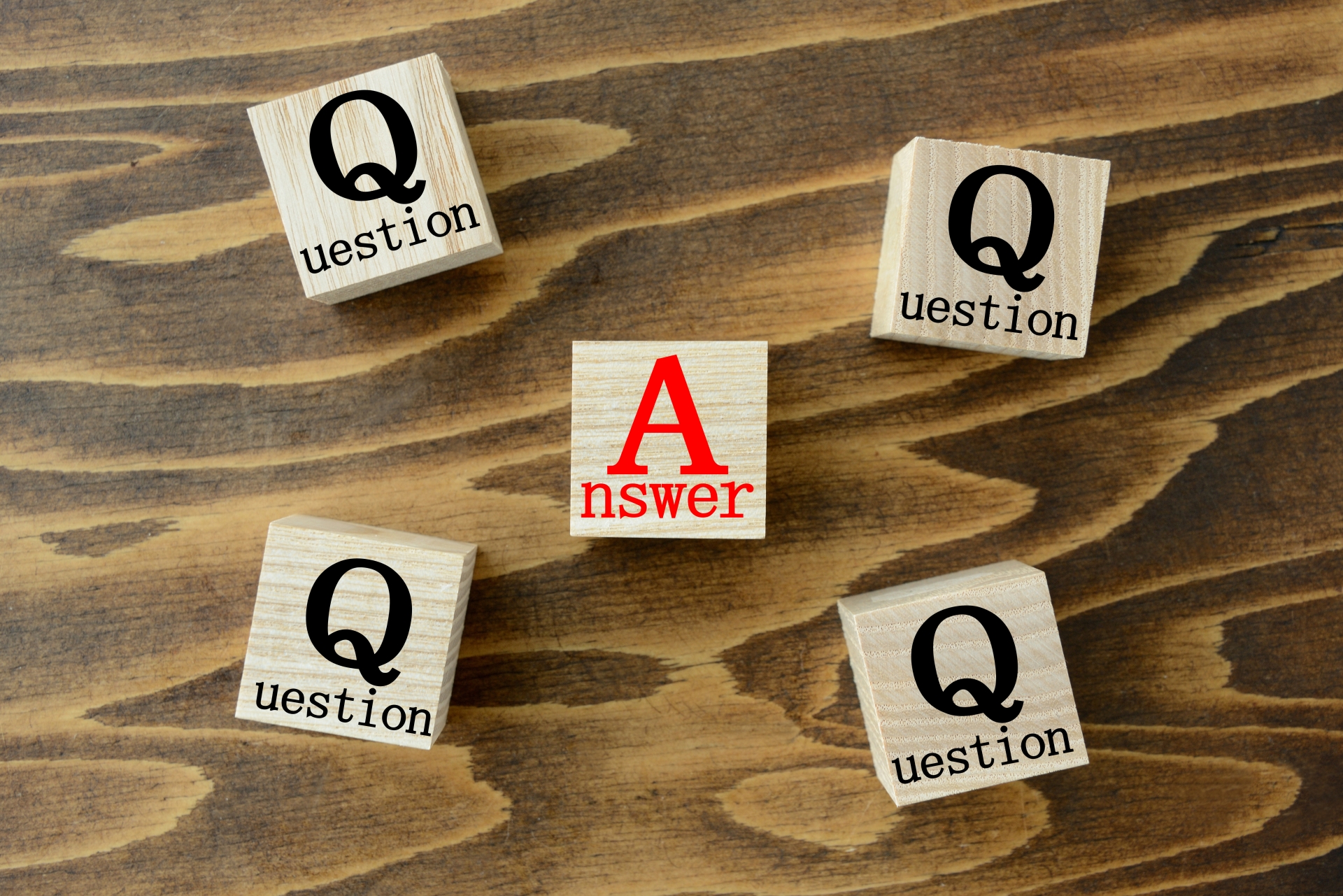
最後に、外国人労働者の問題と解決策に関するよくある質問と回答を紹介します。
外国人労働者に関連するトラブル件数や傾向はどうなっていますか?
厚生労働省の「令和5年外国人雇用実態調査」によると、外国人労働者の就労上のトラブルの発生状況は「なし」が82.5%で「あり」が 14.4%です。
外国人労働者のトラブル内容の内訳を、以下の表にまとめました。
| トラブル内容 | 割合 |
| 紹介会社(送出し機関含む)の費用が高かった | 19.6% |
| トラブルや困ったことの相談先がわからなかった | 16.0% |
| 事前の説明以上に高い日本語能力が求められた | 13.6% |
| その他 | 34.5% |
出典:厚生労働省「令和5年外国人雇用実態調査」
特に、紹介会社の費用負担や相談先の不明確さが主な課題として挙げられています。
最近の外国人労働者問題に関するニュースで注目すべき点は何ですか?
最近の外国人労働者問題で最も注目すべき点は、2027年までに段階的に導入される「育成就労制度」の創設です。
この制度は、従来の技能実習制度に代わる新しい仕組みとして位置づけられており、外国人労働者の受け入れ環境の大幅な改善が期待されています。
育成就労制度では、転籍条件の緩和や労働者の権利保護の強化など、従来の制度で課題となっていた点が改善される予定です。
制度の詳細や技能実習制度との違いについては、以下の記事で詳しく解説していますので、参考にしてみてください。
【関連記事】
育成就労制度とは|いつから始まる?技能実習との違いや転籍の条件を徹底解説
外国人労働者問題の具体的な解決策を見つけて働きやすい職場づくりをしよう

外国人労働者の雇用における問題は、言語の壁によるコミュニケーション不足や在留資格の複雑な手続き、文化・価値観の違いによるトラブルなど多岐にわたります。
しかし本記事で紹介した適切な解決策を実施することで、外国人労働者が働きやすい職場環境の構築は可能です。
とはいえ、在留資格の申請・更新手続きや外国人社員の生活支援、多言語でのコミュニケーション体制の構築など、専門知識を要する業務や企業単独での対応が難しいケースも起こりえます。
日本人と外国人の双方が働きやすい職場づくりのためには、外国人採用に特化した専門機関への依頼を検討し、計画的に外国人雇用を進めましょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。


