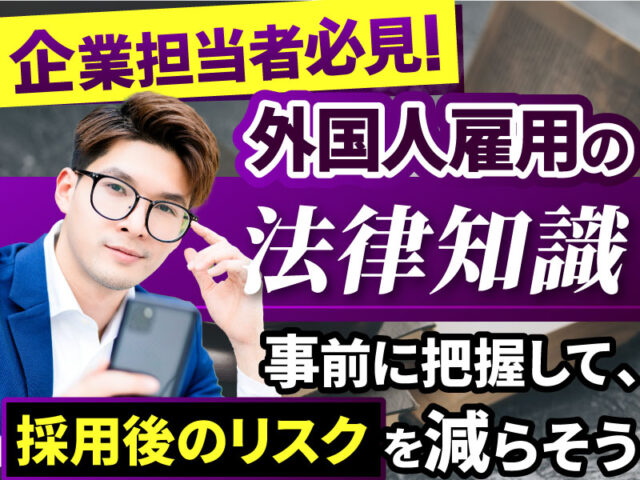外国人を雇用する際には、日本人と同様の待遇を確保するだけでなく、入管法や労働基準法など多くの法律を順守する必要があります。しかし、在留資格ごとの就労範囲や、労働条件の設定、社会保険の加入要件など、確認すべき事項は多岐にわたり、担当者にとっては複雑に感じられる場面も少なくありません。適切な理解と管理ができなければ、企業側にも罰則やトラブルのリスクが生じます。
この記事では、外国人雇用に関係する主な法律を体系的に整理し、それぞれの概要や注意点をわかりやすく解説します。
入管法や技能実習法など外国人特有の規定から、労働基準法や最低賃金法といったすべての労働者に共通する法律まで幅広く取り上げ、企業担当者が押さえるべきポイントをまとめます。
INDEX
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
外国人の雇用や生活に関係する法律・ルール
外国人を雇用する際には、出入国や就労関係の許可など、継続的な在留に直結する制度の正確な理解が欠かせません。
ここでは、外国人雇用に特有の各種法令や、その運用における注意点について解説します。
入管法
出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)は、日本への入国・出国の管理や、在留資格の許可・取消、不法滞在の取締り、強制送還、難民認定などを包括的に規定する外国人受入れ制度の根幹となる法律です。
この法律では、29種類の在留資格ごとに認められる活動の範囲や就労の可否が定められ、不法就労や在留資格外活動に対する罰則も規定されています。
外国人を雇用する企業は、在留カードや資格外活動許可の有無、就労時間の上限などを確認し、入管法違反を防ぐ管理体制を整えなければなりません。
また、入管法は本体の法律に加えて、施行規則や上陸基準省令、特定技能基準省令、高度専門職省令などの政省令、さらに告示によって詳細な運用が定められています。
適切な外国人雇用のためには、これら複数の法令を横断的に確認し、常に正確な情報を把握する姿勢が不可欠です。
入管法施行規則
入管法施行規則は、入管法で定められた制度や義務を実務的に運用するための詳細を規定する省令です。
この規則では、在留資格の申請や変更、更新の手順、必要書類の種類と記載事項、提出期限など、具体的な手続きの流れが示されています。
企業が雇用する外国人従業員の各種申請をサポートする場合も、この規則に基づいて正確な対応を行う必要があります。
また、特定技能の在留資格を持つ従業員が行方不明になった場合など、一定の事態が発生した際の届出義務についてもこの省令に規定されています。
こうした定めは不法就労防止や適正な在留管理の確保を目的としており、違反すれば企業側にも行政処分や罰則が及ぶ可能性があります。
上陸基準省令
上陸基準省令は、入管法に基づき、各在留資格を取得するために必要な条件を具体的に定めた省令です。
例えば特定技能では、許可取得の基準として、年齢、健康状態、技能水準、日本語能力、不当な財産移転契約の排除、外国人が定期負担する費用の適正性などの詳細な要件が規定されています。
外国人が日本で継続的に活動するためには、入国時だけでなく在留期間の更新や資格変更の際にも、在留資格ごとの上陸許可基準を満たし続ける必要があります。
これらの基準設定により、日本の産業や国民生活への影響を考慮しつつ、受け入れ条件を調整しながら制度を運用する仕組みが構築されています。
特定技能基準省令
特定技能基準省令は、特定技能外国人を受け入れる企業が遵守すべき雇用契約や支援体制の要件を定めた省令です。
この中では、日本人と同等の報酬水準の確保、差別的待遇の禁止、出入国時の送迎、生活オリエンテーションの実施義務など、適正な受け入れのための具体的基準が規定されています。
また、過去の法令違反や不適切な受け入れがあった場合の欠格期間(受け入れ停止期間)も規定されており、特定技能制度を活用して外国人を多く雇用する企業にとって、必ず確認しておくべき重要な内容となっています。
高度専門職省令
高度専門職省令は、高度専門職1号および2号の在留資格取得時に適用される、ポイント制による評価基準を定めた省令です。
この制度は、「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「教授」「研究」などと同様の業務に従事する予定の、高度な専門能力を有する外国人材を対象としています。
ポイントは、学歴や職歴、年収、研究実績、日本語能力など複数の要素で算出され、一定の基準を満たすことで在留資格に関する優遇措置が受けられることです。
高度専門職の在留資格を取得すると、長期の在留期間や永住許可要件の緩和、家族帯同の範囲拡大など、通常の就労資格を上回る特典が付与されます。
特に「技術・人文知識・国際業務」の従業員を多く抱える企業は、該当人材が基準を満たしているか確認することで、雇用戦略の幅を広げられます。
技能実習法
技能実習法は、外国人技能実習制度の運用方法や実習生の権利保護を目的として制定された法律です。
技能実習の在留資格や出入国管理に関する枠組みは入管法で規定されていますが、実習内容や受け入れ体制の詳細は技能実習法に基づいて運用されます。
実習計画の認定や監理団体の許可、受け入れ企業の遵守事項などに関するルールが規定されており、適正な技能移転を促す仕組みになっています。
また、技能実習法には監査拒否や虚偽報告、実習計画に反する行為などに対する罰則が設けられており、違反があれば許可の取消や刑事罰が科される可能性があります。
技能実習生を受け入れる事業者は、入管法の遵守だけでなく、技能実習法により定められた禁止事項を理解し、適切な管理を行うことが求められます。
労働施策総合推進法
労働施策総合推進法は、労働者の雇用安定と社会的地位の向上を通じて経済や社会の発展を促すことを目的とした法律です。
この法律では、外国人を雇用した場合や離職した場合に「外国人雇用状況の届出」を行う義務が定められており、企業はそれぞれの事由が発生した月の翌月末までにハローワークへ届け出る必要があります。
ただし、雇用保険の被保険者資格を取得または喪失する届出を行う場合は、同時に外国人雇用状況の届出についても実施したものとみなされます。雇用保険の届出期限は、雇い入れ時が翌月10日まで、離職時が翌日から起算して10日以内とされており、外国人雇用状況の届出を単独で行う場合とは期限が異なるため注意が必要です。
二国間協定
二国間協定は、特定技能や技能実習などの分野で、日本と相手国が受入れ条件を調整するために締結する取り決めです。
特定技能や技能実習においては、「二国間協力覚書」により、両国の法制度や労働慣行を踏まえた運用ルールが策定されます。
また、経済連携協定(EPA)に基づき、外国人看護師や介護福祉士の受入れが行われるケースもあり、制度ごとに対象国や内容が異なります。
海外から人材を採用する際は、送り出し国の規制に抵触しないよう、必ず二国間協定などの関連ルールを確認しておくことが重要です。
参考:出入国在留管理庁|特定技能に関する二国間の協力覚書
参考:厚生労働省|技能実習に関する二国間取決め(協力覚書)
日本人・外国人双方に適用される法律
日本国内で働くすべての労働者には、国籍を問わず労働条件や安全衛生などに関する法律が適用されます。
ここでは、日本人と外国人の双方に共通して適用される主な法律と、その概要について解説します。
労働基準法
労働基準法は、日本国憲法第27条第2項を根拠に、労働条件の最低基準を定め、労働者の権利を保護する法律です。
この法律は、労働契約や賃金、労働時間、休日、有給休暇などに関する基準を示し、労使間の契約が不公平にならないよう一定の制約を設けています。
さらに、国籍や性別、身上による差別を禁止しており、不法就労者であっても日本国内で雇用されている限り、労働条件についてはこの法律による保護を受けられます。
違反した事業主には罰則が科される可能性があるため、外国人雇用においても基準を満たした労働条件を整備することが不可欠です。
労働安全衛生法
労働安全衛生法は、労働者の安全確保や健康保持を目的に、災害防止策や責任体制の整備の基準を定める法律です。
この法律は、危険物の取り扱いや作業環境の改善、安全教育の実施など、職場の安全管理に関する具体的な義務を定めています。
特定技能の在留資格申請では、企業が労働法令違反の有無を申告する必要があり、この法律に違反している場合に「違反なし」として申請すると、発覚時に虚偽申請と判断される可能性があります。
そのため、特定技能外国人を雇用する企業は、労働安全衛生法の内容を正確に理解し、違反を防ぐための体制づくりと日常的な安全管理の徹底が必要です。
最低賃金法
最低賃金法は、国が定める賃金の最低基準を下回らないよう使用者に義務づける法律です。
最低賃金には、都道府県ごとに定められる地域別最低賃金と、特定の産業に適用される産業別最低賃金の2種類があり、いずれか高い方を適用します。
外国人雇用では、特に技能実習などで最低賃金を下回る条件で雇用できると誤解する事例がありますが、そのような待遇は最低賃金法違反となります。
最低賃金を下回る労働契約を結んだ場合、賃金に関する合意は無効とされ、差額支払いに加え、最低賃金法や労働基準法の罰則規定が適用される可能性があります。
労働契約法
労働契約法は、労働者と使用者の間で締結される労働契約の基本原則や契約内容の明確化、変更手続きなどを定めた法律です。
この法律は、労使双方が対等な立場で合意することを前提とし、労働契約の成立や契約内容の更新、懲戒、解雇などに関するルールを定めており、安定的かつ適正な雇用関係の形成を目的としています。
外国人雇用においても、日本人労働者と同様に不当な労働契約の無効化や契約内容の書面化の努力規定など、労働契約法のルールが適用されます。
特に、外国人の場合は、言語や文化の違いから契約内容の理解不足が生じやすいため、翻訳書面の作成や平易な日本語を用いた説明、契約書の多言語化など、理解を促す工夫が重要です。
健康保険法
健康保険法は、労働者やその扶養家族が病気や怪我、出産などの際に必要な医療給付や手当金を受けられるよう制度を定めた法律です。
この法律は、事業所に適用される健康保険の加入義務や、保険料の負担割合、給付内容などを規定し、健康維持と生活の安定を図ることを目的としています。
外国人雇用においても、一定の条件を満たす労働者は日本人と同様に健康保険への加入が義務づけられます。特に、在留資格や契約期間にかかわらず、所定労働時間や日数が要件を満たす場合には加入対象となるため、企業は雇用契約時に適用の有無を正確に判断する必要があります。
厚生年金法
厚生年金法は、老齢・障害・死亡といった生活上のリスクに備え、労働者やその家族に年金給付を行う制度を定めた法律です。
事業所に適用される厚生年金保険の加入義務や保険料の負担割合、受給資格などを規定し、長期的な生活保障を目的としています。
外国人を雇用する場合も、日本人と同様の条件で厚生年金保険の加入義務が発生します。業種や事業規模により要件は異なりますが、週の所定労働時間や雇用期間が基準を満たせば加入対象となるため、採用時点で適用可否を正確に判断することが重要です。
さらに、年金の受給資格を得る前に帰国する外国人は、脱退一時金を請求できる制度があります。企業担当者は、必要に応じてこの請求手続きの案内やサポートを行える体制を整えておくことが望まれます。
労災保険法
労災保険法は、業務上または通勤途中に発生した負傷や疾病、障害、死亡に対して、労働者や遺族へ必要な給付を行う制度を定めた法律です。
この制度は労働者の生活と健康を守ることを目的とし、事業主は原則としてすべての労働者を対象に加入義務を負います。外国人を雇用する場合も、国籍や在留資格に関わらず、日本国内で就労する労働者であれば労災保険の適用対象となります。
特に技能実習生や特定技能労働者の受入れでは、労災保険未加入や不適切な手続きが後に重大なトラブルに発展する可能性があるため、雇用契約時に確実な加入と適正な管理を行うことが重要です。
雇用保険法
雇用保険法は、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難になった際に、生活の安定や再就職を支援する給付を行う制度を定めた法律です。
この制度には失業給付のほか、育児休業給付、教育訓練給付、介護休業給付などが含まれ、労働者の生活保障と職業能力の向上を目的としています。外国人を雇用する場合も、労働時間や契約内容が加入要件を満たせば、日本人と同様に雇用保険への加入義務が生じます。
加入義務がある場合は速やかな手続きが必要であり、怠った場合には企業が行政指導や罰則の対象となる可能性があります。採用時や離職時には、必要書類を整え確実に届出を行うことが重要です。
まとめ
本記事では、外国人の雇用や生活に関わる国内外の制度、日本人と外国人の双方に共通して適用される法律について解説しました。
各法律の概要や適用範囲、遵守すべき義務を整理することで、雇用管理における見落としやすいリスクを明確にできます。
外国人材を受け入れる企業担当者は、在留資格ごとの活動範囲や労働・社会保険関連の義務を正確に把握し、手続きや契約内容を常に適法な状態に保つことが重要です。
採用計画の段階から関係法令を確認し、必要に応じて専門機関や行政窓口に早めに相談することで、トラブルの未然防止につながります。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。