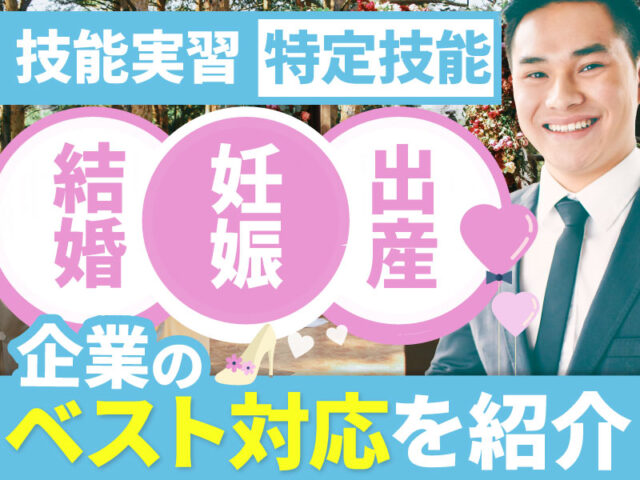技能実習生や特定技能外国人を雇用する企業にとって、従業員が結婚や妊娠をした際の対応は大きな課題となります。
異国で働く彼らの生活は在留資格の許可に基づいており、企業側が制度や法律上の正しい取り扱いを理解していなければ、思わぬトラブルへと発展するおそれがあります。
本記事では、技能実習と特定技能それぞれの制度における結婚・妊娠・出産のルールを整理し、企業がとるべき適切な対応をわかりやすく解説します。
結婚相手の在留資格による違い、産休・育休や給付制度、さらには子どもの在留資格まで幅広く取り上げ、雇用主が安心して対応できるための基礎知識をまとめています。
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
技能実習生や特定技能外国人の結婚に関するルール
技能実習や特定技能で働く外国人が結婚する際に、特別な制限は設けられていません。結婚の手続き自体は、母国の法律や国際結婚における一般的な手続きに沿って進められます。
ただし、結婚後も日本での生活を継続する場合には、配偶者の在留資格について理解しておくことが重要であり、適切な確認と対応が必要となります。
結婚相手が日本人や永住者の場合
結婚相手が日本人である場合には、在留資格として「日本人の配偶者等」を取得できる可能性があります。この資格を得ると就労制限がなくなり、職種にとらわれず幅広い分野で働けるようになります。
また、配偶者が永住者である場合には「永住者の配偶者等」という在留資格を取得できる可能性があり、こちらも同様に就労制限が設けられていないため、取得できれば活動の選択肢が大きく広がります。
さらに、日本人または永住者の配偶者であれば、婚姻生活が実体を伴って3年以上継続し、かつ1年以上日本に滞在していることで、永住許可の年数要件を満たすとされています。
そのため、通常よりも早い段階で永住許可取得の道が開かれる点も大きな特徴といえるでしょう。
結婚相手が定住者の場合
結婚相手が定住者の在留資格を持っている場合、その配偶者も審査で認められれば「定住者」の在留資格に変更することが可能です。この資格は就労制限がなく、多様な職種で働くことができる点が特徴です。
定住者としての在留を続けた場合、在留期間が5年以上に達すると永住許可の申請要件を満たすことができます。
結婚相手がその他の在留資格の場合
結婚相手が他の在留資格を持つ外国人である場合、在留資格の種類によっては配偶者に「家族滞在」が認められることがあります。
この資格では、資格外活動許可を受けても就労時間に制限があり、技能実習や特定技能と比べると働ける時間が短い点に注意が必要です。
そのため、結婚後も継続して就労するのであれば、技能実習や特定技能から家族滞在へ変更する必要性は高くないといえます。
ただし、技能実習や特定技能の在留期間が上限に近づいている場合には、家族滞在へ変更することで結果的に在留を長く続けられる可能性もあります。
技能実習からは原則として在留資格変更はできない
技能実習制度は、発展途上国の人材が日本で技能や知識を習得し、帰国後に母国で活かすことを目的として設けられています。
そのため、技能実習から他の在留資格へ変更することは原則認められておらず、例外的に特定技能への移行のみが可能とされています。
しかし、配偶者の妊娠や子どもの出生といった人道的な理由が認められる場合には、配偶者ビザなどへの在留資格変更が許可される可能性があります。
その際、取得可能な在留資格は配偶者の属性や申請理由などにより異なります。
さらに、一度帰国して技能実習を修了した後に改めて配偶者ビザを申請する方法もありますが、帰国直後の申請は審査が厳しくなる傾向があります。
技能実習と特定技能どちらも日本で妊娠・出産可能
技能実習生や特定技能外国人も、日本で妊娠や出産をすることが認められています。
ここからは、妊娠や出産に関わる具体的な制度や、企業や本人が取るべき対応について順を追って解説していきます。
妊娠期間中に就労できなくても入管法違反にはならない
在留資格を持つ外国人は、その資格に定められた活動を継続して3カ月以上行わない場合、在留資格の取り消し対象となる可能性があります。
しかし、妊娠や出産を理由に就労ができない期間については、やむを得ない事情があると判断されます。
したがって、技能実習や特定技能の従業員が妊娠により一定期間勤務できなかったとしても、入管法違反に当たることはありません。
企業側もこの点を正しく理解し、在留資格に影響が及ばないことを従業員へ説明することが重要です。
不利益な取り扱いの禁止
男女雇用機会均等法では、婚姻や妊娠、出産を理由として女性労働者に不利益な取り扱いを行うことは明確に禁止されています。
さらに、技能実習制度においても、結婚や妊娠に関する制限や不利益な取扱いは「私生活の自由を不当に制限する行為」とされており認められていません。
特定技能制度では、受け入れ機関が出入国や労働法令に関する不正や著しく不当な行為を行った場合、新規の受け入れが5年間停止される欠格期間に該当することとなります。
妊娠・出産期間の取扱い
技能実習制度では、妊娠や出産に伴う就労困難な期間は実習期間に含まれません。例えば3年間の技能実習を予定している場合でも、妊娠や出産によって一定期間働けなくなった場合には、その期間を延長して在留が認められる仕組みとなっています。
一方で、特定技能制度では令和7年8月時点において、妊娠や出産の期間を在留資格の上限年数から除外する取り扱いは導入されていません。
そのため、特定技能1号では上限である5年間に妊娠・出産による休業期間も含まれることになります。
もっとも、制度の改善を求める声は強く、有識者会議の提言を踏まえ、政府は特定技能制度においても妊娠や出産による休業期間を在留期間から除外する方向で検討を進めています。
出産した子供の在留資格
技能実習や特定技能1号の在留資格では、配偶者や子どもを扶養家族として呼び寄せることが制度上認められていません。そのため、技能実習や特定技能1号の外国人が日本で出産した場合でも、子どもに「家族滞在」の在留資格を直接付与することはできません。
しかし、日本で出生した子どもについては、人道上の観点から特例的に「特定活動」の在留許可が認められるケースがあります。
また、夫婦の一方が他の在留資格を有している場合には、その資格に応じて子どもに「家族滞在」や「永住者の配偶者等」などを申請することも可能です。
妊娠が判明した際に企業が従業員に説明すべきこと
技能実習制度では、従業員が妊娠した際に企業が行うべき説明内容について指針が定められています。
これらの内容は技能実習生に限らず、特定技能外国人にも共通して適用できるため、以下で詳しく解説します。
婚姻、妊娠、出産等を理由として解雇されないこと
婚姻や妊娠、出産を理由に解雇されないことを伝えることは、外国人従業員の不安を和らげる上で重要な説明のひとつです。中には、妊娠や出産によって一時的に働けなくなると職を失うのではないかと心配する人も少なくありません。
しかし、男女雇用機会均等法などの法制度により、婚姻や妊娠、出産を理由とする解雇は明確に禁止されています。
そのため、企業は本人が退職を希望しない限り、就労を継続できることを丁寧に説明する必要があります。
産休や育休などの休業制度
産前休業は出産予定日の6週間前から取得でき、双子以上を妊娠している場合は14週間前から利用することが可能です。
さらに、出産後には8週間の産後休業が法律で保障されており、母体の回復を最優先にできる制度が整っています。
また、育児休業は原則として子どもが1歳に達するまで取得でき、条件を満たせば延長することも認められています。
こうした休暇制度を従業員に正しく周知することで、安心して出産や育児に臨める職場環境を築くことができます。
出産一時金などの給付制度
健康保険に加入している従業員は、出産に際して出産育児一時金を受け取ることができます。また、出産のために勤務を休んだ場合には出産手当金が支給される制度があり、収入減少を補う仕組みが整えられています。
加えて、産前産後休業中は社会保険料の免除が認められており、本人と企業双方の負担を軽減することが可能です。
この他、自治体ごとに出産祝い金や子育て関連の助成制度が設けられている場合があります。
出産後に必要な手続き
子どもが日本で生まれた場合は、出生日から14日以内に市区町村役場へ出生届を提出する必要があります。
さらに、外国籍の子どもが60日以上日本に滞在する場合には、出産から30日以内に在留資格取得許可申請を行わなければなりません。
あわせて、親の国籍国の大使館や領事館に対しても出生に関する届出を行い、必要な手続きを完了させることが求められます。
妊娠中の女性労働者への対応
ここからは、妊娠中の女性労働者が安心して勤務を続けられるよう、雇用主が配慮すべき点や法令で定められた就業制限について具体的に解説します。
医師の指導による勤務内容の変更
男女雇用機会均等法では、妊娠中や出産後の女性労働者が医師などから就業上の配慮を求める指導を受けた場合、その内容を事業主に申し出ることができます。
事業主はその趣旨を尊重し、従業員が安心して働き続けられるよう勤務形態の変更や業務の軽減など必要な措置を講じる義務があります。
この制度は、母体や胎児の健康を守りながら就業の継続を可能にするために設けられており、労働環境の柔軟な調整が求められます。
また、従業員が安心して申し出を行えるように社内の体制を整え、制度の内容を正しく説明することも企業の責務といえます。
以下では、事業主が実施すべき具体的な措置について順に解説します。
妊娠中の通勤緩和
医師の指導に基づき妊娠中の従業員から申し出があった場合、事業主は通勤時の混雑を避けられるよう配慮する義務があります。
特にラッシュアワーの満員電車や長時間の移動は、母体や胎児に負担をかけるおそれがあるため、通勤緩和の措置を取ることが重要です。
対応策としては、始業・終業時刻を30分から60分程度ずらすことで混雑時間帯を避けられるようにする方法があります。
また、フレックスタイム制度を導入して柔軟な勤務時間を設定し、従業員の体調や生活リズムに合わせた働き方を実現することも有効です。
妊娠中の休憩に関する措置
医師の指導を受けた妊娠中の従業員から申し出があった場合、事業主は休憩の取り方について適切な配慮を行う義務があります。
身体への負担を軽減し、健康状態を維持するために、通常の勤務体制とは異なる休憩を設定することが求められます。
具体的な措置には、休憩時間を延長して身体を休める時間を確保する方法があります。また、1日の中で休憩の回数を増やすことで、体調の変化に応じて柔軟に休息できるようにすることも有効です。
さらに、従業員の体調や症状に合わせて休憩を取る時間帯を変更するなどの配慮も必要となります。
妊娠中または出産後の症状等に対応する措置
妊娠中や出産後に体調上の問題が生じ、医師の指導を受けた従業員から申し出があった場合、事業主は業務の調整を行う必要があります。
具体的には、重量物の取り扱い作業や長距離の歩行を伴う外勤業務、全身を常に動かすような作業は制限の対象となります。
また、頻繁な階段昇降や腹部を圧迫する姿勢を強いられる作業、全身に振動が伝わる作業についても適切な配慮が必要です。
その他、勤務時間を短縮するなどの対応も重要であり、従業員が医師の指導に従って安心して働ける環境を整えることが求められます。
労働基準法による妊婦の就業制限
労働基準法では、妊娠中の女性労働者を保護するために特定の業務や働き方に制限が設けられています。
ここからは、その具体的な制限内容について順に解説していきます。
軽易な業務への配置転換
妊娠中の女性労働者が請求した場合には、事業主はその状況に配慮し、他の軽易な業務に転換させることが労働基準法により義務付けられています。
この規定は母体の健康を守るとともに、安心して就労を継続できる環境を確保するための重要な仕組みです。
危険有害業務の制限
妊産婦を妊娠や出産に有害なおそれのある作業に従事させることは、労働基準法及び関連規則により禁止されています。
そのため、事業主は女性労働基準規則で明示された危険や健康上の影響が大きい作業に妊婦を従事させてはなりません。
具体的には、重量物の取り扱いやボイラーの操作、溶接などの業務、多量の高温・低温物体を扱う作業、極端な暑熱または寒冷の環境下での労働、異常な気圧下での業務などが挙げられます。
変形労働時間制の適用制限
変形労働時間制が導入されている場合であっても、妊産婦が請求したときには労働時間の上限が適用されます。
すなわち、1日8時間や1週40時間といった法定労働時間を超えて働かせることはできず、母体保護の観点から厳格に制限されています。
時間外労働、休日労働、深夜業務の制限
妊産婦が申し出を行った場合、事業主は時間外労働や休日勤務を命じることはできません。
また、午後10時から午前5時までの深夜勤務についても従事させることは法律上認められていません。
まとめ
本記事では、婚姻や妊娠・出産を理由とした不利益取扱いの禁止や、産休・育休などの休業制度、さらには医師の指導に基づく勤務内容の調整や労働基準法による就業制限について解説しました。
加えて、技能実習制度や特定技能制度における在留資格上の取扱い、出産後に必要な各種手続きや給付制度についても整理しました。
もし妊娠や出産に伴う働き方で不安を抱えている場合は、まず職場に相談し、各種の制度を正しく活用することが重要です。
必要に応じて自治体や労働局などの公的機関にも確認を行い、自身や家族が安心して生活できる環境を整えることから始めましょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。