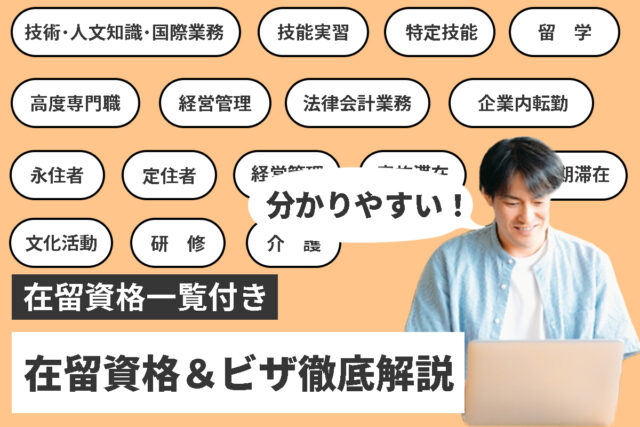「ビザと在留資格って同じものじゃないの?」
「外国人を採用する際に、どちらを確認すればいいの?」
こんな悩みはありませんか。
ビザは日本に入国するために必要となる入国許可証です。一方で在留資格は、日本に滞在してどのような活動ができるかを定めるものです。
両者は混同されがちな用語ですが全く異なるものなので、外国人雇用に携わる方は理解を深めておきましょう。
本記事では、ビザと在留資格の違いを解説します。さらに就労可能な資格の一覧も紹介しますので参考にしてみてください。
外国人採用の窓口では「外国人採用をはじめる前の基本チェックリスト」がわかる資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人採用前に
知っておくべき
チェックリスト

この資料でわかること
- 外国人採用前のチェックシート
- 採用前の具体的なチェックポイント
- 人材紹介会社を利用するメリット
- 優良な人材紹介会社の選び方
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
ビザと在留資格の違い

ビザとは、外国人が外国に入国する際に必要な上陸許可証です。
出入国管理及び難民認定法(入管法)により、日本に入国する外国人は日本国領事館などの「査証(さしょう)=ビザ」を受けたものを所持しなければ入国できません。
一方、在留資格とは、外国人が日本に入国・在留するときに従事できる活動内容や入国・在留を認めている身分や地位について法律上決めたものです。
在留資格は全部で29種類あり、外国人は許可された在留資格の範囲内でのみ活動できます。
【関連記事】
在留資格とは?取得方法や全29種類の活動内容について徹底解説します
参考:出入国管理及び難民認定法|法務省
ビザ(査証)の種類と取得方法

ビザは、日本への入国を希望する外国人が最初に取得すべき重要な許可証です。入国目的によって種類や申請先が異なり、違いを理解しておく必要があります。
以下の2つの観点から詳しく解説します。
- ビザの種類
- ビザの取得方法
どのようなビザが存在するのかを、詳しく見ていきましょう。
ビザの種類
日本のビザは、滞在期間や目的に応じて外務省が分類しています。
主なビザの種類は以下の8つです。
| ビザの種類 | 目的 |
|---|---|
| 外交査証 | 外国の元首・政府関係者などが公式の外交活動を行う |
| 公用査証 | 国際機関職員や政府関係者が、公務で日本を訪問する |
| 就業査証 | 企業勤務や専門職など、報酬を得る |
| 一般査証 | 留学・文化活動・家族滞在など、就労以外の一般的な滞在をする |
| 短期滞在査証 | 観光・親族訪問・商談など、90日以内滞在する |
| 通過査証 | 他国へ渡航する際に日本を経由する |
| 特定査証 | 日本政府が特別な理由で指定する (例:日系人・特定技能など) |
| 医療滞在査証 | 日本での治療や長期療養をする (医療滞在者向けのビザ) |
参考:査証(ビザ)|外務省
各ビザの発行要件は外務省が定めており、国や渡航目的によって必要書類が変わります。
ビザの取得方法
海外から人材を招く場合のビザ取得の流れは、まず日本の受け入れ企業が在留資格認定証明書を取得します。
その認定証を海外に送付し、外国人本人がビザ申請を行います。
ビザの申請先は、外国にある日本大使館または領事館です。
審査に通れば、ビザが発給され、日本への入国が可能になります。
在留資格の種類と取得方法

在留資格は、日本でどのような活動を行うかを法的に定める資格です。本章では、以下の2点を解説します。
- 在留資格の種類
- 在留資格の取得方法
外国人採用時に重要な確認項目となるため、種類と取得の流れを把握しておきましょう。
在留資格の種類
在留資格は、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき、活動内容別に29種類あります。大きく居住資格4種類と就労資格25種類に分けられます。
在留資格の一例
例えば、就労資格の「技術・人文知識・国際業務」は、大学の専攻内容と関連した業務に従事する場合に与えられる在留資格です。※その他にも要件あり
「技術」ではプログラマーやシステムエンジニア、「人文知識」では経理・マーケティング、「国際業務」では通訳や海外向け営業などが該当します。
同じく就労資格の「特定技能」は、一定の専門的な技能と日本語能力を有する外国人を受け入れるための在留資格です。人手不足が深刻な16の産業分野において、即戦力として働くことを目的としています。
以下の記事では、就労系の在留資格について詳しく解説しています。取得する条件や方法も紹介しているので、気になる方は、あわせてご覧ください。
【関連記事】
就労ビザとは?在留資格16種や期限、取得する条件・方法を解説
参考:在留資格一覧表|出入国在留管理庁
在留資格の取得方法
在留資格を取得する方法は、海外在住の外国人と日本在留の外国人とで取得方法が異なります。
海外在住の場合
海外在住の外国人は日本に入国する前に、企業側が管轄の出入国在留管理局にて在留資格認定証明書を申請します。申請には雇用契約書、事業内容を示す書類、本人の学歴や職歴を証明する書類が必要です。
在留資格証明書が交付されたら、外国人本人に国際郵便で送り、母国の日本大使館や領事館でビザ申請してもらいます。その後、日本に入国すると空港で在留カードが交付され正式に在留資格が取得されたことになります。
日本在留の場合
日本に在住している外国人が転職や活動内容の変更を行う場合は、出入国在留管理局にて在留資格変更許可申請が必要です。
在留資格の申請手続きができるのは原則外国人本人です。しかし、申請取次の認定を受けている行政書士であれば、申請を代行できます。
行政書士は、公的手続きの専門家です。なかでも申請取次の認定を受けた行政書士は、外国人雇用における労働関係の書類作成や在留資格の申請手続きに精通しているため、業務を委託すれば企業の事務負担を軽減できます。
「外国人採用の窓口」では行政書士事務所をまとめて探せる無料の検索サービスを提供しています。希望する地域や業種などの条件を指定して比較・検索できるため、ニーズに合った事務所をスムーズに見つけられます。ぜひお気軽にご利用ください。
在留資格の有効期間

在留資格の有効期間は、3ヵ月・6ヵ月・1年・3年・5年など複数の区分があり、在留資格の種類や活動実績によって異なります。
在留期間の例
例えば、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」などの就労資格では、初回が1年、更新時に3年または5年と延長される場合があります。
また、永住者や日本人の配偶者等などの身分に基づく資格は、原則として無期限もしくは最長5年です。
企業が外国人を採用する際は、必ず在留カードを確認し、有効期間の満了日を記録しておく必要があります。
更新忘れは在留資格の失効につながり、在留期間が切れた外国人労働者を雇う企業は不法就労と見なされるおそれがあるため、チェックしておきましょう。
以下の記事では、在留資格の有効期間を詳しく解説しています。長期の在留期間を取得する方法も紹介しているので、気になる方は、あわせてご覧ください。
【関連記事】
就労ビザの在留期間は何年?長期の在留許可を受ける方法や在留資格ごとの期間決定のルールを解説 | 外国人採用の窓口
参考:在留資格一覧表 |厚生労働省
在留資格の更新方法

在留資格の更新手続きは、在留期間が満了する日のおおむね3ヵ月前から申請可能です。
申請先は、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で、本人または法定代理人が行います。
例えば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」のケースでは以下の書類が在留資格の更新に必要です。
在留資格の更新に必要な書類の一部
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 顔写真
- 返信用封筒
- 所属機関がどこのカテゴリーに該当するかを証明する文書
- 専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(専門士又は高度専門士の称号を付与された者)
- 派遣先での活動内容を明らかにする資料(申請人が被派遣者の場合)
審査期間はおよそ2週間から1ヵ月程度です。
更新が許可されると、新しい在留カードが発行され、以前と同じ在留資格で活動を続けられます。在留資格の更新は、日本での活動を継続するために欠かせない手続きです。
更新の流れを理解しておくことで、外国人雇用を途切れさせずに安定して続けられます。
なお、活動内容が変更されている場合は更新ではなく、在留資格変更許可申請となります。
参考:在留期間更新許可申請|出入国在留管理庁
在留資格と在留カードの違い

在留資格と在留カードは混同されがちですが、役割はまったく異なります。両者の違いを正しく理解することで、採用時の確認ミスを防げます。
それぞれの特徴は以下の通りです。
| 在留資格 | 在留カード |
|---|---|
| ・外国人が日本で行える活動内容を示す法的な資格
・活動内容や滞在目的を示す ・在留資格がなければ日本で働けない |
・在留資格の内容を証明するために発行される身分証明書
・氏名・国籍・在留資格・在留期間・就労制限などが記載されている ・常に携帯が義務付けられている |
企業が採用時に在留資格を確認する際は、在留カードを通じて情報の正確性を確認します。
在留資格一覧表

在留資格は、出入国管理及び難民認定法の別表第一と第二に記載されています。
2025年10月時点で、在留資格は29種類とされています。
表は出入国管理庁の令和7年9月発表の内容にもとづいて作成しています。
在留資格5つの表の分類
- 一の表…就労資格
- 二の表…就労資格、上陸許可基準の適用あり
- 三の表…非就労資格
- 四の表…非就労資格
- 五の表…特定活動
- 入管法別表第二の上欄…民住資格(身分にもとづくもの)
一の表・・・就労資格
いわゆる就労ビザです。決められた活動範囲内で働くことが認められています。
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 外交 | 日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 | 外交活動の期間 |
| 公用 | 日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。) | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 | 5年、3年、1年、3月、30日又は15日 |
| 教授 | 本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動 | 大学教授等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 芸術 | 収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(二の表の興行の項に掲げる活動を除く。) | 作曲家、画家、著述家等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 宗教 | 外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 | 5年、3年、1年又は3月 |
| 報道 | 外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 | 外国の報道機関の記者、カメラマン | 5年、3年、1年又は3月 |
二の表・・・就労資格、上陸許可基準の適用あり
それぞれの在留資格で、どのような活動を行っていいか、働いていいかが細かく決められています。
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 高 度 専 門 職 | 1号
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う次のイからハまでのいずれかに該当する活動であって、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの |
イ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営し若しくは当該機関以外の本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導若しくは教育をする活動 | ポイント制による高度人材 | 5年 |
| ロ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学若しくは人文科学の分野に属する知識若しくは技術を要する業務に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||||
| ハ 法務大臣が指定する本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い若しくは当該事業の管理に従事する活動又は当該活動と併せて当該活動と関連する事業を自ら経営する活動 | ||||
| 2号
1号に掲げる活動を行った者であって、その在留が我が国の利益に資するものとして法務省令で定める基準に適合するものが行う次に掲げる活動 |
イ 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究、研究の指導又は教育をする活動 | 無期限 | ||
| ロ 本邦の公私の機関との契約に基づいて自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動 | ||||
| ハ 本邦の公私の機関において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動 | ||||
| ニ 2号イからハまでのいずれかの活動と併せて行う一の表の教授、芸術、宗教、報道の項に掲げる活動又はこの表の法律・会計業務、医療、教育、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能2号の項に掲げる活動(2号イからハまでのいずれかに該当する活動を除く。) | ||||
| 経 営 管 理 | 本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。) | 企業等の経営者・管理者 | 5年、3年、1年、6月、4月又は3月 | |
| 法 律 会 計 業 務 | 外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動 | 弁護士、公認会計士等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 医 療 | 医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動 | 医師、歯科医師、看護師 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 研 究 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(一の表の教授の項に掲げる活動を除く。) | 政府関係機関や私企業等の研究者 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 教 育 | 本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動 | 中学校・高等学校等の語学教師等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 技術 人文知識 国際業務 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授、芸術、報道の項に掲げる活動、この表の経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、介護、興行の項に掲げる活動を除く。) | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 企業内転勤 | 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項に掲げる活動 | 外国の事業所からの転勤者 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 介 護 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動 | 介護福祉士 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 興 行 | 演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動(この表の経営・管理の項に掲げる活動を除く。) | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 | 3年、1年、6月、3月又は15日 | |
| 技 能 | 本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等 | 5年、3年、1年又は3月 | |
| 特 定 技 能 | 1号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約(入管法第2条の5第1項から第4項までの規定に適合するものに限る。次号において同じ。)に基づいて行う特定産業分野(人材を確保することが困難な状況にあるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野として法務省令で定めるものをいう。同号において同じ。)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人 | 1年、6月又は4月 |
| 2号 | 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動 | 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 | 3年、1年又は6月 | |
| 技 能 実 習 | 1号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 | 技能実習生 | 法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲) |
| ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第一号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて、講習を受け、及び技能等に係る業務に従事する活動 | ||||
| 2号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | ||
| ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第二号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | ||||
| 3号 | イ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号企業単独型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | 法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲) | ||
| ロ 技能実習法上の認定を受けた技能実習計画(第三号団体監理型技能実習に係るものに限る。)に基づいて技能等を要する業務に従事する活動 | ||||
三の表・・・非就労資格
以下、四の表を含む5つは非就労資格と分類されますが、留学と家族滞在の在留資格は許可を得れば一部の就労が認められます。
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 | |
|---|---|---|---|---|
| 文化活動 | 収入を伴わない学術上若しくは芸術上の活動又は我が国特有の文化若しくは技芸について専門的な研究を行い若しくは専門家の指導を受けてこれを修得する活動(四の表の留学、研修の項に掲げる活動を除く。) | 日本文化の研究者等 | 3年、1年、6月又は3月 | |
| 短期滞在 | 本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動 | 観光客、会議参加者等 | 90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間 | |
四の表・・・非就労資格
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 留学 | 本邦の大学、高等専門学校、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)若しくは特別支援学校の高等部、中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の中学部、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校の小学部、専修学校若しくは各種学校又は設備及び編制に関してこれらに準ずる機関において教育を受ける活動 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒 | 法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲) |
| 研修 | 本邦の公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得をする活動(二の表の技能実習1号、この表の留学の項に掲げる活動を除く。) | 研修生 | 1年、6月又は3月 |
| 家族滞在 | 一の表の教授、芸術、宗教、報道、二の表の高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、三の表の文化活動又はこの表の留学の在留資格をもって在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 | 法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
五の表…特定活動
ワーキングホリデーや外交官等の家事使用人など、法務大臣が個々に活動内容を指定する在留資格です。
| 在留資格 | 本邦において行うことができる活動 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 特定活動 | 法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 | 5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
入管法別表第二の上欄・・・民住資格(身分にもとづくもの)
日本人や永住者と結婚したり、日本人や永住者の子として生まれた場合の身分にもとづく在留資格です。永住者のみ在留期間は無期限となります。
| 在留資格 | 本邦において有する身分または地位 | 該当例 | 在留期間 |
|---|---|---|---|
| 永住者 | 法務大臣が永住を認める者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。) | 無期限 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者 | 日本人の配偶者・子・特別養子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者 | 永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子 | 5年、3年、1年又は6月 |
| 定住者 | 法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者 | 第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等 | 5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲) |
参考:在留資格一覧表|出入国在留管理庁
外国人の在留資格を採用時に確認する方法

外国人の在留資格を採用時に確認する方法は、応募者が所持している在留カードを使います。
参考:在留カードとは?|出入国在留管理庁
在留カードの表面には以下の内容が記載されています。
在留カード表面に記載されている情報の一例
- 在留資格
- 在留期間
- 就労制限の有無
在留カードを見れば就労可能かどうかを判断できます。さらに確認する際は、在留カードの有効期間と在留資格の範囲も見ておきます。
また、在留カードが偽造されていないか有効性を事前にチェックしておくと、トラブル防止に効果的です。確認方法は、出入国在留管理庁の「在留カード等番号失効情報照会サイト」で、カード番号を入力すると判断できます。
以下の記事では、在留カードが更新できない理由を解説しています。更新手順も紹介しているので、気になる方は、あわせてご覧ください。
【関連記事】
在留カード更新ができない理由とは?更新手順も解説!
外国人雇用をご検討中なら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「外国人雇用を検討しているけど何から初めていいの?」
「雇用したいけど手続きや流れがわからない」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した監理団体や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。条件検索できるため、あなたの業界・業種に精通した特定技能の就労支援に強いパートナー企業とのマッチングをお手伝いします。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けているので、外国人の受け入れに疑問や不安がある方もお気軽にお問い合わせください。
ビザと在留資格の違いを理解して採用活動を進めよう

外国人採用を成功させるためには、ビザと在留資格の違いを正しく理解することが重要です。両者を区別できることで、入国から雇用までの流れを把握でき、法令違反を防げます。
ビザは入国の許可証、在留資格は滞在と活動の根拠として機能します。採用担当の方は、応募者の在留資格が職務内容と合致しているかを必ず確認しましょう。
弊社では、外国人向けの人材紹介会社や登録支援機関、監理団体、行政書士事務所を一括検索できるサービスを提供しています。無料で利用できるので、信頼できるパートナーをお探しの方は、お気軽にご活用ください。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。