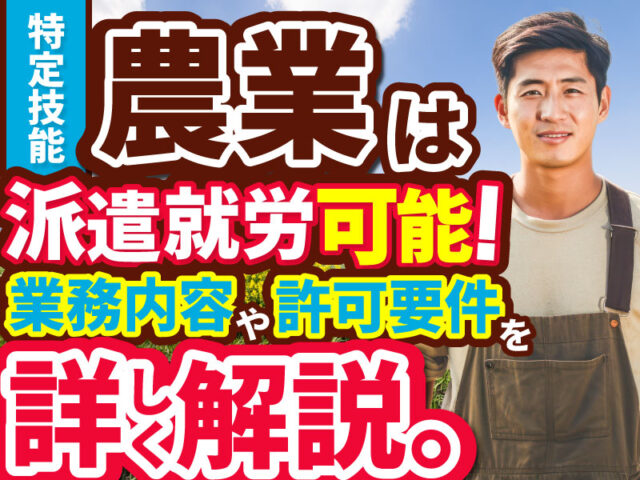人手不足が深刻化するなか、「即戦力となる外国人材を採用したい」と考える農業経営者にとって、特定技能「農業」は有力な選択肢となります。ただし、従事できる業務の範囲や在留資格の許可基準、技能試験の内容など、事前に確認すべき点は少なくありません。
この記事では、特定技能「農業」で認められる主な業務内容や関連作業、1号・2号それぞれの許可要件、受け入れ機関に求められる基準、さらに技能実習制度との違いについてわかりやすく解説します。
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
特定技能「農業」とは
特定技能「農業」は、日本国内の多くの産業が直面している人手不足に対応するために創設された特定技能制度の一分野です。
ここでは、制度の基本的な仕組みや特定技能「農業」の在留者数、従事できる業務内容について順を追って解説していきます。
特定技能1号と2号の比較
特定技能には1号と2号の2種類があり、求められる技能水準に違いがあります。
1号は相当程度の知識や技能を必要とする業務に従事でき、主に現場での実務を担うことが想定されています。
2号は、熟練した技術を要する業務に従事するための在留資格で、より高度な役割を担うことを前提としています。
許可の基準や従事できる活動の範囲は両者で異なりますので、詳細は以下の表をご覧ください。
|
特定技能1号と2号の比較表 |
||
| 在留資格 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 上限なし(更新は必要) |
| 技能水準 | 一定水準以上の技能 | 熟練した技能 |
| 日本語能力水準 | JLPT(N4)相当以上 | 定めなし |
| 実務経験 | 不要 | 管理者として2年以上、または現場で3年以上の就労経験が必要 |
| 支援義務 | 10項目の義務的支援あり | 支援義務なし |
| 家族帯同 | 不可 | 配偶者と子の帯同可 |
特定技能「農業」の在留者数
令和6年12月末時点で、特定技能「農業」の在留者数は29,331人となっており、特定技能全体の在留者数284,466人のうち10.3%を占めています。
日本政府は農業分野において、令和10年度に32万8,000人規模の人材不足が見込まれるとし、令和6年度から5年間で7万8,000人を上限として特定技能人材の受け入れを進める方針を示しています。
この方針を前提にすると、農業分野で特定技能の在留資格で就労する外国人は、令和11年までに最大で5万人程度増加する可能性があります。
特定技能「農業」の主な業務内容
特定技能「農業」には、「耕種農業全般」と「畜産農業全般」の二つの業務区分があります。
耕種農業とは、田畑で米や野菜、果物、穀物、花などを育てる農業のことです。
畜産農業は牛や豚、鶏、羊といった家畜を飼育し、肉や乳、卵、毛皮などを生産する農業のことです。
特定技能1号では、耕種農業は「栽培管理や農産物の集出荷・選別」、畜産農業は「飼養管理や畜産物の集出荷・選別」といった作業が対象となります。
特定技能2号になると、これらに加えて現場を統括する「管理業務」も主な役割に含まれます。
特定技能「農業」の関連業務
特定技能には「関連業務」という枠組みがあり、主な業務に付随する範囲で従事できる作業が定められています。
ただし、関連業務だけに専属で従事することは認められていません。
農業分野の特定技能で従事可能な関連業務は、以下のとおりです。
- 生産した農畜産物を原料または材料の一部として使用する製造や加工の作業
- 農畜産物の生産に伴う副産物(稲わら、家畜排泄物など)を原料または材料の一部として使用する製造や加工の作業
- 農畜産物の運搬、陳列、販売に関する作業
- 農畜産物を原料として製造・加工された物の運搬、陳列、販売に関する作業
- 農畜産物の副産物を原料として製造・加工された物の運搬、陳列、販売に関する作業
- その他、特定技能所属機関で耕種農業または畜産農業に従事する日本人が通常行っている作業
このように関連業務は、農畜産物の生産や流通に伴う多様な作業を対象としており、現場での業務を柔軟に進められるように制度が設計されています。
派遣形態での就労が認められる
通常、特定技能制度では派遣形態での就労は認められていませんが、農業と漁業分野に限っては例外的に派遣労働が認められています。
その理由について政府は、農業分野には、冬季は農作業ができないなど季節による繁閑があること、そして同一地域内でも作目ごとに収穫や定植のピーク時期が異なることといった特性があり、農繁期の人手確保や産地間での労働力調整といった実務上の需要に対応するためと説明しています。
特定技能1号「農業」の許可要件
特定技能1号「農業」の在留資格を取得するためには、入管法で定められた許可要件を満たさなければなりません。
ここからは、申請時に求められる具体的な要件について詳しく解説していきます。
1号農業技能測定試験に合格する
特定技能1号「農業」の在留資格を取得するには、1号農業技能測定試験に合格し、必要な技能を有していることを証明する必要があります。
試験は「耕種農業」と「畜産農業」に分かれ、学科と実技の問題に加えて日本語で指示された農作業内容を理解する聴解問題も含まれています。
試験の実施形式はCBT(Computer Based Testing)方式です。
受験資格は原則として試験日に満17歳以上(インドネシア国籍の場合は18歳以上)で、日本国内外の指定会場において受験することが可能です。
日本語試験に合格する
特定技能1号「農業」を取得するには、日本語試験に合格して求められる日本語能力を証明する必要があります。
対象となる試験は、日本語能力試験(JLPT)N4以上と国際交流基金が実施する日本語基礎テスト(JFT-Basic)のいずれかです。
JLPTは年2回、国内外で大規模に開催され、読解や聴解を通じて一定の日本語運用力を測ります。
一方でJFT-BasicはCBT方式で年6回実施され、より柔軟に受験機会が提供されているのが特徴です。
技能実習からの移行は試験免除制度がある
技能実習2号を良好に修了した場合には、特定技能1号への移行時に技能試験と日本語試験が免除される制度が設けられています。
耕種農業職種の「施設園芸」「畑作野菜」「果樹」の作業において、技能実習2号を良好に修了した人は、耕種農業分野の技能測定試験と日本語試験の両方が免除されます。
畜産農業職種の「養豚」「養鶏」「酪農」の作業において、技能実習2号を良好に修了した場合も同様に、畜産農業の技能測定試験と日本語試験の両方が免除されます。
それ以外の職種・作業の技能実習2号を良好に修了した者については、日本語試験のみが免除されます。
特定技能2号「農業」の許可要件
特定技能2号「農業」の在留資格を取得するには、日本語能力の証明は不要ですが、技能試験の合格と実務経験の証明が必要です。
以下に、特定技能2号「農業」の具体的な許可要件を詳しく解説します。
2号農業技能測定試験に合格する
特定技能2号「農業」を取得するには、農業技能測定試験2号に合格して熟練技能を有していることを証明する必要があります。
試験は「耕種農業」と「畜産農業」に分かれ、それぞれ学科と実技問題に加え、安全衛生管理に関する内容も含まれています。
受験資格は満17歳以上(インドネシア・ミャンマー国籍は18歳以上)で、かつ農業分野で2年以上の管理経験または現場で3年以上の就労経験を持つことが条件です。
一定年数以上の実務経験があること
特定技能2号「農業」を取得するには、耕種農業または畜産農業での一定の実務経験が求められます。
実務経験の要件には2つのパターンがあり、1つは複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程全体を管理した経験が2年以上あることです。
もう1つは、現場で3年以上の実務経験を有していることです。
いずれかを満たすことで、特定技能2号の実務経験要件をクリアできます。
受け入れ事業者側に課せられる要件
特定技能制度を利用して外国人を雇用する際には、受け入れる事業者にも一定の条件が課されています。
ここからは、事業者側に求められる許可要件について詳しく解説します。
農業特定技能協議会に加入する義務がある
農業分野で特定技能外国人を雇用する事業者は、在留資格申請の前に農業特定技能協議会への加入が義務付けられています。
加入申請は専用フォームを通じてインターネット上で行い、届出内容に不備がなければおおむね2週間で加入通知書が発行されます。
受け入れ事業者は、農業特定技能協議会に加入すると所在の都道府県を管轄する地域協議会の構成員にも自動的に登録され、関係法令の遵守や情報提供への協力が求められます。
過去5年以内に6カ月以上の雇用経験があること
農業分野で特定技能外国人を受け入れるには、原則として過去5年以内に同一業務の労働者を6カ月以上継続して雇用した経験が必要です。
一方で雇用経験がなくても、過去5年以内に6カ月以上にわたり同一業務の労働者を対象に労務管理を行った経験があれば要件を満たすとされています。
この労務管理の経験には、親が営む農場で労務を担当したケースや、農業法人の従業員として管理業務を経験したうえで独立した事例なども含まれます。
雇用条件が適正であること
特定技能外国人を受け入れる事業者は、適正な雇用条件を整備することが求められます。
適正な契約内容として代表的な条件は以下のとおりです。
- 業務内容が特定技能「農業」で認められる内容であること
- 所定労働時間が他の職員と同等であること
- 報酬が日本人と同等以上に設定されていること
- 教育訓練や福利厚生において差別的な取扱いをしないこと
- 一時帰国を希望する際に必要な有給休暇を取得できること
1号の場合は支援義務を履行すること
特定技能1号の外国人を雇用する際、受け入れ企業には生活面や職場への適応を支援するための計画を策定し、実行する義務があります。
支援内容として求められるのは以下の10項目です。
- 事前ガイダンスの実施
- 出入国時の送迎支援
- 住居の確保や生活に必要な契約手続きの補助
- 生活オリエンテーションの実施
- 行政機関での公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会提供に関する支援
- 相談や苦情への対応窓口の設置
- 地域住民との交流を促す取組
- 契約解除時の転職支援(雇用主都合の離職時)
- 定期的な面談と必要に応じた行政機関への通報
支援業務は登録支援機関に委託できる
特定技能1号の外国人を受け入れる企業には、生活や就労に関する支援を提供する義務があります。
ただし、この支援業務は入管庁の名簿に登録された登録支援機関へ委託することが認められています。
支援の実施には専門知識や多大な労力を要するため、支援実務を外部に委ねる事業者も少なくありません。
登録支援機関に適切に委託した場合は、受け入れ企業の支援義務を果たしたものとみなされます。
労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること
特定技能外国人を雇用する際、労働条件の整備や社会保険の加入、税金の適正な納付に不備があると、在留資格申請が不許可となる可能性があります。
さらに、これらの法令遵守は申請時だけでなく、雇用を継続する限り常に求められます。
そして、雇用中に違反が発覚した場合には、更新許可が認められず、雇用の継続が困難になる可能性があります。
欠格事由に該当しないこと
特定技能制度を活用して外国人材を受け入れるためには、雇用主が欠格事由に該当しないことが条件となっています。
欠格事由の主な内容は以下の通りです。
- 直近1年以内に同一業務で離職者(日本人を含む)を発生させていないこと
- 直近1年以内に外国人従業員の行方不明者を発生させていないこと
- 過去5年以内に拘禁刑以上の刑を受けていないこと
- 過去5年以内に労働法令違反で罰金刑以上を受けていないこと
- 過去5年以内に社会保険関連法令違反で罰金刑以上を受けていないこと
- 過去5年以内に入管法や労働法令に関して不正または著しく不当な行為を行っていないこと
特定技能と技能実習の違い
外国人材の受入れを考える際に、特定技能と並んで比較されることが多いのが技能実習制度です。
ここからは両制度の仕組みや目的の違いについて解説していきます。
受け入れ目的
特定技能制度の目的は、日本国内の慢性的な人手不足を補うことにあります。
国内での人材確保や生産性向上の取り組みを行ってもなお人材が不足する分野において、一定の技能を備えた外国人を受け入れる仕組みとして運用されています。
技能実習制度は国際貢献を目的とし、開発途上国への技能移転を推進するために導入された制度です。
技能実習計画を通じて実習生に技能習得を求め、定期的な試験や評価を通じて人材育成をすることを重視しており、労働力確保を前提とする特定技能とは根本的に異なる制度となっています。
人材採用ルート
特定技能では、海外から直接採用する方法に加え、日本国内で学校を卒業した留学生の新卒採用や、すでに就労している外国人材の転職など、複数のルートでの受け入れが可能です。
技能実習は受け入れ対象が海外からの人材に限られており、基本的には監理団体を通じて組合員として実習生を受け入れる仕組みとなっています。
従事可能な業務
特定技能の業務区分は「耕種農業全般」と「畜産農業全般」に大きく分かれ、栽培から管理まで幅広い作業に従事でき、同じ業務区分の範囲内の業務であれば、必要に応じて複数の作業を横断して担当することが可能です。
技能実習は「施設園芸」「畑作野菜」「果樹」「養豚」「養鶏」「酪農」の6作業に細分化され、業務内容はそれぞれ外国人技能実習機構から認定を受けた実習計画で認められた範囲内に限定されます。
転職(転籍)の制限
特定技能制度では、本人の意思による転職が認められています。
ただし、実際に職場を移る際には入管庁から在留資格変更許可を受ける必要があります。
技能実習は原則として本人都合の転籍が認められていないため、受け入れ先から人材が流出しにくい仕組みになっています。
まとめ
本記事では、特定技能「農業」の業務範囲や受け入れの条件、技能試験の概要、さらに技能実習との制度的な違いについて整理しました。
農業経営者にとって、人材確保の手段をどう選ぶかは今後の生産体制に直結します。自社の作業内容や人材採用の方針を踏まえて、特定技能と技能実習のどちらが適しているのかを見極めることが重要です。採用を検討する際は、制度の仕組みを正しく理解し、早めに準備を始めることが円滑な受け入れにつながります。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。