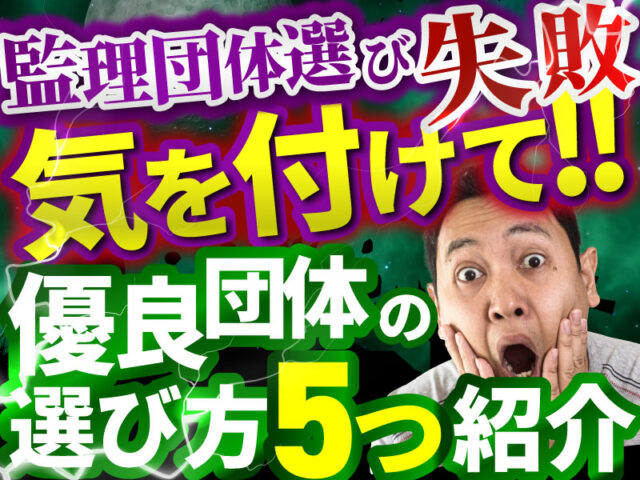「優良な監理団体はどうやって選んだらいいの?」
「自社に合った監理団体の選び方が知りたい」
このような疑問をお持ちの方もいるでしょう。
監理団体を選ぶ際には、まず監理費用が適正かどうか比較し、さらに監理体制やサポート内容が整っているかを確認しましょう。
本記事では、監理団体の概要や失敗しない選び方のポイント、失敗するパターンをわかりやすく解説します。監理団体を選ぶ際の注意点も解説していますので、技能実習生の受け入れを検討中の方は参考にしてみてください。
外国人採用の基本で
お悩みの方に
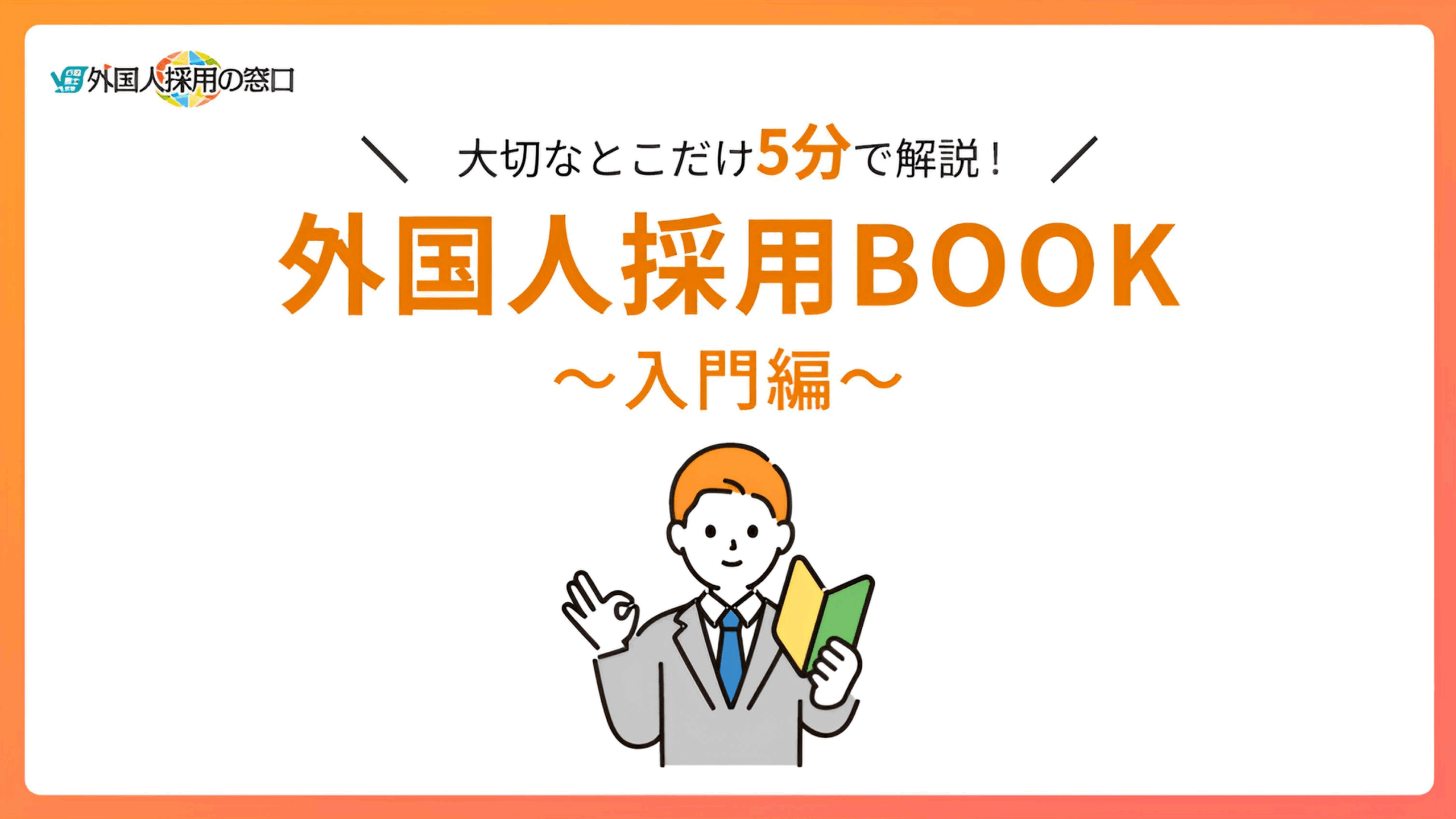
この資料でわかること
- 外国人労働者の現状
- 雇用できる在留資格の確認方法
- 外国人雇用における注意点
- 外国人を受け入れる流れ
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
監理団体とは?

監理団体とは、技能実習生の送出国にある送り出し機関と契約を結び、受け入れ企業に代わって技能実習生の受け入れをおこなう非営利団体です。
日本国内の企業に技能実習生を紹介するだけでなく、受け入れ企業への指導やサポートも実施します。
監理団体として活動するには、監理事業を運営できる能力や欠格事由の有無など各項目の審査を受けて、国から許可を受けなければなりません。
技能実習生の受け入れ方法は、大きく分けて2つあります。
1つは監理団体を介して技能実習をおこなう方法の「団体監理型」で、もう1つは日本企業が海外の子会社やグループ企業などから直接実習生を受け入れる方法の「企業単独型」です。
それぞれの方法を詳しく解説します。
団体監理型
団体監理型とは、事業協同組合や商工会などの営利を目的としない団体が技能実習生を受け入れ、傘下の企業で技能実習をおこなう方式です。
この仕組みでは、監理団体が技能実習生の受け入れや生活サポート、実習実施者への巡回指導などを担い、企業を支援します。
そのため、自社で直接すべての手続きをおこなうのが難しい中小企業でも技能実習生を受け入れやすいのが特徴です。
企業単独型
企業単独型では、受け入れ企業が送り出し機関と契約を結び、技能実習生を直接受け入れて指導をおこないます。
この方法では、監理団体を通さずに企業自身が技能実習計画の作成、生活支援、定期報告などを担う必要があります。そのため、十分な体制が整っている大企業や、専門性の高い実習内容を提供できる企業で採用されるケースが多いです。
一方で、監理団体のサポートが受けられない分、法令遵守や実習生の生活支援において企業側の負担が大きくなる点には注意が必要です。
監理団体の許可基準
監理事業をおこなうには、下記の許可基準に適合しなければ国からの許可は得られません。
■監理団体の許可基準(抜粋)
| ①営利目的でない法人であること(商工会議所、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益財団法人、公益社団法人など)
②以下の業務を適切におこなえる能力があること
③監理事業を健全に遂行できる財政的基礎があること ④個人情報の適正な管理ができること ⑤外部役員、外部監査の措置を実施していること ⑥基準を満たす送り出し機関と契約を締結すること ⑦優良要件に適合していること |
上記の基礎的な要件に加えて、「実習実施状況の監査や業務体制」「技能の修得に係る実績」「法令違反の発生状況」といった複数項目が、優良な監理団体の基準要件として定められています。
監理団体を選ぶ際には、基本的な許可基準を満たしているかはもちろんのこと、監理団体の役割である実習監査状況や支援実績などを総合的に確認して信用できる団体に依頼しましょう。
監理団体の数
監理団体の数は、2025年9月時点で一般許可監理団体は2,173件、特定許可監理団体は1,583件あります。
一般許可監理団体は、技能実習生1号~3号すべての実習監理をおこなえます。一方、特定許可監理団体は技能実習生1号、2号のみしか対応できないため、選ぶ際は間違えないよう確認してください。
これらの監理団体は、外国人技能実習機構(OTIT)のサイト内からダウンロードできる許可監理団体一覧のExcel/PDFファイルから確認が可能です。
しかし、件数が多く検索が難しいため、自社に合った団体を見つけるためには各種条件から一括検索ができる「外国人採用の窓口」をご利用ください!
監理団体の主な役割
監理団体の主な役割は以下の3つです。
| ①監理・指導
監理団体の許可基準に基づき、実習実施者に対する技能実習状況の確認や指導をおこないます。 技能実習制度はさまざまな法令を守りながら適切に進めなくてはなりません。 専門的知識をもち、多様な立場の人や団体とコミュニケーションをとり、適切な指導と監理をおこなう役目があります。 |
| ②技能実習制度の趣旨の理解と周知
技能実習制度は、人材不足で労働力を確保するための制度ではなく、実習生に日本の技能を伝えるための制度です。 技能実習制度の趣旨が国際協力や国際貢献であると正しく理解し、実習実施者だけでなく受け入れ機関にも周知していく役割があります。 |
| ③監査と報告
3ヵ月に1度以上の定期監査を実施し、その結果を地方出入国在留管理局へ報告をします。 以下の記事では、監理団体の役割やサポート内容をさらに詳しく説明していますので、参考にしてみてください。 |
【関連記事】
【5分でわかる】監理団体とは?サポート内容や選び方のポイントを解説
監理団体の選び方

監理団体についての基本事項を理解したところで、監理団体の選び方を確認していきましょう。
日本全国に3,000以上ある監理団体の中から、自社にあった適切な団体を選ぶためのポイントは以下の5つです。
- 出入国在留管理庁に登録されているか
- 監理費用は適正価格か
- 監理体制やサポートが整っているか
- 技能実習生の教育体制はあるか
- トラブル時に対応可能か
それぞれ詳しく解説します。
出入国在留管理庁に登録されているか
監理団体は、出入国在留管理庁から許可を受け、登録されている必要があります。
未登録の団体を利用すると、制度違反に該当し行政指導や受け入れ停止などのリスクを負いかねません。
監理団体を選ぶ際は、外国人技能実習機構の公式サイトに記載されている「監理団体許可番号」や「登録状況」を確認し、適正な法的根拠のもとで活動しているかを必ずチェックしましょう。
多くの監理団体の中から自社に合った団体を見つけるには「外国人採用の窓口」をご利用ください。弊社は、外国人採用に特化した監理団体を一括で検索できるサービスを無料で提供しています。
無料相談も受け付けておりますので、監理団体選びでお困りの方もお気軽にお問い合わせください。
監理費用は適正価格か
監理団体に依頼する際は、入会金と技能実習期間中の監理費用などの支払いが必要です。
外国人技能実習機構が2022年1月24日におこなったアンケートによると、監理費の平均値は以下の通りでした。
| 初期費用 | 定期費用(1号) | 定期費用(2号) | 定期費用(3号) | 不定期費用 |
| 34万1,402円 | 3万551円 | 2万9,096円 | 2万3,971円 | 15万4,780円 |
この調査結果から、技能実習生の受け入れから技能実習が修了までにかかる1名あたりの費用(初期費用+各号の定期費用の年額)は、技能実習1号(1年間)までは約71万円、技能実習2号(3年間)までは約141万円、技能実習3号(5年間)までは約198万円です。
この平均値よりも高額な手数料やサービス料を請求する場合は悪徳な団体である可能性もあります。適正な価格設定をしている信頼できる監理団体を選択しましょう。
以下の記事では、技能実習制度のおおまかな流れや費用の内訳を詳しく解説しています。採用後に必要な費用のシミュレーションもできるため、技能実習生の受け入れを考えている方は参考にしてみてください。
【関連記事】
『技能実習生』の受け入れ費用、監理団体の料金相場を解説【費用項目一覧表あり】
監理体制やサポートが整っているか
以下は監理団体が実施すべきサポート業務の一例です。
サポート業務の一例
- 実習実施者に対して定期監査を3ヵ月に1回以上実施する
- 事業所に足を運んで実地を確認する
- 宿泊施設など実習生の生活環境を確認する
- 事業所の設備や帳簿類を確認する
こういった細かな監査を適切に実施しているのか、過去の監査でどういった課題を発見しアドバイスしてきたかなどを、見積り時や商談の際に直接話して確認すると良いでしょう。
技能実習生の教育体制はあるか
技能実習生は海外現地での研修だけでなく、入国後も監理団体から一定期間の講習を受けるルールとなっています。
講習では日本の生活ルールや日本語、技能実習制度に関するルールなどを教育します。
監理団体の専門知識や講習力を確認するために、技能実習生の教育に関する体制や過去実績などを直接聞いてみると良いでしょう。
実習生の母国語を話せるスタッフがいるかどうか、誰がどのくらい講習実績をもっているか1つずつ質問することで、各監理団体の対応力も見えてくるはずです。
トラブル時に対応可能か
監理団体によっては、事務的に監理事業をおこなうところもあれば、マニュアル外のトラブル対応にも柔軟にサポートしてくれる団体もあります。
技能実習制度に則って、実務を確実にこなす力はもちろんですが、実習生の予期せぬトラブルに対して、その都度きめ細やかに支援してくれる対応力も重要です。
対応力を見極めるポイント
- 問い合わせ時のメールの返信が早いかどうか
- 過去のトラブル事例や実習実施者向けのアドバイス内容に説得力があるか
など、多角的な視点から対応力を見極めましょう。
監理団体の選び方で失敗するパターン

監理団体の選び方で失敗するパターンは以下の通りです。
- 費用の安さだけで選ぶ
- サポート内容が決まっていない
- 過去の実績を確認していない
順番に解説します。
費用の安さだけで選ぶ
費用の安さだけで監理団体を選ぶのは危険です。
費用を抑える代わりに、監査や生活指導などの基本的なサポートが削られているケースもあるためです。
結果として、実習生が早期に離職して再募集・再教育の費用が発生したり、トラブル対応時に専門家への相談料がかかったりするなど、余計なコスト発生につながりかねません。
費用だけではなく、監理体制の質や対応範囲を総合的に判断しましょう。
外国人採用の窓口では、「外国人雇用にかかる費用徹底分析」の資料を無料配布しております。外国人雇用にかかる費用が気になる方は、30秒でダウンロードできますので以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人雇用にかかる費用を
事前に知りたい方へ

この資料でわかること
- 外国人雇用にかかる費用一覧
- 海外在住の外国人採用にかかる費用
- 日本在留の外国人採用にかかる費用
- 外国人雇用のコストを抑える方法
サポート内容が決まっていない
監理団体との契約前に「どこまでサポートしてもらえるのか」を必ず確認し、自社に必要な内容を事前に決めておきましょう。
通訳派遣、生活支援、トラブル発生時の対応などが不明確なまま契約すると、あとから「それは対象外」と言われ、追加費用や対応遅れに直面するケースがあります。
契約書や規約に、定期監査の回数や通訳・翻訳の派遣対応の有無と費用、生活指導(住居・病院・口座開設など)の範囲が明記されているかをチェックしてください。
過去の実績を確認していない
監理団体の過去の実績を調べずに契約すると、適切な監査をおこなっていない団体や、法令違反歴のある団体を選んでしまうリスクがあります。
実習生の受け入れ人数や監査件数、過去のトラブル対応事例などを確認することで、その団体の信頼性を客観的に判断できます。
監理団体を選ぶ際の注意点

監理団体を選ぶ際は、必ず複数の団体を比較して、費用やサービス内容を確認しましょう。
1社のみでは限られた情報しか得られないため、適切な判断ができません。
複数社の費用を比較すれば相場感がわかり、不必要に高い手数料やサービス料を支払うリスクを避けられます。
また、比較すれば避けられた「実績が少ない」「サポート体制が不十分」といった会社に当たるリスクも減らせます。
自社にあった監理団体をスムーズに見つけたいなら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「監理団体の選び方を誰かに相談したい…」
「監理団体がたくさんあって探すのが大変…」
「どの監理団体が自社に合っているのか分からない…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した監理団体や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
貴社の採用したい実習生の国籍や1号・2号・3号に合わせて、優良な監理団体とのマッチングをお手伝いをいたします。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けておりますので、技能実習生の受け入れを前向きにご検討中の方は、お気軽にご相談ください。
監理団体の選び方に関するよくある質問
 優良な監理団体の定義とは?
優良な監理団体の定義とは?
法律を遵守し、過去に大きな違反や行政処分がないことが前提です。
さらに、国が定める採点方式に則った評価で一定の基準を満たす必要があります。
具体的には各評価項目で150点満点中90点以上(6割以上)の得点を獲得すれば、優良な監理団体として認定されます。
優良な監理団体には定期的な監査に加え、通訳や生活サポート、トラブル対応など、実習生と企業の両方を支えてくれる体制が整っていることが求められます。
良い監理団体を見極めるためには、どんな質問をしたら良いですか?
監理団体との契約前には、過去の実績やサポート体制について具体的に質問しておきましょう。
事前に確認することで信頼できる団体かどうかを判断でき、後々のトラブルも防ぎやすくなります。
例えば、以下のような質問がおすすめです。
質問例
「監理団体を設立してから何年になりますか?」
「実習生を配属した後のサポート内容を教えてください」
「監理費にはどのような項目が含まれていますか?」
設立からの年数は、その団体の運営実績や安定性を測る指標になります。
歴史が長ければ、監査やトラブル対応のノウハウを積み重ねている可能性が高く、安心して任せやすいと言えます。
また、受け入れ後の支援の違いにより、実習生の定着率や企業側の負担は大きく変わります。
通訳派遣、生活面の支援、トラブル発生時の対応などが明確に示されれば、安心感のある監理団体と判断できます。
監理費は団体によって大きく差があり、内訳が不明確な場合は不要な費用が上乗せされている可能性があります。
具体的にどの業務にいくら使われているかを確認することで、適正な費用かどうか把握できるでしょう。
監理団体を途中で変更することはできますか?
監理団体は途中からでも変更可能です。
もし現在の監理団体の対応に不安を感じる場合は、安心して実習を進めるためにも必要に応じて検討してみましょう。
監理団体変更の流れは以下の通りです。
監理団体変更の流れ
- 新しい監理団体を探す
- 現在の監理団体・送り出し機関・技能実習生の合意を得る
- 必要な書類を準備する
- 現在の監理団体との契約解除手続きを行う
- 送り出し機関と新しい監理団体で契約を結ぶ
監理団体の変更には1ヵ月半〜3ヵ月程度かかるため、事前に複数の監理団体を比較しておくと良いでしょう。
以下の記事では、監理団体の変更を検討するポイントやメリット・デメリットを詳しく解説しています。変更する際の注意点も解説していますので、こちらの記事も参考にしてみてください。
【関連記事】
監理団体を変更するメリット・デメリット、手続き、費用、注意点まで解説【2025年最新】
監理団体の選び方を知り技能実習生の受け入れを成功させよう

技能実習制度において、監理団体選びは非常に重要なポイントです。
費用の安さだけで判断するのではなく、監理事業を正しくおこなってくれるか、自社の状況や実習生に合わせた柔軟な対応をしてくれるか、サポート内容と費用のバランスはとれているかなど複数の視点から確認し、慎重に選んでいきましょう。
「自社にあう監理団体をうまく探せる自信がない…」という方は、当サービスをご利用ください。
弊社では、監理団体や外国人向けの人材紹介会社、外国人雇用の手続きに強い行政書士事務所を一括検索できるサービスを提供しています。
無料で利用できるので、信頼できるパートナーをお探しの方は、お気軽にご活用ください。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。