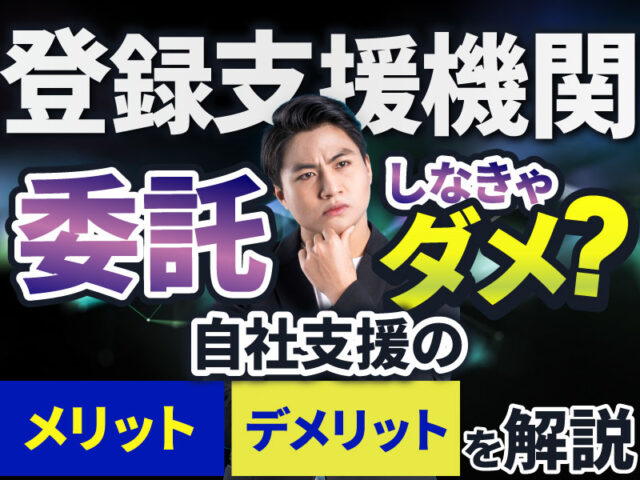特定技能1号の外国人を受け入れる企業は、入管法に基づき生活支援や相談対応など、さまざまな「支援義務」を負います。多くの企業では登録支援機関に委託して対応していますが、最近ではコスト削減や人材育成の観点から「自社で支援を行う」ケースも増えています。しかし、自社支援には法令遵守や体制整備などのハードルもあるため、慎重な検討が必要です。
この記事では、登録支援機関に委託せずに自社で支援を行う場合のメリットとデメリットを比較し、実施にあたって求められる条件や注意点をわかりやすく解説します。
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
1号特定技能外国人を雇用すると支援義務がある
特定技能1号の外国人を雇用する企業は、入管法に基づき受け入れ後の生活支援や相談対応など、一定の支援を行う義務を負います。これは、外国人が日本で安心して就労・生活できる環境を確保するために設けられた制度です。
一方で、特定技能2号の在留資格にはこの支援義務は課されていません。日本での生活に十分慣れているとみなされるため、企業による支援は不要とされています。
以下では、1号特定技能外国人を雇用する場合に必要な支援の内容や自社で実施する際の条件について順を追って解説します。
義務的支援と任意的支援
特定技能1号の支援には「義務的支援」と「任意的支援」の2種類の支援があります。
義務的支援とは、生活や就労環境を安定させるために法律上義務付けられた支援内容であり、これを実施しなければ特定技能1号の外国人を雇用することはできません。
一方、任意的支援は法令で義務付けられていない支援であり、企業が自主的に行うものです。ただし、在留資格申請時に提出する支援計画書に任意的支援を実施すると記載した場合、その内容を履行する義務が生じます。
このように、義務的支援と任意的支援は法的性質が異なるため、企業はそれぞれの範囲を正確に理解した上で支援体制を整える必要があります。
義務的支援10項目
義務的支援は法務省令で定められており、受け入れ企業はこの支援義務を適正に履行できる体制を整備しなければ、特定技能1号の外国人を雇用することはできません。
支援内容は、外国人が日本で安心して生活・就労できるようにするためのもので、以下の10項目が定められています。
| 義務的支援10項目 |
|
任意的支援の代表例
任意的支援は、受け入れ企業が自主的に実施する支援であり、法令上の実施義務はありません。内容は企業の判断に委ねられており、柔軟な取り組みが可能です。
入管庁では任意的支援の代表例として、以下の事例を挙げています。
| 任意的支援の代表例 |
|
支援業務は登録支援機関に委託できる
登録支援機関とは、特定技能1号の外国人に対する支援を専門的に行う機関であり、入管庁の名簿に登録された事業者のことです。企業からの委託を受け、入管法で定められた義務的支援を代行する役割を担っています。
受け入れ企業は、登録支援機関に支援業務を委託した場合、適正に支援を実施したものとみなされます。
自社で支援を行う体制が整っていない場合や、法令で求められる条件を満たせない場合には、登録支援機関を活用するのが一般的です。
特に外国人雇用や外国語によるコミュニケーションに不慣れな企業では、委託の仕組みを活用することでリスクを軽減できます。
自社支援をするための条件
特定技能1号の外国人に対して自社で支援を行う場合、企業は法務省令で定められた条件を満たす必要があります。これらの基準に適合しないと、在留資格申請の審査で不許可となる可能性があります。
ここからは、自社支援の実施に必要な条件を順に解説します。
就労系在留資格の外国人を適正に受入・管理した実績
自社支援を実施するためには、過去2年以内に就労系の在留資格を持つ外国人を適正に受け入れ、または管理した実績が必要とされています。
ここでいう「受け入れ」とは、主に自社で外国人を雇用し、労働環境や生活上のトラブルなく適切に雇用した経験を指します。
一方、「管理した実績」とは、登録支援機関や技能実習の監理団体として、直接の雇用関係がなくとも、外国人の就労や生活を継続的に支援・監督した実績を指します。このような経験があれば、支援業務を円滑に遂行できる能力を有していると判断されます。
ただし、これらの実績がない場合でも、過去2年以内に外国人の生活相談業務に携わった経験がある者や、それと同等に支援を適正に行える体制があると認められた場合には、自社での支援が可能です。
支援責任者と支援担当者を選任していること
自社で特定技能外国人の支援を行うためには、企業の役員または職員の中から支援責任者と支援担当者を選任する必要があります。
支援責任者は、原則1名選任する必要があり、支援業務の統括的な役割を担いますが、非常勤の者でも務めることが可能とされています。
一方、支援担当者は実際に支援を実施する立場であり、事業所ごとに1名以上の常勤職員を配置しなければなりません。
また、支援責任者と支援担当者を同一人物が兼務することも認められています。
ただし、この場合は支援担当者としての条件に合わせ、事業所の常勤職員であることが求められます。
これらの人員体制を適切に整えることで、支援業務の継続性と信頼性を確保することができます。
外国人が理解できる言語で支援する体制があること
自社で特定技能外国人を支援する場合、企業には外国人本人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制を整えることが求められます。
使用する言語は必ずしも外国人の母国語である必要はなく、本人が支援内容を十分に理解できる言語であれば問題ありません。
ただし、入管庁は「十分に理解できる言語」の具体的な基準を示していません。
一般的にN4程度の日本語能力を持つ外国人に日本語のみで支援を実施する体制では不十分と判断されるおそれがあります。
そのため、支援業務を適切に実施するためには、社内に多言語対応ができる職員を配置するか、外部の通訳者に必要に応じて委託する体制を整えることが望まれます。
なお、通訳者への委託はあくまで翻訳・通訳業務に限定され、支援業務そのものを外部に丸ごと任せることは認められていません。
支援状況に関する文書を作成・管理すること
特定技能1号の外国人を自社支援で受け入れる企業は、支援状況を記録した文書を作成し、適切に管理する義務があります。
これらの記録は、行政機関からの確認に備えて保存する必要があり、特定技能雇用契約が終了した日から少なくとも1年以上の保管が求められます。
管理が必要とされているのは、主に以下の4つを記録した文書です。
- 支援実施体制に関する管理簿
- 支援の委託契約に関する管理簿
- 支援対象者に関する管理簿
- 支援の実施に関する管理簿
中立な支援を実施できる体制があること
自社で特定技能外国人の支援を行う場合は、社内の職員が支援を担うため、支援体制の中立性を確保することが不可欠です。支援担当者が企業側の利益に偏らず、公平な立場で外国人を支援できる環境を整えることが求められます。
そのため、支援責任者や支援担当者は、支援対象となる外国人を直接監督・指揮する立場にあってはなりません。例えば、社長や直属の上司といった、業務上の命令権を持つ人物は支援担当者や責任者に選任することができません。
また、企業と外国人との間でトラブルが発生した際にも、中立的な立場で調整を行える人物である必要があります。こうした体制を構築することで、外国人が安心して相談できる環境を整えることができます。
過去5年以内に支援義務の不履行がないこと
特定技能1号の外国人を支援する企業は、過去5年以内に支援義務を怠った事実がないことが条件となります。
支援を怠った経歴がある場合、外国人の生活や就労を適切にサポートできる体制が整っていないとみなされ、特定技能雇用契約の締結が認められない可能性があります。
また、契約締結後に支援を怠った場合も同様に問題視されるため、継続的な遵法意識と管理体制の維持が求められます。
定期面談の体制を有していること
自社で特定技能外国人を支援するためには、支援責任者または支援担当者が定期的に面談を実施できる体制を整えていることが必要です。
この面談は、外国人本人とその職場の上司など監督的立場にある者の双方と行うことが求められます。業務上の課題や生活上の悩みを把握し、必要に応じて支援内容を見直す機会とすることが目的です。
自社支援のメリット
ここからは、登録支援機関に委託せずに自社で支援を行う場合のメリットについて解説します。
以下でその具体的な内容を順に見ていきましょう。
委託にかかるコストが削減できる
登録支援機関に支援業務を委託する場合、1人あたり月額2〜3万円の費用がかかり、年間ではおおよそ24万〜36万円の支出となります。
一方で、自社で支援を実施すれば外部委託費用を削減でき、長期的にはコストの圧縮が期待できます。
特に、特定技能1号の受け入れ人数が多い企業では、社内の人材に支援責任者や支援担当者を兼任させることで、外部委託よりも経済的に効率のよい運用が可能となる場合があります。
近い距離で支援を実施できる
登録支援機関に委託する場合、専門的な支援を受けられる反面、担当者が定期訪問を行う形となるため、支援の実施頻度や対応の柔軟性に制限が生じる場合があります。
一方で、自社支援を実施する場合は、支援担当者が同じ職場に常駐しているため、日常的な会話を通じて外国人の状況を把握しやすくなります。移動時間が不要で、トラブルや不安を即座に確認できる点も大きなメリットです。
社内にノウハウが蓄積される
特定技能1号の支援には、生活支援や行政手続きの案内など幅広い分野の知識が求められます。自社で支援を行う場合、初期段階では制度理解や書類作成に時間がかかるなど、一定の負担が生じます。
しかし、支援業務を通じて外国人との関わり方や行政対応の流れを社内で体系化できれば、次回以降の対応が円滑になり、組織全体のスキル向上につながります。
こうしたノウハウの蓄積は、外国人に限らず日本人社員の定着支援にも応用できるため、長期的には人材マネジメント力の強化にも寄与します。
採用プロセスを一元管理できる
特定技能1号の外国人を採用する際は、雇用契約の締結に加えて在留資格申請や支援体制の整備など、多くの手続きが必要となります。外部の登録支援機関を利用する場合には、委託先の選定や契約締結など追加の調整も発生します。
一方で、自社支援を滞りなく実施できる体制があれば、採用決定後の事前ガイダンスや支援計画の策定などのプロセスを社内で一元管理できます。
その結果、採用後の外部機関とのやり取りなどの負担が軽減され、人材受け入れがスムーズになる場合があります。
自社支援のデメリット
ここからは、自社支援を実施する場合のデメリットについて解説します。
自社支援体制づくりには一定の負担が伴いますが、以下でその具体的な内容をお伝えします。
支援実施の時間と労力がかかる
特定技能1号の外国人を雇用する場合、支援業務は採用前後の一時的なものではなく、雇用を継続する限り常に適正に行う必要があります。生活支援や定期面談など、日常的なフォローを怠ると制度上の義務違反となる可能性もあります。
採用当初は十分に対応できていたとしても、業務の繁忙期や人員異動などにより支援が後回しになってしまうケースも想定されます。
そのため、自社支援を選択する際は、長期的に支援体制を維持できるか慎重に検討することが求められます。
支援責任者と支援担当者の育成が必要
特定技能1号の支援業務では、支援計画の作成から実施まで一定の専門知識と経験が求められます。
そのため、社内に経験者がいない場合は、支援責任者や支援担当者を一から育成する必要があります。育成には時間とコストがかかるうえ、担当者の定着も重要な課題です。
体制を構築する際は、法的条件を満たすだけでなく、継続的に質の高い支援を提供できるよう実務レベルでの設計を行うことが大切です。
人件費や教育費など内部コストが発生する
自社支援を行う場合は、支援責任者と支援担当者を社内で任命し、継続的に支援業務を実施する体制を整える必要があります。そのためには人件費や教育費といった内部コストが発生します。
一方で、登録支援機関へ委託する場合は外部費用がかかるものの、社内リソースの負担を軽減できる利点があります。
したがって、どちらの方法がより費用対効果に優れているかを比較し、事業規模や人員体制を踏まえて総合的に判断することが重要です。
入管法令の知識が必要になる
登録支援機関は、支援業務だけでなく特定技能制度や入管法令に関しても豊富な知識を有している場合が多く、入管庁への問い合わせや最新情報の収集をサポートしてくれる場合が多くあります。
自社支援を選択する場合は、こうした外部の専門機関に頼ることができないため、在留資格制度の理解不足が申請や支援業務に影響を及ぼすおそれがあります。
そのため、入管関連の法令や制度改正にも継続的に対応できる体制を整えることが重要であり、必要に応じて専門家への助言を受けられる仕組みを検討することが望まれます。
まとめ
自社支援を行うには、特定技能外国人が理解できる言語での支援体制や、支援記録の管理、中立性の確保など、法令で定められた多くの要件を満たす必要があります。その一方で、委託費用の削減や支援ノウハウの蓄積など、企業経営にとって長期的なメリットも期待できます。
自社支援を検討する際は、制度上の条件をクリアするだけでなく、社内の人員体制や知識の習得コストを含めて慎重に判断することが大切です。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。