「就労ビザってどういうものなの?」
「在留資格って種類がたくさんあるみたいだけど、違いが分からない…」
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
結論から言うと、就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な「在留資格」のことを指します。
日本には全部で29種類の在留資格が存在しますが、就労活動が認められている在留資格は19種類です。
在留資格ごとに、認められる活動内容や取得条件が異なるため、受け入れ企業は理解を深めた上で採用活動を進めていく必要があります。
本記事では、就労ビザについて詳しく解説します。在留資格の種類や取得条件、取得方法も紹介しているので、参考にしてみてください。
外国人採用の基本で
お悩みの方に
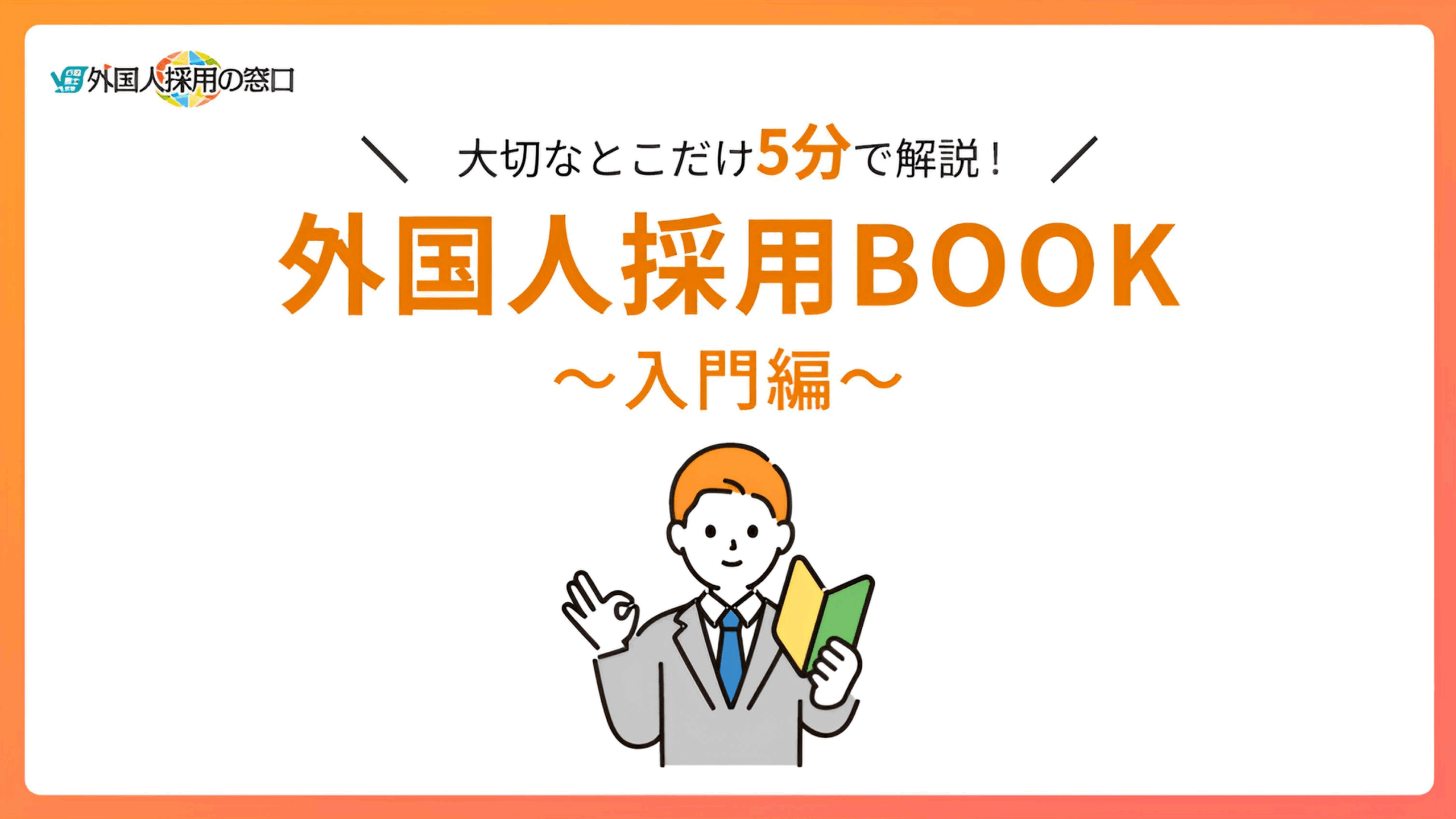
この資料でわかること
- 外国人労働者の現状
- 雇用できる在留資格の確認方法
- 外国人雇用における注意点
- 外国人を受け入れる流れ
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。自社でも監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士・外国人雇用管理主任者資格保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
就労ビザの正式名称は「在留資格」

まず、就労ビザは通称で、正式名称ではありません。
正式には、就労目的で在留が認められる「在留資格」と呼びます。
在留資格とは、外国人が日本で活動するために滞在が許可された資格です。一方でビザは、他国への入国許可を得ている「入国証明証」のことです。
混同されがちな概念のため、違いを整理しておきましょう。
在留資格とビザの違いは、以下の記事で詳しく解説しています。理解を深めたい方は、あわせてご覧ください。
【関連記事】
在留資格一覧付!在留資格とビザの違いとは?|初めての外国人採用の知識
外国人採用の窓口では「外国人採用をはじめる前の基本チェックリスト」の資料を無料配布しております。これから外国人の採用活動をされる方に役立つ資料です。
30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人採用前に
知っておくべき
チェックリスト

この資料でわかること
- 外国人採用前のチェックシート
- 採用前の具体的なチェックポイント
- 人材紹介会社を利用するメリット
- 優良な人材紹介会社の選び方
就労が認められている在留資格は全部で19種類

日本には、29種類の在留資格が存在します。在留資格は活動目的ごとに以下3つのカテゴリーに分けられます。
- 就労が認められている在留資格
- 就労制限のない在留資格
- 就労が認められない在留資格
それぞれの在留資格の特徴を解説します。
就労が認められている在留資格
一般的に「就労ビザ」と呼ばれる、就労が認められている在留資格は、全部で19種類あります。
以下の表に、在留資格の種類と従事が認められる職種例をまとめました。※リンクが付いている在留資格名をタップすると、詳細記事をご覧いただけます
| 在留資格 | 該当する職業例 |
| 外交 | 外国政府からの大使や公使等(およびその家族) |
| 公用 | 外国政府等の公務に従事する者(およびその家族) |
| 教授 | 大学教授等 |
| 芸術 | 作曲家や画家、芸術作家等 |
| 宗教 | 外国から派遣された宣教師等 |
| 報道 | 外国の報道機関に属する記者やカメラマン等 |
| 高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
| 経営・管理 | 企業等の経営者等 |
| 法律・会計業務 | 弁護士や公認会計士等 |
| 医療 | 医師や看護師等 |
| 研究 | 公的機関や企業における研究者等 |
| 教育 | 中学校や高等学校等における語学教師等 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 技術者や通訳翻訳、システムエンジニア等 |
| 企業内転勤 | 日本企業の海外支店からの転勤者 |
| 介護 | 介護福祉士 |
| 興行 | 俳優や歌手、プロスポーツ選手等 |
| 技能 | 外国料理の調理師等 |
| 特定技能 | 特定産業分野において相当程度の知識・技能を要する業務に従事する者、熟練した技能を要する業務に従事する者 |
| 技能実習 | 技能実習生 |
参考:在留資格一覧表|出入国在留管理庁
在留資格ごとに定められている活動内容に見合った職種でなければ、資格の許可が下りません。就労が認められている在留資格で外国人を雇用する場合には、自社の職種と活動内容が一致しているかチェックしましょう。
就労制限のない在留資格
日本人もしくは永住者の配偶者や子どもなど、身分に関係する在留資格には就労制限はありません。職種や業種に関係なく自由に働けます。
就労制限のない在留資格は以下の4種類です。
| 在留資格 | 該当例 |
| 永住者 | 日本への永住許可を受けた外国人 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者や実子、特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者や特別永住者の配偶者、日本で生まれそのまま在留している実子 |
| 定住者 | 日系3世や外国人配偶者の連れ子、第三国定住難民、中国残留邦人等 |
参考:在留資格一覧表|出入国在留管理庁
活動に制限がなく、幅広い職種で活躍できるため、採用しやすい人材と言えます。
就労が認められない在留資格
就労が認められない在留資格も存在します。
種類は以下の5つで、収入を伴う日本での就労は原則認められません。
| 在留資格 | 該当例 |
| 文化活動 | 文化研究者等(収入を伴わないもの) |
| 留学 | 大学、専門学校、日本語学校等の学生 |
| 研修 | 日本で技能の習得を行う外国人(技能実習と留学を除く) |
| 家族滞在 | 「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「特定技能2号」「文化活動」「留学」の在留資格を持ち日本に在留する外国人の配偶者と子 |
| 短期滞在 | 日本に短期間滞在して行う観光、保養、スポ―ツ、親族の訪問、見学、講習への参加、業務、連絡など |
参考:在留資格一覧表|出入国在留管理庁
アルバイトする場合は、出入国在留管理庁から「資格外活動許可」の申請が下りれば就労可能です。
また、ここまで紹介した在留資格28種類の他に「特定活動」の在留資格もあります。特定活動は、法務大臣が個々の外国人に指定する活動が認められる在留資格です。
【関連記事】
在留資格とは?取得方法や全29種類の活動内容について徹底解説します
就労ビザ(在留資格)の取得条件

就労が認められている在留資格の取得条件は、資格の種類ごとに異なります。
いくつかの在留資格をピックアップして、取得条件をまとめました。※リンクが付いている在留資格名をタップすると、詳細記事をご覧いただけます
| 在留資格 | 取得条件 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ・各分野の知識・技術・感性を活かせる業務内容に従事すること ・海外もしくは日本の大学、日本の専門学校を卒業すること ・専攻学科と職種に関連性があること ・学歴が満たない場合は、実務経験が「技術」「人文知識」は10年以上、「国際業務」は3年以上あること など |
| 特定技能 | ・18歳以上であること ・各分野の技能試験および日本語能力試験に合格すること(技能実習2号を良好に修了した外国人は免除) など |
| 技能実習 | ・18歳以上であること ・帰国後、習得した知識・技術を要する業務への従事を予定していること など |
参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁
特定技能外国人を受け入れるまで|外務省
技能実習生に関する要件|厚生労働省
企業側に求める要件や必要書類も在留資格ごとに違うので、事前によく確認しましょう。
就労ビザ(在留資格)の取得方法

ここでは、就労が認められている在留資格の取得方法について解説します。
以下2つのケースよって、取得方法は異なります。
- 海外在住の外国人を雇用する場合
- 日本に滞在する外国人を雇用する場合
それぞれの方法を詳しく見ていきましょう。
海外在住の外国人を雇用する場合
海外在住の外国人を雇用する場合は「在留資格認定証明書」の取得が必須です。
採用活動での人材募集・面接を経て、外国人材と雇用契約を結んだあと、企業側が出入国在留管理庁に在留資格認定証明書の申請をします。
証明書が交付されたら、海外にいる外国人に送付します。
外国人が在留資格認定証明書を受け取ったら、現地の日本在外領事館・大使館に提出し、入国ビザ(査証)の取得手続きを進めるよう促してください。
入国ビザが取得できたら、日本に入国し、空港にて外国人が在留カードを受け取ります。これにより、在留資格を取得したことが証明されます。
【関連記事】
海外在住の外国人を採用する方法とは?元送り出し機関職員が解説
在留資格認定証明書の申請方法と入国までの流れや手続きの注意点について解説
日本に滞在する外国人を雇用する場合
日本に滞在する外国人で、就労が認められる在留資格を取得する場合、在留資格変更許可申請をしなくてはなりません。
以下は在留資格を変更するケース例です。
在留資格を変更するケース
- 在留資格「留学」(就労が認められない資格)から変更する
- 前職と違う職種に転職する場合に変更する
- 身分系の在留資格から変更する
どのケースでも、外国人材と雇用契約を結んだのち、出入国在留管理庁に在留資格変更許可申請をします。在留資格の取得要件が満たされているか審査され、問題なければ就労目的の在留資格に切り替えられます。
なお「在留資格認定証明書」の申請や、在留資格変更許可申請は、行政手続きに該当し、ある程度の知識がないと対応するのが難しいです。
自社での対応が難しいと判断した場合は、外国人雇用の手続きに強い行政書士事務所に業務を委託すると確実かつスムーズに申請が進められます。
「外国人採用の窓口」では行政書士事務所の一括検索サービスを提供しており、ご希望のエリアや業種などを条件検索して探せます。
無料相談も受け付けておりますので、外国人雇用に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
弊社では「外国人採用BOOK~入門編~」の資料を無料配布しております。外国人雇用における基本的な知識が学べる内容です。
30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人採用の基本で
お悩みの方に
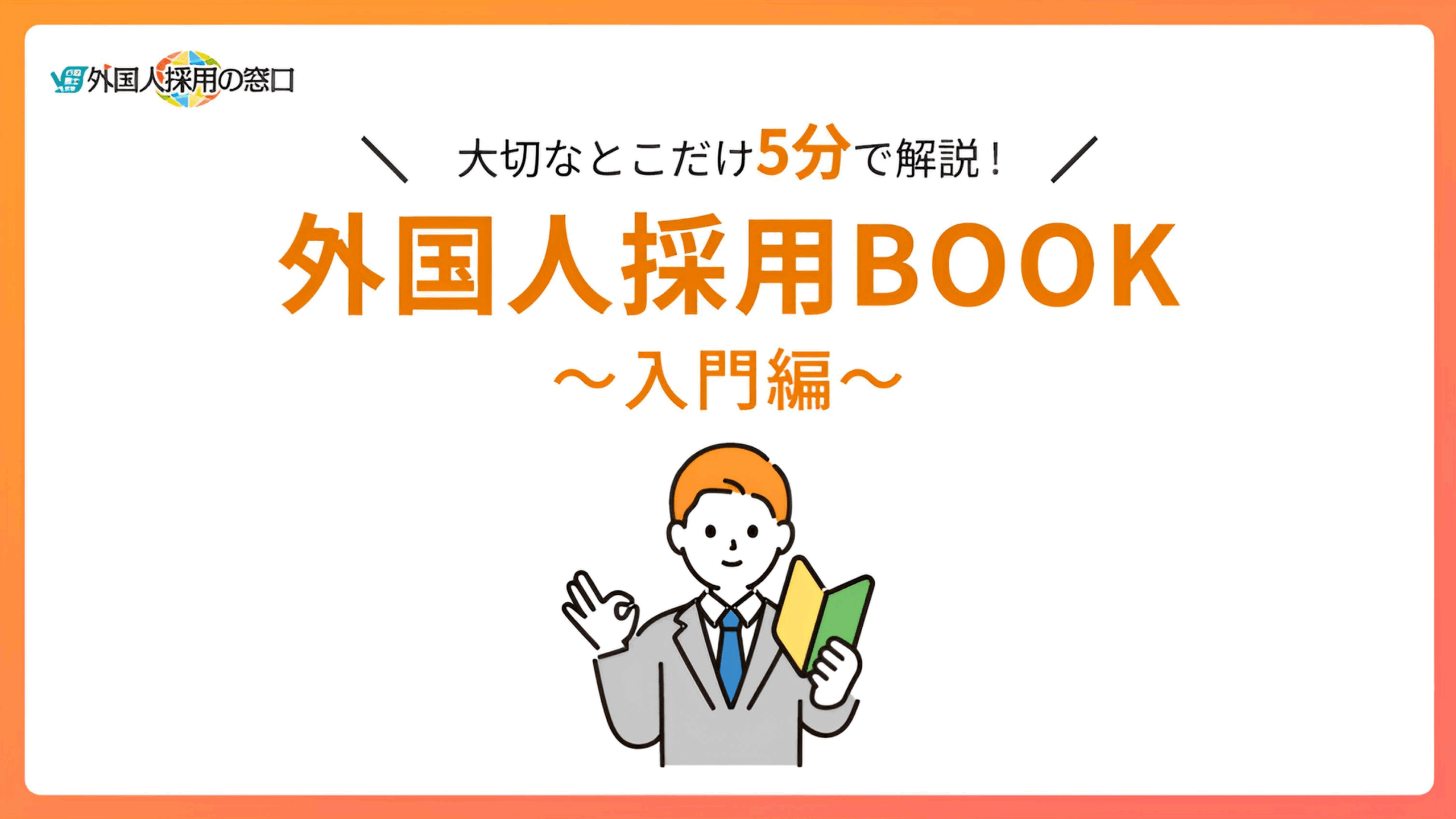
この資料でわかること
- 外国人労働者の現状
- 雇用できる在留資格の確認方法
- 外国人雇用における注意点
- 外国人を受け入れる流れ
就労ビザ(在留資格)の在留期間

在留期間は在留資格ごとに異なります。
在留資格をいくつかピックアップして、それぞれの在留期間を以下の表で紹介します。
| 在留資格 | 在留期間 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 5年、3年、1年または3ヵ月 ※在留期間は法務大臣の判断で決められる |
| 特定技能 | ・特定技能1号の場合:1年を超えない範囲 ・特定技能2号の場合:3年、1年または6ヵ月 ※在留期間は法務大臣の判断で決められる |
| 技能実習 | ・技能実習1号の場合:1年を超えない範囲 ・技能実習2号の場合:2年を超えない範囲 ・技能実習3号の場合:2年を超えない範囲 ※在留期間は法務大臣の判断で決められる |
参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」|出入国在留管理庁
在留資格「特定技能」|出入国在留管理庁
在留資格「技能実習」|出入国在留管理庁
日本で継続して働きたい場合は、在留期間が満了する前に出入国在留管理庁で在留期間更新許可申請をします。
更新手続きをせずに、日本に在留し続けた場合は、オーバーステイ(不法残留)となり、外国人は強制退去処分を受け、企業側は法的責任を問われる可能性があります。
【関連記事】
就労ビザの在留期間は何年?長期の在留許可を受ける方法や在留資格ごとの期間決定のルールを解説
就労ビザ(在留資格)を申請して不許可になるケース

就労目的の在留資格は申請をしても不許可になる場合があります。
不許可になりやすいケースは以下の3つです。
- 提出書類に不備や虚偽がある
- 取得の条件を満たしていない
- 企業側に問題がある
対策に努めて許可率を高めましょう。
提出書類に不備や虚偽がある
提出書類に不備や虚偽があると不許可になる可能性が高いです。
起こりやすい書類作成時のミスを以下にまとめました。
起こりやすい書類作成時のミス
- 誤字・脱字が目立つ
- 必要な情報の記入が漏れている
- 学歴や職歴の内容があっていない
- 添付書類が不足している
- 日付や署名が間違っている
書類の不備は審査に必要な情報が伝わらない原因となります。また、情報の誤りや偽った記載は、信頼性に欠け許可が下りにくいです。
書類を作成する際は、正しい情報を記載し、提出前に記載漏れや誤記がないか最終チェックを念入りにしましょう。
自社での対応が難しいと判断した場合は、外国人雇用の手続きに強い行政書士事務所に業務を委託すると確実かつスムーズに申請が進められます。
「外国人採用の窓口」では行政書士事務所の一括検索サービスを提供しており、ご希望のエリアや業種などを条件検索して探せます。
無料相談も受け付けておりますので、外国人雇用に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
取得の条件を満たしていない
在留資格の取得条件を満たしていない場合も、不許可になります。
例えば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の取得条件の1つは、学歴での専攻学科と業務内容の関連性があることです。
それぞれの分野と関連性のある職種は以下の通りです。
分野と関連性のある職種
- 技術:プログラマー、システムエンジニアなど
- 人文知識:営業職、コンサルティングなど
- 国際業務:通訳・翻訳、語学学校の講師など
技術分野の外国人が、通訳・翻訳の業務に従事したり、反対に国際業務の外国人がプログラマーとして働く場合、在留資格の許可は下りません。
各在留資格の条件を厳守して許可率を高めましょう。
企業側に問題がある
在留資格の申請審査では、企業側の経営状況や労務の管理状況も審査対象です。
以下のような問題があると「外国人を適切に雇用できない企業」と判断され、不許可になる確率が高いです。
企業側の問題例
- 赤字が続いている
- 雇用している外国人労働者の失踪者が多い
- 外国人労働者の給料が日本人よりも低い
- 労働基準法違反の履歴がある
日本で働く外国人は日本人同様に、労働関係法令(労働基準法、最低賃金法など)や、同一労働同一賃金の原則が適用されます。
そのため、最低賃金を下回る給料や日本人と異なる給料を設定したり、残業代を支払わずに長時間労働させたりするのは法令違反となります。
就労ビザ(在留資格)の許可率を上げるコツ

就労目的の在留資格の許可率を上げるコツを3つ紹介します。
- 申請手続きのサポートをする
- 申請取次の認定を受ける
- 申請取次行政書士に委託する
できる方法に取り組み、許可率を高めましょう。
申請手続きのサポートをする
在留資格の申請手続きにおける書類作成や窓口での申請は、原則外国人本人しかできません。※在留資格認定証明書の取得申請は企業側がおこなう
しかし、企業側が以下のようなサポートをすることは可能です。
企業側ができるサポート
- 書類に書かれている内容を説明する
- 必要書類の準備を手伝う
- 記入方法をアドバイスする
- 提出前の書類チェックを行う
- 申請先の出入国在留管理庁を案内する
慣れない手続きを外国人一人で進めるのは、難しいです。企業側ができる範囲のサポートをして申請をスムーズに進めましょう。
申請取次の認定を受ける
申請等取次制度において、出入国在留管理庁が適当と認める者は、外国人に代わって申請の取次ができます。
申請取次者として認められるには、制度で定められている条件をクリアした者に限られます。
外国人の申請手続きを徹底的にサポートしたい場合は、企業の職員が申請取次者の認定を得る選択肢も検討してみましょう。
参考:申請等取次制度について|出入国在留管理庁
申請取次行政書士に委託する
在留資格の手続きを申請取次行政書士に委託する方法もあります。
申請取次行政書士は、行政手続きの専門家である行政書士の中で、出入国在留管理庁から申請取次の認定を受けた者です。
申請取次行政書士は、豊富な専門知識と経験を持っています。審査が通る傾向も掴んでいるため、許可率アップが期待できます。
書類作成の代行や必要書類の準備もサポートしてもらえるため、企業は自社の業務に専念しやすいです。
数ある行政書士事務所の中でどの事務所に依頼すれば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。条件検索にてあなたのお近くのエリアで、自社のニーズにマッチした事務所を探せます。
無料相談も受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。
就労ビザ(在留資格)の申請にお困りなら「外国人採用の窓口」をご利用ください

「就労ビザ(在留資格)に関して誰かに相談したい!」
「信頼できる行政書士事務所を見つけたい…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した登録支援機関や行政書士事務所、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
条件検索できるため、あなたが雇用したい国籍、業界、職種、在留資格の就労支援に強い会社をご紹介します。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けているので、就労ビザ(在留資格)に関するお悩みがある方もお気軽にお問い合わせください。
就労ビザに関するよくある質問
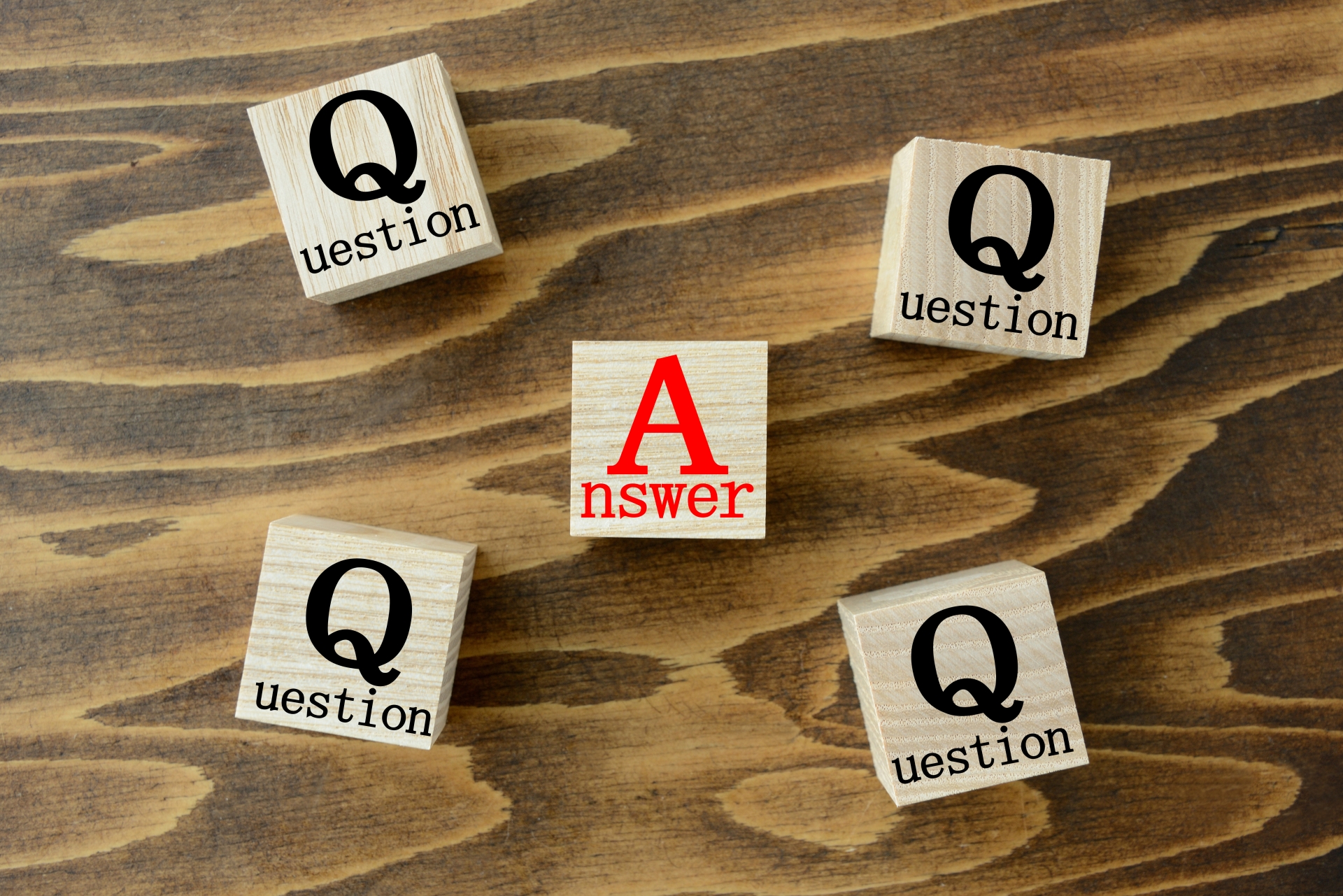
最後に就労ビザに関するよくある質問と回答を紹介します。
就労ビザと在留カードの違いを教えてください
就労ビザは、就労が認められている在留資格のことを指します。
在留カードは、日本での在留が許可されたことを公的に証明するカードです。
就労ビザは誰が申請しますか?
就労が認められている在留資格の申請は、原則外国人本人がおこないます。
しかし、出入国在留管理長から「申請取次者」としての許可を得た者は、外国人に変わって申請が可能です。
参考:申請等取次制度について|出入国在留管理庁
日本で就労ビザの許可をもらうのは難しいですか?
在留資格ごとに取得条件が異なるため、一概に難しいとは言えません。
しかし、定められている条件を的確に満たすのは簡単ではないほか、外国人本人が申請書を作成するのは困難です。
許可率を少しでも高めたい場合は、外国人雇用の手続き支援に強い行政書士事務所に業務を委託するのがおすすめです。
就労ビザ(在留資格)の理解を深めて外国人をスムーズに雇用しよう

在留資格は、種類ごとに認められる活動内容や在留期間が異なります。
自社にあったニーズの人材を確保するためには、在留資格における基本知識の習得が欠かせません。
本記事で紹介した在留資格の種類や取得条件を参考に、自社とマッチする在留資格を見つけてみてください。
自社だけで在留資格の申請サポートや、受け入れ準備をするのが不安な場合は、各分野の専門家に業務を委託する選択肢もあります。
外部機関の力をうまく借りながら、外国人雇用を進めましょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。


