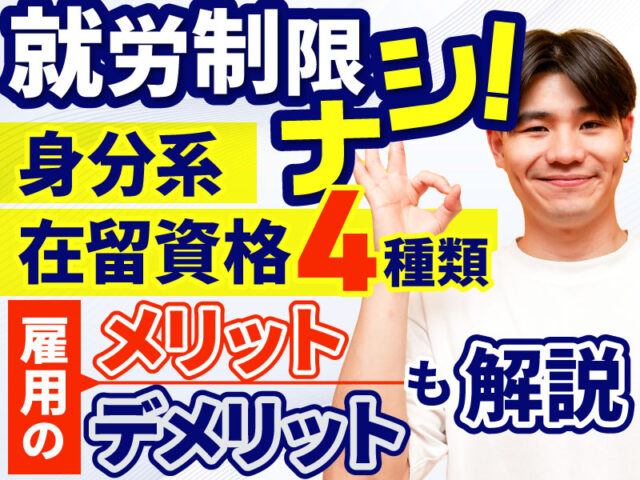「身分系の在留資格って何?」
「就労系の在留資格との違いは何?」
このような悩みをお持ちの方も多いでしょう。
身分系在留資格は、永住者・永住者の配偶者等・日本人の配偶者等・定住者の4種類にわけられます。
就労制限がなく、ほぼすべての業種や職種で働くことが可能な在留資格です。
また、更新上限がなく長期雇用につながりやすいため、採用や定着に課題を抱える企業にとって大きな戦力となります。
本記事では4種類に分かれる身分系在留資格の特徴や就労系在留資格との違いを詳しく解説します。
雇用のメリットや注意点まで紹介しているので、参考にしてみてください。
外国人採用の窓口では、「外国人採用BOOK入門編」の資料を無料配布しております。
外国人採用に不可欠な在留資格の基本と種類をまとめた資料です。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
外国人採用の基本で
お悩みの方に
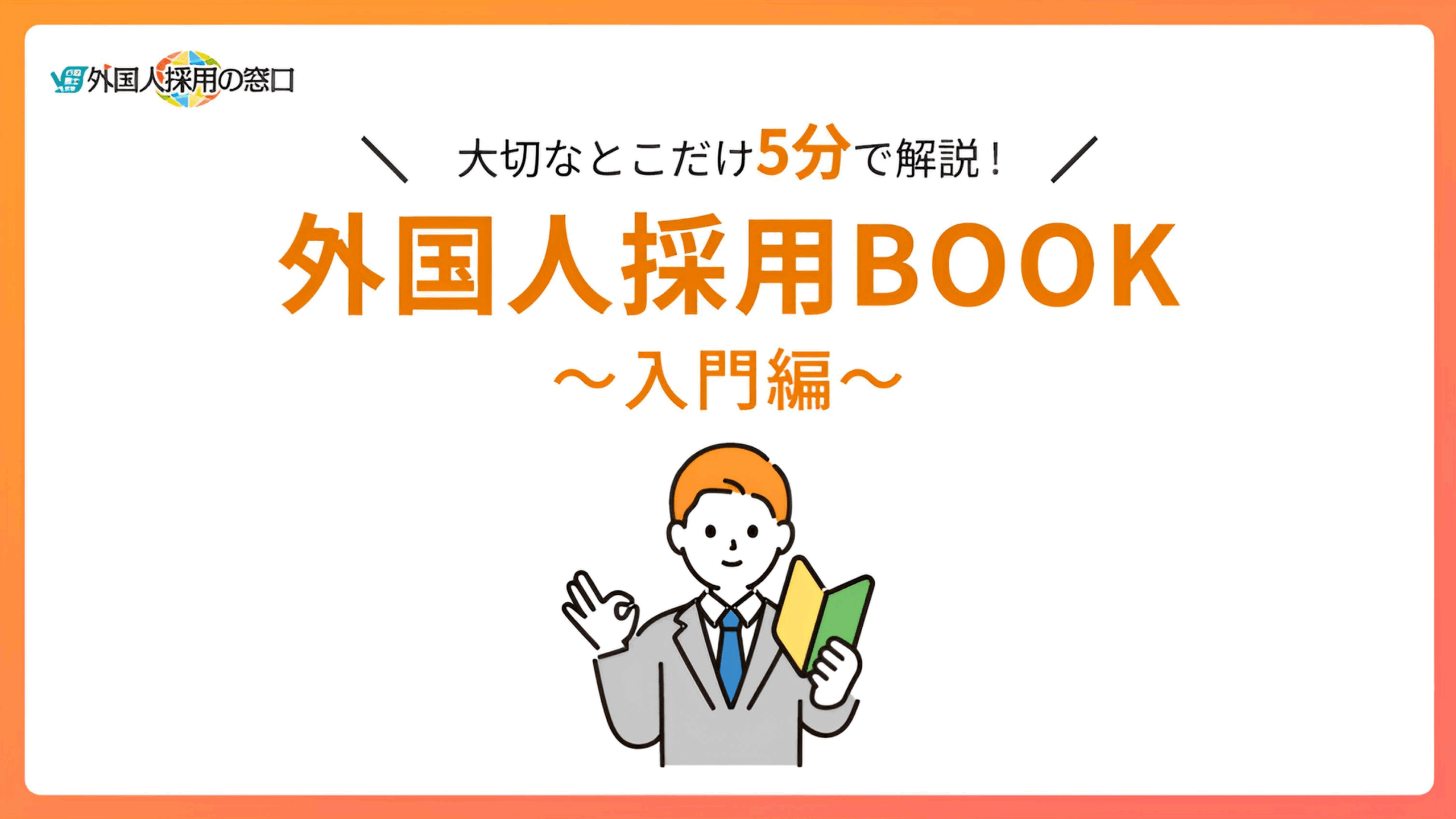
この資料でわかること
- 外国人労働者の現状
- 雇用できる在留資格の確認方法
- 外国人雇用における注意点
- 外国人を受け入れる流れ
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
INDEX
身分系在留資格は4種類|特徴を解説

身分系在留資格とは、「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」の4種類をまとめた呼び方です。
いずれも身分や地位に基づいて付与される在留資格であり、活動内容に制限がなく、幅広い職種での就労が認められています。
身分系在留資格という名称は入管法において「一定の身分もしくは地位を有する者に与えられる在留資格」と分類されていることに由来しています。
「特定技能」など就労系在留資格や「留学」などの非就労系在留資格と異なり、在留資格取得の根拠が活動内容ではなく、身分・地位関係にある点が特徴です。
なお、出入国在留管理庁はこれら4つの在留資格を総称して「居住資格」と呼んでいます。
以下4つの在留資格の概要についてそれぞれ解説していきます。
- 永住者
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
詳しく見ていきましょう。
永住者
「永住者」は、日本に無期限で滞在することを認められた在留資格であり、就労や居住に関する制限がほとんどない点が特徴です。
法務大臣から永住許可を受けた外国人は、在留期間更新の必要がなく、幅広い職種での就労が可能になります。
ただし、日本国籍を取得するわけではないため、出入国時には再入国許可が必要であり、一定の条件を満たさなければ在留資格を失う可能性もあります。
在留資格を得るための代表的な要件は以下の通りです。
永住者の在留資格を得るための要件
- 素行が善良であること
- 独立して生計を営むに足りる資産や技能を持つこと
- 日本国の利益に合致すると認められること
永住許可の審査においては、納税や社会保険料の適切な納付など、公的義務の履行が厳格に審査されます。
前提条件は以下の通りです。
永住許可申請の前提条件
ただし、「日本人の配偶者等」や「永住者の配偶者等」、「定住者」「高度専門職」などの場合には、短縮された特例の条件が適用されることがあります。
このように永住者は安定した生活基盤を持つことが前提となる資格であり、企業にとっても安心して雇用できる人材である一方、取得には長期間の在留実績や社会的信用の積み重ねが不可欠となっています。
【関連記事】
永住ビザの条件とは?失効する原因や取得するメリットを解説!
日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、または日本人の子として出生した外国人に与えられる在留資格です。
永住者と同様に就労制限はありません。
この在留資格は、国際結婚や親子関係に基づいて日本に滞在するための資格であり、結婚や出生の事実だけではなく、入管庁による在留資格の審査を経て在留許可が与えられます。
「日本人の配偶者等」の主な許可要件は以下の通りです。
日本人の配偶者等の在留資格を得るための要件
- 婚姻関係・家族関係が真実であること
- 安定した生活のための経済的基盤があること
- 素行が不良でないこと
この在留資格を申請する際には、在留資格取得目的の偽装結婚による申請を防ぐために厳しい審査がおこなわれます。
交際の経緯や生活実態などを具体的に説明する資料が必要となり、二人の婚姻関係が虚偽ではないことを立証する責任が生じます。
また、生活基盤の安定も重要な審査項目です。
申請者本人や日本人配偶者が安定した収入を有し、公共の負担とならない生活が見込まれることが求められます。
収入や職業の状況によっては、真実の婚姻関係が成立していても不許可となるケースがあるため、経済的基盤の確立が欠かせません。
永住者の配偶者等
「永住者の配偶者等」は、永住者または特別永住者の配偶者、そして永住者等の子として日本で出生し、その後も継続して日本に在留している人に与えられる在留資格です。
この在留資格は就労の制限はなく、雇用形態や職種を問わず働くことが可能です。
審査の基準は「日本人の配偶者等」と同様に婚姻の真実性や収入の安定性などが確認されます。
「永住者の配偶者等」の主な許可要件は以下の通りです。
永住者の配偶者等の在留資格を得るための要件
- 婚姻関係・家族関係が真実であること
- 安定した生活のための経済的基盤があること
- 素行が不良でないこと
注意点として、永住者等の子が申請をおこなう場合の要件は「日本で出生し、そのまま在留を継続している子」に限られます。
海外で出生した子や出生後に出国し日本で在留を継続していない子の場合は、在留資格の該当性を失う点に注意が必要です。
ただし、その場合も「定住者」の在留資格を取得できる可能性はあります。
定住者
「定住者」は法務大臣が特別な事情を考慮して居住を認める者に与えられる在留資格で、就労の制限はありません。
定住者の在留資格には、あらかじめ告示で具体的な類型を定めた「告示定住」と、個々の事情を都度個別に判断する「告示外定住」があります。
告示定住の一覧は以下の通りです。
| 告示定住者の一覧 |
| 1号:第三国定住難民
2号:削除 3号:日本人の子として出生した者の実子(日系2世・3世) 4号:日本国籍離脱者が国籍を離脱した後に生まれた実子の実子(日系3世) 5号:日本人の子として「日本人の配偶者等」で在留する外国人の配偶者、定住者の配偶者 6号:帰化日本人、永住者、特別永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子 7号:日本人、永住者、特別永住者、定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の容姿 8号:中国残留邦人とその親族 |
一方、告示外定住は具体的な類型が定められていないため、どのような場合に許可が取得可能であるか明確に事前把握することはできません。
ただし、以下のような場合には告示外定住が取得可能と言われています。
| 告示外定住の代表例 |
| 難民認定:告示定住1号以外で法務大臣が難民と認定した者
離婚定住:日本人、永住者、特別永住者と離婚した者 死別定住:日本人、永住者、特別永住者の配偶者と死別した者 日本人実子 扶養定住:日本人の実子を監護・養育する者 特別養子 離縁定住:特別養子の離縁により「日本人の配偶者等」でなくなった者 |
なお、告示外定住は入国前に申請することはできないため、申請するにあたっては他の在留資格で日本に在留している状態で在留資格変更許可申請等をおこなって許可を受ける必要があります。
【在留資格一覧あり】就労系在留資格との違い

身分系在留資格と就労系在留資格の違いは、就労に関する制限の有無です。
身分系は活動内容に制限がなく、就労系は許可された範囲内でのみ働けます。
在留資格は大きく分けて以下のように分類されます。
| 身分系在留資格 | 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 |
| 就労系在留資格 | 技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能、技能実習など |
| 非就労系在留資格 | 留学、家族滞在、文化活動など |
就労系在留資格は職種や業務内容が限定され、転職時には資格変更が必要になります。
一方で、身分系在留資格は職種を問わず自由に働けるため、企業側の採用の選択肢が広がります。
身分系在留資格を検討するうえで、雇用時に何を確認すべきか迷うケースも少なくありません。
「外国人採用の窓口」では、身分系在留資格に詳しい行政書士事務所や登録支援機関、人材紹介会社を無料で検索できます。
初めての外国人採用でも、安心して相談できるパートナーを見つけたい方は、ぜひご活用ください。
身分系在留資格者を雇用するメリット

身分系在留資格を持つ外国人を雇用すると、制度面と実務面の双方で以下のような多くの利点があります。
- 就労制限がない
- 在留期間の通算上限がない
- 企業側の申請負担が少ない
- 日本の生活に慣れている人が多い
- 信頼できる人材を紹介してもらえる可能性がある
ここからは、企業目線で知っておきたい身分系在留資格のメリットを順に解説します。
就労制限がない
身分系在留資格の最も大きな特徴は、従事できる業務に制限が設けられていない点にあります。
そのため、労働基準法や最低賃金法などの労働関連法規を守っている限り、飲食業や製造業、事務職、研究職など幅広い分野で日本人と同じように勤務することが可能です。
例えば午前中に現場作業をして、午後から事務作業をするなど複数の業務に跨るような就労形態も可能です。
在留資格が有効である限りは不法就労に該当するリスクがなく、外国人雇用に不慣れな企業にとっても安心して採用できるという利点があります。
在留期間の通算上限がない
身分系在留資格には在留期間の通算の上限がないため、安定した長期雇用につながりやすい特徴があります。
永住者に付与される在留資格には期間の制限がなく、一度許可を得れば更新手続きをおこなう必要がありません。
また、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者については5年、3年、1年または6ヵ月といった期間が与えられ、その都度更新手続きをおこなう必要があります。
そのため、雇用主にとっては永住者を採用する場合は在留期間を気にすることなく継続的な雇用が見込め、その他の身分系資格保持者についても更新を前提としながら長期的な就労が期待できる点が大きなメリットです。
【関連記事】
就労ビザの在留期間は何年?長期の在留許可を受ける方法や在留資格ごとの期間決定のルールを解説
企業側の申請負担が少ない
身分系在留資格は個人の身分関係に基づいて与えられるため、許可の条件が雇用契約そのものとは切り離されています。
そのため、在留期間の更新や変更といった入管手続きにおいて、企業が申請代理をおこなったり書類作成の補助をしたりする義務は発生しません。
外国人を採用する際に入管法の専門知識を持たなくても、雇用をスムーズに開始できるという利点があります。
日本の生活に慣れている人が多い
身分系在留資格を持つ外国人の多くは、日本で長期間生活しており、日本語での意思疎通や職場環境への適応に優れています。
特に日本で生まれ育った人や幼少期から日本で暮らしている人は、日本の教育を受けている場合が多く、読み書きや会話を含む日本語能力が高い傾向です。
このような人材を採用することで、業務上の指示理解や顧客対応を日本人同様におこなえる場合が多く、企業にとっては教育や研修の負担を軽減できる利点があります。
さらに、日本の生活習慣や価値観に慣れているため、文化的な違いによる摩擦や早期離職のリスクを抑えられる点も、雇用の大きな魅力といえるでしょう。
信頼できる人材を紹介してもらえる可能性がある
日本に暮らす外国人の多くは、同じ国や地域の出身者どうしで作られたコミュニティに所属しており、職場環境や待遇が良ければ知人を紹介してもらえる可能性があります。
特に身分系在留資格を持つ人材は、同じ境遇の外国人とのつながりを持っているケースが多く、企業が信頼関係を築ければ、自然な流れで採用ルートが広がることが期待できます。
このように、既存従業員からの紹介は、採用コストを抑えつつ適切な人材を確保できる点で、企業にとって大きな利点です。
柔軟な雇用形態で活用できる
身分系在留資格を持つ外国人は、日本人と同様の条件で就労できるため、雇用形態を柔軟に設定することが可能です。
このため、労働基準法などの法令を守っている限り、副業やアルバイトとしての雇用、人材派遣を活用した採用もおこなえます。
加えて、業務委託契約を結んで特定の業務を依頼したり、フリーランスとして活動している身分系外国人に外注したりすることも問題ありません。
このように幅広い活用が可能である点は、企業にとって人材戦略の選択肢を広げる大きなメリットとなります。
ただし、雇用形態が柔軟に選べる一方で、業務委託として扱えるか、在留資格・労働法令に違反しないかを確認しなければなりません。
行政書士は公的手続きの専門家です。外国人雇用に関する行政手続きにも精通している専門家に相談することで、企業側の負担を軽減できます。
「外国人採用の窓口」では、身分系在留資格の雇用形態に詳しい行政書士事務所を無料で検索できます。
自社の雇用方針に合った採用方法を検討したい方は、ご活用ください。
身分系在留資格者を雇用する場合の注意点

身分系在留資格を持つ外国人は、就労制限がなく柔軟に働ける反面、採用や人材管理の面で以下のような注意が必要な点もあります。
- 日本語コミュニケーションに課題が生じる場合がある
- 外国人雇用状況の届出を必ず提出する
- 在留カードの有効期限を定期的にチェックする
- 永住者も在留カード更新を忘れずにおこなう
ここからは、企業が把握しておくべき注意事項について解説します。
日本語コミュニケーションに課題が生じる場合がある
身分系在留資格を持つ外国人の中には、日本語での会話が十分におこなえない人もいます。
例えば「永住者の配偶者等」の資格を持つ場合、家庭内で母語を中心に使用しているケースが多く、日本語を学ぶ機会が限られていることがあるためです。
また、「定住者(日系)」などでは、日系人コミュニティの中で生活が完結してしまうこともあり、日本語の習得が進みにくい環境に身を置いている人もいます。
そのため、生活上は問題なく日本に適応しているように見えても、実際の日本語能力に差があることは珍しくありません。
短時間の面接だけで語学力を判断すると、業務で必要な日本語能力水準に達していない人材を採用してしまい、職場で意思疎通の齟齬が生じる可能性があります。
身分系の在留資格は日本語能力や仕事との適正に関係なく在留が認められるため、採用にあたってはコミュニケーション能力を含めた適性を慎重に確認することが求められます。
外国人採用の窓口では、「外国人社員とのコミュニケーションのコツ」の資料を無料配布しております。日本人と外国人労働者の間で壁となる文化的な背景や考え方の違いをまとめた資料です。
30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
外国人社員との
やりとりでお困りの方に

この資料でわかること
- 外国人雇用における言語課題
- 伝わりにくいコミュニケーション例
- 伝わりやすいコミュニケーション例
- 外国人社員にあった指導方法
外国人雇用状況の届出を必ず提出する
外国人を採用した事業主には、雇い入れ時や離職時に「外国人雇用状況の届出」をハローワークへ提出する義務があります。
これは身分系の在留資格を持つ外国人を雇用する場合も同じです。
ただし、雇用保険に加入する対象となる外国人を採用する場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」の提出によって「外国人雇用状況の届出」をおこなったものとみなされます。
労働時間が短い場合など、雇用保険の適用外となる外国人従業員を雇用する際には、事業者が自ら「外国人雇用状況の届出」を提出しなければならない点に注意が必要です。
在留カードの有効期限を定期的にチェックする
身分系の在留資格を持つ外国人のうち、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は、審査のたびに在留期間が付与され、満了前には必ず更新手続きが必要です。
しかし、更新を怠ったり婚姻関係が解消されたりすると、在留資格を維持できなくなる場合があります。
その状態で雇用を続けると不法就労に該当し、雇用主も罰則の対象となるおそれがあります。
このため、企業が身分系在留資格者を雇用する際には、在留カードを定期的に確認し、更新が確実におこなわれているかをチェックすることが不可欠です。
適切な管理体制を整えておくことで、法令違反のリスクを防ぎ、安心して雇用を継続できます。
永住者も在留カード更新を忘れずにおこなう
永住者の在留カードには有効期限が設けられており、通常7年ごとに更新手続きが必要です。
ただし、永住者は在留期間が無期限であるため、在留カードの有効期限が切れても不法残留とは扱われず、退去強制の対象になることはありません。
外国籍の方の場合は、有効な在留カードを常時携帯する義務が課されており、期限切れのカードではその義務を果たさない状態になります。
在留カード不携帯は20万円以下の罰金が科される可能性があるため、永住者を雇用する企業においても在留カードの更新状況を把握しておくことが重要です。
【関連記事】
在留カード更新ができない理由とは?更新手順も解説!
身分系在留資格に関するよくある質問

身分系在留資格の労働者は日本にどれくらいいますか?
厚生労働省の外国人雇用状況によると、身分系在留資格者は約63万人が日本で就労しています。
これは外国人労働者全体の約3割を占め、重要な労働力となっています。
特に永住者と定住者が多く、製造業やサービス業など幅広い業種で活躍しています。
また、近年は日本人の配偶者等の就労も増加傾向にあります。
身分系在留資格者は今後も日本の労働市場で重要な役割を担っていくでしょう。
参考:「外国人雇用状況」の届け出状況|厚生労働省
身分系在留資格を雇う際に外国人雇用契約書は必要ですか?
外国人雇用契約書の作成は任意とされており、法律上の作成義務はありません。
しかし、トラブル防止のため日本人と同様に雇用契約書を作成しておきましょう。
契約書を作成する際は、在留資格と就労可能な業務内容の確認や、契約期間が在留期間を超えないようにするなど複数のポイントがあります。
詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
【テンプレートあり】外国人雇用契約書の概要や作成時の注意点を解説
ビザと在留資格の違いはなんですか?
ビザとは、外国人が日本へ入国するために事前に取得する入国の許可証です。
日本に入国する外国人は、出入国管理及び難民認定法に基づき、日本の大使館や領事館で発行される査証を取得していなければ入国できません。
一方、在留資格とは、日本に入国した後、どのような活動ができたり、どのような身分や立場で滞在できたりするのかを法律で定めた制度です。
在留資格によって、働ける仕事内容や在留できる期間が決まるため、企業が外国人を雇用する際は在留資格の確認が必要です。
【関連記事】
ビザと在留資格の違いを詳しく解説|種類や在留カードとの違いも紹介
在留資格は全部で何種類ありますか?
在留資格は現在29種類が設定されており、活動内容や身分関係に応じて分類されています。
さらに細かく以下の4つに分類されます。
在留資格の分類
- 就労資格:就労が認められる
- 非就労資格:就労が認められない
- 居住資格:雇用形態や就労内容に制限が無い
- 特定活動:法務大臣が個別に指定する活動内容に基づき滞在を認められる
企業が外国人を雇用する際は、該当する在留資格を正確に把握していきましょう。
29種類の詳しい在留資格の活動については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
【関連記事】
在留資格とは?取得方法や全29種類の活動内容について徹底解説します
在留カードと在留資格の違いはなんですか?
在留資格は日本での活動を許可する法的な地位で、在留カードはその証明書です。
在留カードには在留資格の種類、在留期間、就労の可否などが記載されています。
例えば、永住者という、身分系の在留資格を持つ方は、その情報が記載された在留カードを携帯します。
雇用時には在留カードで在留資格を確認し、就労可能な資格かを判断していきましょう。
身分系在留資格の強みを活かして外国人を雇用しよう

身分系在留資格を持つ外国人の雇用は、就労制限がないため長期雇用が可能で、手続きも比較的簡易です。
一方で、業務の適性確認や在留期間の更新状況を企業自らが継続的に把握する姿勢が欠かせません。
また、今後は永住許可制度の運用が一層厳格化される見通しもあり、企業側には制度全体を正しく理解し対応する力が求められる可能性があります。
もし、不安や疑問がある場合は、外国人材採用に特化した紹介事業者や法令の専門家に相談し、適切な措置を取ることが、採用計画の円滑な実現とトラブル防止につながります。
外国人採用の窓口では、身分系在留資格者の採用に対応した人材紹介会社や登録支援機関、監理団体、行政書士事務所を無料で検索できます。
エリアや在留資格の条件から、自社に合う信頼できるパートナーを見つけ、外国人雇用の体制づくりに役立てていきましょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。