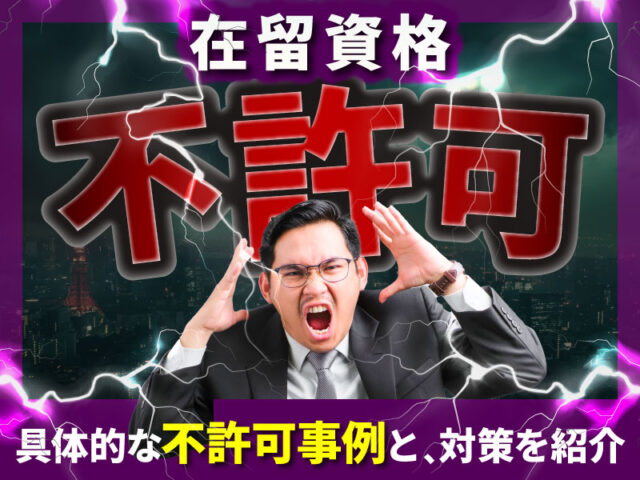外国人を採用した際に避けて通れないのが、在留資格の審査です。しかし、申請すれば必ず許可が下りるわけではなく、不許可となるケースも少なくありません。
せっかく人材を確保しても在留資格の取得が認められなければ雇用は実現せず、企業にとって大きな損失となります。そのため、不許可の原因や対策を事前に知りたいと考える雇用主は多いでしょう。
この記事では、在留資格が不許可になる代表的な理由や実際の事例を紹介しながら再申請を行う際に企業が取るべき対応について解説します。
審査での注意点や改善策を理解することで、申請の成功率を高め、安心して外国人材を受け入れることが可能となります。
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
在留資格申請の主な種類
在留資格に関する手続きにはいくつかの種類があり、外国人を雇用する企業にとってはその違いを理解することが重要です。
例えば、外国人が日本に新たに入国する前の事前手続きである在留資格認定証明書交付申請や、在留を継続するための在留期間更新許可申請、活動内容を変更する場合の在留資格変更許可申請などがあります。
これらの手続きは、申請の種類ごとに審査基準が異なるため、不許可の原因を正しく把握するためには、それぞれの特徴を知っておく必要があります。
在留資格認定証明書交付申請
在留資格認定証明書交付申請は、外国人が日本に入国する前に必要となる重要な手続きであり、通常は外国人を受け入れる企業などの機関が代理申請を行います。
この申請は地方出入国在留管理局で審査され、要件を満たしていると判断された場合に在留資格認定証明書が交付されます。
認定証明書を取得した外国人は、滞在国にある日本大使館や総領事館で査証の発給を受けることができます。
その後、日本に入国する際に空港などで入国審査を受け、在留資格が正式に付与されることで、初めて就労活動を開始できる流れとなります。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は、日本に滞在する外国人が現在の在留資格を維持したまま、在留期間だけを延長するために必要な手続きです。
更新申請では入管による審査が行われ、適法な在留状況の維持、安定した収入の確保、納税義務の履行といった共通基準に加え、在留資格ごとに定められた要件を満たしていることが求められます。
また、在留資格の種類によっては更新が認められないものや、一定期間を上限として繰り返し延長できないものもあるため注意が必要です。
在留資格変更許可申請
在留資格変更許可申請は、日本に滞在している外国人が活動内容を変える際に必要となる手続きです。
例えば、留学生が卒業後に日本で就職する場合や、技能実習を終えた人が特定技能へ移行する場合などが典型的なケースとして挙げられます。
在留資格変更許可申請は、就職や転職、結婚や離婚、起業など、人生の大きな転機に際して行われることが多い手続きです。
在留資格の許可要件
在留資格申請の許可要件は、日本に入国する前に行う認定証明書交付申請と日本滞在中に行う更新申請や変更申請とで内容が異なります。
それぞれの申請における基本的な要件を正しく理解しておくことは、不許可を避けるうえで有効であり、安定した在留の実現にもつながります。
新規上陸の要件
在留資格認定証明書交付申請の審査は、以下の3つの基準に基づいて行われます。
- 日本で予定している活動が、申請した在留資格の活動に該当していること
- 法務省令で定められた在留資格ごとの基準に適合していること
- 申請内容や申請に至った経緯に虚偽がないこと
さらに、空港での上陸審査においては、これらに加えて有効な旅券や査証(ビザ)の提示、そして入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないことが求められます。
更新・変更の要件
在留期間の更新や在留資格の変更は、すでに日本に滞在している外国人が行う手続きであり、その際には日本入国以降の在留状況が適切であるかどうかが重要な審査ポイントとなります。
更新や変更の際に求められる主な要件は次の通りです。
- 予定する活動が、申請した在留資格の活動に該当していること
- 法務省令で定められた在留資格ごとの基準に適合していること
- 申請時点で現に有する在留資格に応じた活動を行っていること
- 素行が不良でないこと
- 自立した生活を営むに足りる資産または技能を有していること
- 雇用や労働条件が適正であること
- 納税義務を履行していること
- 入管法に基づく各種届出を適切に行っていること
このように、新規の上陸審査と比べると更新や変更の申請にはより多くの条件が課されています。
しかし、これらの申請はすでに過去に許可を受けて日本に滞在している外国人を対象とするため、新規上陸前の在留資格認定証明書交付申請と比べて許可率が低いというわけではありません。
在留資格審査で不許可になる確率
在留資格の申請は、あらかじめ許可要件を確認することはできますが、具体的な審査基準が不明瞭なものもあり、要件を満たさず不許可となる場合もあります。
以下では、申請の種類ごとに不許可率を整理して解説します。
在留資格認定証明書交付申請の不許可率
2024年の統計によると、在留資格認定証明書交付申請の処理件数は690,681件となっています。
そのうち交付が認められたのは636,511件であり、全体の約92.1%が許可されています。
一方で、不交付処分や申請の取下げを含めた割合は約7.9%となり、一定数が不許可や手続き不成立に至っていることが分かります。
参考:e-Stat|在留資格認定証明書交付申請の受理及び処理人員
在留期間更新許可申請の不許可率
2024年の統計によると、在留期間更新許可申請の処理件数は1,146,867件でした。
そのうち許可が下りたのは1,131,093件であり、全体の約98.6%が更新を認められています。
不許可やその他の処分となった割合は約1.4%にとどまり、多くの申請が認められていることが分かります。
在留資格変更許可申請の不許可率
2024年における在留資格変更許可申請の処理件数は442,697件となっています。
そのうち許可が下りたのは423,505件であり、全体の約95.6%が認められました。
不許可やその他の処分は約4.4%を占め、更新申請に比べるとやや低い許可率となっています。
在留資格審査の不許可事例
在留資格申請が不許可となる場合には、必ず何らかの理由が存在します。
理由は多岐にわたりますが、事前に典型的な事例を把握しておくことで、予期せぬ不許可処分を避けられる可能性が高まります。
ここからは、審査で不許可となりやすい代表的な事例を紹介します。
申請する在留資格の活動に該当していない
在留資格にはそれぞれ活動できる範囲が定められており、その範囲を逸脱した内容で申請を行うと不許可となります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格を申請する際に、業務内容を工場での現場作業として記載すると、入管法で定められた技人国の活動範囲と一致しないため、不許可となる可能性が高くなります。
外国人の学歴・経歴と業務の関連性がない
就労を目的とする多くの在留資格では、学歴や職歴、資格など外国人の知識や技能と従事予定の業務内容との関連性が低いと判断されると不許可の理由となる可能性があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の申請において、専門学校でIT学科を専攻した外国人が建設業の施工管理業務に従事しようとする場合など、その外国人の専門分野と業務内容の不一致を理由に不許可となる可能性が高いです。
虚偽申請の可能性が疑われる
在留資格の申請で書類の内容に虚偽が含まれていると判断されれば不許可となる可能性が高く、悪質な場合には入管法違反として刑事罰の対象となることもあります。
在留資格認定証明書交付申請では、「活動の内容が虚偽でないこと」が審査基準に含まれており、申請内容の適正性を申請者が証明する必要があります。
例えば、留学を目的とする場合には、資金力を示す残高証明書や学歴を証明する卒業証書を提出しますが、これらに疑義が生じれば虚偽と確定されなくても、入国審査官の判断で不交付とされる可能性があります。
保有する在留資格の活動を行っていない
たとえ適正な手続きを経て在留資格を取得していても、実際にその資格に基づく活動を行っていない場合は、更新や変更の申請が不許可となる可能性があります。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で企業に雇用されていた外国人が、退職後に長期間就労活動を行わず、在留期限直前に別の会社と契約して更新を申請した場合は不許可と判断されるリスクが高まります。
雇用・労働条件が適正でない
在留資格の審査では、労働条件が法令に適合しているかどうかが重視され、最低賃金を下回る契約や違法な勤務形態では許可を得ることはできません。
さらに、多くの在留資格の審査基準では「日本人と同等額以上の報酬を支払うこと」が求められ、外国人だからといって給与や福利厚生で不合理な差別を設けることは認められていません。
例えば、特定技能1号の在留資格で建設分野に従事する外国人を雇用する場合、日本人従業員が月額25万円の報酬を得ているのであれば、外国人も同額の待遇を受けなければならず、この均等待遇が守られていないと不許可の対象となります。
刑事処分やその他の不法行為などがある場合
在留資格の審査では、申請者の素行が善良であることが基本とされ、過去に重大な刑事処分を受けている場合は不許可の理由となります。
特に、不法就労のあっせんや虚偽の申請など、入管関連の不正行為は厳しく判断されます。
そのため、刑事罰や不法行為の経歴がある場合には、在留資格の変更や更新が認められない可能性が高まり、申請時にはその履歴が慎重に審査されることになります。
納税義務を履行していない
在留資格の審査においては、納税義務を適切に履行しているかが重要な判断要素となり、未納がある場合には不許可の要因となり得ます。
特に、税金の不履行によって刑事処分を受けている場合は、より厳格に評価され、更新や変更の審査に大きな影響を及ぼします。
さらに、国民健康保険料など税という名称が付されていなくても、法令により納付が義務付けられているものを長期間滞納した場合には、税の未納と同様に取り扱われ、不利益な判断につながる可能性があります。
入管法上の届出義務を履行していない
入管法では、住所変更や所属機関の異動、在留カードの記載事項変更などについて、速やかな届出を行うことが義務付けられています。
これらの義務を怠ると在留状況の適正な管理ができなくなるため、更新や変更の申請時にマイナス要因として評価され、不許可につながる場合があります。
不許可後に再申請する場合に行うべき対策
在留資格の申請が不許可となった場合でも、直ちに帰国しなければならないわけではなく、一定の条件を満たせば再申請が可能です。
その際には、前回の不許可理由を正確に把握し、必要な資料や説明を補強することが重要となります。
ここからは、再申請を行う際に意識すべき具体的な対策について解説していきます。
不許可の具体的な理由を突き止める
在留資格の申請が不許可となった場合には、必ず理由が存在し、その内容は不許可通知で簡潔に示されますが、詳細を把握するには地方出入国在留管理局で一度だけ受けられる説明の機会を活用することが重要です。
その際には、漠然と「なぜ不許可なのか」と尋ねるのではなく、どの基準に適合しないと判断されたのか、補足が必要な書類があるのかといった具体的な観点から質問することが望まれます。
さらに、不許可理由を確認したうえで、入管法や上陸許可基準、関連する運用要領を参照し、再申請に必要な修正点を整理して戦略的に準備を進めることが大切です。
理由書などで申請内容を補強する
在留資格の申請では、法令で定められた必要書類を提出すれば形式的に審査は開始されますが、それだけで全ての要件を十分に立証できるとは限りません。
そのため、申請内容を補強する目的で理由書や追加資料を添付し、背景事情や正当性を丁寧に説明することが有効です。
特に経歴や活動計画に懸念がある場合は、隠さず正直に記載し、具体的な事情を説明することで不利な評価を軽減できる可能性があります。
また、所属機関の経営状況や本人の勤務態度など、審査に有利となる要素がある場合には積極的に示すことで、許可の可能性を高めることにつながります。
在留期間に余裕のある申請を心掛ける
在留資格の更新や変更を申請する際は、在留期限ぎりぎりではなく、できる限り余裕をもって行うことが重要です。なぜなら、不許可となった場合に再申請を行うには、在留期間が残っていることが前提となるからです。
仮に審査中に在留期限を迎えた場合は、審査が終了するか期限から2か月が経過するまで在留は認められますが、その結果が不許可となれば在留資格は「特定活動(出国準備)」に切り替わり、30日以内に退去しなければなりません。
そのため、更新や変更の手続きは計画的に進め、万が一不許可の判断を受けても在留期間が残っているうちに再申請できるよう準備しておくことが大切です。
まとめ
本記事では、在留資格の審査において不許可となる典型的な事例や再申請に向けた対応策などについて整理しました。
申請内容と実際の業務の不一致や学歴・経歴の関連性不足、労働条件の不備、納税や届出義務の不履行など、さまざまな要素が審査に影響することを解説しました。
在留資格の申請や更新に不安を感じている方は、まずは自らの状況を客観的に確認し、必要に応じて専門家に相談することが有効です。
早めの準備と適切な情報収集が、不許可を避けるための第一歩になります。次の行動を考える際には、在留期限に余裕を持って申請手続きを進め、改善点を的確に補強することを意識しましょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。