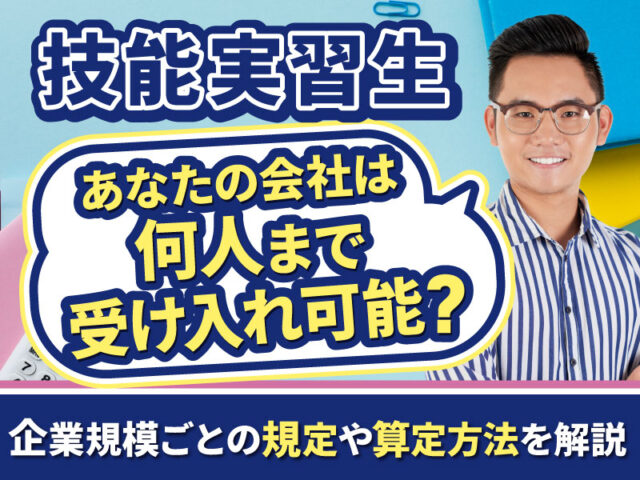「技能実習生の受け入れ人数は?」
「受け入れ人数の算定方法を知りたい」
このような悩みや疑問をお持ちの方もいるでしょう。
技能実習制度では、企業が受け入れられる技能実習生の人数に上限が設けられています。
技能実習生の受け入れ人数は常勤職員数や優良認定の有無などによって異なります。
受け入れ人数の算定方法を把握し、自社で受け入れ可能な技能実習生の人数を確認してください。
本記事では、技能実習生の受け入れ人数枠の計算方法や業種別の特例を解説します。
優良認定による人数枠の変化や、具体的なシミュレーションも紹介しているので参考にしてみてください。
外国人採用の基本で
お悩みの方に
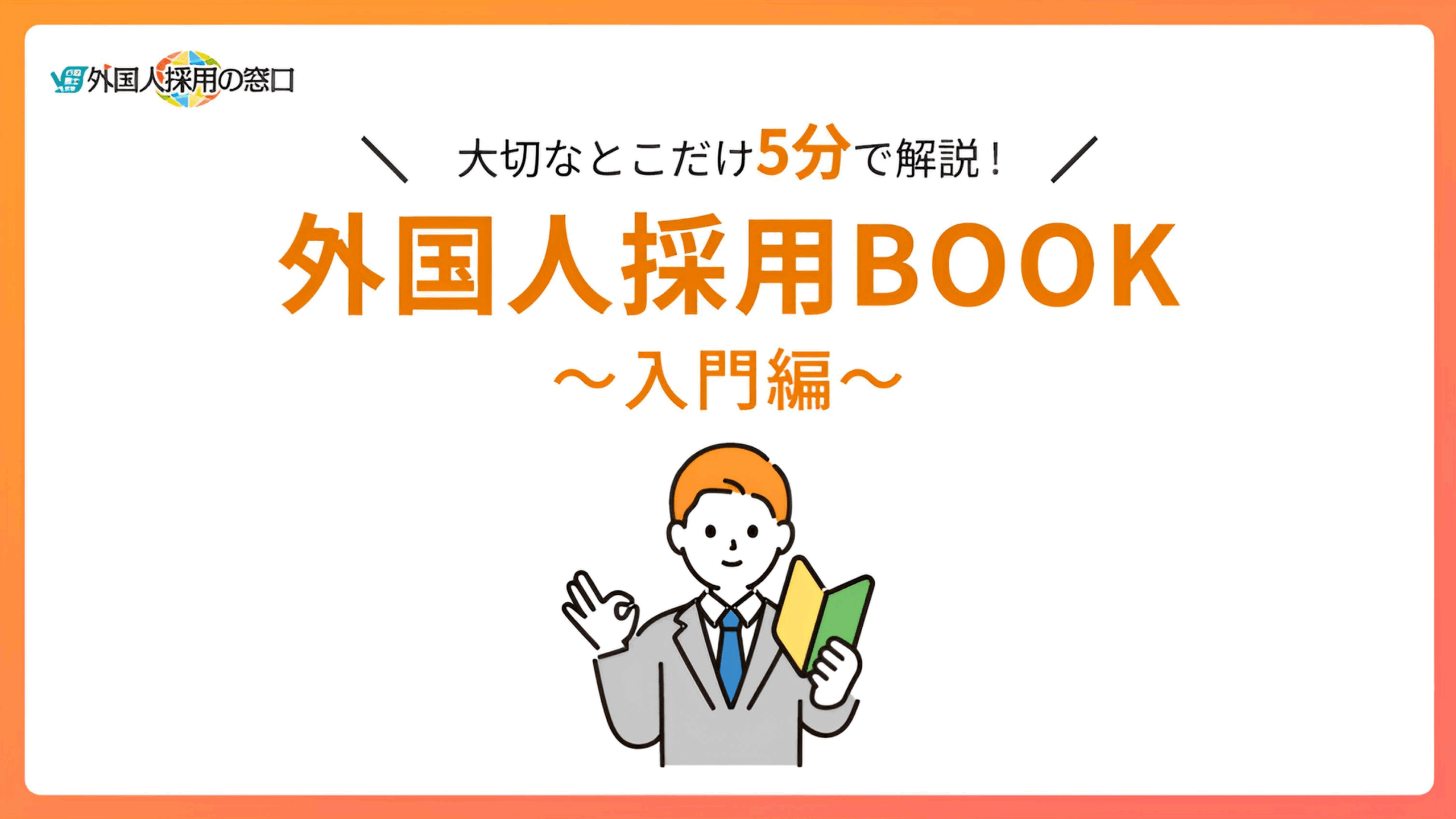
この資料でわかること
- 外国人労働者の現状
- 雇用できる在留資格の確認方法
- 外国人雇用における注意点
- 外国人を受け入れる流れ
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
INDEX
技能実習生の受け入れ人数枠における基本ルール

技能実習制度では、受け入れ人数枠にルールが設定されています。
基本的なルールを紹介します。
- 人数枠の上限は「常勤職員総数」で決まる
- 企業単独型と団体監理型で人数枠は異なる
基本ルールを押さえ、技能実習生の受け入れ準備を進めましょう。
人数枠の上限は「常勤職員総数」で決まる
技能実習生の受け入れ人数枠は、受け入れ企業の常勤職員総数を基準として算定されます。
常勤職員の定義は以下の通りです。
常勤職員の定義
- 所定労働日数が週5日以上かつ年間217日以上で、週所定労働時間が30時間以上の者
- 雇用保険の被保険者で、週所定労働時間が30時間以上の者
技能実習生本人や短時間労働者、海外事業所に所属する職員などは常勤職員に含まれません。
技能実習制度は単なる労働力確保ではなく技術移転を目的とする制度であるため、適切な指導体制を確保する観点から受け入れ人数に上限が設けられています。
企業単独型と団体監理型で人数枠は異なる
技能実習制度の受け入れ形態は、団体監理型と企業単独型の2種類あります。
| 技能実習制度の 受け入れ形態 | 仕組み |
| 団体監理型 | 監理団体が技能実習計画の作成支援や生活指導、実習先への訪問監査などを行い、実習実施者の受け入れを支援する仕組み。 |
| 企業単独型 | 日本企業が自社の海外現地法人や合弁企業などから職員を直接受け入れる仕組み。 |
多くの中小企業が団体監理型を採用しており、監理団体を通して制度運用の適正化が図られています。
受け入れ形態によって人数枠の算定方法が異なるため、自社がどちらに該当するかを確認してください。
多くの監理団体の中から自社に合った団体を見つけるには「外国人採用の窓口」をご利用ください。
弊社は、外国人採用に特化した監理団体を一括で検索できるサービスを無料で提供しています。
無料相談も受け付けておりますので、監理団体選びでお困りの方もお気軽にお問い合わせください。
【早見表あり】技能実習1号2号3号の受け入れ人数枠

技能実習は1号・2号・3号の3段階に分かれており、それぞれ受け入れ人数枠が異なります。
- 技能実習1号の受け入れ人数枠
- 技能実習2号の受け入れ人数枠
- 技能実習3号の受け入れ人数枠
技能実習1号・2号・3号の受け入れ人数枠を把握し、自社で受け入れ可能な実習生の人数の目星を付けましょう。
技能実習1号・2号・3号の違いを以下の記事で紹介しているので、あわせてご覧ください。
また、外国人採用の窓口では「他者に差をつける戦略的外国人採用」の資料を無料配布しております。
30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
戦略的な外国人採用で
他社と差別化したい方へ

この資料でわかること
- 中小企業と外国人採用の相性
- 外国人採用で差をつける方法
- 外国人が持つ在留資格の特徴
- 特定技能外国人の採用戦略
技能実習1号の受け入れ人数枠
技能実習制度における受け入れの基本人数枠は、実習実施者の常勤職員数に基づいて設定されています。
基本人数枠とは、団体監理型における技能実習1号の受け入れ可能枠のことであり、2号や3号に移行した技能実習生の人数はこの枠にはカウントされません。
以下の表は団体監理型で技能実習生を受け入れる際に適用される実習実施者(受け入れ企業)の常勤職員総数別の基本人数枠の一覧です。
| 団体監理型における技能実習1号の基本人数枠 | |
| 実習実施者の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
| 301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
| 201人〜300人 | 15人 |
| 101人〜200人 | 10人 |
| 51人〜100人 | 6人 |
| 41人〜50人 | 5人 |
| 31人〜40人 | 4人 |
| 30人以下 | 3人 |
※特有の事情のある職種(介護職種等)の受け入れ人数は、事業所管大臣が個別に定めます。
※本表は優良認定を受けていない場合の受け入れ人数です。
企業単独型の技能実習の受け入れ人数枠は以下の通りです。
| 企業単独型における技能実習1号の受け入れ人数枠 |
|---|
| 常勤職員総数の20分の1 |
技能実習2号の受け入れ人数枠
技能実習2号の受け入れ人数枠は、技能実習1号の基本人数枠を基に算定されます。
団体監理型の2号受け入れ人数枠は「1号の基本人数枠の2倍」となり、企業単独型の2号受け入れ人数枠は「常勤職員総数の10分の1」です。
常勤職員30人以下の団体監理型の企業では、1号の基本人数枠は3人であるため、2号の受け入れ人数枠は6人です。
受け入れ人数を増やしたい企業は、まずは技能実習2号を目指してください。
技能実習3号の受け入れ人数枠
技能実習3号は、優良認定を受けた場合のみ移行可能です。
優良認定を受けていない場合は3号への移行ができないため、人数枠の設定自体がありません。
優良認定を取得した場合の3号人数枠は団体監理型では基本人数枠の6倍、企業単独型は常勤職員総数の10分の3で、大幅に受け入れ枠が拡大します。
優良認定の要件については次章で詳しく解説します。
優良認定により技能実習生の受け入れ枠が2倍になる

技能実習制度では優良認定を受けると、受け入れ人数枠が拡大します。
- そもそも優良認定とは?
- 優良認定を受けた場合の人数枠
より多くの技能実習生を受け入れたい企業は、優良認定について確認しましょう。
そもそも優良認定とは?
優良認定とは、技能実習の実施状況や実習生への支援体制が一定の基準を満たしていると認められた監理団体・実習実施者に付与される認定です。
複数の評価項目について点数化され、満点(150点)の6割以上(90点以上)を取得することで認定されます。
優良な実習実施者の要件と配点は以下のとおりです。
| 優良な実習実施者の要件と配点 | 詳細 |
| 技能等の修得等に係る実績(70点) | 過去3技能実習事業年度の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率など |
| 技能実習を行わせる体制(10点) | 直近過去3年以内の技能実習指導員、生活指導員の講習受講歴 |
| 技能実習生の待遇(10点) | ・第1号技能実習生の賃金と最低賃金の比較 ・技能実習の各段階の賃金の昇給率 ・技能実習生の住環境の向上に向けた取組 |
| 法令違反・問題の発生状況(5点)※違反等あれば大幅減点 | ・直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合 ・直近過去3年以内に実習実施者に責めのある失踪の有無 |
| 相談・支援体制(45点) | ・母国語で相談できる相談員の確保 ・他の機関で実習継続が困難となった技能実習生の受け入れ実績 ・実習先変更支援サイトへの受け入れ可能人数の登録など |
| 地域社会との共生(10点) | ・技能実習生に対する日本語学習の支援 ・地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供 |
出典:技能実習制度における優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件|厚生労働省
優良な監理団体の要件と配点は以下のとおりです。
| 優良な監理団体の要件と配点 | 詳細 |
| 実習の実施状況の監査その他の業務を行う体制(50点) | ・監理事業に関与する常勤の役職員と実習監理を行う実習実施者の比率 ・監理責任者以外の監査に関与する職員の講習受講歴など |
| 技能等の修得等に係る実績(40点) | 過去3技能実習事業年度の基礎級、3級、2級程度の技能検定等の合格率など |
| 法令違反・問題の発生状況(5点)※違反等あれば大幅減点 | 直近過去3年以内の改善命令の実績、失踪の割合 |
| 相談・支援体制(45点) | ・他の機関で実習が困難となった技能実習生の受け入れに協力する旨の登録を 行っていること ・他の機関で実習継続が困難となった技能実習生の受け入れ実績 ・技能実習生の住環境の向上に向けた取り組みなど |
| 地域社会との共生(10点) | ・実習実施者に対する日本語学習への支援 ・実習実施者が行う地域社会との交流を行う機会・日本文化を学ぶ機会の提供への支援 |
出典:技能実習制度における優良な実習実施者及び監理団体(一般監理事業)の要件|厚生労働省
90点以上を獲得し、優良認定を取得することで、受け入れ人数枠の拡大や3号への移行が可能です。
「外国人採用の窓口」では、優良認定された監理団体も多数登録されています。
希望するエリアの監理団体を検索でき、貴社のニーズを満たした最適なパートナーを見つけることができます。
無料で利用できるので、お気軽にお試しください。
優良認定を受けた場合の人数枠
優良認定を受けることで、受け入れ人数枠の拡大や技能実習3号への移行が可能となります。
以下の表は優良基準適合時の受け入れ人数枠の一覧です。
| 優良基準適合時の人数枠(団体監理型) | |
| 技能実習1号 | 基本人数枠の2倍 |
| 技能実習2号 | 基本人数枠の4倍 |
| 技能実習3号 | 基本人数枠の6倍 |
| 優良基準適合時の人数枠(企業単独型) | |
| 技能実習1号 | 常勤職員総数の10分の1 |
| 技能実習2号 | 常勤職員総数の5分の1 |
| 技能実習3号 | 常勤職員総数の10分の3 |
より多くの技能実習生の受け入れや、技能実習3号の育成を目指す場合は、優良認定の取得が必須条件です。
【業種別】建設業と介護職における人数枠の特例

技能実習制度では、一部の業種において通常とは異なる受け入れ基準が設けられています。
- 建設業の場合
- 介護職の場合
自社の業種が該当する場合は、必ず固有の要件や人数制限を確認しておきましょう。
建設業の場合
建設分野における技能実習の受け入れに際しては、他業種とは異なる制度上の要件が複数設けられています。
具体的には、実習実施者が建設業許可を有していることが前提条件とされており、許可のない事業者による技能実習の実施は認められていません。
また、建設分野では「建設キャリアアップシステム(CCUS)」の登録が義務づけられており、企業および技能実習生の双方がこのシステムに登録していることが受け入れの要件です。
建設キャリアアップシステムの登録により、技能習得の履歴や就労状況を客観的に把握できる体制が整えられ、適正な実習の実施体制が確保される仕組みとなっています。
なお、建設職種の人数制限については、他職種と同様に常勤職員数に基づいた基本人数枠が適用されます。
介護職の場合
介護分野における技能実習は、利用者の安全と福祉の質を確保する観点から、他の職種よりも厳格な制度運用が求められており、受け入れ人数にも特有の制限が存在しています。
特に受け入れ人数の上限については、他の職種と比較して、厳しい制限があります。
例えば、常勤の介護職員が10名の施設では、技能実習1号の実習生は最大で1名までしか受け入れることができず、他の職種の基本人数枠である3名よりも大幅に少ない枠が設定されています。
また、介護職種特有の要件として、日本語能力要件が存在しており、技能実習1号の場合は「N4相当」、2号の場合は「N3」相当の日本語能力が求められます。
| 団体監理型における介護職種の受け入れ人数枠 | ||||
| 事業所の常勤介護職員の総数 | 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
| 1号 | 全体(1号・2号) | 1号 | 全体(1~3号) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 3~10 | 1 | 3 | 2 | 3~10 |
| 11~20 | 2 | 6 | 4 | 11~20 |
| 21~30 | 3 | 9 | 6 | 21~30 |
| 31~40 | 4 | 12 | 8 | 31~40 |
| 41~50 | 5 | 15 | 10 | 41~50 |
| 51~71 | 6 | 18 | 12 | 51~71 |
| 72~100 | 6 | 18 | 12 | 72 |
| 101~119 | 10 | 30 | 20 | 101~119 |
| 120~200 | 10 | 30 | 20 | 120 |
| 201~300 | 15 | 45 | 30 | 180 |
| 301~ | 常勤介護職員の 20分の1 | 常勤介護職員の 20分の3 | 常勤介護職員の 10分の1 | 常勤介護職員の 5分の3 |
| 企業単独型における介護職種の受け入れ人数枠 | |||
| 一般の実習実施者 | 優良な実習実施者 | ||
| 1号 | 全体(1号・2号) | 1号 | 全体(1~3号) |
| 常勤介護職員の 20分の1 | 常勤介護職員の 20分の3 | 常勤介護職員の 10分の1 | 常勤介護職員の 5分の3 |
※法務大臣および厚生労働大臣が継続的で安定的な実習をおこなわせる体制を有すると認める企業単独型技能実習の場合は、団体監理型の人数枠と同じになります。
【シミュレーション】技能実習生の受け入れ人数を実際に計算してみよう

技能実習生の受け入れ人数のシミュレーションを紹介します。
- 常勤職員30人以下のケース
- 優良認定を取得した場合のケース
自社の状況と照らし合わせて参考にしてみてください。
常勤職員30人以下のケース
まずは常勤職員30人以下のケースで受け入れ可能な人数のシミュレーションを紹介します。
常勤職員30人以下のケース
- 常勤職員数:30人以下
- 受け入れ形態:団体監理型
- 優良認定:なし
年ごとの受け入れ人数の推移は以下の通りです。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | |
| 1期生 | 1号3人 | 2号3人 | 2号3人 | 帰国 |
| 2期生 | – | 1号3人 | 2号3人 | 2号3人 |
| 3期生 | – | – | 1号3人 | 2号3人 |
| 4期生 | – | – | – | 1号3人 |
| 受け入れ人数 | 3人 | 6人 | 9人 | 9人 |
1年目に1期生3人を受け入れ、2年目に1期生が2号へ移行すると同時に2期生3人を新規受け入れます。
3年目に3期生を加えて最大9人となりますが、優良認定はないため3号への移行はできず、1期生は3年目終了後に帰国となります。
4年目以降も同様のサイクルを繰り返し、常時最大9人の受け入れが可能です。
優良認定を取得した場合のケース
次に優良認定を取得した場合のケースで受け入れ可能な人数のシミュレーションを紹介します。
優良認定を取得した場合のケース
- 常勤職員数:30人以下
- 受け入れ形態:団体監理型
- 優良認定:あり
年ごとの受け入れ人数の推移は以下の通りです。
| 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | |
| 1期生 | 1号6人 | 2号6人 | 2号6人 | 3号6人 | 3号6人 | 帰国 |
| 2期生 | – | 1号6人 | 2号6人 | 2号6人 | 3号6人 | 3号6人 |
| 3期生 | – | – | 1号6人 | 2号6人 | 2号6人 | 3号6人 |
| 4期生 | – | – | – | 1号6人 | 2号6人 | 2号6人 |
| 5期生 | – | – | – | – | 1号6人 | 2号6人 |
| 6期生 | – | – | – | – | – | 1号6人 |
| 受け入れ人数 | 6人 | 12人 | 18人 | 24人 | 30人 | 30人 |
| 最大受け入れ人数 | 6人 | 18人 | 18人 | 36人 | 36人 | 36人 |
優良認定を取得すると3号へ移行できるため、毎年6人ずつ受け入れられます。
最長5年間在籍でき、最大受け入れ人数は36人です。
優良認定を取得した場合、倍以上の人材を確保できます。
新たな「育成就労制度」で受け入れ人数枠はどう変わる?
技能実習制度は廃止され、新たに育成就労制度が令和9年(2027年)4月1日に施行されます。
育成就労制度・特定技能制度Q&A(Q22)|出入国在留管理庁によると、受け入れ機関ごとの受け入れ人数枠を含む育成・支援体制等の要件については、育成就労制度でも維持される見込みです。
施行後も約3年間は移行期間として技能実習制度と育成就労制度が併存します。
現在、技能実習生を受け入れている企業は最新情報を確認しながら新制度への移行準備を進めてください。
育成就労制度について以下の記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。
【関連記事】
育成就労制度とは|いつから始まる?技能実習との違いや転籍の条件を徹底解説
技能実習生の受け入れ人数を把握したうえで採用しよう
技能実習生の受け入れ人数枠は常勤職員数を基準としつつ、実習の段階や優良認定の有無、業種によって異なります。
自社で受け入れ可能な人数枠を正しく把握し、受け入れ準備を進めてください。
しかし、受け入れ可能人数を正確に把握できているか不安だったり、優良認定の取得に向けた準備がわからなかったりする場合もあるでしょう。
弊社は、外国人採用に特化した行政書士事務所や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
自社だけで外国人の支援が難しいと感じたら、当サービスの条件検索にて、あなたの業種・雇用したい在留資格・国籍に対応した仲介会社を探してみてください。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。