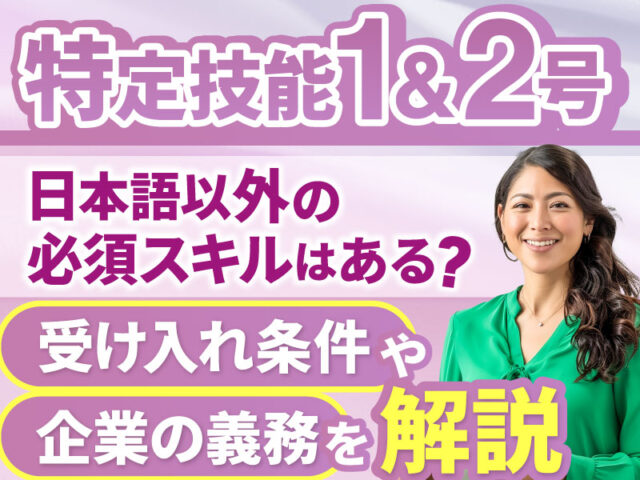「特定技能外国人の受け入れ条件って何があるの?」
「特定技能1号と2号で条件は違うの?」
このような疑問をお持ちの方も多いでしょう。
特定技能外国人になるには、健康状態や年齢といった基本条件に加え、日本語能力と技術力の試験合格が必要です。
特定技能1号では日本語能力試験N4相当以上と各分野の技能試験の合格、特定技能2号は熟練した技能を測る2号評価試験への合格が求められます。
また、受け入れ企業側は、法令の遵守や特定技能の運用要領で定められた条件を満たさなければいけません。
本記事では、特定技能1号・2号の制度概要をはじめ、外国人本人と企業側に求められる受け入れの条件、企業側の支援義務や受け入れの流れについてわかりやすく解説します。
特定技能外国人の
採用を検討したい方へ
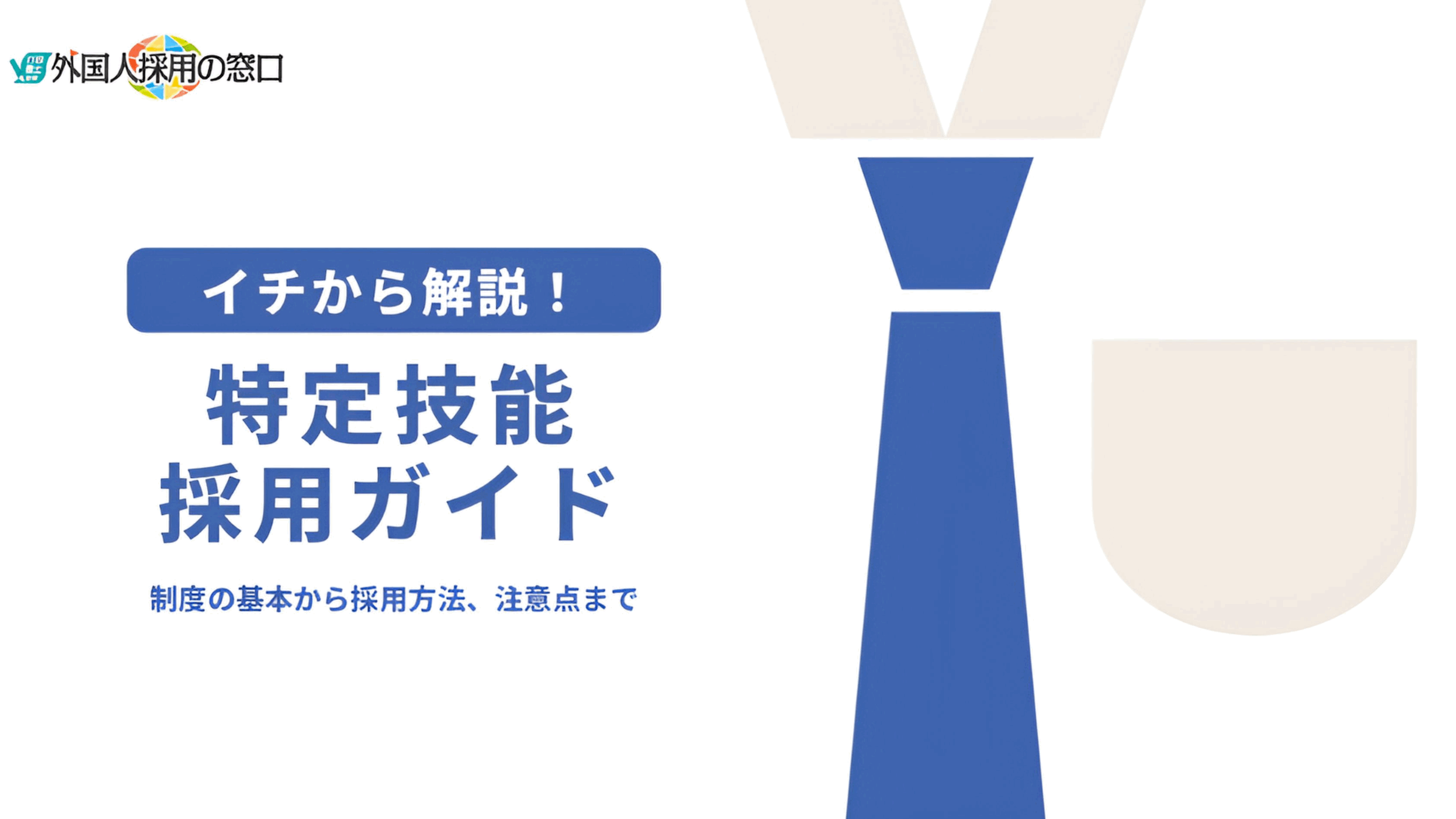
この資料でわかること
- 特定技能制度で従事できる分野
- 在留資格「特定技能1号」の取得条件
- 特定技能1号外国人を雇用する流れ
- 登録支援機関の役割と仕事内容
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
INDEX
【基礎知識】特定技能制度とは

特定技能制度は、日本社会が直面する深刻な人手不足に対応するために創設された制度です。2019年4月の出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)の改正により新設されました。
この制度では、IT化や機械化などの生産性向上や国内人材確保のための取組をおこなっても、人手不足が深刻化する特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人の就労を認めています。
特定技能制度は、産業上の人材確保を目的としている点で、国際貢献を目的とする技能実習制度とは制度趣旨が異なります。
【関連記事】
技能実習と特定技能の違いとは?11のポイントを比較表で徹底解説
特定技能1号と2号の違い
特定技能には1号と2号の2種類があり、それぞれ受け入れ対象や在留期間などに違いがあります。
特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人が対象です。一度に付与される在留期間は最長1年で、通算した在留期間は5年が上限となります。原則として家族の帯同は認められていません。
特定技能2号は、熟練した技能を要する業務に従事する外国人を対象としています。一度に付与される在留期間は最長3年で、在留期間の更新に上限がなく、長期的に日本での就労が可能です。また、配偶者および子の帯同が認められています。
【関連記事】
特定技能2号とは?在留資格取得の条件、受け入れ可能な業種、在留可能な期間などを解説
受け入れ対象の産業分野
特定技能制度は、受け入れられる産業分野があらかじめ定められており、分野ごとに制度運用の方針や試験制度が整備されています。
特定技能1号は、相当程度の知識または経験を必要とする業務に従事する外国人を対象としており、2024年3月に4分野が追加され2025年4月時点で16分野が受け入れ対象です。
特定技能2号は、より熟練した技能を必要とする業務が対象で、現時点で11分野が受け入れ可能とされています。
以下は、出入国在留管理庁が公表している特定技能の受け入れ対象分野の一覧です。※分野の項目をタップすると、各分野の関連記事をご覧いただけます
| 在留資格の種類 | 受け入れ対象分野 |
| 特定技能1号(16分野) | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、自動車運送業、鉄道、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業 |
| 特定技能2号(11分野) | ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業 |
以下の記事では、特定技能の各分野の具体的な業務内容について解説しているので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
特定技能の職種一覧と各産業分野・業務区分の概要、仕事内容について徹底解説 | 外国人採用の窓口
また、外国人採用の窓口では「飲食料品製造業における特定技能外国人の採用」「外食産業における特定技能外国人採用マニュアル」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、どうぞお受け取りください。
特定技能外国人を受け入れる企業に求められる条件

特定技能外国人を受け入れる企業は、特定技能所属機関として所定の基準に適合している必要があります。特定技能外国人を受け入れる企業に求められる条件は以下の7つです。
- 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守する
- 非自発的離職者・失踪者を発生させない
- 欠格事由に該当しない
- 各種帳簿書類を備え付ける
- 保証金の徴収・違約金契約をしない
- 適切な報酬・労働条件を提供する
- 安定した雇用を維持できる
順番に解説します。
なお、特定技能制度で外国人を受け入れる場合には、全ての分野で共通の基準に加え、分野ごとに定められた個別の基準も満たさなくてはなりません。
たとえば建設分野では、受け入れ機関が建設業法に基づく建設業許可を有していることや建設キャリアアップシステムに登録していること、受け入れ人数が常勤職員数を超えないことなどの追加要件が設定されています。
また、介護分野においては、事業所ごとの受け入れ人数の上限が設定されており、日本人等の常勤介護職員の総数を超えないことが条件です。
日本人等には永住者や日本人の配偶者等、在留資格「介護」などで在留する外国人の常勤職員も含まれます。
これらの分野特有の要件は、分野別運用方針で定められています。
労働関係法令・社会保険関係法令を遵守する
特定技能所属機関は、労働関係法令、社会保険関係法令および租税関係法令を適切に遵守していることが必要です。
これらの法令に違反している場合には、特定技能外国人の受け入れが認められない可能性があります。
具体的には、所定の保険制度への未加入や賃金未払い、税務上の義務違反などが確認された場合、所属機関としての信頼性が欠けると判断される場合があります。
そのため、受け入れ機関は日常的に法令遵守の体制を整えておかなければなりません。
非自発的離職者・失踪者を発生させない
特定技能所属機関としての適格性を判断するにあたっては、過去1年以内に非自発的離職者を発生させていないことが要件です。
非自発的離職者とは、本人の責めによらない事由により雇用契約が終了した外国人であり、企業側の都合による解雇や労働環境の不備による離職などが該当します。
また、企業側の責めに帰すべき事由によって行方不明者(いわゆる失踪者)が発生している場合も、受け入れが停止される理由となります。
欠格事由に該当しない
特定技能外国人を受け入れるにあたって、受け入れ機関が法定の欠格事由に該当しないことが求められています。
具体的には、受け入れ機関やその役員が過去5年以内に禁錮以上の刑に処せられた場合や、入管法令・労働関係法令・社会保険関係法令などに違反して罰金以上の刑に処せられた場合などが欠格事由です。
また、虚偽の申請、名義貸し、不当な手数料徴収、労働者の人権侵害など、制度の趣旨に反する不正行為が確認された場合は、たとえ罰金などの刑に処せられていなくても欠格事由に該当すると判断される場合があります。
各種帳簿書類を備え付ける
特定技能所属機関は、受け入れている特定技能外国人に関する帳簿の備え付けが求められています。
帳簿には、以下の事項を記載する必要があります。
帳簿に記載するべき事項
- 氏名
- 国籍
- 在留資格および在留期間
- 従事する業務の内容
- 就業場所
- 雇用開始日
- 報酬額 など
これらの帳簿は、特定技能外国人の活動状況を正確に把握し、制度の適正な運用を確保するために必要なものです。所属機関は、帳簿の整備・保存をおこない、入管庁からの求めに応じて提出できるよう管理することが求められます。
保証金の徴収・違約金契約をしない
特定技能所属機関は、特定技能外国人またはその親族等が以下の事項を認識している場合には、その外国人との間で特定技能雇用契約を締結してはならないとされています。
特定技能雇用契約を締結してはならない場合
- 保証金を徴収されていること
- 財産を管理されていること
- 違約金に関する契約を締結させられていること
これらは、外国人の自由な意思を不当に制限するものであり、制度の趣旨に反する行為です。
受け入れに際しては、こうした状況が存在しないことを確認する責任が所属機関にあります。確認が不十分なまま契約を締結した場合には、適格性が問われる可能性があります。
適切な報酬・労働条件を提供する
特定技能外国人の受け入れでは、入管法令の基準を満たす適切な報酬・労働条件の提供が義務付けられています。
具体的には、以下が守るべき報酬・労働に関する条件です。
業務内容
特定技能制度においては、外国人が従事する業務が、入管法及び関係法令に定められた業務区分に該当していることが必要です。
また、業務内容は、外国人本人が技能評価試験等で技能水準を証明した内容と一致していなければなりません。
所定労働時間
特定技能外国人の労働時間は、当該業務に通常従事する日本人と同等であることが求められており、著しく短い労働時間での雇用は適正とされません。
また、始業および終業の時刻、休憩時間、休日、時間外労働の有無など、労働時間に関する項目を雇用条件書に明示することが必要です。
これらの条件は、労働基準法をはじめとする労働関係法令に適合していなければならず、差別的取扱いは認められていません。
報酬・福利厚生
特定技能雇用契約では、報酬の額が、同種の業務に従事する日本人が受ける報酬と同等以上であることが必要とされています。
比較対象となる日本人が社内に存在しない場合は、賃金規程その他の客観的資料をもとに、職務内容が最も近い日本人と比較して判断されます。
また、教育訓練の機会や福利厚生施設の利用についても、日本人と同様に取り扱うこととされており、不合理な差別的取扱いは認められていません。
【関連記事】
特定技能外国人の給与相場は?報酬の決め方や分野別の平均賃金について詳しく解説
一時帰国のための有給休暇
特定技能外国人から一時帰国の申し出があった場合には、業務上やむを得ない事情があるときを除き、外国人が休暇を取得できるように配慮することが求められています。
この「休暇」には、年次有給休暇のほか、特別休暇(法定外休暇)やその他の有給・無給の休暇も含まれます。
すでに年次有給休暇をすべて取得している場合であっても、受け入れ機関は一時帰国の必要性に応じて、可能な範囲での配慮が必要です。
安定した雇用を維持できる
特定技能の受け入れでは、外国人の安定した雇用・生活を維持できる体制の整備が求められています。
特定技能制度では、外国人の健康状態および生活状況を定期的に把握するための体制を整え、以下の取り組みが必要です。
安定した雇用を維持する取り組み
- 定期的な面談による状況把握
- 雇用時の健康診断・の定期健康診断
- 生活相談窓口の設置
- 帰国時の費用負担に関する準備
外国人本人が契約終了後に帰国する際の旅費を負担できない場合、受け入れ機関側が帰国費用を負担する措置を講じるよう定められています。
また、特定技能外国人の受け入れでは、各分野で設置されている「分野別協議会」への加入が義務となっています。分野別協議会は、受け入れ機関間の情報共有や、制度の適正運用を目的とした組織です。
受け入れ企業が加入する分野別協議会については以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
特定技能の分野別協議会とは?加入の義務や時期、入会費用について解説します | 外国人採用の窓口
ここまで解説してきた、特定技能外国人の受け入れ条件を自社が満たしているかどうかを確認したい方に向けて、外国人採用の窓口では「特定技能外国人の受入れ診断チェック」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下の画像をクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
特定技能外国人を
受け入れるかお悩みの方に
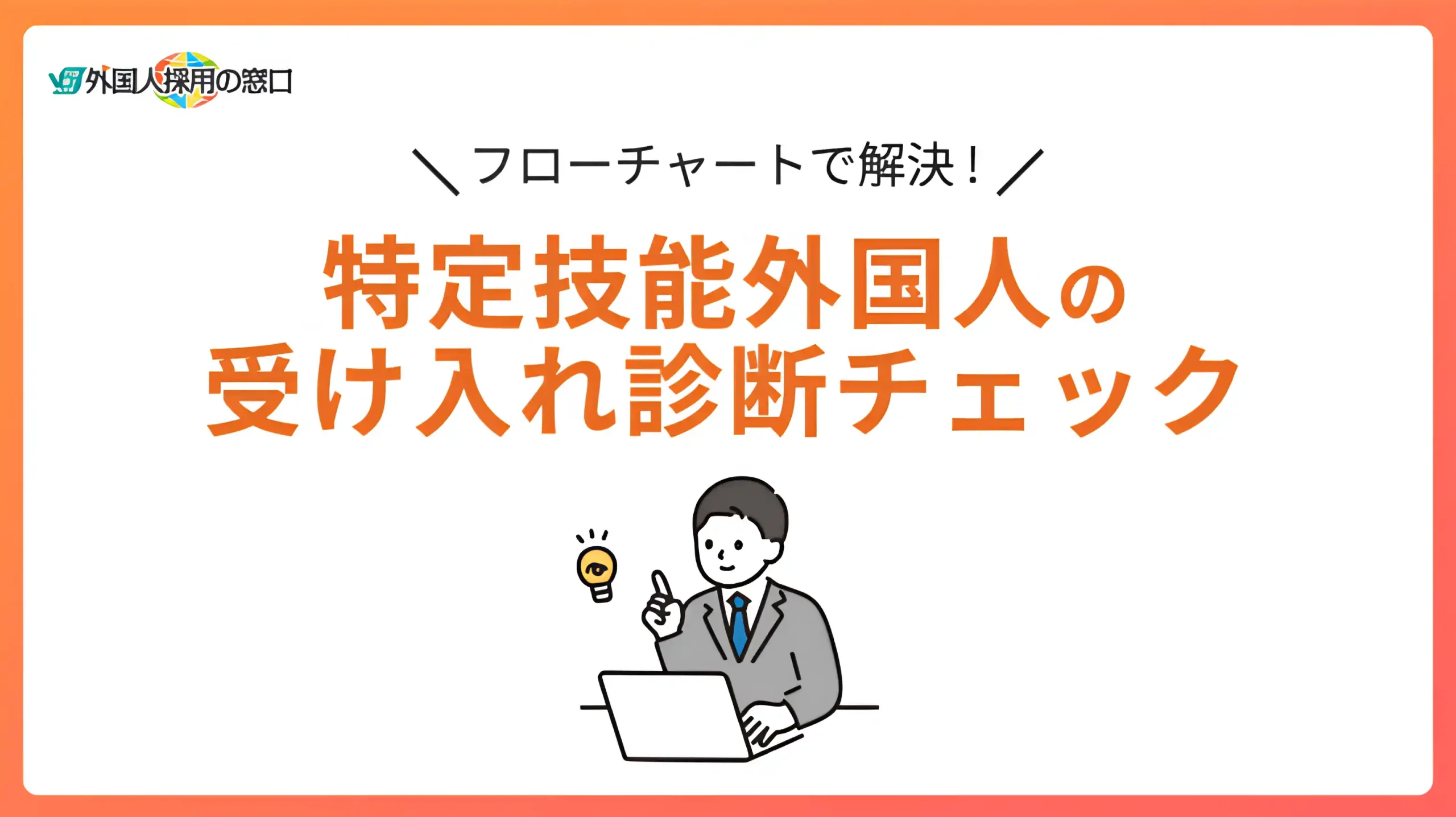
この資料でわかること
- 外国人雇用の簡易診断チャート
- 在留資格「特定技能」の特徴
- 特定技能の対象分野
- 特定技能外国人受け入れの基本条件
特定技能外国人になるための条件

特定技能の在留資格審査では、外国人本人の年齢や健康状態などに加え、技能水準や日本語能力なども審査対象となります。
- 特定技能1号の基準
- 特定技能2号の基準
それぞれ解説します。
特定技能1号の基準
特定技能1号の在留資格を取得するには、外国人本人が入管法令で定められた基準に適合している必要があります。
主な基準として、分野別に定められた技能試験に合格していることや、日本語能力試験N4相当以上(JLPT N4またはJFT-Basic)に合格していることなどが必要です。
ただし、技能実習2号または3号を良好に修了している場合は試験が免除されます。
また、分野により追加の要件が設けられている場合があります。
例えば介護分野では介護日本語評価試験の合格が必要となり、自動車運送業分野のバス・タクシー運転者や、鉄道分野の運輸係員は日本語能力試験N3の合格が求められることとなります。
参考:特定技能「自動車運送業」とは?
特定技能2号の基準
特定技能2号の主な要件は、対象分野別に定められた実務経験の期間を満たすことと、特定技能2号評価試験に合格することです。なお、漁業と外食業においては、日本語能力試験N3の合格が求められます。
特定技能2号の場合は、技能実習の修了などによる試験免除制度はありません。
特定技能1号外国人に対する支援の義務

特定技能1号の外国人を受け入れる場合、入管法に基づく支援の実施は受け入れ機関が果たすべき義務です。
特定技能外国人への支援は、以下の2つに分けられます。
- 義務的支援
- 任意的支援
それぞれの支援内容を詳しく見ていきましょう。
義務的支援10項目の内容
特定技能1号の外国人を受け入れるにあたって、受け入れ機関または登録支援機関は、入管法令上定められた10項目の義務的支援を適切に実施する必要があります。
義務的支援10項目は、以下の通りです。
特定技能1号外国人に対する義務的支援
①事前ガイダンスの実施
②入国・帰国時の送迎
③住居の確保や生活に必要な契約支援
④生活オリエンテーションの実施
⑤公的手続等への同行
⑥日本語学習の機会の提供
⑦相談・苦情への対応
⑧日本人との交流促進支援
⑨転職時の支援(人員整理等の場合)
⑩定期的な面談と行政機関への報告
以下の記事では、義務的支援の一つ「生活オリエンテーションの実施」の具体的内容について解説しています。自社で対応できるかどうかを見極めたい方はあわせてご覧ください。
【関連記事】
特定技能の「生活オリエンテーション」を解説!実施内容・時間・注意点など【事例付き】 | 外国人採用の窓口
任意的支援の内容
任意的支援とは、法令上実施が義務付けられていないものの、受け入れ機関または登録支援機関がおこなう自主的な支援を指します。
これは、特定技能1号の外国人がより安定して日本での生活・就労を継続できるようにする目的で、任意に追加実施される支援措置です。
任意的支援は、制度上の義務ではありませんが、適切に実施されることで外国人の生活支援の充実が図られ、共生社会の形成にも資するものとされています。
外国人採用の窓口では「特定技能外国人の受入れ後のサポート体制」がわかる資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人採用後の
サポート体制を整えたい方へ
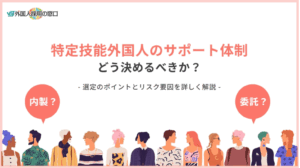
この資料でわかること
- 義務的支援の内容
- 自社対応と外部委託の選択肢
- 登録支援機関の委託状況
- 支援業務における注意点
特定技能1号は登録支援機関への委託可能

特定技能1号外国人を受け入れる企業には、法令で定められた10項目の義務的支援の実施が求められます。義務的支援は登録支援機関への委託が可能です。
義務的支援とは企業からの委託を受けて、特定技能1号を外国人の就労をサポートする専門機関です。
義務的支援を自社でおこなう場合、担当者の確保や専門知識の習得が必要です。一方、登録支援機関へ委託する場合、企業は業務に集中しながら適切な支援体制の構築ができます。
登録支援機関の詳しい業務内容や選び方については、以下の記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説
登録支援機関の選び方|7つのチェック項目と選定を成功させるコツ
また、外国人雇用の支援に強い登録支援機関をお探しの際は「外国人採用の窓口」をご利用ください。あなたが雇用したい国籍、業界、職種の特定技能外国人の支援に強い登録支援機関をご紹介します。
無料相談も受け付けておりますので、外国人雇用に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
特定技能外国人を受け入れる流れ
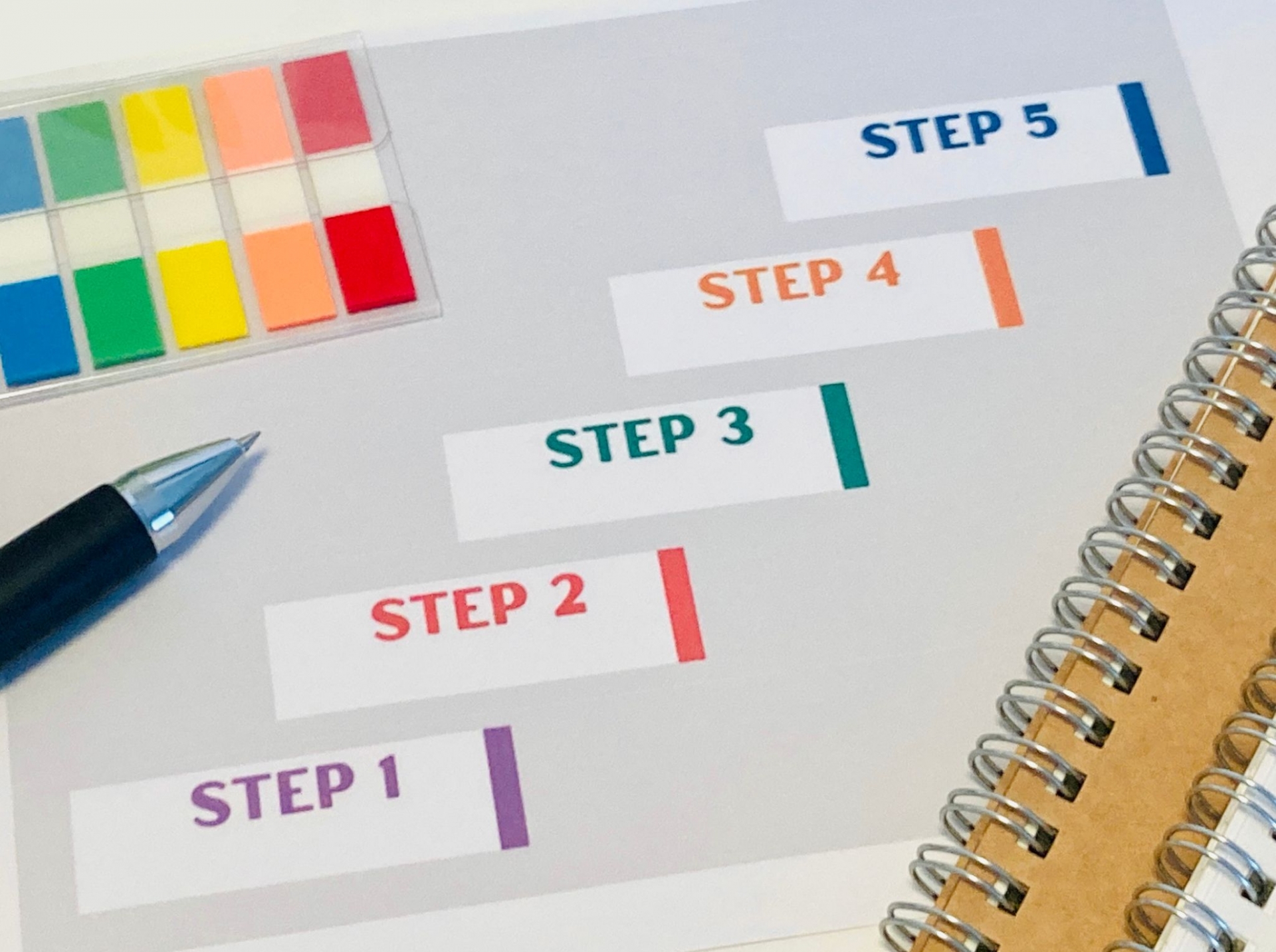
特定技能外国人を受け入れる際は、以下の5つのステップで進めます。
- 人材の募集・選考
- 雇用契約の締結
- 支援計画の作成
- 在留資格申請の手続き
- 正式入社・入社後の継続的な支援
詳しく見ていきましょう。
人材の募集・選考
特定技能外国人の募集には、以下の方法があります。
| 募集方法 | 内容 |
| 直接募集 | ・求人サイトへの掲載 ・学校への求人票提出 ・自社サイト・SNSなど |
| 職業紹介機関の活用 | ・外国人専門の人材紹介会社 ・ハローワーク |
選考時は、保有している在留資格の種類と有効期限を必ず確認してください。また、技能試験と日本語試験の合格証明書の提出を求め、自社の業務に必要なスキルレベルを満たしているかを判断します。
面接時には、採用後のミスマッチを防ぎたい方に向けて「特定技能外国人の面接で使える質問集」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、どうぞお受け取りください。
特定技能外国人の募集・選考を効率的に進めたい場合には、外国人専門の人材紹介会社の活用がおすすめです。「外国人採用の窓口」では、無料で外国人紹介会社の一覧を検索でき、雇用したい国籍、業界、職種、在留資格の就労支援に強い会社をご紹介します。
無料相談も受け付けておりますので、特定技能外国人の受け入れにお困りの方もお気軽にお問い合わせください。
雇用契約の締結
特定技能外国人を受け入れる際の契約では、「特定技能雇用契約及び特定技能外国人支援計画の基準などを定める省令」の第一条で以下のように明確に定められており、法令に基づき雇用契約書を作成します。
特定技能の雇用契約に関する条件
- ある程度の知識や経験が必要な仕事に就労すること
- 労働時間は、その会社で働く日本人と同等であること
- 給料は、同じ仕事をする日本人の給料と同等もしくは多く支給すること
- 外国人であることを理由にした差別をしないこと
- 外国人が母国に一時帰国する場合に、必要な有給休暇を取得させること
- 他社に派遣して働かせる場合は、派遣先の会社名・住所・派遣期間を事前に決めること
- それぞれ業界特有の追加ルールを守ること
外国人労働者を日本人と同じように公平に扱い、外国人が理解できる言語で作成します。契約内容について十分に説明し、双方が納得した上で「特定技能雇用契約書」の締結が必要です。
外国人が十分に理解できなければ、通訳・翻訳の準備が必要になる場合もあります。以下の記事で通訳・翻訳の規定や必要になる場面について解説していますので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
特定技能外国人の雇用で通訳・翻訳は必須?必要な場面や依頼方法を解説
支援計画の作成
特定技能1号外国人を受け入れる場合、10項目の義務的支援を含む支援計画書の作成が必要です。
支援計画は自社で実施するか、登録支援機関への委託が可能です。2023年3月末の時点では84.4%の企業が登録支援機関への委託を選択しています。
参考:特定技能制度の現状について|出入国在留管理庁
在留資格申請の手続き
在留資格の申請方法は、外国人の状況に応じて以下のように手続きが異なります。
| 状況 | 申請書類 |
| 日本国内在住者の場合 | 在留資格変更許可申請書 |
| 海外から入国の場合 | 在留資格認定証明書交付申請書 |
参考:特定技能関係の申請・届出様式一覧 | 出入国在留管理庁
管轄の地方出入国在留管理局にて申請後は審査がおこなわれ、許可されれば新しい在留カードが交付されます。
詳しい手続き方法については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
在留資格申請を自社で行うための基礎知識やメリット・デメリットについて解説 | 外国人採用の窓口
在留資格申請の手続きは雇用契約書、雇用条件書、本人・企業に関する書類に加え、納税証明書や社会保険関係書類など多数の書類があります。
法的知識も必要なため、自社での対応に不安がある…という方は専門知識を持った行政書士に依頼することも可能です。
行政書士は、公的手続きの専門家です。外国人雇用の行政手続きに詳しい行政書士に任せれば、自社の負担を軽くできます。「外国人採用の窓口」では、外国人雇用に精通した信頼できる行政書士事務所を無料で検索できます。
正式入社・入社後の継続的な支援
在留資格が許可されたら、正式に入社となります。入社後も、特定技能外国人への以下のような継続的な支援業務が必要です。
継続的な支援業務
- 定期面談の実施(3ヵ月に1回以上)
- 生活相談への対応
- 日本語学習の継続支援
- 職場環境の改善
- 日本人との交流促進
- 相談・苦情への対応
また、受け入れ機関には出入国在留管理庁への各種届出義務があります。
義務付けられている届出
- 定期届出:年1回(支援実施状況、活動状況など)
- 随時届出:雇用契約変更時、支援計画変更時など
これらの継続的な支援業務を自社での対応が困難な場合は、登録支援機関への委託もできます。
しかし数多く存在する登録支援機関の中から気になる機関を探し出すのは大変です。自社の条件に合った登録支援機関をお探しの際は「外国人採用の窓口」をご利用ください。
ご希望のエリアや雇用したい国籍・在留資格などの条件で検索し、最適な機関をご紹介できます。完全無料のサービスなのでお気軽にお試しください。
特定技能外国人の雇用をご検討中なら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「特定技能外国人を採用したいけれど、何から始めれば良いかわからない」
「信頼できる支援機関や行政書士を見つけたい」
「在留資格の変更手続きは専門家に委託したい…」
このようなお悩みをお持ちなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した登録支援機関や人材紹介会社、行政書士事務所を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
条件検索により、あなたの業界・業種に精通した特定技能の就労支援に強いパートナー企業とのマッチングをお手伝いします。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けているので、特定技能に関するお悩みがある方もお気軽にお問い合わせください。
特定技能の条件に関するよくある質問

最後に特定技能の条件に関するよくある質問をまとめます。
特定技能の受け入れにかかる費用はどのくらいですか?
特定技能外国人の受け入れには、在留資格の申請費用、登録支援機関への委託料、人材紹介料などさまざまな費用が発生します。
初期費用として30万円〜150万円程度、月額の支援費用として3万円〜5万円程度が一般的な相場です。
国内での採用か、現地採用かによっても総額は変わります。詳細な費用項目と相場については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
【関連記事】
『特定技能外国人』の受け入れ費用、登録支援機関の料金相場を解説【費用項目一覧表あり】
特定技能外国人は転職できますか?
特定技能外国人は技能実習とは異なり、以下のような場合に転職の自由が認められています。
転職できる場合
- 同一の業務区分内
- 試験により技能水準の共通性が確認されている業務区分
転職時に、受け入れ機関や業務分野が変わる場合には、出入国在留管理庁での手続きが必要です。また、転職先の企業も受け入れ基準を満たしている必要があります。
転職に関する具体的なルールや手続き、企業が注意すべきポイントについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
特定技能外国人は『転職』できる!企業が知っておくべきルール・手続き・注意点【事例付き】
技能実習から特定技能1号に移行する時の条件はありますか?
技能実習2号または3号を良好に修了した外国人は、以下の条件を満たせば技能試験と日本語試験が免除され、特定技能1号への移行が可能です。
技能実習から特定技能1号に移行する時の条件
- 技能実習と特定技能での対象分野が一致している
- 移行時に在留資格変更の許可申請をする
- 新たな受け入れ機関との雇用契約を締結する
技能実習と特定技能の詳細な違いや移行条件については、以下の関連記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
技能実習と特定技能の違いとは?11のポイントを比較表で徹底解説
在留資格変更許可申請には法的な知識と正確な書類作成が不可欠です。申請の不備や条件の見落としがあると不許可になるリスクがあります。
【関連記事】
在留資格申請を自社で行うための基礎知識やメリット・デメリットについて解説 | 外国人採用の窓口
在留資格の審査が不許可になる原因と再申請時の対策について具体的な事例をもとに解説します | 外国人採用の窓口
在留資格の手続きを不備なくスムーズに進めたい場合は、外国人雇用に特化した行政書士への相談がおすすめです。
数ある行政書士事務所の中でどの事務所に依頼すれば良いのか迷ったら「外国人採用の窓口」をご利用ください。無料であなたの地域や条件に合う事務所を検索できます。
特定技能外国人を受け入れる条件を理解してスムーズに雇用しよう!

特定技能外国人の受け入れには、外国人本人と受け入れ企業の両方に条件が設けられています。
外国人側では、技能試験と日本語試験の合格、年齢や健康状態の基準を満たすことが必要です。特定技能1号は相当程度の技能レベル、特定技能2号はより熟練した技能が求められます。
企業側では、適切な労働条件の提供、安定した雇用の維持、支援体制の整備が義務付けられています。日本人と同等以上の報酬設定や、分野別協議会への加入なども必要な条件です。
特定技能制度は人手不足の解消を目的とした制度であり、適切に活用すれば企業の成長につながる重要な人材確保手段となります。一方で、在留資格の申請手続きや支援業務には専門的な知識が必要です。
義務的支援や在留資格の手続きなど、自社での対応が困難な場合は、登録支援機関への委託や行政書士への相談を検討しましょう。
弊社では、外国人向けの人材紹介会社や登録支援機関、監理団体、行政書士事務所を一括検索できるサービスを提供しています。無料で利用できるので、信頼できるパートナーをお探しの方は、お気軽にご活用ください。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。