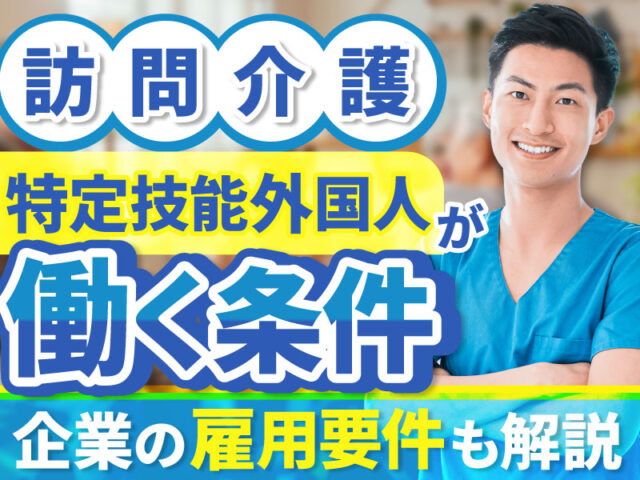2025年4月から、訪問介護分野でも特定技能外国人の受け入れが認められるようになりました。
ただし、訪問介護は利用者の自宅でサービスを提供するという性質上、安全性や信頼性を確保するための複雑な許可要件が定められています。
本記事では、特定技能「介護」の在留資格で訪問介護に従事する際の受け入れ対象施設やサービスの範囲、基本的な取得要件、訪問介護特有の追加要件、そして企業が行うべき手続きの流れについて、わかりやすく解説します。
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
2025年4月から特定技能の訪問介護が解禁
介護分野の特定技能制度は、施設系介護事業所などの身体介護を中心に人手不足の現場を支えてきましたが、2025年4月から新たに訪問介護でも受け入れが解禁されました。
訪問介護とは、利用者の自宅に職員が赴き、食事や入浴、排せつなど日常生活の支援を行うサービスであり、高齢化が進む社会では欠かせない役割を担っています。
一方で、訪問介護は施設型サービスとは異なり、介護職員が単独で利用者宅を訪れるため、より高度な判断力や緊急時対応の知識が求められます。
このため、制度上も受け入れ事業所や従事者に対し、研修・同行支援・安全体制の整備など、施設介護よりも複雑な要件が設けられています。
今回の制度改正により、一定の条件を満たす特定技能外国人が訪問系サービスで活躍できるようになり、在宅介護の担い手拡大が期待されています。
受け入れ対象の施設・事業所
特定技能外国人が新たに従事できるようになった訪問系サービスは、「児童福祉法」「障害者総合支援法」「老人福祉法・介護保険法」に基づいて運営される施設・事業所の業務です。
ここからは、受け入れ対象となる施設・事業所について解説します。
児童福祉法関係
児童福祉法に基づく施設・事業所のうち、新たに特定技能外国人の受け入れが認められることとなった訪問系サービスは「居宅訪問型児童発達支援」です。
この事業は、障害のある子どもの自宅を訪問し、日常生活の支援や発達促進を目的とした指導を行うサービスです。
特定技能外国人がこの業務に従事するためには「障害児に対して入浴、排せつ、食事などの介助を行い、あわせてその介護を担う家族等に対して介護方法の助言を行う業務に3年以上従事した経験」が必要です。
障害者総合支援法関係
障害者総合支援法に基づく事業のうち、特定技能外国人が新たに従事できるようになった訪問系サービスは以下の通りです。
|
障害者総合支援法関係の訪問系サービス |
|
これらの事業では、「従事するサービスごとに必要となる研修課程を修了していること」が受け入れの要件とされています。
訪問入浴サービスの固有要件
訪問入浴サービスでは、複数の職員によるチーム体制でサービスを提供することを前提に、特定技能の外国人介護人材の就労が認められています。
また、受け入れ事業者は、現場で必要となる入浴介助や衛生対応に関する研修を実施し、適切な指導体制を整備しなければなりません。
老人福祉法・介護保険法関係
老人福祉法および介護保険法に基づく施設・事業所のなかで、特定技能外国人が新たに従事できることとなった訪問系介護サービスは次の通りです。
|
老人福祉法・介護保険法関係の訪問系サービス |
|
これらのうち、特定技能外国人が訪問入浴介護または介護予防訪問入浴介護の業務に従事する場合は、介護職員初任者研修課程の修了が必須ではありません。
そのため、受け入れ事業者は、適切な指導体制を整備するとともに、現場で必要となる入浴や介助に関する研修を実施することが求められています。
特定技能「介護」の許可要件
特定技能「介護」の受け入れにあたっては、訪問系サービスに限らず、施設系サービスや居住支援系サービスなど、すべての施設・事業所に共通する許可要件があります。
ここでは、特定技能「介護」における基本的な許可要件について解説します。
介護技能評価試験に合格する
特定技能「介護」で就労するには、介護技能評価試験に合格する必要があります。
この試験は、介護の基本知識や介助技術を確認するもので、身体介護・生活支援・安全衛生など実務に直結する内容が問われます。
合格者は、介護現場で即戦力として働ける一定の技能水準を有しているものとして認められます。
JLPTまたはJFT-Basicに合格する
特定技能「介護」の許可を取得するためには、一定水準の日本語能力を証明することが求められます。
具体的には、日本語能力試験(JLPT)でN4以上に合格するか、もしくは国際交流基金が実施するJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)に合格する必要があります。
JLPTは読解・聴解を中心に、日常会話に必要な日本語理解力を測る試験で、N4は「基本的な日本語を理解できる」レベルに相当します。
一方、JFT-Basicは外国人労働者向けに設計され、会話や日常生活に必要な日本語運用力を確認することを目的としています。
どちらの試験も、介護現場で利用者や職員との円滑なコミュニケーションを行うために重要な基礎力を示すものです。
介護日本語評価試験に合格する
介護日本語評価試験は、特定技能「介護」で働く外国人が介護現場で必要とされる日本語運用能力を確認するための試験です。
試験では、介護現場で発生する具体的な場面を想定した日本語理解力が求められます。単に文法知識を問うものではなく、現場で安全に業務を遂行するための実践的な日本語力を確認する内容となっています。
この試験に合格することで、介護現場で働く上での日本語能力の証明となり、特定技能「介護」の在留資格取得要件の一つを満たすことができます。
技能実習2号修了者は試験免除される
介護職種・作業の技能実習2号を良好に修了した外国人は、「介護技能評価試験」「介護日本語評価試験」「JLPT(N4以上)またはJFT-Basic」のすべてが免除され、追加試験を受けずに特定技能「介護」へ移行することが認められています。
介護以外の職種で技能実習2号を修了した場合は、介護技能評価試験などの受験が必要ですが、日本語試験(JLPTまたはJFT-Basic)のみ免除される扱いとなっています。
特定技能で訪問介護に従事するための追加要件
特定技能「介護」で訪問介護に従事する場合は、通常の特定技能の許可要件に加えて、訪問系サービスに特有の追加要件を満たす必要があります。
ここからは、訪問系介護サービスで特定技能外国人を受け入れるための固有要件について順を追って解説します。
介護職員初任者研修課程などを修了していること
特定技能「介護」で訪問介護に従事する場合は、日本人職員と同様に、介護職員初任者研修課程を修了していることが条件となります。
なお、初任者研修には特別な受講資格がなく、年齢・学歴・国籍を問わず誰でも受講することができます。
必要な知識及び技能を習得させる講習を行うこと
訪問介護は利用者の居宅で一対一の支援を行うため、特定技能外国人には高度な専門知識と実践的な技能が求められます。
そのため、受け入れ事業所は、外国人介護人材が円滑に業務を行えるよう、訪問介護に特化した講習を実施しなければなりません。
講習の内容は、訪問系サービスの基礎事項に加え、生活支援技術や利用者・家族・地域住民との適切なコミュニケーション方法などを含むこととされています。また、日本の生活習慣、緊急時対応などについても講習に取り入れることが求められています。
一定期間の同行など必要なOJTを行うこと
訪問介護の現場では、特定技能外国人が単独で適切にサービスを提供できるようになるまで、一定期間のOJT研修が必要とされています。
その際、サービス提供責任者などの経験者が同行し、実際の支援を通じて指導・確認を行う体制を整える必要があります。
同行の回数や期間は、利用者の状態や外国人職員の習熟度に応じて柔軟に判断することとされています。無理なく段階的にOJTを実施することで、安全かつ質の高い介護サービスの提供が可能になります。
キャリアアップ計画を作成すること
特定技能外国人を受け入れする事業所は、外国人介護職員が訪問系サービスを行う際に、業務内容や注意事項について丁寧に説明し、本人の意向を確認したうえでキャリア形成を支援する体制を整える必要があります。
この際、外国人職員が将来どのような専門職を目指すかを踏まえ、従事する業務内容や目標、事業所が提供する研修・指導の内容を明確にしたキャリアアップ計画を作成することが求められます。
作成した計画は、巡回訪問等を行う実施機関に提出し、継続的な育成・評価の仕組みとして活用していくことが求められます。
ハラスメント防止のための措置を講ずること
訪問介護事業所は、外国人職員が安心して働ける環境を整えるため、ハラスメント防止に関する具体的な措置を講じる必要があります。
事前対策として、対応マニュアルの整備や管理者の役割明確化、ハラスメント発生時の対応ルールの作成・共有を行い、利用者や家族にも周知することが求められます。
加えて、ハラスメントが発生した際には、定められたルールに基づいて迅速に対応し、外国人職員が安心して相談できる窓口を設けるとともに、その存在を十分に知らせることが重要です。
緊急時の連絡体制の整備を行うこと
訪問介護に従事する特定技能外国人が安心して業務を行えるよう、事業所は緊急時の体制を整備することが求められます。
緊急連絡先や対応手順を明記したマニュアルを作成し、万が一の際に他の職員が速やかに駆けつけられる体制を確保することが重要です。
加えて、サービス提供記録や申し送り内容を職員間で共有できる仕組みを整える必要があります。コミュニケーションアプリの導入やICTの活用により、介護現場や日常生活での困りごとを気軽に相談できる環境づくりが効果的です。
1年以上の実務経験があること
訪問介護で特定技能外国人が業務に従事するためには、一定の実務経験を有していることが求められます。
具体的には、介護事業所などで原則として1年以上の経験を積んでいることが条件とされており、これはサービスの質を確保し、緊急時にも的確に対応できるようにするための基準として設けられています。
実務経験なしで訪問介護に従事する要件
特定技能外国人であっても、一定の条件を満たせば実務経験がなくても訪問介護に従事することが可能です。
その条件は「日本語能力試験N2相当の日本語力を有すること」と「同行訪問を一定期間行うこと」の2点です。
同行期間は、週1回のサービス提供の場合は6か月間とされています。
この同行訪問期間は、利用者や家族から同意を得たうえで、サービス提供時に見守りカメラなどICT機器を活用して常時事業所と連携できる体制を整えれば、3か月間に短縮することも可能です。
また、週2回のサービス提供では3か月、週3回以上の場合は2か月の同行が必要とされており、それ以上のサービス提供頻度の場合も最短でも2か月間の同行訪問を行うことが義務付けられています。
利用者や家族からの同意を得ること
訪問介護において1号特定技能外国人が利用者の居宅に訪問する場合、事業所は事前に利用者やその家族へ必要な説明を行い、書面で同意を得ることが求められます。
説明内容には、外国人職員が訪問する可能性があることや、その職員の実務経験などの概要を含める必要があります。
また、ICT機器を使用して介護業務を行う場合がある旨を伝えるとともに、不安や懸念が生じた際に利用者または家族が連絡できる事業所の連絡先を伝えます。
これらの説明を文書で交付し、署名を得ることで、利用者側の理解と安心を確保することが求められます。
企業側が行う受け入れの手続き
訪問介護分野で特定技能の外国人を受け入れる場合、事業所には通常の雇用手続きに加えて、入管法や訪問介護特有の基準に基づく各種手続きが求められます。
ここからは、受け入れ企業が行う手続きを順に解説します。
特定技能協議会への加入
介護分野で特定技能外国人を受け入れる事業者は、「介護分野における特定技能協議会」への加入が義務付けられています。
入会手続きは協議会申請システムを通じて行い、事務局による確認後、通常2週間程度で入会証明書が発行されます。入会費や年会費などの費用は発生しません。
適合確認申請
訪問系介護サービスに特定技能外国人を従事させる場合、受け入れ機関は事前に「介護分野における特定技能協議会」から適合確認書の交付を受ける必要があります。
協議会による審査を経て、外国人ごとに「特定技能外国人の訪問系サービスへの従事にかかる適合確認書」が発行され、この書面が訪問介護に従事する要件を満たしていることの適合性を証明する書類として扱われます。
在留資格申請
特定技能協議会から入会証明書と適合確認書の発行を受けた後、受け入れ機関または外国人本人は、地方出入国在留管理局に在留資格申請を行います。
審査には通常1〜3カ月程度を要し、許可が下りた時点で特定技能外国人は訪問介護業務に従事できるようになります。
巡回訪問への対応
訪問系サービスに特定技能外国人を従事させる事業所では、巡回訪問等実施機関による巡回確認が行われます。
この確認では、適正な受け入れ体制や遵守事項が適切に整備されているかを確認されます。
事業所は、事前質問票など必要な書類を提出し、法令遵守状況を説明するなどの協力を行うことが求められます。
定期報告
特定技能外国人が訪問系サービスの就労を開始してから1年が経過した時点で、受け入れ事業所は介護分野における特定技能協議会へ定期報告を行う必要があります。
また、特定技能外国人を雇用する全ての事業者は、毎年4月1日から5月末までの間に、地方出入国在留管理局へ定期届出を提出しなければなりません。
まとめ
訪問介護で特定技能外国人を受け入れるには、試験合格や実務経験に加え、講習・OJTの実施、キャリアアップ計画の策定など多くの要件を満たす必要があります。
また、利用者や家族の同意の取得、緊急時対応体制の整備、ハラスメント防止策など、現場での支援体制を整えることも不可欠です。
特定技能制度を活用することで人材確保の選択肢は広がりますが、手続きや要件は複雑です。訪問介護事業者が受け入れを検討する際は、制度の流れを正確に把握し、申請準備から受け入れ後の支援体制まで計画的に進めることが重要です。
手続きに不安がある場合は、制度に詳しい専門機関へ早めに相談するとよいでしょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。