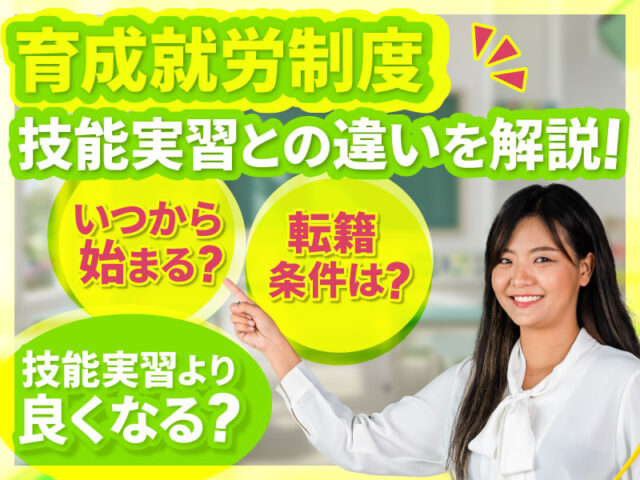報道などで「技能実習」が廃止されるというニュースを目にした方も多いでしょう。
しかし、新たに創設される育成就労制度の詳細については、あまり報道で見かける機会は多くありません。
この記事では、技能実習廃止後の新制度である「育成就労」の詳細や開始時期、技能実習との違い、転籍の条件、特定技能への移行要件などを詳しく解説します。
なお、育成就労制度については、今のところ政省令が定められておらず未確定な部分も多いため、「有識者会議」や「関係閣僚会議」などの法案作成に関係する議事録の内容をもとに解説しています。
INDEX
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
育成就労制度とは
育成就労制度とは、育成就労産業分野において「特定技能1号水準の人材の育成」と「育成就労産業分野の人材確保」を目的として、日本国外から外国人労働者を受け入れる制度です。
令和5年11月30日に法務大臣に提出された「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」の最終報告書で、「現行の技能実習制度を発展的に解消し、人材確保と人材育成を目的とする新たな制度を創設することが望ましい」と提言されたことがきっかけで、この制度が創設されることとなりました。
育成就労産業分野とは
育成就労産業分野とは、育成就労制度を利用して外国人を受け入れることが可能な産業分野のことです。2025年2月現在、育成就労産業分野の詳細な枠組みは確定していませんが、特定技能制度の特定産業分野と原則一致させると公表されています。
現行の技能実習(2号)の職種・作業は、全体のうち30%(27職種47作業)が特定技能の特定産業分野と一致していません。
そのため、これらの職種・作業の区分は、育成就労制度移行後には廃止される可能性がありますが、職種・作業ごとの人材確保や人材育成の機能や必要性などを考慮し、今後特定産業分野への追加が検討されることになっています。
また、国内での育成になじまない分野は育成就労の対象外とする方向で検討されています。
「外食」など現行の技能実習制度では受け入れが認められていない分野は、たとえ特定技能の特定産業分野に該当していても、育成就労制度の受け入れ対象とはならない可能性があるため注意が必要です。
いつから施行されるのか
育成就労制度は、令和9年(2027年)6月20日までに施行される予定です。
育成就労制度がスタートしてから一定期間は、技能実習制度と並行して運用されることとなり、2030年を目処に完全に移行する予定です。
技能実習制度はなぜ廃止されるのか
技能実習制度は、「人材育成を通じた国際貢献」を目的に平成5年に創設されました。
数々の制度改正を経て現在に至りますが、実態としては「人材確保」のための手段として利用されてきた側面があり、創設当初に掲げた基本理念とのかい離が指摘されています。
また、技能実習制度では、原則として転籍(転職)は認められず、やむを得ない事情がある場合を除き、実習先を変更することができません。
暴行など悪質な法令違反を受けた場合は転籍可能ですが、技能実習生の自由な意思による転籍は認められません。
本来は、「人材確保」のためではない制度を労働力の供給源として利用することによりさまざまな問題が発生しているため、「人材育成」と「人材確保」の両方の実態に即した新制度の創設が必要と判断されました。
以下に現行の技能実習制度で発生しやすいトラブルについて解説します。
問題点1:賃金・労働時間のトラブル
厚生労働省によると、令和4年の一年間で、全国の労働基準監督機関が9,829件の監督指導を行い、その73.7%に当たる7,247件の実習実施者で労働基準関係法令違反が認められたと報告しています。
そのうち、「賃金の支払いに関する違反」が997件、「割増賃金の支払いに関する違反」が1,666件、「労働時間に関する違反」が1,547件と多くを占めており、給与や労働時間に関する問題が多数発生しています。
令和4年の実習実施者の総数は64,945者であり、全体の11.1%の割合で違反行為が行われていたことが判明しています。
問題点2:職場内のハラスメント
各種報道やSNSなどで技能実習生に対する暴行やハラスメントの問題が度々話題になります。
具体例としては、「上司や同僚からの暴行・暴言」や「不当なノルマを課される」「セクシャルハラスメント」「妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメント」などが挙げられます。
出入国在留管理庁の調査では、技能実習生全体のうち54.7%が借金をして来日していることが判明しています。そのため、多くの技能実習生は、仕事を失うリスクを避けるために、暴行やハラスメントの問題を強く訴えることなく我慢をしてやり過ごそうとする傾向があります。
このような問題は一部の限られた実習先だけで起こることではありますが、発覚が遅れる要因などは技能実習制度そのものの問題であるため、制度全体が抜本的に見直されることとなりました。
問題点3:労働災害の発生率
技能実習生の労働災害による年間死傷者数は、令和5年の数字で1,692人です。
技能実習生1,000人のうち、4.1人が死傷していることとなり、これは日本人を含む全ての労働者の死傷率と比較すると約1.7倍高い数字です。
技能実習の対象職種・作業には、労働災害の発生率の高い仕事が多く含まれているため、単純比較はできませんが、言語や労働環境の違いなどが事故発生率増加の一因になっていると考えられます。
有識者会議では、技能実習の技能検定試験について、「労働安全衛生上の視点が不足している」との指摘があったため、今後は労働安全衛生に関する規制が強化される可能性があります。
問題点4:多数の失踪者
令和5年の技能実習生の失踪者数は9,753人です。失踪者の中には、在留期限が切れる前に出国する者も含まれているため、全てが不法滞在に繋がるわけではありませんが、これだけの数の技能実習生の失踪は大きな問題となっています。
失踪の主な原因は、「賃金の不払い」「労働条件のミスマッチ」「職場内での孤立」「SNSなどの違法な仕事の誘い」などです。
有識者会議においては、失踪問題の対策として「悪質な送り出し機関の排除」や「外国人技能実習機構の監理団体に対する監督指導権限の強化」「外国人技能実習機構の職員増員及び予算拡大」が提言され、今後の状況改善が求められています。
以下の記事では、
参考:送り出し機関は問題だらけ?認定要件や選び方を徹底解説します!
育成就労と技能実習の違い
2025年2月現在、育成就労の制度の詳細はまだ確定していない部分も多いですが、有識者会議の提言やその後の関係閣僚会議の決定内容を踏まえ、技能実習からの変更点や新たに追加される可能性の高い点について解説します。
外国人技能実習機構の権限強化
技能実習から育成就労への制度移行に伴い、外国人技能実習機構は外国人育成就労機構に名称が変更されます。
技能実習制度が抱えていた多くの問題点を解消すべく、育成就労移行後はさまざまな権限が強化されることとなります。変更が予定されている具体的な内容は以下の通りです。
職員の増員と予算の拡大
受け入れ機関に対する監督指導機能の強化
外国人に対する支援・保護機能の強化
労働基準監督署との相互通報の取り組みの強化
地方出入国在留管理局との連携強化
転籍支援に関するハローワークとの連携
特定技能の相談援助業務を新たに開始する
転籍制限の緩和
技能実習制度においては、やむを得ない事情がある場合を除き、転籍は認められません。しかし、育成就労制度では、一定の条件を満たせば本人の自由意思によって転籍することが可能です。有識者会議で提言された一定の条件は以下の通りです。
同一機関での就労が1年を超えていること
技能検定試験基礎級等に合格していること
日本語能力A1相当以上の試験に合格していること
転籍前と同じ業務区分であること
適切な転籍先であること
また、転籍前の受け入れ機関が負担した初期費用については、正当な補填が受けられるよう措置が講じられる予定です。
外部監査人の義務化
技能実習制度の監理団体においては外部監査人の設置は任意ですが、育成就労制度においては外部監査人の設置が義務化されます。
外部監査人は、現行制度においても、弁護士や行政書士、社会保険労務士などが選任されている実情があり、資格者等の選任を義務付けた上で氏名などを公表する措置を講ずるべきとの提言がなされています。
前職要件の撤廃
現行の技能実習制度においては、日本で従事する予定の業務と同種の業務に母国で従事した経験(前職要件)を有することが求められます。
この前職要件は、技能実習生が日本に入国した後の労働安全上のリスクを軽減させる観点から重要なものとされていました。
しかし、実情としてブローカーが介入し、手数料を取って前職の証明書を発行するなど、制度が形骸化していることが指摘されています。
そのため、育成就労制度においてこの要件は撤廃されることとなりました。
再入国制限の緩和
技能実習制度では、帰国後に改めて日本に入国し、再実習をすることは原則として認められません。
一方で、育成就労制度においては、本人事情や業務内容のミスマッチを理由に帰国した場合であっても、通算滞在年数が2年以下であれば再度業種を変えて3年間の育成就労の活動を行うことが認められます。
ただし、未熟練労働者である育成就労外国人の再入国を無制限に認めるのは適切ではないため、通算の滞在期間は最長5年までに限るとされています。
日本語能力向上の方策
育成就労制度においては、受け入れ職種・作業における技能の向上だけでなく、段階的な日本語能力の向上も必要とされています。
有識者会議で提言された具体的な内容としては、日本語教育支援に取り組んでいる受け入れ機関を優良認定し、優遇措置を設けることや認定日本語教育機関を活用する仕組みづくりなどをすべきと言及されています。
特定技能制度への移行
技能実習制度においては、「技能実習2号または3号を良好に修了すること」が特定技能1号移行の要件とされています。
一方で育成就労制度では、特定技能1号に移行するためには、以下の要件を満たす必要があります。
技能検定試験3級等または特定技能1号評価試験合格
日本語能力A2相当以上の試験(N4相当)合格
なお、育成就労から特定技能1号に移行するための要件については、当分の間は試験合格ではなく「相当講習を受講することでも可」と説明されています。当分の間がどの程度の期間であるかは不明です。
また、特定技能1号移行のための試験不合格者については最長1年の在留延長を認めることについても提言されています。
監理団体は監理支援機関に変わる
技能実習の監理団体は、育成就労制度移行後に「監理支援機関」に名称が変更されます。
監理支援機関が行う「監理支援」の業務は大きく分けて、「雇用のあっせん」と「育成就労実施者(受入れ企業など)に対する監理」の2点です。
技能実習制度においては、同じ意味で「実習監理」という言葉が使用されています。
技能実習の監理団体と育成就労の監理支援機関の位置づけや業務内容には大きな違いはありませんが、育成就労制度においては「中立性・独立性の確保」「職員の配置」「財政基盤」「相談対応体制」などの許可要件が厳格化される方向で検討されています。
育成就労と技能実習の違い比較表
以下の表は、育成就労と技能実習の制度の違いの一覧です。
現状、育成就労について公表されている内容の多くは、有識者会議の提言や関係閣僚会議の決定内容など一定の信頼性のある情報に基づいています。
ただし、施行令や施行規則、その他運用要領などは未公表であり、確定事項ではない情報も多く含まれていることにご注意ください。
| 制度の種類 | 技能実習 | 育成就労 |
| 制度の目的 | 技術移転による国際貢献 | 人材育成と人材確保 |
| 受け入れ可能な分野 | 91職種(167作業) | 特定技能と一致(国内での育成になじまない分野を除く) |
| 在留期間 | 1号(1年)、2号(2年)、3号(2年) | 原則3年 |
| 転籍 | やむを得ない事情がある場合を除き不可 | 一定条件を満たせば本人希望の転籍も可能 |
| 前職要件 | 従事予定の業務と同種の業務の経験が必要 | なし |
| 同一目的での再入国 | 帰国後の再実習は原則不可 | 通算2年以下で帰国した場合は異なる分野で再入国可能(通算5年まで) |
| 在留資格の種類 | 技能実習1号~3号(イ、ロ) | 育成就労(予定) |
| 雇用のあっせん | 監理団体 | 監理支援機関 |
| 外部監査人の選任 | 任意 | 選任義務有り |
| 特定技能1号への移行要件 | 技能実習2号または3号を良好に修了 | 技能試験及び日本語試験の合格が必要 |
| 特定技能以外の在留資格への変更 | 原則不可 | 現状不明 |
| 他の在留資格から育成就労への変更 | 不可 | 現状不明 |
まとめ
育成就労制度の詳細は、現状では確定していない部分も多いですが、今後「育成就労法施行令」や「育成就労法施行規則」などの政省令で具体的な内容が定められます。
また、制度の運用要領や各種手引きなども随時公開されることとなりますが、2030年までは技能実習制度と並行して運用されることになります。混乱を避けるためには、両制度の違いを意識しながら情報収集をすることが大切です。
複雑な育成就労(技能実習)の制度も、高い専門性を持つ監理団体(監理支援機関)のサポートを受けることで、非常に有効な人材確保の手段として活用することが可能です。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。