「技能実習生の給与はいくらに設定すれば良いの?」
「技能実習生は低賃金って聞いたけど、それって本当?」
このような悩みや疑問をお持ちの方もいるでしょう。
技能実習生の給与相場は月額19〜23万円が目安です。
中には、残業代の未払いや不透明な天引きにより、低賃金で働かされる事例もあるようです。
技能実習生を受け入れる企業は、最低賃金法や同一労働同一賃金の原則など法令に則った給与に設定してください。
本記事では、技能実習生の給与相場や賃金を定めるうえでの基本ルールを解説します解説します。
不当な給料を設定した場合の企業側のリスクや、給料に関するトラブルを防止するための対策も紹介しているので参考にしてみてください。
外国人雇用にかかる費用を
事前に知りたい方へ

この資料でわかること
- 外国人雇用にかかる費用一覧
- 海外在住の外国人採用にかかる費用
- 日本在留の外国人採用にかかる費用
- 外国人雇用のコストを抑える方法
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
INDEX
技能実習生の給与相場と実態

技能実習生の給与水準は、実習段階や業種によって大きく異なります。
ここでは、技能実習生の給与相場と実態を解説します。
- 外国人技能実習生の平均給与と手取り額
- 【実態解明】「時給300円」の真実
順番に見ていきましょう。
外国人技能実習生の平均給与と手取り額
技能実習制度では、実習段階が進むにつれて技能の習熟度が高まるため、それに応じた報酬の引き上げが求められます。
また、制度上も実習段階ごとの昇給率は、優良な実習実施者を認定する際の審査で加点の対象です。
給与から控除される項目には、所得税や住民税、健康保険料などがあり、これらを差し引いた金額が実習生の手取り額です。
手取り額は実習生が実際に使える金額であり、生活費や仕送りに充てられます。
そのため、受け入れ企業は総支給額だけでなく手取り額も考慮した給与設定が必要です。
次項では、技能実習1号・2号・3号の各実習段階における業種別の給与相場について解説します。
- 技能実習1号の報酬相場
- 技能実習2号の報酬相場
- 技能実習3号の報酬相場
給与相場を把握し、給与設定の参考にしてください。
【関連記事】
技能実習1号・2号・3号の違いとは?移行方法や受け入れ可能な職種も解説
技能実習1号の報酬相場
令和5年度の技能実習1号の平均月額給与は全産業で191,309円となっており、業種ごとに差が見られます。
以下は業種別における第1号技能実習生の給与支給額及び控除額を示した表です。
| 令和5年度 業種別第1号技能実習生の給与支給額及び控除額(単位:円) | ||||||||
| 業種別平均月額 | 全産業 | 農業,林業 | 漁業 | 建設業 | 製造業 | 医療,福祉 | サービス業 | その他 |
| きまって支給する現金給与額 | 191,309 | 184,296 | 182,630 | 187,820 | 195,336 | 176,390 | 187,372 | 191,878 |
| 期末手当等 | 8,748 | 6,167 | 8,767 | 7,626 | 9,725 | 20,859 | 4,583 | 4,986 |
| 控除総額 | 47,490 | 33,800 | 27,350 | 49,355 | 48,761 | 45,057 | 48,230 | 47,441 |
※きまって支給する現金給与額には、「超過労働給与」「通勤手当」「精皆勤手当」「家族手当」が含まれます。
※控除総額には税・社会保険料のほか、食費・居住費の控除額が含まれます。
参照:【公表用】令和5年度における技能実習の状況について(統計資料)|外国人技能実習機構
医療、福祉の業種では17万円台にとどまる一方、製造業では195,336円と比較的高く、職種の特性や地域の賃金水準が反映されています。
なお、令和3年度の1号技能実習生の現金給与額の全産業平均は175,421円で、令和4年度の平均は185,579円です。
毎年5千円から1万円程度月額給与が上昇しています。
支給額に含まれる超過労働給与や通勤手当、精皆勤手当などの手当の構成は業種によって異なります。
ほかの業種と比較して、製造業の平均給与が高い理由は超過労働給与の支給額が多いことが主な要因です。
製造業では生産ラインの維持や納期対応のため時間外労働が発生しやすい傾向があり、それに伴う割増賃金が総支給額を押し上げていると考えられます。
技能実習2号の報酬相場
令和5年度の技能実習2号における全産業の平均月額給与は201,829円で、技能実習1号と比較して約1万円高い水準です。
以下は業種別における第2号技能実習生の給与支給額及び控除額を示した表です。
| 令和5年度 業種別第2号技能実習生の給与支給額及び控除額(単位:円) | ||||||||
| 業種別平均月額 | 全産業 | 農業,林業 | 漁業 | 建設業 | 製造業 | 医療,福祉 | サービス業 | その他 |
| きまって支給する現金給与額 | 201,829 | 190,945 | 189,154 | 203,025 | 203,602 | 202,756 | 200,034 | 200,807 |
| 期末手当等 | 29,038 | 20,579 | 13,314 | 30,523 | 24,988 | 95,158 | 18,065 | 17,883 |
| 控除総額 | 49,695 | 35,156 | 30,073 | 53,218 | 50,752 | 50,284 | 52,232 | 50,998 |
※きまって支給する現金給与額には、「超過労働給与」「通勤手当」「精皆勤手当」「家族手当」が含まれます。
※控除総額には税・社会保険料のほか、食費・居住費の控除額が含まれます。
参照:【公表用】令和5年度における技能実習の状況について(統計資料)|外国人技能実習機構
業種別では、製造業が最も高く203,602円、次いで建設業が203,025円、医療,福祉が202,756円となっており、専門性や労働負担の高い業種ほど給与が高くなる傾向があります。
一方で、農業・林業は190,945円、漁業は189,154円と、平均を下回る水準にとどまっています。
なお、令和3年度の2号技能実習生の現金給与額の全産業平均は192,976円で、令和4年度の平均は196,272円です。
毎年3千円から5千円程度月額給与が上昇しています。
技能実習3号の報酬相場
技能実習3号の全産業における平均月額給与は229,829円で、技能実習1号や2号と比べて最も高い水準にあります。
以下は業種別における第3号技能実習生の給与支給額及び控除額を示した表です。
| 令和5年度 業種別第3号技能実習生の給与支給額及び控除額(単位:円) | ||||||||
| 業種別平均月額 | 全産業 | 農業,林業 | 漁業 | 建設業 | 製造業 | 医療,福祉 | サービス業 | その他 |
| きまって支給する現金給与額 | 229,829 | 203,948 | 212,712 | 258,178 | 220,191 | 227,086 | 220,311 | 219,046 |
| 期末手当等 | 46,623 | 34,036 | 17,248 | 57,511 | 42,942 | 175,359 | 35,525 | 33,079 |
| 控除総額 | 55,868 | 36,655 | 32,227 | 63,815 | 54,025 | 57,986 | 57,097 | 57,363 |
※きまって支給する現金給与額には、「超過労働給与」「通勤手当」「精皆勤手当」「家族手当」が含まれます。
※控除総額には税・社会保険料のほか、食費・居住費の控除額が含まれます。
参照:【公表用】令和5年度における技能実習の状況について(統計資料)|外国人技能実習機構
技能実習3号に移行すると給与水準が大幅に上昇する理由としては、技能実習2号修了後は転職の制限が緩和される点や特定技能に無試験で移行する要件を満たすなど給与相場を押し上げる要因が複数存在することが挙げられます。
業種別では建設業が最も高く258,178円に達しており、医療・福祉は227,086円、サービス業が220,311円と続いています。
平均給与が最も低いのは、農業・林業の203,948円で、次いで漁業が212,712円と、他業種に比べてやや低い数字になっています。
なお、令和3年度の3号技能実習生の現金給与額の全産業平均は213,986円で、令和4年度の平均は222,179円です。
毎年7千円から8千円程度月額給与が上昇しています。
外国人採用の窓口では「外国人雇用にかかる費用徹底分析」の資料を無料配布しております。
給料に関する法律や設定方法も理解できる内容です。
30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
外国人雇用にかかる費用を
事前に知りたい方へ

この資料でわかること
- 外国人雇用にかかる費用一覧
- 海外在住の外国人採用にかかる費用
- 日本在留の外国人採用にかかる費用
- 外国人雇用のコストを抑える方法
【実態解明】「時給300円」の真実
一部のメディアやSNSで「技能実習生が時給300円で働かされている」という報道を目にした人もいるでしょう。
残業をさせたのにもかかわらず、適切な残業代を支払わない企業や、過度に家賃・食費を給与から天引きする企業があり実質時給が300円になったケースもあるようです。
これらはいずれも労働基準法や最低賃金法に違反する行為です。
受け入れ企業は、法令を遵守した適正な給与設定を心がけてください。
技能実習生の給与を決める4つの基本ルール

技能実習生の給与を決める4つの基本ルールは以下の通りです。
- 地域別・産業別の最低賃金以上に設定する
- 労働基準法に基づき割増賃金を支払う
- 日本人従業員と同等以上の報酬にする
- 賞与は日本人従業員と同様の社内基準を適用させる
基本ルールを守らない場合、技能実習計画の認定取消しや新規受け入れの停止などの行政処分を受ける可能性があります。
【関連記事】
技能実習制度をわかりやすく解説!目的や条件、受け入れ方法を紹介
技能実習と特定技能の違いとは?11のポイントを比較表で徹底解説
地域別・産業別の最低賃金以上に設定する
技能実習生であっても、日本国内で労働する以上、最低賃金法の規定が等しく適用されます。
最低賃金には以下の2種類があります。
最低賃金の種類
- 都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」
- 産業ごとに定められた「特定(産業別)最低賃金」
この両方が適用される場合は、金額の高い方を基準として給与を設定しなければなりません。
仮に技能実習生本人が最低賃金以下での雇用に同意していたとしても、その合意は法的に無効となります。
最低賃金を下回る給与を支払った場合は最低賃金法違反となり、技能実習生の受け入れ停止などの行政処分を受ける可能性があります。
最低賃金は毎年改定されるため、受け入れ企業は改定のタイミングで給与水準を見直し、最低賃金を下回っていないか確認してください。
労働基準法に基づき割増賃金を支払う
技能実習生が時間外労働や休日出勤をした場合は、日本人労働者と同様に労働基準法に基づく割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金の割合は以下の通りです。
| 時間外労働をした場合(1日8時間・週40時間超) | 25%以上 |
| 深夜労働をした場合(午後10時~午前5時の労働) | 25%以上 |
| 休日労働をした場合(法定休日) | 35%以上 |
| 月60時間超の時間外労働 | 50%以上 |
2023年4月1日からは月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率50%以上の規定が中小企業にも適用されています。
技能実習生を受け入れている中小企業も、長時間労働の抑制と適切な割増賃金の支払いが求められます。
日本人従業員と同等以上の報酬にする
技能実習制度では、技能実習生の報酬が「同種の業務に従事する日本人と同等以上」であることが必要とされており、その判断は職務内容と責任の程度に照らしておこなわれます。
具体的には、従事する作業の種類、技能水準、業務量などに基づいて、日本人労働者と技能実習生の実務上の差異を検討することが求められます。
技能実習計画認定申請の際には、「日本人労働者と同等の報酬であること」の説明資料の提出が求められるため、就業規則や賃金規定等で客観的に立証しやすい状態を整備してください。
また、実習の定期監査や実地検査時に賃金台帳などにより適切に給与が支払われているか確認されることとなるため、入国時点だけではなく技能実習が継続する期間内すべてにおいて違反のない状態を維持しなければなりません。
賞与は日本人従業員と同様の社内基準を適用させる
賞与(ボーナス)は、法律上必ず支給しなければならないものではありませんが、技能実習生に対しても日本人従業員と同様の社内基準を適用することが求められます。
通常、賞与が支給される職種や雇用形態にある日本人と同等の業務内容であれば、実習生にも同様の基準で判断する必要があり、不支給とする場合には合理的な理由が必要です。
雇用契約には賞与の有無が明記されるのが一般的であり、支給を記載しながら実際に支給しない場合は違反と見なされる可能性があります。
賞与の取り扱いにあたっては、雇用条件書や就業規則と照らし合わせながら、待遇に不公平が生じないよう運用体制を確保してください。
【2020年施行】技能実習生の月給制義務化について

2020年1月より、建設分野の技能実習生に対する報酬の支払い方法が法改正により変更されました。
これまで時給制や日給制での支払いも認められていましたが、改正後は原則として月給制での支払いが義務化されています。
月給制にすることで実習生が安定した収入を得られ、生活費や母国への仕送りなどの計画を立てやすくなります。
なお、申請者が雇用しているほかの職員が月給制でない場合も技能実習生に対しては月給制で給与を支払う必要があります。
受け入れ企業は雇用契約書や賃金規程を月給制に対応した内容に整備し、実習生に対しても月給制の仕組みを丁寧に説明することが求められます。
技能実習生に対する給与の支払い方法|天引きされる項目も紹介
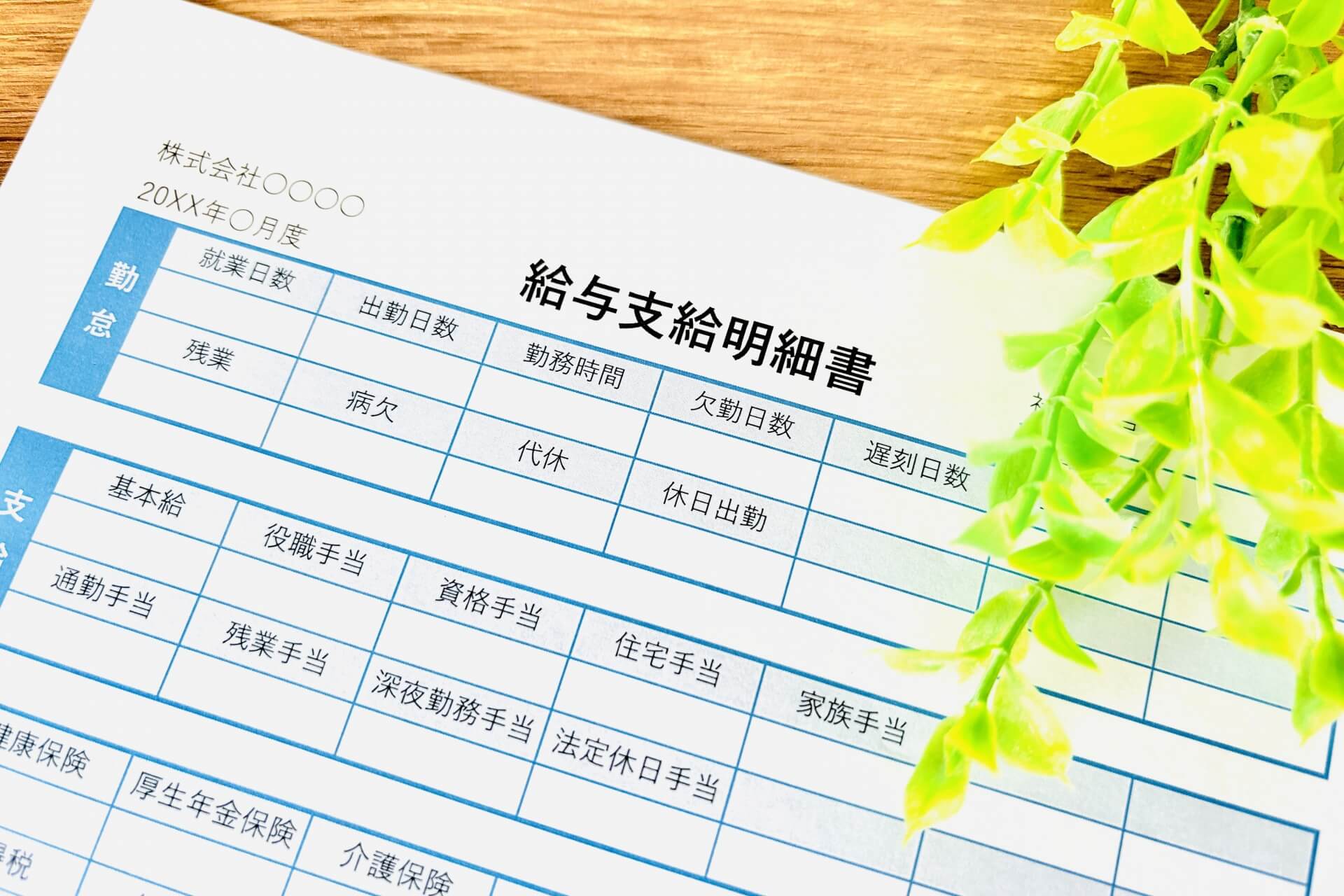
技能実習生への給与の支払いは、現金払いや口座振込など任意に選択できます。ただし、支払いの事実を客観的に証明できる記録を残さなければいけません。
ここでは以下2つの項目について解説します。
- 給料の支払い方法
- 給与から天引きされる項目|税金、保険料、家賃など
給与の支払い方法や天引きされる項目を事前に把握し、技能実習生に給与を支払う準備を整えてください。
給料の支払い方法
給与の支払い方法を以下2つのパターンに分けて紹介します。
給与の支払い方法
- 預貯金口座への振込みの場合
- 預貯金口座への振込み以外の場合
支払い方法のパターンを把握し、自社に合った支払い方法を見つけてください。
預貯金口座への振込みの場合
預貯金口座への振込みによって報酬を支払う場合は、振込みが適切におこなわれたことを証明する書類の保存が必要です。
具体的には、口座振込明細書や金融機関の取引明細書の写しなど、支払い日・金額・振込先名義などが明記された書類を保管することが求められます。
技能実習生を受け入れる企業は、報酬支払いに関する適正な記録を保管し、必要に応じて説明できる体制を整備しなくてはなりません。
預貯金口座への振込み以外の場合
預貯金口座への振込み以外の方法で報酬を支払う場合は、支払いの事実を客観的に確認できる書類の保存が必要です。
この場合、給与明細の写しや、受領したことを証明する報酬支払い証明書などを用意し、記録として適切に管理することが求められます。
証明書類には、支払日や金額、受領者の署名などが明記されていることが望ましく、不備があると支払いが認められないおそれがあります。
可能であれば、振込み記録が自動的に残る銀行振込みを用いる方が、実務上も確認が容易であり、リスクの低減につながります。
給与から天引きされる項目|税金、保険料、家賃など
技能実習生の給与から天引きされる項目は、主に以下の通りです。
| 法令で定められた項目 | 労使協定で定められた項目 |
| 税金 社会保険料など | 寮費 食費など |
法令で定められた項目と労使協定で定められた項目は、給与から天引きできます。
ただし、具体的な使途を明らかにできない項目は賃金控除協定を締結していたとしても天引きできません。
給与から天引きする項目詳細は給与明細に分かりやすく記載し、実習生が理解できる言語で説明することがトラブル防止につながります。
技能実習生の給与を最低賃金に設定した場合のリスク

技能実習生の給与を最低賃金に設定した場合のリスクは以下の通りです。
- モチベーションが下がり生産力が低下する
- 待遇に不満を感じて失踪する
- 転職可能な特定技能に移行した際に離職される
法律上は最低賃金以上の給与を支払っていれば問題ありませんが、最低賃金での給与設定にはさまざまなリスクが伴います。
技能実習生の安定した雇用を目指す場合は、最低賃金にとどまらない給与設計を検討してください。
モチベーションが下がり生産力が低下する
給与への不満は、技能実習生の労働意欲の低下に直結します。
仕事の内容や環境に対して給与が見合っていないと感じると、日々の業務に対するモチベーションが下がり、生産性に影響をおよぼしかねません。
給与に対する期待と現実のギャップが大きいと、精神的なストレスが蓄積し、職場でのトラブルに発展する場合があります。
適正な給与設定は単なるコストではなく、人材の定着と生産性向上のための投資と捉えてください。
待遇に不満を感じて失踪する
最低賃金での給与設定が続くと、技能実習生の失踪を誘発する可能性があります。
近年はSNS等を通じて他県や他企業の技能実習生と給与情報を交換することが一般的になっており、給与の差が大きいと労働意欲に影響します。
地域による最低賃金の格差は合理的な理由があるものの、技能実習生にとっては理解しにくいです。
失踪者が出た場合、受け入れ企業はペナルティが科される可能性があります。
失踪を防ぐためにも、最低賃金に少し上乗せした給与設定を検討してください。
技能実習生が失踪する理由について以下の記事で紹介しているので、ぜひご覧ください。
【関連記事】
【完全版】技能実習生の失踪対策|原因、対応、相談先を徹底解説 | 外国人採用の窓口
転職可能な特定技能に移行した際に離職される
特定技能は技能実習と異なり、同一分野内であれば転職が認められています。そのため、給与水準の低い企業からはより好条件の企業へ人材が流出するリスクがあります。
自社で育成した人材に長く活躍してもらいたい場合は、技能実習の段階から計画的に昇給させ、特定技能移行後も継続して働きたいと思える待遇を整備してください。
外国人採用の窓口では「外国人社員とのコミュニケーションのコツ」の資料を無料配布しております。
30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。
外国人社員との
やりとりでお困りの方に

この資料でわかること
- 外国人雇用における言語課題
- 伝わりにくいコミュニケーション例
- 伝わりやすいコミュニケーション例
- 外国人社員にあった指導方法
技能実習生の給与トラブルを防ぐために企業側ができること

技能実習生の給与トラブルを防ぐために企業側ができることは以下の通りです。
- 雇用関連の書類を多言語版で交付する
- 入国後の講習手当を支給する
- サポート力が強い監理団体を見つける
技能実習生との給与に関するトラブルを未然に防ぐために企業が取り組むべき具体的なポイントを把握しておきましょう。
雇用関連の書類を多言語版で交付する
報酬に関するトラブルを防ぐためには雇用契約書や雇用条件書、重要事項説明書などを技能実習生が理解できる言語で交付することが基本です。
また、就業規則や賃金規程など社内の規定についても、実習生が理解できるよう丁寧に説明してください。
雇用契約書の作成や在留資格申請書類の作成は、行政書士に委託することも可能です。
「外国人採用の窓口」では行政書士事務所の一括検索サービスを無料で提供しています。
ご希望のエリアや業種などを条件検索して探せますので、お気軽にご活用ください。
入国後の講習手当を支給する
入国後講習は原則として労働には該当しませんが、講習期間中に食費や居住費などの自己負担が発生する場合は、必ず自己負担額以上の講習手当を支給する必要があります。
講習手当は、現金または現物で支給することとされており、受け入れ企業に配属されるまでの間、収入のない実習生が入国後講習に専念できるよう設けられている制度です。
技能実習計画の認定申請時には、講習手当の有無や金額、支給方法を重要事項説明書に記載し、実習生の署名を得ておく必要があるため、制度の趣旨を十分理解したうえで準備をおこなうことが求められます。
サポート力が強い監理団体を見つける
技能実習生の給与に関するトラブルを防ぐためには、サポート力が強い監理団体と契約してください。
サポート力が強い監理団体と契約することで、給与に対する相談や実習生への説明などをしてもらえます。
特に初めて技能実習生を受け入れる企業にとっては、給与設定の適正性や法令遵守の確認など、専門的な知識が求められる場面が多くあります。
監理団体のサポートを受けることで、企業側の負担を軽減しながら適切な給与管理体制を構築可能です。
契約前に、複数の監理団体と面談して比較検討してください。
【関連記事】
監理団体の選び方|失敗しない5つのポイントと注意点を徹底解説
技能実習生の給与相場を把握して受け入れ準備を進めよう

技能実習生の給与は月額19〜23万円が目安で、最低賃金以上かつ日本人と同等以上が原則です。
最低賃金での給与設定は法律上問題ありませんが、失踪や特定技能移行後の転職、モチベーション低下による生産性への影響といったリスクがあります。
長期的な人材確保を目指すのであれば、最低賃金に少し上乗せした給与設定と計画的な昇給制度の整備が効果的です。
弊社は、外国人採用に特化した行政書士事務所や登録支援機関、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
自社だけで外国人の支援が難しいと感じたら、当サービスの条件検索にて、あなたの業種・雇用したい在留資格・国籍に対応した仲介会社を探してみてください。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。


