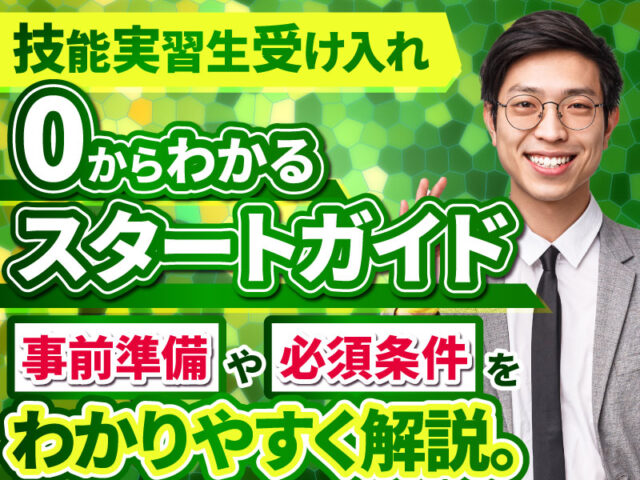外国人材の受け入れニーズが高まるなか、「技能実習生を受け入れたいが、何から始めればよいのか分からない」「制度やルールが複雑で不安」と感じている企業も少なくありません。
制度の全体像を十分に理解しないまま受け入れを進めると、手続きの不備や想定外のトラブルが発生する可能性もあり、企業側の信頼にも関わる重大な問題となりかねません。
この記事では、技能実習生を受け入れるために企業が満たすべき条件や、整備すべき体制について詳細を解説し、制度に沿った適正な受け入れをするために必要な知識をお伝えします。
INDEX
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
技能実習生制度とは
技能実習制度は、日本での技能や技術の修得を通じて、外国人が母国の発展を担う人材へと成長することを目的とした技術移転及び国際貢献のための制度です。
対象となる職種や作業は技能実習法施行規則で定められており、外国人実習生は、認定された実習計画に基づく作業を通じて、段階的に技能を深めることができるよう制度設計されています。
実習の実施にあたっては、監理団体と受け入れ企業が連携しながら、実習計画を遂行していくことが求められます。
技能実習生受け入れの流れ
技能実習制度は、開発途上国の人材育成と技術移転を目的としているため、実習生の受け入れは日本国内に在留している外国人ではなく、原則として海外からの新規入国を基本としています。
受け入れの流れは、まず受け入れ企業が技能実習計画を作成し、外国人本人の選定とあわせて、外国人技能実習機構への認定申請を行います。
技能実習計画が認定された後は、出入国在留管理庁から在留資格認定証明書の交付を受けて、実習生が現地で査証を取得し、日本に新たに入国して実習を開始します。
実習生の選考から入国、企業への配属までにはおおむね6か月程度の期間を要するため、入国予定日から各段階の手続きの時期を逆算するなど計画的な準備が求められます。
実習実施者と監理団体の役割
技能実習制度における「実習実施者」とは、技能実習生を直接受け入れ、職場において技能の修得・習熟を支援する日本国内の企業等を指します。
一方、「監理団体」とは、主に中小企業などが技能実習生を受け入れる際に関与する協同組合などの非営利法人であり、技能実習が適正に行われるように支援・監督を行う役割を担います。
監理団体は、技能実習計画の作成支援や申請手続の補助、実習実施者への監査、実習生への生活指導など、制度運用の多くの役割を担っています。
また、監理団体として活動するには、一定の要件を満たしたうえで、主務大臣の許可を受けることが法律上義務づけられています。
受け入れ企業に求められる条件
技能実習生を受け入れるには、企業が制度上の要件を満たし、実習生にとって適正な就労・生活環境を確保できる体制を整えている必要があります。
受け入れ企業は「実習実施者」として、技能実習計画に基づいた技能修得の場を提供し、関係法令を遵守したうえで実習の実施責任を負います。
以下では、実習実施者に求められる具体的な条件について、体制面・法令面・設備面の観点から順を追って解説します。
技能実習責任者・技能実習指導員・生活指導員
技能実習を適正に実施するためには、受け入れ企業が「技能実習責任者」「技能実習指導員」「生活指導員」をそれぞれ選任し、役割に応じた体制を整える必要があります。
技能実習責任者は、技能実習の実施全般を統括し、関係法令や制度に基づく管理の責任を負う立場にあり、原則として過去3年以内に所定の講習を受講していることが求められます。
技能実習指導員は、実習現場で技能や知識の指導を行う担当者であり、同種の業務に5年以上の実務経験があることが要件とされています。
生活指導員は、技能実習生の日本での生活を支援する立場として、生活習慣や社会ルールの指導、相談対応などを行い、実習生が安心して生活できる環境を整える役割を担います。
労働関係法令の遵守
技能実習生を受け入れる企業は、労働基準法や最低賃金法、労働安全衛生法などの労働関係法令を遵守し、実習生にとって適正な雇用環境を整える必要があります。
とくに、最低賃金以上の報酬の支払いや法定の労働時間、休憩・休日の確保は必須であり、他の労働者と同様に労働条件通知書などによる明示も求められます。
さらに、健康保険、厚生年金保険、雇用保険などの社会保険制度にも適切に加入させ、保険料の負担や手続は原則として日本人と同様に取り扱うことが必要です。
これらの法令に違反した場合、技能実習計画の認定取消しやその後の技能実習生の受け入れの停止処分を受ける可能性があります。
技能実習日誌・帳簿の作成管理
技能実習制度では、実習の適正な実施を確保するため、企業が各種帳簿を作成・管理することが義務付けられています。
主な帳簿には、実習生の名簿や履歴書、雇用条件書などを管理する「技能実習生の管理簿」、技能実習計画の進行状況を記録する「認定計画の履行状況に係る管理簿」などがあり、いずれも常時備え付けておく必要があります。
加えて、実習の内容や進捗を日々記録する「技能実習日誌」についても、継続的に記載・保管することが求められます。
これらの帳簿は、監理団体や関係行政機関による監査や実地検査の対象となるため、常に正確かつ適切な形で保管・管理する必要があります。
宿舎や生活環境の整備
技能実習生を受け入れる企業は、技能実習生が生活する宿舎について、法令で定められた基準を満たした施設を提供する必要があります。
居室は、1人あたり4.5平方メートル以上の広さが確保され、窓や換気設備があり、十分な採光・照明・暖房などの基本的な住環境が備わっていなければなりません。
さらに、台所、浴室、トイレ、洗濯設備といった共用設備が使用可能であることが必要であるほか、鍵がかけられる私物保管設備を設置するなど、プライバシーの確保と盗難防止に配慮することが求められます。
これらの宿舎の整備状況は、監理団体による定期監査や外国人技能実習機構の実地検査において確認の対象となる場合があります。
技能実習計画の策定と認定要件
外国人を技能実習生として受け入れるためには、入管法令および技能実習法令に定められた要件を満たし、地方出入国在留管理局において、在留資格「技能実習」の申請をする必要があります。
その際、「技能実習」の在留許可を得るための条件として、「事前に技能実習計画の認定を受けること」が求められます。
この技能実習計画は、実習内容や期間、指導体制、実施場所、実習生の待遇などを詳細に記載したものであり、外国人技能実習機構という認可法人によって認定事務が行われます。
技能実習計画とは?内容と重要性
技能実習計画とは、技能実習をどのような内容・体制で実施するのかを記した計画書であり、受け入れ企業が技能実習生を受け入れるために必ず作成しなければならないものです。
この計画には、実習の目的、実施場所、対象となる職種・作業、指導体制、実習期間、報酬の額など、制度で定められた項目を具体的に記載する必要があります。
作成された技能実習計画は、外国人技能実習機構による審査を受け、適正と認められた場合に認定されます。
この認定を受けていなければ、技能実習の在留資格を申請することができないため、技能実習を開始するための大前提となる重要な手続です。
提出書類と認定手続の流れ
技能実習計画の認定申請は、技能実習法に基づき、受け入れ企業が外国人技能実習機構に対して行います。
申請には、技能実習計画認定申請書をはじめ、技能実習生の履歴書、受け入れ企業の概要書、職種や作業内容に関する説明資料、各種の誓約書など、必要な書類を提出します。
外国人技能実習機構は、提出された書類をもとに、技能実習計画の認定基準に適合しているかを審査し、必要に応じて実地検査を行ったうえで、適正と認められる場合に認定を行います。
計画の認定を受けた後は、出入国在留管理庁に対し、在留資格「技能実習」の認定証明書交付申請を行い、証明書の交付を受けたうえで、外国人本人の入国手続に進むことになります。
計画認定後の監査・実地検査
技能実習計画が認定された後も、実習が計画どおりに適正に実施されているかを確認するため、監理団体や外国人技能実習機構による監査・実地検査が行われます。
監理団体は、技能実習法に基づき、少なくとも3か月に1回の頻度で、実習実施者に対する定期監査を実施することが義務づけられています。
また、外国人技能実習機構は、必要に応じて技能実習の実施状況について実地により検査を行い、技能実習が認定計画に適合しているかを確認します。
技能実習生本人に関する条件
技能実習制度では、実習を適正に実施するために、企業側の体制整備だけでなく、外国人本人にも一定の条件が設けられています。
技能実習は、開発途上国への技術移転を目的とする制度であるため、日本国内で既に在留している外国人が在留資格を変更して行うものではなく、外国から新たに来日して実習を行う者のみが対象とされています。
外国人の本国での経歴や、本人が技能実習制度の趣旨を理解していること、本国の公的機関からの推薦を受けていること、などが考慮され技能実習計画の認定可否が判断されます。
年齢や職歴などの基本要件
技能実習生の年齢は、技能実習(入国後講習を含む)の開始日に18歳以上であることが求められます。
職歴については、「技能実習を行う予定の業務と同種の業務に従事した経験」、または「団体監理型技能実習を行う特別な事情」があることが求められます。
団体監理型技能実習を行う特別な事情とは、「教育機関で6カ月以上(または320時間以上)、同種の業務に従事する教育を受けたこと」や「技能実習を行う必要性を具体的に説明でき、かつ必要最低限の訓練を受けていること」などが該当します。
本国での修得困難性の要件
技能実習計画が認定されるためには、対象となる技能が、技能実習生の本国等では容易に修得できない業務であることが求められます。
この要件は、技能実習制度が国際貢献を目的とする人材育成制度であるという趣旨により、「本国で習得可能な技能を、あえて日本で実習する必要はない」との考え方に基づいて定められています。
帰国後に修得技能の活用が予定されていること
技能実習制度では、外国人が日本で修得した技能等を、帰国後に本国で活用することを予定していることが重要な要件となっています。
そのため、技能実習修了後は、原則として、他の在留資格への変更は認められず、在留期限の満了日が到来する前に日本から出国する必要があります。
ただし、技能実習2号または3号を良好に修了した実習生は、特定技能1号に在留資格を変更して継続的に日本で就労することが可能です。
政府機関からの推薦を受けていること
技能実習制度では、外国人が技能実習を行うにあたり、原則として出身国の政府機関または地方政府機関などからの推薦を受けていることが求められています。
推薦を行う機関や方法は、送出し国と日本政府との間で締結された「協力覚書」に基づき、それぞれの国ごとに定められています。
推薦を受けていない者は、原則として技能実習の対象者とは認められず、技能実習計画の認定申請に必要な要件を満たさないことになります。
技能実習生の受け入れが認められないケース
技能実習生が入国するためには、技能実習計画認定申請や在留資格認定証明書交付申請の各要件に適合している必要がありますが、入国時点だけでなく実習が行われるすべての期間内において、適正な在留を継続しなければなりません。
以下に、技能実習生の受け入れが認められないケースの詳細を解説します。
入管法の規定による入国拒否・在留資格取り消し
技能実習計画が認定された場合でも、入国や在留には入管法に基づく審査が必要であり、すべてのケースで在留が許可されるとは限りません。
出入国管理及び難民認定法では、虚偽の申請や上陸拒否事由に該当するなど、一定の事由が疑われる場合には、上陸拒否処分となる場合があります。
また、入国後であっても、住居地の届出義務違反、無許可の資格外活動などの行為が確認された場合、同法に基づき在留資格が取り消される可能性があります。
技能実習法の規定による欠格事由・認定取り消し
技能実習法では、技能実習計画の認定を受けることができない者、いわゆる欠格事由が定められています。
たとえば、過去に虚偽の申請を行って認定を受けたことがある者や、労働法令違反で罰金刑を受けた者、不法就労助長行為を犯した場合などは、新たに計画の認定を受けることができません。
また、計画認定後においても、実習内容の不履行や法令違反が確認された場合には、技能実習計画の認定が取り消されることがあります。
まとめ
技能実習生の受け入れには、技能実習計画の認定、実習生本人の適格性の確認など、複雑な制度の把握と適正な実習計画を遂行するための体制整備が求められます。
制度の全体像を正しく理解し、丁寧に準備を進めることが必要なため、不明点があれば早めに監理団体など専門機関に相談することをおすすめします。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。