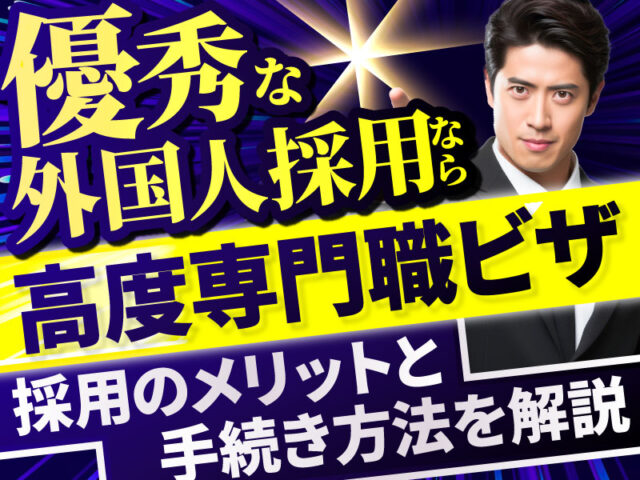●専門性の高い優秀な外国籍人材を採用し、事業の成長を加速させたい
●しかし、複雑な在留資格の手続きが、採用活動の障壁になっている
●『高度専門職』の企業側のメリットや活用方法が分からない
このような課題を抱える企業の採用・人事担当者様は多いのではないでしょうか。
グローバルな人材獲得競争が激化する現代において、「高度専門職」ビザは、優秀な外国籍人材を惹きつけ、日本国内で長期的に活躍してもらうための強力な切り札となります。
この制度は、他の就労ビザにはない数多くの優遇措置を提供しており、これらを戦略的に活用することで、企業の採用力を飛躍的に高めることができます。
この記事では、企業の採用・人事担当者の皆様が、高度専門職ビザの制度を理解し、採用活動に活かしていただけるよう、制度の概要、採用におけるメリット、ケース別の手続き、採用後のマネジメント上の注意点等について、最新情報に基づき解説します。
 この記事の監修
サポート行政書士法人
ビザコンサルタント 汲 澄澄(Kyu ChanChan)
この記事の監修
サポート行政書士法人
ビザコンサルタント 汲 澄澄(Kyu ChanChan)
サポート行政書士法人・東京本社所属。外国人の在留資格申請や会社設立支援で累計1,000件以上の実績を持ち、日本へ進出する外国企業が増加する中で、双方にとってWin-Winとなる事業創出に貢献しています。日本で働く中国人として、異文化間のビジネスにおけるシナジーの最大化に情熱を注いでいます。なぜ今「高度専門職ビザ」か? 企業が享受できる5つの採用メリット
高度専門職ビザは、日本の学術研究や経済の発展への貢献が期待される高度な能力を持つ外国籍人材を受け入れるために創設された在留資格です。単に就労を許可するだけでなく、様々な優遇措置が付与されている点が特徴です。
これらの優遇措置は、候補者本人だけでなく、その家族にも及ぶため、企業の採用ブランディングや福利厚生の魅力を高め、競合他社と差別化を図る上で有効にはたらきます。
①永住権取得要件の大幅な緩和による「長期定着」の促進
通常、外国籍の方が日本の永住権を申請するには、10年以上の継続した在留が必要です。
しかし、高度専門職ビザの場合、ポイントが70点以上の方は在留3年、80点以上であれば1年で永住権の申請資格を得られます。これは、日本での永続的な生活基盤を望む人材にとって、とても魅力的な条件です。
企業としては、安定した身分を早期に得られるという展望を提示することで、候補者に対して長期的なキャリアパスと生活設計の安心感を与え、採用後の早期離職を防ぎ、長期的な定着と貢献を促すことができます。
②配偶者の就労が自由化され「家族単位での生活」を支援
一般的な就労ビザでは、配偶者の就労は週28時間以内という制限があります。
しかし、高度専門職人材の配偶者は、一定の要件を満たせば、学歴や職歴を問わず、フルタイムで就労することが可能です。これにより、世帯収入の安定化や、配偶者自身のキャリア形成も可能になります。
企業はこの点をアピールすることで、候補者が家族と一緒に日本で生活を始める際の経済的・心理的なハードルを下げ、より安心して入社を決断できる環境を整えることができます。
③「親の帯同」許可による優秀な人材の獲得機会拡大
高度専門職人材は、世帯年収800万円以上など、一定の要件を満たすことで、本人または配偶者の親(7歳未満の子の養育等が目的)を日本に呼び寄せ、同居することが認められています。
特に、育児中の人材にとって、親からのサポートを受けられることは、仕事と育児を両立させる上で大きな安心材料となります。
他の在留資格にはないこのユニークな優遇措置は、子育て世代のハイキャリア人材を獲得する際の強力なインセンティブとなり得ます。
④複数の在留活動が許容され「柔軟な人材活用」が可能に
高度専門職ビザでは、許可された主たる活動に関連する事業であれば、自ら経営を行うことも可能です。
例えば、企業で研究開発に従事しながら、関連分野で個人的なコンサルティング事業を立ち上げるといった、複合的な活動が認められます。さらに、3年以上の活動を経て「高度専門職2号」へ移行すれば、活動内容の制限がほぼなくなり、極めて自由度の高いキャリア形成ができるようになります。
企業にとっては、従業員の多様な能力を活かし、イノベーションを創出する機会を広げることにもつながります。
高度人材採用の要「高度人材ポイント制」を企業目線で理解する
高度専門職ビザの許可は、「高度人材ポイント制」という客観的な基準で判断されます。この仕組みを理解し、候補者が基準(合計70点以上)を満たすか、事前に評価しておきましょう。
ポイント計算の仕組みと企業が確認すべき項目
ポイントは主に「学歴」「職歴」「年収」「年齢」等の一般的な加算項目と、各種のボーナスポイントで構成されます。
■学歴・職歴の確認
候補者の履歴書と職務経歴書に加え、学位証明書、在職証明書、在籍証明書といった客観的な資料で裏付けを取りましょう。特に職歴は、従事予定の業務との関連性が問われるため、具体的な業務内容を詳細にヒアリング&立証する必要があります。
■年収設定の重要性と注意点
年収はポイントに大きく影響します。採用時に提示する年収額が、ポイント基準を満たすかを確認しなければなりません。
候補者の年齢にもよりますが、年収のポイント400万円以上から加算され、1,000万円を超えると40ポイントもの高得点が得られます。
年収のポイントを立証するために、賞与や手当を含めた年収見込額を正確に計算し、それを証明する「給与の見込証明書」などを準備する必要があります。
企業側で加算を後押しできるボーナスポイント
採用したい候補者のポイントが70点にわずかに届かない場合でも、企業側の条件やサポートによってポイントを加算し、採用に繋げられる可能性があります。
【ボーナスポイントの例】
■日本語能力
日本語能力試験N1取得者には15点、N2取得者には10点が加算されます。N2は保持しているがN1には届かない候補者に対し、入社後のN1取得支援(受験料補助、学習支援など)を約束することも、入社の動機づけになるかもしれません。
■イノベーション促進支援措置を受けている企業
貴社が経済産業省などから「イノベーション促進支援措置」を受けている場合、それだけで10点のボーナスポイントが加算されます。自社が対象かどうか、一度確認してみてはいかがでしょうか。
■研究開発費の比率が高い企業
中小企業の場合、試験研究費および開発費の合計額が、総収入金額の3%以上であれば5点のボーナスポイントが得られます。
【ケース別】高度専門職外国人を採用する際の具体的な手続き
採用する人材の状況によって、必要な手続きは異なります。
ここでは3つの主要なケースに分けて、企業が担うべき役割と準備すべき書類を解説します(企業のカテゴリーによって、準備すべき書類が異なる場合があります)。
①海外から新規で呼び寄せる場合(在留資格認定証明書交付申請)
海外に在住する人材を新たに採用し、日本に呼び寄せる場合の手続きです。
【手続きの流れ】
①候補者と雇用契約を締結する
②企業が代理人となり、日本の出入国在留管理庁へ「在留資格認定証明書交付申請」を行う
③証明書が交付されたら、候補者本人へ送付する
④候補者は、現地の日本大使館・領事館で証明書を提示し、ビザ(査証)の発給を受ける
➄来日し、空港で在留カードの交付を受ける
【企業が準備すべき主な書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・ポイント計算表及びそれを証明する資料(候補者から取り寄せ)
・雇用契約書の写し
・収入見込証明書
・企業の登記事項証明書、決算報告書の写し
・会社の事業内容を明らかにする資料(パンフレット等)
②国内の他社で就労している人材を採用する場合(在留資格変更許可申請)
すでに日本国内の他企業で高度専門職として働いている人材を、転職で採用するケースです。
転職では「再申請」が必要
高度専門職ビザは、特定の所属機関(前職の会社)で活動することを前提に許可されています。
そのため、転職する際には必ず「在留資格変更許可申請」を行い、転職先の労働条件をもとに再度ポイントを計算し、審査を受け直す必要があります。
この手続きを怠ると、候補者は不法就労状態となり、在留資格取消の対象となるため注意が必要です。
【手続きの流れ】
①候補者と雇用契約を締結する
②候補者が主体となり(企業は必要書類の提供等で協力)、出入国在留管理庁へ「在留資格変更許可申請」を行う
③審査期間(通常1〜3ヶ月)を経て、許可されれば新しい在留カードが交付される。
★手続きの注意点
前職の退職日と貴社での入社日の間に空白期間が生じないよう、申請のタイミングを候補者と綿密にすり合わせる必要があります。
今まで提出した職歴や職務内容の整合性を確認しましょう。企業が準備すべき主な書類は、ケース1の書類とほぼ同じです。
③既に自社で働く社員を高度専門職へ切り替える場合
現在「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いている社員が、要件を満たす場合に、高度専門職ビザへ切り替えるケースです。
【切り替えのメリットとタイミング】
社員にとっては、前述の優遇措置を受けられる大きなメリットがあります。企業にとっても、優秀な社員の定着率向上や、ロイヤリティ向上に繋がります。
昇給や勤続年数の経過により、ポイントが70点に達したタイミングで、企業側から切り替えを提案・支援することは有効な施策となります。
【手続きの流れ】
必要書類を準備してから「在留資格変更許可申請」を行います。企業側は、最新の労働条件通知書(または在職証明書)、収入見込証明書など、申請に必要な書類の作成に協力する必要があります。
【重要】採用後に企業が注意すべきポイントとマネジメント
高度専門職人材の採用はゴールではなくスタートです。採用後もその在留資格を維持できるよう、企業側にも適切なマネジメントが求められます。
ポイント維持の重要性と企業の責任
在留資格は、申請時の条件を維持することが前提です。特に、以下の点には注意が必要です。
■給与の変動
業績不振などを理由に給与を引き下げた結果、年収ポイントが下がり、合計点が70点を下回った場合、技人国への変更申請をすることになります。人事評価や給与改定の際には、在留資格への影響を常に念頭に置く必要があります。
■職務内容の変更
配置転換により、専門性と関連の薄い業務に従事させることになった場合、ポイントの前提が崩れ、在留資格の維持が困難になる可能性があります。キャリアパスを検討する際には、本人の専門分野との整合性を確認することが不可欠です。
高度専門職2号への移行サポート
高度専門職1号で3年以上良好に活動を続けた社員は「高度専門職2号」へ移行できます。
2号の最大のメリットは、在留期間が「無期限」になることです。これは企業にとって、当該社員を長期的に安定して雇用できることを意味します。
企業は、対象となる社員に対し、2号への移行を積極的に推奨し申請をサポートすることで、より強固な信頼関係を築き、持続的な会社の成長につなげることができます。
【まとめ】高度人材の採用成功は、制度の深い理解と戦略的な活用から
高度専門職ビザは、単なる就労許可ではなく、企業の採用戦略を強化し優秀な人材の獲得と定着を促進するための強力な手段となります。
しかし、そのメリットを最大限に引き出すためには、採用担当者がポイント制度や手続きを正確に理解し、候補者の状況に応じた適切なサポートを提供することが必要です。また、採用後の労務管理においても、在留資格の維持に配慮したマネジメントが求められます。
今回解説した内容を参考に、高度専門職ビザ制度を戦略的に活用し、グローバルな事業展開の加速にお役立てください。
 この記事の監修
この記事の監修