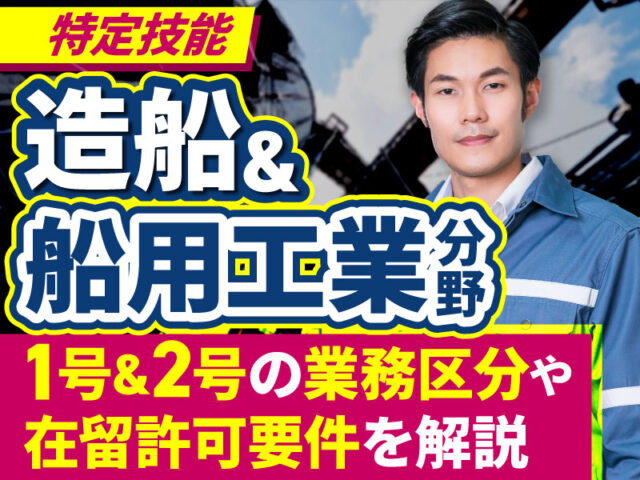国土交通省は、「海事生産性革命」プロジェクトの一環として、生産性向上を図るための人材育成に注力しています。中でも、外国人材は造船現場を支える上で欠かせない存在と位置づけられており、今後は特定技能制度の活用もさらに進むと見込まれています。
本記事では、特定技能「造船・舶用工業」分野における採用の流れや必要な要件、求められる技能・日本語能力、さらに分野別協議会への加入手続きまで、実務に役立つポイントをわかりやすく解説します。外国人材の受け入れを検討している企業担当者の方は、ぜひご一読ください。
INDEX
 この記事の監修
この記事の監修きさらぎ行政書士事務所
行政書士 安藤 祐樹
きさらぎ行政書士事務所代表。20代の頃に海外で複数の国を転々としながら農業や観光業などに従事し、多くの外国人と交流する。その経験を通じて、帰国後は日本で生活する外国人の異国での挑戦をサポートしたいと思い、行政書士の道を選ぶ。現在は入管業務を専門分野として活動中。愛知県行政書士会所属(登録番号22200630号)
特定技能「造船・舶用工業」とは
特定技能とは、深刻な人材不足が続く16の特定産業分野で、一定の技能や経験を持つ外国人労働者の就労を可能にする制度です。この制度には、基礎的な知識・技能を持つ「特定技能1号」と、より熟練した技術が求められる「特定技能2号」が用意されています。
造船・舶用工業分野は、船舶の製造やその関連機械の生産を担う産業であり、日本の中でも特に広島県や愛媛県、香川県といった中四国エリアに事業所が集まっている点が特徴です。
受入れ人数と国籍
令和6年12月末時点で、造船・舶用工業分野の特定技能1号で働く外国人の在留人数は9,665人となっています。
この中で最も多い国籍は、フィリピンの5,235人、次いでインドネシアが1,946人、ベトナムが1,526人という構成です。
一方、特定技能2号の在留者は同時点で74人にとどまり、その内訳はフィリピン37人、ベトナム31人、インドネシアが1人、その他5人となっています。このように、特定技能2号は全体に占める人数がまだ少なく、今後の動向が注目されます。
特定技能「造船・舶用工業」の業務区分
特定技能制度では、それぞれの分野ごとに複数の業務区分が設けられており、技能試験の内容や従事できる仕事の範囲が分類されています。
造船・舶用工業分野では、造船、舶用機械、舶用電気電子機器の3つの業務区分が設定されています。ここからは、これら3つの区分ごとにどのような業務が含まれるのか、その詳細を確認していきます。
造船区分の主な業務
造船区分では、船舶の建造現場におけるさまざまな専門作業が業務の中心となっています。
具体的には、金属をつなぎ合わせる溶接や塗料を塗る塗装のほか、鉄骨の加工を担う鉄工、足場の設置を行うとび作業、配管の取り付けや修理、そして全体の船舶加工といった各工程が含まれています。
これらの作業は、どれも船の品質や安全性を左右する重要な役割を持ち、現場ごとに高度な技能と正確さが求められます。
造船区分に従事する外国人材は、こうした幅広い工程に携わりながら即戦力としての活躍が期待されています。
舶用機械区分の主な業務
舶用機械区分では、エンジンや各種機械設備の製造工程において専門的な技術が求められる業務が数多く含まれています。
具体的な作業としては、金属部品の接合を担う溶接や塗装、形状や強度を整える鉄工や仕上げ、そして精密な加工が必要となる機械加工や配管の取り付けが挙げられます。
また、鋳造や金属プレス加工、強化プラスチックの成形といった素材の特性を活かした工程も担当し、機械の維持や管理を行う機械保全、舶用機械加工といった工程まで幅広く従事します。
こうした多様な業務を担うことで、舶用機械の品質や耐久性の向上に寄与しており、現場では正確性の高い技術が重視されています。
舶用電気電子機器区分の主な業務
舶用電気電子機器区分における業務は、電気・電子分野の専門知識が求められる作業が幅広く含まれています。
たとえば、機械加工や金属プレス加工をはじめ、基板となるプリント配線板製造や電子機器組立てなど、繊細な精度が必要な工程を担当します。また、電気機器組立てや配管、設備全体の状態を維持するための機械保全や舶用電気電子機器加工なども重要な役割を担っています。
このような多岐にわたる業務を通じて、舶用電気電子機器の安全性や機能向上に寄与している点が大きな特徴です。
関連業務について
造船・舶用工業分野では、特定技能外国人も日本人と同じように関連する業務に付随的に従事することが認められています。ただし、関連業務のみを専ら担当することや、外国人だけが関連業務に従事することは制度上認められていません。
主な関連業務は以下の通りです。
読図作業
作業工程の管理
各種検査
機器、装置、工具の保守管理
機器や運搬機の運転操作
材料の管理や配置
部品の養生
梱包・出荷
足場の組立て・解体
廃材処理
資材や製品の運搬
入出渠(にゅうしゅっきょ)
清掃
なお、こうした作業はあくまで主業務に付随するものとされており、必要な範囲でのみ認められている点に注意が必要です。
特定技能1号と2号の違い
造船・舶用工業分野では、すべての業務区分で特定技能1号と2号が設けられています。
この両者には求められる技能水準や役割に違いがあるため、以下でその特徴を簡潔にご紹介します。
在留資格の違い
特定技能1号の在留資格は、通算5年間まで日本での滞在が認められていますが、家族の帯同は原則として許可されていません。また、永住権取得に必要な就労年数のカウント対象外となっている点も特徴です。
一方、特定技能2号は通算在留期間の上限が設けられておらず、長期的な滞在が可能となります。この資格では、配偶者や子どもの帯同が認められており、就労年数も永住許可申請時の要件として加算されます。
このように、2号の方が高い熟練度を求められ、より安定した生活を日本で送ることができる制度となっています。
| 1号と2号の在留資格の違い | ||
| 在留資格名 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験を必要とする技能 | 熟練した技能 |
| 日本語能力 | N4相当以上 | 基準なし |
| 実務経験 | 不要 | 監督者として2年以上の経験が必要 |
| 在留期間 | 通算5年が上限 | 上限なし(更新は必要) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者および子) |
| 永住申請の年数要件 | 就労年数の要件を満たさない | 5年の就労年数にカウントされる |
| 支援義務 | 10項目の義務的支援が必要 | 支援義務なし |
業務範囲の違い
特定技能1号の業務範囲は、監督者の指示を理解し、もしくは自身の判断で船舶の製造工程に関わる各種作業を行うことが求められています。
一方で、特定技能2号は複数の作業員を指揮・命令・管理しつつ、船舶の製造プロセス全体を統率しながら造船作業に従事する立場となります。
そのため、2号は1号よりも現場全体をまとめる責任の重い役割を担っており、より高い実務能力とマネジメント力が求められます。
なお、特定技能1号から2号へ移行するには、監督者として2年以上の実務経験が必要です。したがって、監督的な役割は2号に限らず、1号の段階でも制度上認められており、現場の運営体制や本人の適性に応じて、指導的な立場で働くことが可能です。
支援義務の有無の違い
特定技能1号の在留資格で働く外国人を受け入れる際、受け入れ機関には10項目の義務的支援の履行が求められます。
義務的支援の10項目は以下の通りです。
事前ガイダンスの実施
出入国時の送迎
住宅確保や生活に必要な契約の支援
生活オリエンテーションの実施
公的手続きの同行
日本語学習の機会提供
相談や苦情への対応
日本人との交流促進
転職時の支援(人員整理などの場合)
定期面談・行政機関への通報
このような支援を通じて、1号特定技能外国人が日本で安心して就業・生活できる環境を整えることが制度上の目的です。
なお、2号の受入れにおいては、支援義務はありません。
特定技能1号の在留許可要件
特定技能1号で日本に在留するためには、入管法令により定められた複数の要件を満たす必要があります。
ここでは、造船・舶用工業分野での1号の在留資格取得の際に必要な条件について分かりやすく解説します。
技能水準
特定技能1号の技能水準は、業務内容ごとに設けられた造船・舶用工業分野特定技能1号試験や技能検定3級の合格によって評価されます。
どちらの試験も特定技能の業務区分ではなく、より詳細な業務内容ごとに異なる試験科目(溶接、塗装、鉄工など)が設定されているため注意が必要です。
なお、技能実習2号を良好に修了しており、職種・作業が特定技能の業務に対応するものである場合は、技能試験が免除されます。
日本語能力
特定技能1号の日本語能力基準は、「国際交流基金日本語基礎テスト」または「日本語能力試験(N4以上)」の合格が基本的な要件となります。ただし、「日本語教育の参照枠」におけるA2相当以上と認められる水準であれば、同様に基準を満たしているものとされます。
なお、技能実習2号を良好に修了した場合は、修了した職種や作業に関わらず日本語に関する試験は免除されるため、受験不要です。
支援計画の策定と実施
特定技能1号で外国人を受け入れる場合、雇用する企業は法令に基づき支援義務を履行する必要があります。
また、この支援義務は、ただ履行することが求められるだけではなく、支援計画書を事前に作成し、在留資格の申請時に入管に提出する必要があります。
なお、こうした支援業務の実施は、出入国在留管理庁の名簿に登録された登録支援機関に委託することも認められています。受入れ側の体制や負担に合わせて外部機関の活用を検討することも重要です。
受入れ企業の事業内容
造船・舶用工業分野において特定技能1号の外国人を雇用できるのは、法令で定められた一定の事業を運営している企業・団体等に限られます。
受入れ対象となる事業は以下の通りです。
造船法第6条第1項の事業を行う事業者
小型船造船業法第2条第1項に定められた小型船造船業を営む者
その他造船・舶用工業分野に関係する業務を行う事業者です。
これらいずれかの事業内容に当てはまらない場合は、この分野での外国人材受入れは認められません。自社が該当するか判断できない場合は、国土交通省海事局船舶産業課に問い合わることで詳細を確認することができます。
受入れ企業が協議会の構成員であること
特定技能外国人を採用する企業は、造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入が義務付けられています。
この協議会への入会手続きは、一般的に15営業日ほどを要するため、在留資格申請の前に余裕を持って完了させておくことが重要です。協議会への加盟が確認できない場合には、在留許可申請そのものが認められないため注意が必要です。
協議会に対し必要な協力を行うこと
造船・舶用工業分野特定技能協議会は、受入れ企業への指導や現場の人手不足状況などの調査を担う役割を持っています。そのため、協議会から求められた調査や情報提供などの要請には、企業側は適切に協力することが義務付けられています。
仮に協力を拒否した場合、在留申請が不許可となる、あるいは将来的な受入れが認められなくなる可能性があるため注意が必要です。
国土交通省の調査または指導に協力すること
受入れ企業は、国土交通省による調査や指導が行われる際には、適切に応じなければなりません。
もしも調査や指導への協力を怠ると、その後の特定技能外国人の受入れが認められなくなるなど、不利益が生じる可能性があります。
このため、行政機関からの要請には迅速かつ適切に対応し、法令順守の姿勢を示すことが重要となります。
登録支援機関に委託する場合の追加要件
登録支援機関に特定技能1号の支援義務を委託する場合、その登録支援機関も造船・舶用工業分野特定技能協議会に加入することが求められます。
また、登録支援機関は協議会の求めに応じた調査や指導、国土交通省による調査などにも協力する責任を負います。
このため、委託先の登録支援機関の選定にあたっては、適切に義務を履行してくれる信頼できる機関を選ぶことが重要です。
特定技能2号の在留許可要件
特定技能2号の在留資格を取得するには、より高度な技能や経験が求められるため、1号と比べて難易度の高い要件が設定されています。
ここでは、造船・舶用工業分野で特定技能2号の在留許可を受けるための要件について説明します。
技能水準
特定技能2号の在留資格を取得するためには、造船・舶用工業分野特定技能2号試験に合格するか、技能検定1級に合格する必要があります。
特定技能2号は、複数の作業員を指揮・命令・管理しながら業務に従事することが必要なため、1号の試験と比較して、より難易度の高い知識・技能水準が求められます。
実務経験
特定技能2号の在留資格を取得するためには、監督者としての役割を果たしながら造船・舶用工業分野の業務に2年以上従事した実務経験が求められます。
この監督者とは、グループ長やチームリーダーのように、複数の従業員に対して日常的に業務の指示や工程管理を行う立場を指します。また、実務経験として認められる内容には、作業の割り振りや進捗管理、製品の品質確認、安全対策のための設備点検、作業計画の立案など、幅広い責任を伴う業務が含まれます。
このように、現場での実践力とマネジメント経験を積み重ねていることが、2号資格取得の重要な条件となっています。
受入れ企業が満たすべき要件
特定技能2号で外国人を採用する場合、受入れ企業に求められる事業内容や造船・舶用工業分野特定技能協議会への加入といった基準は1号の場合と同様です。
ただし、2号では特定技能1号で義務付けられていた支援計画の策定や支援業務の実施義務がなくなり、企業側の負担が大きく軽減される点が特徴です。
このように、事業内容に関する基準は変わりませんが、実務面でのサポート義務が緩和されることとなります。
まとめ
この記事では、特定技能「造船・舶用工業」分野の制度概要や業務内容、受入れ企業に求められる条件などについて解説しました。制度の仕組みや申請の際に必要となる要件などは、実際に外国人材を雇用する現場においても必要な知識となります。
造船・舶用工業分野で特定技能人材の活用を検討している方は、最新の制度や手続き方法を確認し、余裕を持って準備を進めることが重要です。疑問や不安が残る場合は、専門機関や行政窓口へ早めに相談し、正確な情報に基づいて計画を立てましょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。