「特定技能外国人を雇いたいけど、住居提供は必須なの?」
「住居を提供する場合、どんな基準や条件を満たせば良いのかわからない」
このような悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか?
特定技能外国人の受け入れ企業は、住居の確保に関して支援義務があります。
社宅や寮の提供ではなくとも、賃貸物件の情報提供や契約手続きのサポートなど、外国人が安心して住める環境を整えなければいけません。
また、住居を提供する際は面積・設備の基準や適正な家賃設定を守る必要があります。
本記事では、特定技能外国人への住居提供の支援義務や、住居に関するルールと基準について解説していきます。また、住居支援を円滑に進めるためのコツについても紹介しているので参考にしてみてください。
特定技能外国人の
採用を検討したい方へ
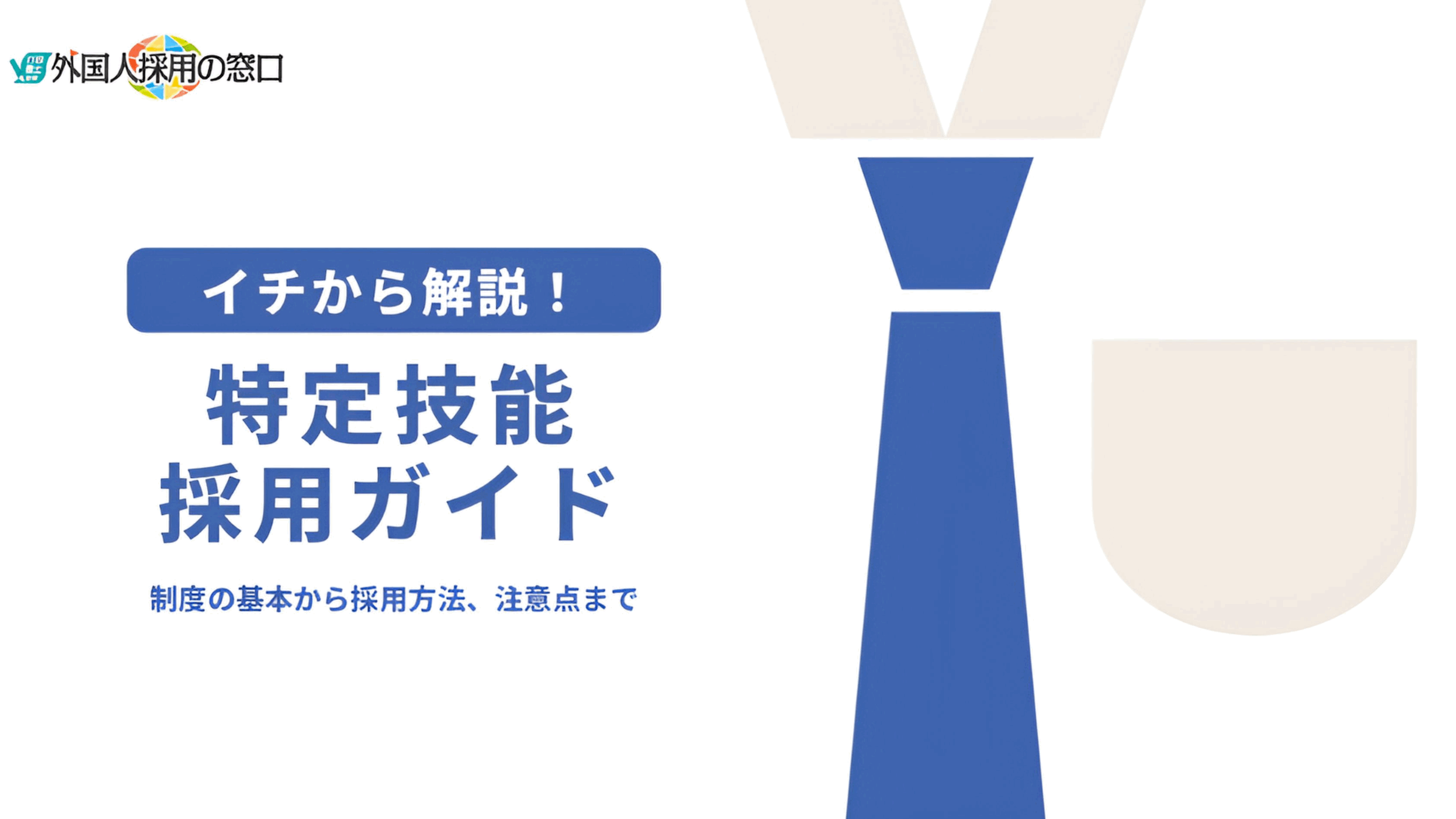
この資料でわかること
- 特定技能制度で従事できる分野
- 在留資格「特定技能1号」の取得条件
- 特定技能1号外国人を雇用する流れ
- 登録支援機関の役割と仕事内容
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人・外国人含め全国で「300社・5,000件」以上の採用支援実績を持つ人材採用コンサルタント。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用にも取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
特定技能外国人の住居提供は企業側の義務?

特定技能外国人の住居提供が企業の義務かどうかは、特定技能1号か2号かによって以下のように異なります。
- 特定技能1号への住居提供は義務的支援
- 特定技能2号への支援は対象外
順番に見ていきましょう。
特定技能1号への住居提供は義務的支援
特定技能1号の外国人に対する住居確保支援は、企業が実施すべき義務的支援の一つとして定められています。
出入国在留管理庁が定める義務的支援は全部で10項目あり、住居に関する支援は「3. 住居確保・生活に必要な契約支援」として規定されています。
義務的支援の10項目は以下の通りです。
義務的支援の10項目
- 事前ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 住居確保・生活に必要な契約支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続等への同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進
- 転職支援(人員整理等の場合)
- 定期的な面談・行政機関への通報
参考:1号特定技能外国人支援・登録支援機関について|出入国在留管理庁
住居確保支援では、賃貸契約時の連帯保証や家賃滞納時の対応、住居に関する各種手続きのサポートなどが求められます。
義務的支援を自社で対応するのが困難な場合は、登録支援機関に委託もできます。登録支援機関とは、企業からの委託を受けて、特定技能1号外国人の支援義務を代行する機関です。
「外国人採用の窓口」では、希望するエリアの登録支援機関を一括検索できるサービスを提供しています。
でき、貴社のニーズを満たした最適なパートナーを見つけることができます。無料相談も受け付けていますので、特定技能外国人に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
なお、技能実習生に対しても住居確保が義務付けられています。詳しくは以下の記事で解説していますので参考にしてみてください。
【関連記事】
技能実習・特定技能の『住居』は会社が用意するの?|家賃負担や部屋基準を解説 | 外国人採用の窓口
特定技能(1号・2号)受け入れの条件と企業側の義務について解説 | 外国人採用の窓口
特定技能2号への支援は対象外
特定技能2号外国人は義務的支援の対象外のため、企業は住居提供・確保に関するサポートをしなくても問題ありません。
特定技能2号は、特定技能1号での経験を経て、より高度な技能や知識を習得した外国人が取得する在留資格です。
そのため、日本での生活や業務に十分慣れており、特定技能1号外国人のような手厚い義務的支援は不要とされています。
特定技能2号外国人は、住居の確保についても自立して対応できる能力があると判断されるため、企業側に住居提供の義務は課せられていません。
【関連記事】
特定技能2号とは?在留資格取得の条件、受け入れ可能な業種、在留可能な期間などを解説
外国人採用の窓口では「特定技能外国人採用ガイド」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
特定技能外国人の
採用を検討したい方へ
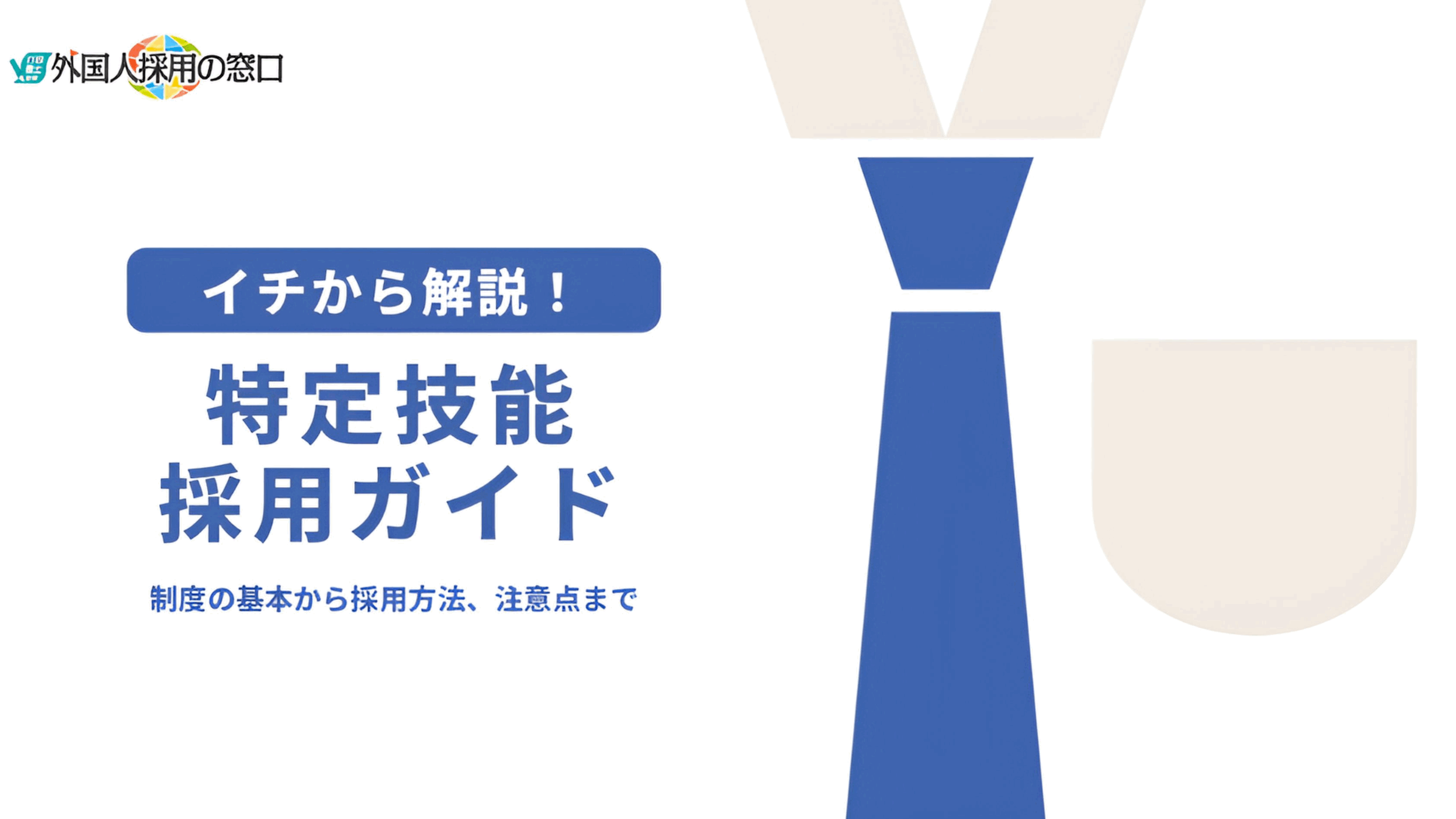
この資料でわかること
- 特定技能制度で従事できる分野
- 在留資格「特定技能1号」の取得条件
- 特定技能1号外国人を雇用する流れ
- 登録支援機関の役割と仕事内容
特定技能1号外国人に住居提供する方法

特定技能1号外国人に住居提供する方法は以下の3つの方法があります。
- 一人暮らしの賃貸契約をサポートする
- 企業が物件を借り上げて提供する
- 社宅や寮を提供する
それぞれ詳しく解説していきます。
一人暮らしの賃貸契約をサポートする
特定技能1号外国人が一人暮らしするための、賃貸物件の契約をサポートするのも義務的支援の一つです。
賃貸契約サポートには以下の内容が該当します。
賃貸契約サポート
- 賃貸物件の情報提供
- 収入や希望条件に合った物件の選定
- 立地・周辺環境の説明
- 不動産会社の紹介
- 物件見学や契約手続きに同行
- 契約書の内容説明
- 必要書類の準備
賃貸契約では連帯保証人が必要な場合が多いため、企業が連帯保証人となったり、保証会社の利用をサポートしたりといった支援も含まれます。
賃貸物件を探す際は、外国人対応に慣れた会社を選ぶと、契約手続きがスムーズに進みやすいです。
企業が物件を借り上げて提供する
特定技能1号外国人の住居を企業が直接確保する方法として、企業が物件を借り上げて提供する場合もあります。
この方法では、企業が賃貸物件を法人名義で契約し、特定技能外国人に貸し出す形で住居を提供します。
企業が物件を借り上げるメリット
企業にとっては、複数の特定技能外国人を同時に受け入れる際に効率的です。
外国人材にとっても、個人で賃貸契約を結ぶ際の言語や手続きの負担が軽減され、安心して入居できます。
ただし、企業は契約者として物件の管理責任が発生するため、家賃の支払いや物件の維持管理などの業務にも対応する必要があります。
社宅や寮を提供する
社宅や寮の提供は、企業が所有または管理する住居施設を特定技能外国人に貸し出す方法です。
企業が自社で保有する社宅や寮がある場合、外国人材の住居として活用できます。
社宅や寮を提供するメリット
社宅や寮には住居費を抑えられたり、同じ職場で働く同僚との交流が深められたりといった利点があります。
また、企業側も住居に関する管理が一元化でき、緊急時の対応やサポートがしやすくなります。
一方で、プライバシーの確保や生活ルールの設定など、集団生活に配慮した環境整備が必要です。
以下の記事では、義務的支援の一つである生活オリエンテーションについて解説しています。規則や注意点を紹介しているので、参考にしてみてください。
【関連記事】
特定技能の「生活オリエンテーション」を解説!実施内容・時間・注意点など【事例付き】
特定技能外国人が入社する前に必ず確認すべき事項とは?
特定技能の住居に関する3つのルール
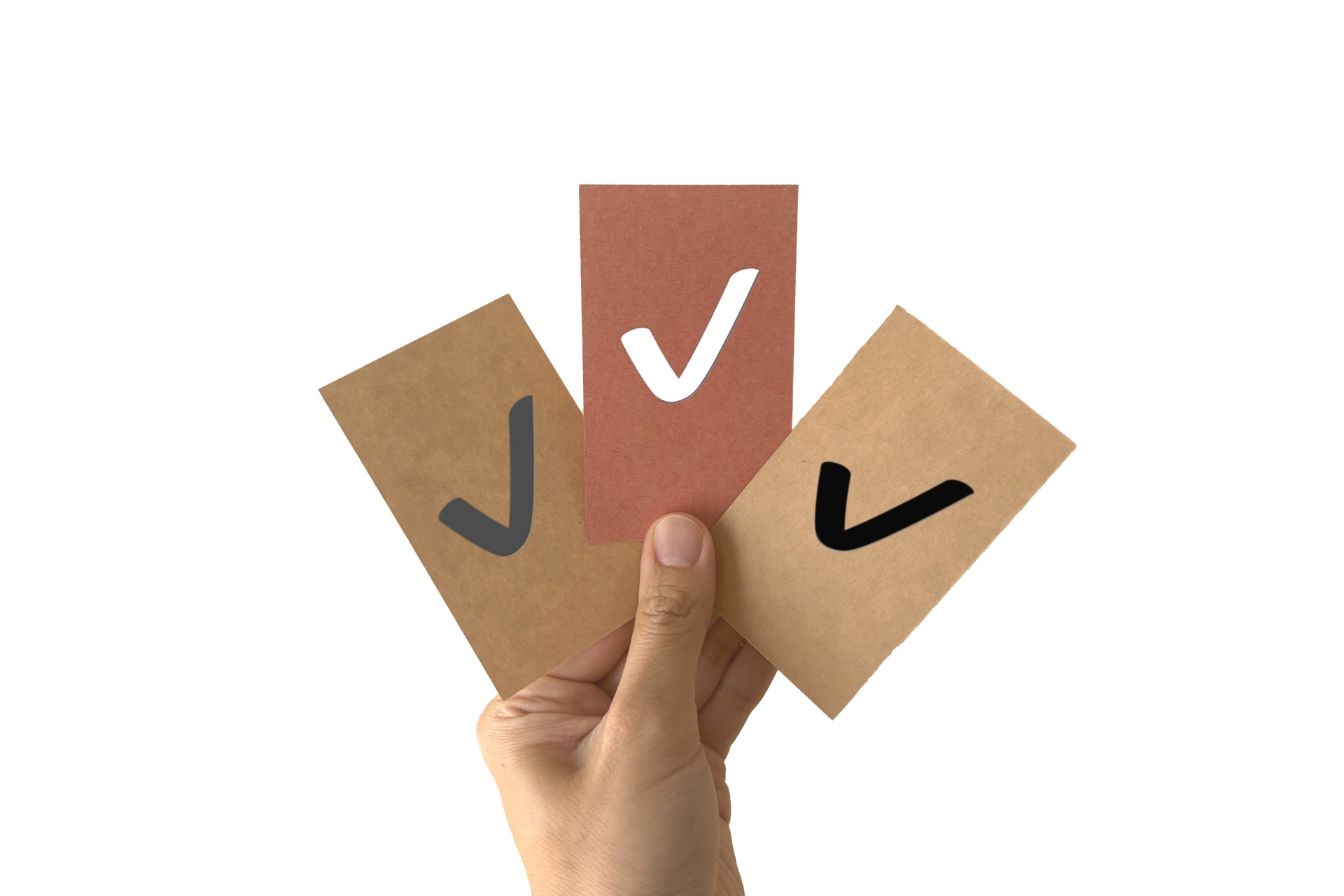
特定技能外国人に住居を提供する際は、以下の3つのルールを守る必要があります。
- 住居の広さについて
- 家賃の上限額について
- 敷金・礼金の負担について
一つずつ見ていきましょう。
住居の広さについて
特定技能外国人に提供する住居は、1人当たり7.5㎡以上(約4.5畳以上)の床面積を確保する必要があります。
この基準は、外国人材が健康で文化的な生活を送るために設けられた最低限の居住面積です。
複数の特定技能外国人がシェアハウス形式で同じ住居を利用する場合も、同様の基準が適用されます。計算方法は以下の通りです。
広さの計算方法
部屋全体の床面積を、居住人数で割った値が7.5㎡以上となることが条件です。
この面積基準を満たさない住居の提供は認められないため、物件選定の際は十分な注意が必要です。
また、共用部分(キッチン、浴室、トイレなど)の面積は床面積に含まれないため、居住用の個人スペースが基準を満たしているかといった視点で、物件を選びましょう。
家賃の上限額について
特定技能外国人から徴収する家賃は、実費相当額を上限とする規定があります。
この規定は特定技能1号・2号の両方に適用され、企業が住居費で利益を得ることを防ぐ目的で設けられています。借り上げ物件と自己所有物件の家賃上限は以下の表の通りです。
| 物件 | 家賃上限 |
| 社宅・寮 | 適正な家賃を設定する ※近隣の類似物件の家賃相場を参考 |
| 借り上げ物件 | 企業が実際に支払っている家賃額が上限 |
光熱費や管理費といった家賃以外の費用は、外国人本人に請求できます。しかし事前に合意を得た上で請求することが条件となっています。
敷金・礼金の負担について
敷金や礼金などの住居契約時の初期費用については、企業が負担する法的義務はありません。ただし、多くの企業では外国人材の経済的負担を軽減するため、初期費用の一部または全額を補助するケースが見られます。
初期費用の負担については、雇用契約書や支援計画書に明記し、外国人に事前に合意を得ておく必要があります。
企業が初期費用を負担する場合でも、退去時の原状回復費用や、故意・過失による損害についての取り決めをしておくと、後のトラブルを防げます。
特定技能外国人に住居を提供するときの注意点

特定技能外国人に住居を提供する場合の注意点は、以下の3つです。
- 企業が利益を得てはならない
- 給与控除は外国人に理解させなければならない
- 自治体へ届け出なければならない
順番に解説します。
企業が利益を得てはならない
住居の提供にあたって、受け入れ企業が利益を得る行為は禁止されています。
家賃の上限額は、実際にかかった費用を居住人数で割った金額以下に設定します。
具体例
例えば、月額8万円の物件に2人の特定技能外国人を住まわせる場合、1人当たりの家賃は4万円以下でなければならず、それを上回る金額の徴収はできません。
企業が控除している家賃が実費を超えた不当請求とみなされた場合、受け入れ機関としての欠格事由に該当する可能性があります。
欠格事由に該当すると、特定技能外国人の受け入れができなくなるため、運用要領に基づいた家賃設定をしましょう。
また、光熱費や管理費などの費用についても、請求できるのは実費相当額が上限となります。
給与控除は外国人に理解させなければならない
家賃や管理費・光熱費などを給与から控除する場合は、雇用条件書の写しに費用名と金額を明記する必要があります。
外国人材が控除内容を正確に理解できるよう、以下の項目を分かりやすく記載しましょう。
控除に関して記載する項目
- 控除する費用の名称(家賃、光熱費など)
- 控除金額
- 控除の算出方法
- 控除時期や頻度
雇用条件書は外国人の母国語または理解できる言語で作成し、内容について十分な説明が必要です。
控除内容について外国人材から質問があった場合は、丁寧に回答し、疑問点を解消してから雇用契約を結びましょう。
自治体へ届け出なければならない
特定技能外国人の受け入れ前に、管轄の自治体へ協力確認書の届け出が必要です。
協力確認書は、特定技能外国人が地域社会で円滑に生活できるよう、自治体と企業が連携するために設けられた書類で、2025年4月から原則として義務化されています。
協力確認書の提出は以下のタイミングで提出します。
| 特定技能の受け入れ状況 | 提出のタイミング |
| 初めての受け入れ企業 | ・外国人との特定技能雇用契約の締結後 ・在留資格認定証明書または在留資格変更許可を申請する前 |
| すでに雇用している企業 | ・初めて在留資格変更または在留期間更新を申請する前 |
自治体への協力確認書を提出後に、在留資格変更・更新の申請となります。
外国人採用の窓口では「特定技能外国人の受入れ後のサポート体制」の資料を無料配布しております。30秒でダウンロードできますので、以下のボタンをクリックの上、どうぞお受け取りください。
外国人採用後の
サポート体制を整えたい方へ
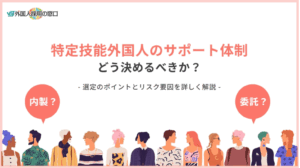
この資料でわかること
- 義務的支援の内容
- 自社対応と外部委託の選択肢
- 登録支援機関の委託状況
- 支援業務における注意点
特定技能外国人の住居支援を円滑に進めるコツ

特定技能外国人への住居支援を円滑に進めるコツは、以下の3つです。
- 起こりうるトラブルの対策を事前に考えておく
- 金銭面の条件を明確にしておく
- 登録支援機関に支援を委託する
企業と外国人の両方が安心できる住居支援を進めましょう。
起こりうるトラブルの対策を事前に考えておく
住居支援では、文化や生活習慣の違いから生じる以下のようなトラブルへの対策を事前に考えておきましょう。
| トラブル | 例 |
| 騒音 | ・複数人でのパーティー ・大声での電話、会話・深夜の洗濯機や掃除機使用 |
| ゴミ出し | ・分別できていない ・日時を守らない |
| 賃貸契約 | ・契約者と違う人が入居 ・契約人数より多い人数で同居 ・退去時の修理費用が理解できていない |
近隣住民とのトラブルを防ぐための、ゴミ出しや騒音に関する注意事項の説明は義務的支援です。地域ごとのルールも合わせて、外国人が理解できるように丁寧に指導する必要があります。
賃貸契約違反や家賃滞納といった問題が発生した場合の対応手順も、あらかじめ定めておくとスムーズな解決が可能です。
特定技能1号外国人に対しては、定期的な面談を通じて住居に関する困りごとを聞き取り、小さな問題のうちに解決すると、トラブルを未然に防げます。
金銭面の条件を明確にしておく
住居に関する費用負担については、外国人が理解できるよう説明した上で、条件を明確にしておきましょう。
例えば、以下の項目について外国人と企業側が、どこまで負担するのかの明確な線引きがあれば支援がスムーズに進みます。
費用負担の項目
- 家賃
- 敷金・礼金
- 光熱費(電気、ガス、水道)
- インターネット回線費用
- 火災保険料
- 生活必需品(家具、家電、寝具など)
- 日用品
これらの条件を雇用条件書や支援計画書に記載し、外国人が理解できる言語で説明することが求められます。
金銭面の条件が明確になっていれば、外国人は安心して生活の準備を進められ、企業側も予算管理がしやすくなります。
また、費用の支払い方法や時期についても事前に合意しておくと、後々のトラブルを防げます。
登録支援機関に支援を委託する
住居支援を自社で対応するには、通常業務以外に人件費や労力・時間といったコストがかかります。自社での対応が難しい場合には、登録支援機関に支援を委託することもできます。
登録支援機関とは
登録支援機関とは、企業からの委託を受けて、特定技能1号外国人の支援業務を請け負う専門機関です。
登録支援機関は特定技能外国人の支援に関する豊富な経験とノウハウを持っており、住居確保から契約手続きまで一貫したサポートを提供できます。
登録支援機関を選ぶ際は、支援実績や対応エリア、サポート内容を照らし合わせ、自社のニーズに合った機関かどうかを検討しましょう。
数多く存在する登録支援機関の中から気になる機関を探し出すのは大変です。自社の条件に合った登録支援機関をお探しの際は「外国人採用の窓口」をご利用ください。
ご希望のエリアや雇用したい国籍・在留資格などの条件で検索し、最適な機関をご紹介できます。無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
【関連記事】
登録支援機関とは?申請方法と失敗しない選び方のポイントを解説
『特定技能外国人』の受け入れ費用、登録支援機関の料金相場を解説【費用項目一覧表あり】
特定技能外国人の雇用をご検討中なら「外国人採用の窓口」にご相談ください

「特定技能外国人の住居支援について専門家のアドバイスが欲しい…」
「住居提供の義務や基準について相談したいが、どこに問い合わせれば良いかわからない…」
「特定技能外国人の支援体制を専門機関に委託したい…」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、外国人採用に特化した登録支援機関や行政書士事務所、人材紹介会社を一括で無料検索できるサービスを提供しています。
条件検索できるため、あなたの業界・業種に精通した特定技能の住居支援に強いパートナー企業とのマッチングをお手伝いします。
当サイトで利用できる無料サービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けているので、特定技能外国人の住居支援に関するお悩みがある方もお気軽にお問い合わせください。
特定技能外国人の住居確保における要件を把握して受け入れ準備をスムーズに進めよう

特定技能外国人への住居提供は、1号外国人の義務的支援に該当します。
特定技能1号外国人に対しては住居確保支援が必須であり、賃貸契約のサポートから物件の借り上げ、社宅・寮の提供まで複数の方法で対応できます。
住居提供の際は、1人当たり7.5㎡以上の面積確保や実費相当額での家賃設定など、法令で定められた基準を遵守しなければなりません。
また、企業が利益を得ることの禁止や給与控除の明確化、自治体への届け出など、注意すべきポイントも多く存在します。
とはいえ、住居支援に関する法令の理解や適切な物件選定、トラブル対応など、企業単独での対応が難しいケースも起こりえます。
外国人材が安心して生活できる住環境を整えるためには、登録支援機関などの専門機関への委託を検討し、計画的に特定技能外国人の受け入れ準備を進めましょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。


