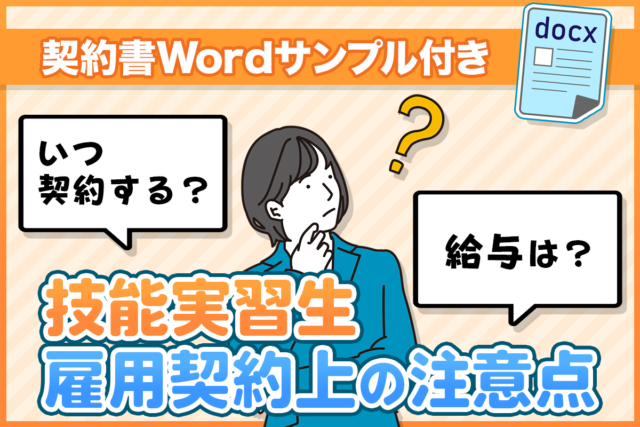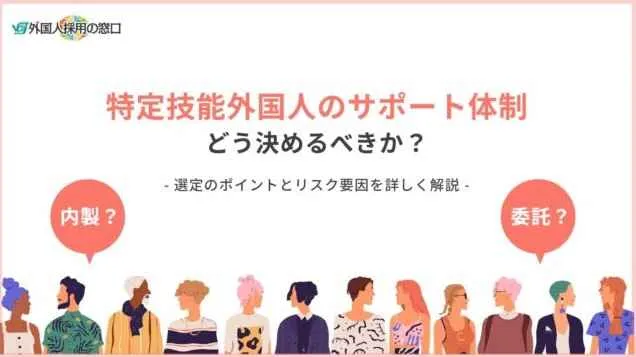「技能実習生を受け入れるとき、雇用契約ってどう結べばいいの?」
「雇用契約書の記入例が知りたい」
このような疑問を持つ採用担当者の方は多いでしょう。
技能実習生を受け入れる企業にとって、雇用契約は必須の手続きです。
契約を結ぶ際は、外国人向けの雇用契約書を作成したり、外国人が理解できる言語で契約内容を説明したりと、日本人と異なる契約手続きが求められます。
適切な契約を結ばなければ、技能実習生の受け入れが認められない可能性があります。また、実習生が内容を理解しないまま手続きを進めるとトラブルにも発展しやすいです。
技能実習生の円滑な受け入れを実現するためにも、正しい雇用契約の進め方を覚えましょう。
本記事では、技能実習生との雇用契約の結び方について徹底解説します。雇用契約書の記入例や作成時の注意点も紹介するので、参考にしてみてください。
弊社「外国人採用の窓口」では、外国人雇用に関する相談を無料で受け付けております。お悩みがございましたら、以下のフォーム・電話にてお気軽にお問い合わせください。
 この記事の監修
この記事の監修(株)アルフォース・ワン 代表取締役
山根 謙生(やまね けんしょう)
日本人、外国人含め「300社・5,000件」以上の採用支援実績。監理団体(兼 登録支援機関)に所属し、技能実習生・特定技能外国人の採用に取り組んでいる。外国人雇用労務士、外国人雇用管理主任者資格、採用定着士認定保有。(一社)外国人雇用協議会所属。
INDEX
技能実習生の雇用契約において大事なポイント7項目

技能実習生の雇用契約において大事なポイントは以下の7項目です。
ポイント
- 雇用契約書の内容
- 雇用契約の期間
- 雇用契約書の様式【記入例あり】
- 雇用契約を結ぶタイミング
- 雇用契約書の締結方法
- 雇用契約の条件が変更した場合の対応
- 雇用契約が解約した場合の対応
一ずつ解説するので、雇用手続きの全体像を掴んでいきましょう。
技能実習制度の概要からおさらいしたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。
【関連記事】
技能実習生を受け入れられる企業の条件は?
雇用契約書の内容
雇用契約の締結にあたり、以下の8つの項目は必ず明記しなければいけません。
記載内容
- 就業場所
- 従事する業務内容
- 契約期間
- 賃金、支払い方法、時期等を含む事項
- 始業、終業時刻や休日休暇に関する事項
- 時間外労働の有無
- 退職に関する事項
- 宿泊施設に関する事項
雇用契約書は、外国人が理解できる言語で作成する義務があります。外国人技能実習機構のサイトより、数ヵ国語に翻訳された雇用契約書のサンプルが入手可能です。
8項目めの宿泊施設に関する事項は、技能実習生特有の内容です。宿泊施設の規定や住居を確保する際の注意点は以下の記事で解説しているので、あわせてご覧ください。
【関連記事】
技能実習・特定技能の『住居』は会社が用意するの?|家賃負担や部屋基準を解説
雇用契約の期間
技能実習生は在留資格「技能実習」で滞在するため、雇用契約期間は在留資格の在留期間を超えて設定できません。
在留資格の更新や変更に合わせて、契約期間も見直す必要があります。
在留資格の区分と在留期間は以下のとおりです。
| 区分 | 在留期間 |
| 技能実習1号 | 最長1年 |
| 技能実習2号 | 最長2年 |
| 技能実習3号 | 最長3年 |
更新のたびに実習計画の認定申請と在留資格更新申請が必要です。
更新手続きを誤ると、オーバーステイ(不法残留)に該当し、企業側は法的責任を問われる可能性があります。
雇用契約書の様式【記入例あり】
技能実習生を受け入れる際には、日本人労働者と同様に労働契約書を作成します。
外国人技能実習機構(OTIT)の公式サイトには、数ヵ国対応の「翻訳版雇用契約書」の雛形が掲載されており、無料でダウンロードが可能です。
以下は企業側の雇用条件を記載する際の記入例です。
| 項目 | 記入例 |
| 契約期間 | 2025年4月1日~2026年3月31日 |
| 業務内容 | 機械加工業務 |
| 就業場所 | 株式会社○○工場(東京都○○区△△町1-1-1) |
| 労働時間 | 9:00~18:00(休憩1時間)、週40時間 |
| 休日 | 土日・祝日 |
| 基本給 | 180,000円 |
| 支払日 | 毎月25日 |
| 住居 | 寮を提供(家賃10,000円/月) |
| 社会保険 | 健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険加入 |
| 契約更新 | 在留資格の更新に基づき1年ごとに判断 |
実際の契約書作成時は、自社の就業規則や労働条件に合わせて各項目を調整してください。
以下の記事では、外国人雇用における契約書について詳しく解説しています。ダウンロード可能な雇用契約書のテンプレートや記載例も紹介しているので、参考にしてみてください。
【参考記事】
【無料DL】外国人を雇用する際の雇用契約書サンプル&解説|作成ポイント、法律、トラブル事例も
雇用契約を結ぶタイミング
技能実習生の雇用契約は、入国前に必ず締結することが法律で義務づけられています。
採用が決まったら雇用契約書を作成し、実習生本人と企業が合意した上で署名・押印をおこないます。
さらに入国後には、改めて契約内容を母国語で説明し、実習生が十分に理解した状態で契約を確認しましょう。
雇用契約書の締結方法
雇用契約書は、日本語と実習生の母国語で二言語作成します。契約の際には実習生本人と企業がそれぞれ署名・押印し、双方が1部ずつ保管しましょう。
監理団体もコピーを保管しておくことで、契約内容に関する誤解やトラブルが発生した際に速やかに確認でき、実習生の権利保護や企業のリスク回避に役立ちます。
なお、実習生が印鑑を持っていない場合は署名で代用可能です。
契約内容を十分に理解してもらうため、重要な部分は通訳を依頼するなど、必ず外国人が理解できる言語で説明します。
雇用契約の条件が変更した場合の対応
労働条件(賃金、勤務時間、勤務地など)を変更する場合は、必ず新しい雇用契約書を作成し直す必要があります。
変更内容を母国語または理解できる言語で説明し、変更の理由や時期、影響を具体的に伝えましょう。
誤解や不安を避けるため、通訳や監理団体の立ち会いを推奨します。
監理団体とは、企業からの委託を受けて、実習生の生活面・就労面をサポートする組織です。
実習生の生活や労働環境に問題があった場合の相談窓口にもなり、契約変更時のサポートもおこなっています。
数ある監理団体の中から適切な団体を探すのが難しい場合は「外国人採用の窓口」へご相談ください。当サービスでは監理団体の一括検索サービスを無料で提供しています。
無料相談も受け付けておりますので、技能実習に関するお悩みがございましたらお気軽にお問い合わせください。
雇用契約が解約した場合の対応
雇用契約を解約する際は労働基準法や入管法に基づいた手続きが求められます。
実習生には母国語など理解できる言語で丁寧に説明し、解約通知や退職届を必ず書面で交わします。
その後、監理団体や出入国在留管理庁、ハローワークへ届出をおこない、必要に応じて帰国の手配を進めましょう。
雇用契約書を作成する際の注意点

雇用契約書は、外国人技能実習機構(OTIT)の参考様式に準拠して作成されるのが基本であり、面接時には日本から印刷して持参するケースが一般的です。
海外現地では契約書に不備があってもその場で修正することが難しい場合もあるため、事前に内容を確認しておきましょう。
雇用契約書を作成する際、注意すべき点は3つです。
契約書を作成する際の注意点
- 給与額は日本人と同等以上にする
- 入国審査の許可が得られているか確認する
- 学歴や職歴の整合性を取る
一つずつ詳しく紹介します。
給与額は日本人と同等以上にする
技能実習生に支払う給与の金額は、日本人と同等以上でなければいけません。
技能実習生にも技能実習生にも労働基準関係法令が適用され、最低賃金法や同一労働同一賃金の原則が反映されるためです。
実際には、技能実習生と同じ業務を行っている日本人と比較して同等の給与を設定します。技能実習生が1年目相当であれば1年目の日本人、3年目相当なら3年目の日本人従業員と同等の設定となります。
学歴や職歴の整合性を取る
前提として、技能実習制度で受け入れを行う業務内容は、受け入れる実習生の職歴と関連性が求められます。
そのため、履歴書に記載されている学歴や職歴の整合性、受け入れ企業で実際に行う業務との整合性がなければ在留資格の許可は下りません。
技能実習生の経歴と実習内容が適切にマッチしているか事前によく確認しましょう。
入国審査の許可が得られているか確認する
受け入れ企業側が実習生の採用を決めたとしても、入国可否の最終判断をするのは出入国在留管理庁です。
つまり、面接をして雇用契約書を結んだとしても、必ず入国が許可されるわけではありません。
雇用契約は在留資格の許可が得られた場合のみ有効であり、もし在留資格の許可が得られなかった場合には内定取り消しとなることを実習生候補者にも理解してもらいましょう。
以下の関連記事では、外国人労働者の受け入れ条件やメリット、注意点を詳しく紹介しています。外国人労働者の募集方法や受け入れるまでの流れも解説しているため、参考にしてみてください。
【関連記事】
【最新】外国人労働者の受け入れ条件とは?雇用時の注意点も解説
雇用契約の内容を候補者に説明する時の注意点

雇用契約書の内容以外にも、外国人採用ならではの注意点が3点あります。
説明する際の注意点
- 母国語または理解できる言語で雇用契約書を準備する
- 雇用契約時は通訳者に同席してもらう
- 社会保険料などの控除について説明する
詳しく解説していきます。
母国語または理解できる言語で雇用契約書を準備する
契約書は、母国語または理解できる言語で翻訳されたものを用意します。
通常、企業には普段から使用している雇用契約書のひな形があるため、日本語版の契約書を翻訳して作成すると良いでしょう。
日本語の文章の下に翻訳を追記する「対訳形式」でも問題なく運用できます。
また、自社で翻訳対応が難しい場合には、監理団体に依頼して翻訳済みの契約書を準備してもらうことも可能です。
契約書は単なる書類ではなく、実習生が安心して働くための大切な理解ツールとなるため、母国語での説明を欠かさないことがトラブル防止につながります。
雇用契約時は通訳者に同席してもらう
雇用契約の場では、翻訳された契約書を用意していても、外国人技能実習生から追加の質問が出ることがあります。
内容を過不足なく伝えるために、通訳者にも一緒に同席してもらいましょう。
通訳者が間に入ることで、契約条件の理解不足や不安を防ぎ、後々のトラブルを避けることにつながります。
また、雇用契約の説明に限らず、前段階のオリエンテーションや面接の時点から同じ通訳者が立ち会うのが一般的であり、実習生にとっても安心感が生まれます。
企業にとっても通訳のサポートは、契約手続きの正確性を高めることができるため、効果的です。
社会保険料などの控除について説明する
給与から差し引かれる社会保険料や税金については、外国人技能実習生にとって非常に理解しにくい部分です。
特に、東南アジアなどの国々では給与が現金払いで支給されることが多く、所得税や社会保険といった仕組みに馴染みがありません。
そのため「なぜ手取りが大幅に減るのか」が分からず、不満や不安を抱きやすいのです。
こうした問題を防ぐためには、社会保険の仕組みを丁寧に説明し、控除金額と手取り額の目安を事前に伝えることが必要です。
また、2年目から発生する住民税についても必ず説明しましょう。1年目は免除されるため、2年目以降に急に手取りが減ると「なぜ控除額が増えたのか」と不安を抱くケースが多いからです。
社会保険料と同様に、あらかじめ予想される控除額を伝えておくことで安心して働いてもらえます。
外国人採用の窓口では「特定技能外国人の受入れ後のサポート体制」を無料配布しております。技能実習生を受け入れる際にも役立つ内容です。
30秒でダウンロードできますので、以下の画像をクリックの上、どうぞお受け取りください。
技能実習生の雇用をご検討中の方は「外国人採用の窓口」をご利用ください

「技能実習生の雇用手続きをサポートしてほしい…」
「雇用契約書の内容が適切かどうか相談したい」
「信頼できる監理団体はどのように見つけたらいいの?」
このようにお悩みなら「外国人採用の窓口」にご相談ください。
弊社は、監理団体や外国人向けの人材紹介会社を一括検索できるサービスを提供しています。
条件検索できるため、あなたの業界・業種に精通した技能実習の就労支援に強い監理団体とのマッチングをお手伝いします。
【完全無料】当サイトで利用できるサービス
- 外国人採用のご相談
- 監理団体のご紹介
- 登録支援機関のご紹介
- 外国人紹介会社のご紹介
- 行政書士事務所のご紹介
無料相談も受け付けているので、技能実習生に関するお悩みがある方もお気軽にお問い合わせください。
技能実習生の雇用契約書に関するよくある質問

技能実習生の雇用形態はなんですか?
技能実習生の雇用形態は、原則として「常用雇用のフルタイム労働者(有期雇用契約)」です。
入国後の最初の1ヵ月間は講習期間となり、この間は雇用関係に入らず生活指導や日本語教育を受けます。
講習終了後は受け入れ企業(実習実施者)との間で正式に雇用契約を結び、日本人労働者と同様の雇用形態です。
実習実施者は技能実習生を正社員(常用雇用)として雇用し、労働保険や社会保険に必ず加入させる義務があります。
雇用条件通知書の作成も必要ですか?
技能実習生であっても雇用条件通知書の作成は必須です。
労働基準法第15条では、労働契約を結ぶ際に「労働条件を書面で明示すること」が使用者に義務付けられています。
これは日本人労働者に限らず、技能実習生にも同様に適用されます。
雇用条件通知書には、賃金・労働時間・休日・契約期間などの基本的な条件を具体的に記載し、技能実習生が内容を理解できるよう母国語または理解できる言語で翻訳することが望ましいです。
雇用契約書とセットで交付しておくことで、条件の認識違いやトラブルを防止できます。
技能実習生の雇用契約における条件や書き方を理解して手続きを進めよう

技能実習生の雇用契約では、労働条件の明示や賃金規定、社会保険加入、住居提供など、日本人労働者と同等の条件を整えることが法律で求められています。
契約書は必ず日本語と母国語で二言語作成し、署名・押印後は双方で保管し、監理団体にも共有しておくと安心です。
さらに、控除や住民税など給与から差し引かれる内容についても事前に説明しておくとトラブル防止につながります。
雇用契約における条件や書き方を理解し、技能実習生も企業も安心して契約の手続きを進めましょう。
あなたの採用活動をサポート!
外国人採用の窓口は
外国人採用に特化したBtoBマッチングサービスです。
日本全国 10,000社 を超える
監理団体・登録支援機関・外国人紹介会社を一括で検索し
簡単に比較・相談・検討することができます。
「外国人の採用方法が分からない」
「技能実習生や特定技能外国人の依頼先が分からない」
「監理団体や会社がたくさんあって探すのが大変」
「手続きや申請が複雑で自社では行えない」
といったお悩みのある方は
今すぐ無料相談ダイヤルまでお電話ください!
外国人採用の専門家が丁寧に対応させていただきます(全国対応)。
・外国人採用のご相談
・監理団体のご紹介
・登録支援機関のご紹介
・外国人紹介会社のご紹介
・行政書士事務所のご紹介
ご利用料金は完全無料です。
サイトのご利用から監理団体・登録支援機関等のご紹介まで
一切料金はかかりません。
安心してご利用くださいませ。